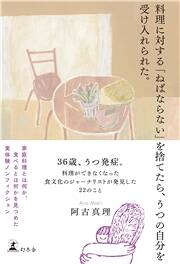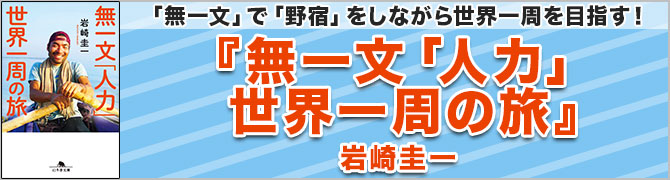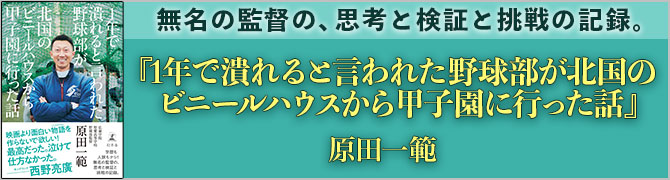ここ数年は、かなり体調がよくなって元気に生活している。日付が変わって帰宅するとさすがに翌日ぐったりするし、1日遊び過ぎて一時的に目玉を動かせない状態に陥ることもあるが、休憩を取りながらなら、たいていのことがこなせる。うれしいのは、近頃午前中の外出にも耐えられるようになりつつあることだ。
元気になれたのは、よく休むこと、自然と接すること、我慢をしないよう気をつけること、しっかり食べることを心掛けてきたから。それに加え、人に支えられたことも大きいのではないか。夫が常に味方でいてくれたこと、友達ができたことはとても大きい。ここまで書く機会がなかったが、夫の親族や子どもの頃から私を知っている叔父夫婦にも支えてもらった。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。
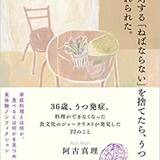
うつ病になったら、料理がまったく出来なくなってしまったー。食をテーマに執筆活動を続ける著者が、闘病生活を経て感じた「料理」の大変さと特異性、そして「料理」によって心が救われていく過程を描いた実体験ノンフィクション。
- バックナンバー
-
- ひとは必ず、うつ病から立ち上がれる(香山...
- 「選ぶ」は、かなり難しい【再掲】
- 食い意地が生きる力を取り戻す【再掲】
- 36歳、うつ発症!【再掲】
- 料理は億劫であり、同時に楽しいものである...
- 料理は楽しいものだと思い出した日のこと
- 家事分担は「量」だけでは語れない
- 料理研究家・辰巳浜子さんの本から学んだ料...
- 「底つき」の馬鹿力
- 二つの震災とうつ
- うつと自分を切り離して考えるようになって...
- 外食の効能について考える
- 料理情報の波に溺れて病まないために
- 「ていねいな暮らし」になぜ私たちは愛憎を...
- 生まれてはじめて「生きてて良かった!」と...
- なぜ日本のキッチンはやる気を奪うのか
- 鍋を食べ終えるために床に寝転ぶ。
- しんどいときは一汁一菜に頼ってきた
- ワンパターン献立に救われる
- 「献立を考える」は何故ハードルが高いのか
- もっと見る