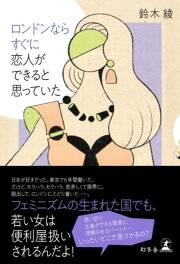8月2日(土)にひらりささんとともに「美容と社会、そして私たち」読書会を開催する鈴木綾さん。お住まいのロンドンから東京にいらっしゃいます。読書会を前に、鈴木さんの初エッセイ『ロンドンならすぐに恋人ができると思っていた』から一部を抜粋してご紹介。ここで描かれた状況は2022年のものですが、いろんな人が暮らす社会の豊かさを感じられる文章です。読書会の詳細は記事一番下をご覧ください。
いろんなコミュニティ、文化がせめぎあう街
家のすぐ近くに自由市場資本主義の素晴らしい事例がある。それはブリックレーンにある二つのベーグル屋さん。オレンジ色の看板の店と2軒先の白い看板の店が何十年も前からフレンドリーに争っている。

ロンドンを訪ねた方々はご存知かもしれない。大体のガイドブックに載っているし、自撮り棒を持って並んで待っている中国人の数からすると誰かが微博(ウェイボー)にも投稿したのだろう。白いほうはなぜか観光客に人気だが、私はオレンジのほうをいつも選んでいる。単にそっちのほうが家に近かったから。連帯感って結構恣意的だよね。
どっちの店舗も暗黙のうちに「近代化」に抵抗している。同じ界隈におしゃれなカフェや古着屋ができているにもかかわらず、座る場所もない、ベーグルが一杯並んでいるカウンターしかなく、メニューもほぼ変わっていない。どっちも支払いは現金のみ。むき出しの蛍光灯の光を浴びてカウンターで働くタフなおばさんたちも何十年も前から変わってないだろう。
彼女たちは挨拶もせず笑顔も見せず注文を受けて手早くベーグルを白い紙の袋に入れ、ぐるぐる巻いてお客さんに渡す。注文を早く決めない素人客は殺人光線のような視線でにらまれる。ある日眠れなくて朝5時にベーグルを買いに行ったら、お客さんは一人もいなくて、珍しくベーグルおばさまに優しくされた。
「あなた、涙が出てるのは目が乾燥してるからだよ、目薬買いなさいよ」。こんなひとさじの優しさを彼女たちからいただくのはまるでおみくじで大吉にあたるようなものだ。早速、目薬を買いに行った。
ロンドン郊外のある高級住宅地に住んでいる親戚が週末に「上倫」したとき、誇りに思っている近所を案内したくてベーグル屋さんに連れて行った。11歳のいとこがお父さんの袖を握りしめた。
「こわい、こわい人がいる」
ドラッグでラリっている痩せ衰えた女性がお店に入って大声で叫んでいた。店員は完全に無視。そうか、いとこはドラッグ中毒者を見たことないのか。たしかにこわいと思うだろう。でも、これがベーグル屋さんの日常。観光客とともに、近所で働いている女性たち、何十年も前から近所に住んでいる労働者階級の人たち、弁護士、銀行員、そして数多くのドラッグ中毒者。ドラッグの中毒者の多くはかわいそうなことに体に障害がある(ブリックレーンで電動車椅子をびゅんびゅん飛ばしているおじさんのあのスピードはたしかにこわいけど)。
ブリックレーンはタワー・ハムレッツ区に位置している。この区はイギリスで一番子供の貧困率が高くて所得格差が大きい。HSBCやバークレイズを含めた有力企業の高層ビルの陰に生活保護受給者、十分に食べられていない子供たち、狭いアパートで窮屈に生きている家族たちがいる。とても貧しい人ととても裕福な人が共存しているが、真ん中の人が少ない。
二つの世界が触れ合う数少ない場所が、ブリックレーンのベーグル屋さん。所得、学歴、人種とは関係なく、みんなにとってベーグル1個の値段は40ペンス(約60円)。
19世紀のロンドンでは、底辺層以下の人たちはresiduumと言われた。直訳すると「残り物」という意味になる。莫大な財産を占拠した、太陽の沈まない大英帝国の中心、ロンドンでは何万人ものresiduumが赤貧の暮らしをしていた。私が今住んでいる、ブリックレーンのベーグル屋さんから歩いて2分のところはその当時、ロンドンで最も貧しいスラム街だった。ここで生まれた赤ちゃんの4人に1人は1歳の誕生日を迎えられなかった。
今や、高級スキンケア・ブランド「イソップ」のお店、高級会員制スポーツクラブ、ミシュラン一つ星レストランができて、この場所の悲惨な歴史を思い出させる目印は一つしか残っていない。それは、赤煉瓦でできていて贅沢に緑が多い公園を囲んで建てられたマンション群「バウンダリー・エステート」。スラム街が撤去された後、低所得家庭のために建てられたイギリス初の市営住宅だった。今でもマンションの2分の1は市営住宅として使われている。
130年もの歴史を誇るバウンダリー・エステートは、この国の多くの市営住宅団地より早くできた。その後、ロンドン市と地方自治体は20世紀の100年をかけて市営住宅建設の政策を進めた。最近のデータでもイギリスの家庭の17パーセントは市営住宅に住んでいる。ロンドンのどこの地区に行っても必ず市営住宅があって、さまざまな所得水準の人たちがともに住んでいる。だからブリックレーンのベーグル屋さんみたいなところで、いろんな階級の人たちが交じり合う。これが、私が訪れ、住んできたいくつもの大都市とは違うロンドン独特の現象。
バウンダリー・エステートができたヴィクトリア朝のころは、貧困の原因が世の中の大関心事だった。当時、貧しい人たちの多くは、貧しいのは自分のせいだ、と思っていた。貧困は、知的、道徳的な弱さの証拠と見なされていた。バウンダリー・エステートもこの「貧困に関する誤解」を反映していた。家賃はスラム街に住んでいたような人たちにとってまだ手が届かなかった。完成後、バウンダリー・エステートに引っ越した5000人のうち、その前のスラム街の居住者はたったの11人だった。建物は小さな丘の上にある野外ステージを囲むように建てられた。丘はスラムの廃棄物でできていた。
ロックダウン中に郵便局に行ったとき、通りで不思議なホームレスっぽい人を見かけた。コロナ禍で路頭に迷っている人は確実に増えていて、スーパーや駅を出るたびに小銭をせびられる。しかし、この男性はそれまで見たホームレスと違っていた。というのも、彼は通りで犬の水彩画を描いていた。よく見たら、隣で気持ちよさそうにぐっすり寝ていた犬の絵だった。絵がめちゃくちゃうまかった。普通にギャラリーで売れるくらいのクオリティ。
「絵を買いたいんですけど」と挨拶をしたら、彼はとても丁寧に絵を紹介して自分の人生を話してくれた。ジョンさんといった。
ジョンは若いときから犯罪に手を染めたり、ドラッグをやったりして何度も刑務所にぶち込まれてホームレスになった。そして、人生を変える出会いが訪れた。他のホームレスの人が面倒を見られなくなった犬のジョージをジョンにくれた。人生で初めて自分以外の生き物の面倒を見なければいけなくなったジョンは世界観が変わった。自分がまた投獄されれば、ジョージは住む場所がなくなる。ジョンは必死になった。
ジョージの世話をするお金を稼ぐために、最初ジョンは路上でお金を乞うたけれど、路上生活の退屈を紛らすために彼は子供のとき以来の筆を手に絵を描き始めた。すると、ジョンは近所にギャラリーを持っていた人にスカウトされ、個人の展示会をやって評判になり、本まで出してベストセラーになった。ジョージとジョンは一緒にBBCに出たぐらい大ブレークした。
しかし、ジョンは自分のエージェントと喧嘩して、生活がまた厳しくなった。路上で会ったとき、彼はしばらく家賃を払っていないと話していた。コロナが蔓延するなかで活躍するのは難しかった。
ジョンは歯がほとんどないし、話し方はかなりぶっきらぼうだけど、明るくてフレンドリー。西洋人は普通目を合わせて話すけど、ジョンは目をそらして話す。彼の中にまだいろいろな不安があるんだろうな、と話していて思った。
その後、何回もジョンとジョージを見かけた。この間、ジョンの絵を額に入れてもらいに行く途中で遭遇した。「あなたの絵を額に入れて家で飾るよ!」と言ったらジョンが微笑んでくれた。ジョージは隣の木におしっこした。
東ロンドンはここ30年、ストリート・アートが盛んだ。世界で最も有名なストリート・アーティスト、バンクシーの作品だって普通に見れる(人に壊されないように箱に入っているけど)。有名なストリート・アーティストでホームレス歴がある人もかなりいる。壁に細長い線で描く巨大な人物像で知られているアーティスト、Stikは何年間も貧乏生活をしてホームレスになったが、2020年、彼の絵が20万ポンドで落札された。
東ロンドンの建物の多くは何十年、場所によっては何百年も前からある。次々と渡英してきた移民たちの記憶が積み重なっている。落書きのアーティストたちはその積み重なった歴史の上に色を塗ってまた新しいレイヤーを残している。そして彼らのアートの上に次の世代が何かを描くだろう。
この間、フランス人の友達とイミグレーション(移民)と多文化社会の構築について議論した。
「フランスでは元植民地の国から来た人たちの多くは社会に溶け込めていない。だから家族が50年以上もフランスに住んでフランス国籍を持っていてフランス語しか喋れない移民4世や5世でも急進的な宗教団体に入ったりする。
なぜかと言うと、フランスは『一枚岩』でできた社会だから。フランスの歴史を勉強するとわかると思うけど、フランス人にとって『フランス』という国、フランス社会、フランス文化、『フランス人でいること』は特別な意味を持つ。移民はどこまでいっても移民。
でもロンドンは違う。ロンドンは『多文化社会』。いろんな文化、いろんな人種がいて、それぞれロンドンに根付いている。コモンウェルス(commonwealth)があるのも大きな違い。フランスだと、典型的なフランス人はパリジャン、ってイメージできるけど、ロンドンに住んでいて、私には『典型的なロンドン人』のイメージが湧かない」
彼女はそう言った。差別的な階級意識が根深く残るイギリスで彼女の意見には100パーセント賛成はできないけど、それでも彼女の発言を忘れられなかった。ブリックレーンや東ロンドンを歩くたびに思い出す。八百屋さんを経営しているバングラデシュ人のおじさん、100年前からある労働者向けカフェで働いているぶっきらぼうなおばさん、オーガニックな野菜しか食べない若くて偉そうなアーティスト、たしかにみんなロンドン人だ。
いろんな文化、いろんなコミュニティがぶつかり合い、せめぎ合うなかでそれぞれが自分の居場所を見つけ、お互いに絶妙な距離をとりながら交ざり合い、でも自分を見失うことなくその地に根付いて、共存するようになる。ここ東ロンドンはそんな場所。
どこに行っても必ず何かしらハプニングがあって、そこに人の悲しみ、喜びがあって、そしてそこには何でも超えられる人の強さが見える。まるで演劇を見ているようだ。辛いときに周りを見ると、人生って演劇にすぎないんだ、辛いのは自分だけじゃない、それでもみんな自分のドラマを精一杯生きているんだって思えて、自分の辛さも笑いに変えて楽になれる。
* * *
読書会のお知らせ
8月2日(土)16時より、美容と社会、そして私たち~ひらりさ×鈴木綾『美人までの階段1000段あってもう潰れそうだけどこのシートマスクを信じてる』読書会を開催します。今回は、綾さんも来日し、会場とオンラインの両方で行います。
詳細・お申込みについては、幻冬舎カルチャーのページをご覧ください。みなさまのご参加お待ちしています!
ロンドンならすぐに恋人ができると思っていたの記事をもっと読む
ロンドンならすぐに恋人ができると思っていた
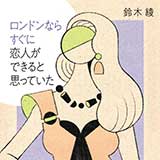
大学卒業後、母国を離れ、日本に6年間働いた。そしてロンドンへ――。鈴木綾さんの初めての本『ロンドンならすぐに恋人ができると思っていた』について
- バックナンバー
-
- 女性がキャリアを築くために必要な「すべき...
- 「典型的なロンドン人」はどこにもいない
- 右翼のロメオ、左翼のジュリエット -「政...
- 結婚でも出産でもなく、「人生を変えたい」...
- 東京での社会人基盤を捨ててロンドンに向か...
- 海外でキャリアを積む優秀な女性たちの存在...
- 「日本が嫌い」「アメリカが完璧」と単純化...
- 「男性登壇者だけのイベントは参加禁止」と...
- 「欠点を愛そう」日本の"金継ぎ"がイギリ...
- 日本をドロップアウトしたけれど、脱皮は日...
- 「日本は取り残されるのでは?」世界の中の...
- 東京からロンドンへ。流転しながら生きる姿...
- 離婚準備中に始まった“鈴木綾の連載”は「...
- 出国子女や帰国子女たちに日本を撹拌してほ...
- 東京もロンドンもどこの国も生きるのは大変...
- 結婚とは異なる「人生のバージンロード」を...
- 日本から脱出する優秀な「出国子女」たちへ...
- 「鈴木綾の言葉」は“自分が人生の主人公”...
- 「国籍」を明かしてもらえない不安感が浮き...
- 「ロンドンのMBA金融ガール」から「上海...
- もっと見る