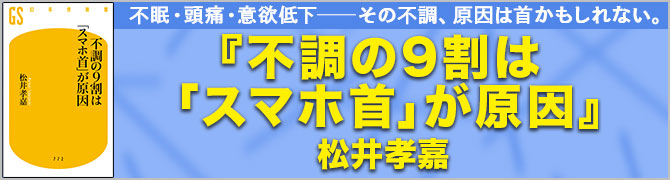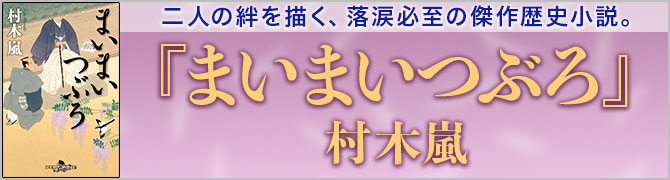「選択的夫婦別姓」制度導入については、先日行われた参議院議員通常選挙でも、候補者それぞれのスタンスが問われました。しかし現状、国が同性婚を認めていないことについて、札幌地裁は「憲法違反」、大阪地裁は「憲法違反ではない」、と司法の判断は分かれています。どうして裁判所ごとに判断が異なるのか、大阪地裁判断に合理性はあるのか、私たちひとりひとりには何ができるのか。法律事務所Z代表の伊藤建弁護士にご寄稿いただきました。
目次 (タップorクリックすると各項目へスクロールします)
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
結婚って何?

<第一弾>事実婚や別居婚、別姓に向けたペーパー離婚など、典型的な結婚制度や生活スタイルに不自由を感じ、自由な形を模索する人が増えてきている今、あなたにとっての「結婚」とは。
<第二弾>社会の意識の変化、要望があっても、“選択的”夫婦別姓や同性婚の法制化が進まないのはなぜなのか。「夫婦同姓」でないと認められない権利や利益とは? 夫婦別姓の各国事情は? 婚姻制度の不平等を考える。
- バックナンバー
-
- みんな結婚する時代は終わった…「結婚の特...
- 同性婚へのささやかな思い
- なぜ同性婚が必要か
- 事実婚ってぶっちゃけどんな感じ? いろん...
- 同性カップルと事実婚、法律婚は、権利がこ...
- 「結婚はこのままでいいのか?」法律で守ら...
- 「同性婚を認めない」のは「憲法違反ではな...
- 結婚はわからない~それでも日常を重ね、互...
- 新しい家族の形「拡張家族」の先に考えた、...
- なぜ最高裁は夫婦別姓を認めないのか?弁護...
- 尼の私がクリスチャン夫と結婚してはや10...
- 結婚は◯◯◯レスになったらもうおしまい~...
- 何も持たない結婚~いつか結婚も手放すかも...
- 眞子様と小室圭さんと近・現代の結婚観~結...
- 30年来のパートナーとは遠距離恋愛でも事...
- 夫は性格も価値観もすべてが違うから~理想...
- 結婚とジョギングは似ている~それは目的が...
- 同じ姓、同じ住居、同じ価値観、同じ幸せ…...