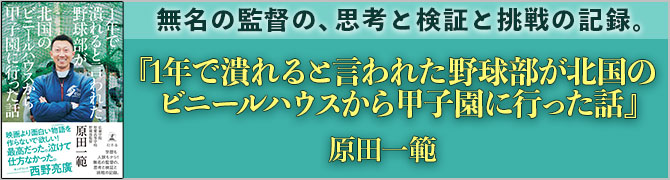コロナ禍は、私たちに世界の不確かさ、予想のつかなさを思い知らせました。宮崎智之さんのエッセイ集『平熱のまま、この世界に熱狂したい「弱さ」を受け入れる日常革命』は本来、私たちの生きている世界とは、もともとそういうものだったと気づかせてくれる一冊です。どんな時でも、新しい年を穏やかな気持ちで迎えられることを願いつつ、抜粋してお届けします。

わからないことだらけの世界で生きている
愛犬を見ていると不思議な気持ちになる。犬は昔から好きだったけど、自分の家では飼ったことがなく、2019年1月にはじめてノーフォーク・テリアのメスを家族に迎えた。
「家族」という言葉が象徴するように、ペットはただの動物ではない。かけがえのない動物であり、たとえば後から先天的な病気が見つかったとしても、当たり前だがブリーダーに文句を言って返したりはしない。人間の子どものように、いつかは独り立ちしてもらわなければいけないというプレッシャーはないものの、だからこそまた別の責任も生じる。「もう十分に育ててもらったから、野生にかえります」なんてことにはならないのだから。
愛犬(名前はニコル)には、できるだけのことはしてあげたいと思う。日々の散歩やエサ、排泄の処理、しつけはもちろんのこと、毎日、楽しく暮らしてほしいし、いろいろなところにも連れて行ってあげたい。ぼくが歌いながら踊るとぴょこぴょこ跳ねて喜ぶような気がするし、首の付け根をなでると気持ちよさそうな顔をしている気がする。あまえたいときは、「クゥン」と鳴く気がするので、その時はなるべくスキンシップを増やしてあげている。
だけど、本当に愛犬がそう思ってくれているのかはわからない。あくまで人間としての視点、人間としての価値観でそう判断しているに過ぎないからだ。犬には犬の思考があって、まったく別のことを感じている可能性もある。飼い主とペットの関係がどのようにすれば適切なものになるのかも、もっと勉強しなければいけない。言葉を喋れないし、人間の身体とも違う感覚を持っているだろうから、体調不良にも気づいてあげる必要がある。
2年近く一緒に過ごしても、愛犬のことをまだほとんどわかっていないのではないか、と日々感じる。感情ゆたかな犬なので、機嫌がいいときと不機嫌なとき、なにかに不満を持っているときがわかりやすい気がするけど、それもぼくの勝手な思い込みかもしれない。わからない、だからこそじっと観察して、少しの変化から想像を膨らます。
だが、これはなにもペットに限ったことではないのではないか。人間ならば言葉でコミュニケーションが取れる、いや取れない人だとしても、なんとなく同じ心や身体的な感覚を持っていると、ついつい考えてしまいがちだ。それは、本当だろうか。「人の気持ちを考えろ」とは言うけど、本当に人は人の気持ちを理解できるのだろうか。そして、自分の気持ちも人に理解されるのだろうか。長年考えてもまだ明確な答えを見出せないでいる。
小学生時代、テレビゲームはすでに登場していたとはいえ、遊びといえばやっぱり外で駆け回ることだった。幸いにも、ぼくが育った東京の郊外にはまだ自然がたくさん残っていて、クワガタやサワガニをつかまえたり、公園や空き地で野球やドッジボールをしたりしてのびのび遊ぶことができた。いつも10人以上の集団で、暗くなるまで遊びまわった。
そのなかに、A君という男の子がいた。毎日のように顔を合わせては笑いあう友達だった。その日も、いつものように夕方5時のチャイムが鳴り、「バイバイ!」とみんなで手を振りながら各々が家路についた。そのとき、A君がぼくを呼び止めたのである。A君は「ちょっと来て」と言って、近くの路地まですたすたと歩いていった。とくになにも考えず、ぼくは付いていった。
路地に入ると、A君はぼくのほうを振り返った。記憶が曖昧だけど、少し間があったのかもしれない。路地は夕日に照らされ、表情は影になってよく見えなかった。
その瞬間、A君は「ぼくは君のこと大っ嫌いだ!」と叫んだのである。全身に力を入れてわななき、言葉だけではなくその小柄な身体すべてを使って、気持ちを伝えようとしているようだった。ぼくが反応する間もなく、A君は全速力でその場を去って行った。
いまだに、あれはなんだったのだろうと思い出す時がある。ぼくは、友達グループで目立つ存在でもなく、かといっていじられるようなタイプでもなかった。ただ、みんなに付いていって、ニコニコ笑っているだけ。A君に大っ嫌いだと言われたことのショックより、自分に対してそんなにも強い感情を抱く人がいるという事実に対して、単純に驚いたことを覚えている。なにせ、まだ自我すらたいして芽生えていない子どもだったのだから。その時は、ただただ衝撃が残って、A君の気持ちや真意を想像することもしなかった。
それからも、A君とは同じ友達グループで遊んでいた。しかし、中学校に入ってバスケットボールに熱中するようになってからは、グループが変わったこともあって、一緒に遊ぶことがなくなった。自然と、A君のことが意識にのぼることも少なくなっていった。
この前、気になって中学校の卒業アルバムを開いてみた。そこに、A君の写真はなかった。もしかしたら、途中で引っ越したのだろうか。あんなことがあったのに、それにすら今まで気づかなかったなんて。
だから、今となってはA君が、なぜぼくにあんなことを言ったのか、ぼくがA君にどんなひどいことを言ったり、してしまったりしたのか確認するすべがない。A君本人も、もうそんな昔のことは覚えていないかもしれない(個人的には、そう願いたいけれど)。それでもなぜか最近、A君が当時、どういう気持ちでいたのかをずっとひとりで考えている。
思えば、育ててくれた親の気持ちだって、本当のことを言うと、ほとんどわかっていないのではないかと感じる。父が71歳で亡くなった時のことを思い出す。入退院を繰り返し、いよいよ父の身体が衰え始めたとき、混乱する母や姉を見て、ぼくはなるべく冷静な判断をするように心がけた。主治医の話を直接じっくり聞き、どのような選択肢があり得るのかを十分考慮した上で、最終的には専門家の意見を尊重し、素人考えで判断しないように家族を落ち着かせようとした。そして、仕事を頑張り、父が生きているうちになるべく多くよい成果を報告できるよう、目の前のことに集中した。
しかし、と思う。もしかしたら、あのとき、父がぼくに取ってほしかった態度は、父の痛みや死への恐怖に寄り添い、慰めることではなかったのか、と。
家族にも言っていないことがある。亡くなる3か月くらい前のことだっただろうか。入院している父から、深夜にショートメールで「助けてくれ」と一言、メッセージが届いたのだ。ぼくはメッセージを受信したことに気づいていたがすぐには返信せず、一晩おいてから、「お医者さんの言うことをちゃんと聞こうね」と返した。返信はなかった。電話しかしなかった父がぼくに送った、最初で最後のメッセージ。父がぼくに弱音を吐いたのもはじめてだった。父が亡くなってから2年以上もの間、ぼくはそのメッセージを開くことも、消すこともできずにいた。偶然、スマートフォンが水没してデータが飛んでしまったとき、どこかほっとしている自分に気がついた。
離婚をし、アルコール依存症になり、会社も辞めてフリーランスで働くぼくは、父にたくさんの心配をかけた。でも、父はそのたびに、ぼくに対して「自分の頭で考えること」の大切さを教え、応援してくれた。だから父に立派な大人としての態度や判断、仕事での成果を見せ、もう心配はいらないんだと伝えることが、ぼくにできる精一杯の親孝行だと思っていた。
しかし、そんなことよりも、できるだけ時間を作って、手を握りながら一緒に痛みや恐怖を感じることが、大切だったのではないか。そんな後悔がいまだに残っている。もちろんなにが正解だったかなんてわからない。大人になってからも一緒に野球観戦に行ったり、実家に帰るたびに好きな文学について熱く議論したりと友達のように仲が良かった父のことですら、ぼくは理解できていなかったのだ。
理性と感情、どっちが大切かなんて、その時々の状況によって違うし、相手によっても違う。それに感情に寄り添ったとしても、本当に「相手の感情」に寄り添っているのかどうかはわからない。それは「自分の感情」かもしれないし、そのことが悪いことなのかどうかも判断しかねる問題だ。
結局のところ、ぼくには想像することしかできない。どんなに想像を膨らませたところで、それは想像の域を出ず、意味などないのではないかと無力感を覚えることもある。一方で、それが独りよがりの想像だったとしても、その想像が父に伝わっていたならばどんなにうれしいか、と祈りに近い思いを抱いている。ぼくは父に立派な姿を見せたかった。父も見たいと思っていると想像した。そんな気持ちが少しだけでも伝わっていたならば、どれだけ救われるか。
身体の痛みについても考える。アルコール依存症のため急性膵炎に二度なり、二度とも入院したぼくは、よく人から「膵炎って、死ぬほど痛いんでしょ?」と聞かれることがある。しかし、「痛さ」を人に伝えるのは難しい。自分と人の身体が、同じ有機物だと割り切るには、人間は複雑にでき過ぎているからだ。心の痛みと同様に、身体の痛みも相手に対して正確に伝えることはできない。
当然、人の身体の痛みも、自分の中で正確に再現することは不可能なのではないか。想像はできても、理解することはできないであろう。父の病気がどれだけ苦痛で、どれだけ痛みを伴うものだったのかは、父にしかわからない。
生きている限り、無意識に誰かを傷つけてしまうことがある。誰かの痛みをそのまま感じることもできないし、完全に寄り添うこともできない。だからこそ思うのが、相手のことを簡単に「わかった」と思ってはいけない、ということだ。相手のことは理解できないし、自分のことも伝わらない。それでも想像しようとすることをやめたいとは、ぼくは思わない。
たとえ、想像することをやめない胆力を持ち続けることしかできなかったとしても、そういう姿勢を崩さないでいることしかできなかったとしても、その態度を「伝える」ことはできるかもしれない。最近では、そんなふうに思っている。
初出「やさしくなりたい 01」
平熱のまま、この世界に熱狂したい

世界を平熱のまま情熱をもって見つめることで浮かびあがる鮮やかな言葉。言葉があれば、退屈な日常は刺激的な場へといつでも変わる。
- バックナンバー
-
- 断酒を経て獲得した「ままならない人生」を...
- 「君のこと大っ嫌いだ!」小学時代の記憶を...
- 「優しさは打算的でいい」と弱さにこだわる...
- 100年残る本屋でありたい店主と実感ある...
- 「“学び”の楽しさと心構えを教えてくれ...
- 4月17日、4月30日「平熱」をめぐる2...
- 「退屈な日常を喜びに変えてくれる本」――...
- 今泉力哉さん、長井短さん、宮崎智之さんが...
- 「行う(do)」ばかりが人生ではない。ポ...
- 「わかっちゃいるけど、やめられない」人間...
- エッセイを書くことは、「一度きりの人生」...
- 「夢日記」とともに現実と格闘したあの頃を...
- 「何者か」になりたいと焦る人にこそ、本書...
- 「弱い」と言い続けるほどに「強さ」を帯び...
- 自己愛増強剤のドーピング熱に浮かされた私...
- フィッシュマンズ「MELODY」を聴くと...
- 柴崎友香さん、今泉力哉さんが推薦コメント...
- 「頑張らないと親に似る」と言われて思い出...