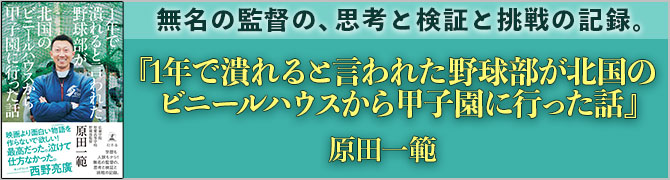1992年のデビュー以来、64作もの作品を生み出してきた恩田陸。59作品目にあたる『蜜蜂と遠雷』で第156回直木賞を受賞したのは記憶に新しいが、その後、間髪を容れずに3作もの新刊を上梓した。しかもその3作は、それぞれ作風が異なる。
なぜ、恩田陸はこれほど多彩な小説を書くことができるのか? そのどれもが読者を惹きつけるのはなぜなのか? 数々の作品を生み出す原動力は何なのか? 受賞後の喧騒がひと段落した恩田陸に話を聞いた。
(インタビュー・文:日野淳)
最前線にいることを確認できた直木賞受賞

「だんだん脊髄反射でしゃべってるみたいになっちゃって」
今年一月、『蜜蜂と遠雷』で第一五六回直木賞を受賞したばかりの恩田陸さん。この作品は刊行直後から読書好きを中心に大きな話題を喚んでいたが、受賞をきっかけに注目度は最高潮に。
当然のように様々なメディアからインタビュー依頼が殺到し、インタビュアーの質問はどうしても重なってしまうものなので、恩田さんから冒頭のような一言が苦笑とともに溢れることになった。
この質問ももはや定番となっているに違いないが、やはり聞かないわけにはいかない。
──受賞によって何か変わりましたか?
「変わったというのは別にないですね。でも励みになるというか、目安にはなります。これまで五回候補に挙げて頂いた度に、自分はこの世界で第一線にはいるんだと実感できたんです。まだ大丈夫なんだ、と。今回、受賞したということは、最前線なんだと自覚できたというか」
恩田さんがデビュー直後からずっと“最前線”にいることは、直木賞を脇に置くとしても、業界内では周知の事実だった。しかし恩田さん自身は常に、そこから後退してしまうのではないかと危機感を抱いていた。
「子どもの頃に好きな作家さんがだんだんつまんなくなっていってすごく残念な思いをしたことがあるので。そうは絶対になるまいという意地があって。私は、“意地”で小説を書いているんです」
意地──。ミステリーにホラー、SF、青春小説、そしてお笑い……百花繚乱という言葉が大袈裟ではないほど様々なジャンルの作品を発表してきた。どの小説にも斬新でひねりの効いたアイディアが惜しげもなく盛り込まれているし、描かれてきた魅力的なキャラクターを数え上げればキリがない。それはつまりデビューから二十五年間、ずっと読者を楽しませ続けてきたということであって、そんな恩田さんの創作活動を支えているものが、意地という言葉で表されるのは意外である。
「もう意地でしかないですよ。連載の締め切りが来たら、この先のことがまったく決まっていなくても、とにかく意地で絞り出して書くしかないんです」
かくして、直木賞受賞から三カ月以内に立て続けに刊行される三冊の新作についてうかがうこのインタビューは、「意地」をキーワードにして行われることになった。
どこから思いついたのか、
思い出せないですね……
とりわけ注目が集まる受賞後第一作は『蜜蜂と遠雷』とは一八〇度違ったテイストだ。ダーク、ビター、そしてヘビーなどという言葉で形容することができそうな連作小説集『失われた地図』。
「『蜜蜂と遠雷』から入った方は面食らうかも知れませんね。でもこういうのも書く人なんだと分かってもらえていいのかな」
舞台となるのは錦糸町、川崎、上野、大阪、呉、六本木。まるで共通点がないようなこれらの場所は、「旧軍部」に関係する重要な施設があったという過去で繋がっている。日本に「戦争をしたがっている人」が増えると、その地に「裂け目」が生まれ、記憶の亡霊のような「グンカ」なる者たちが湧き出てくる。
主人公は、常人には見えない「グンカ」を退治し、「裂け目」を縫うという特殊な任務に就く元夫婦の二人。雑誌の取材チームを装った彼らは、「裂け目」の気配漂う町を訪れ、「グンカ」の力に現実世界が侵食されるのを防がなくてはいけない。
「どこから思いついたんでしょうね……」
この奇異とも時代の空気を反映したともいえる設定が、何をきっかけに生まれたのかと問うと恩田さんは首をひねった。
「確か、かつての軍の記憶が残っている場所っていうのはあちこちにあって、そういう町に行ってみたいというのが先にあったんですよね」
「グンカ」との戦闘シーンが一番の読みどころかもしれない。たとえば川崎では工場地帯の上空に大きな「裂け目」が発生。そこから夥しい数の「グンカ」が飛び出してくる。主人公たちはカメラバッグから色鮮やかな蝶を放って「グンカ」を追い払い、髪に刺したを抜いて空の「裂け目」を縫う。
「結構なスペクタクルですよね。それぞれの町へ取材に行って、ここでなんかあったら嫌だなと思ったことが、書いている時になってフッと浮かんできたんだと思います」
この小説の雑誌連載が始まったのは二〇一一年七月。日本はまだ東日本大震災の衝撃の只中にあり、戦争という言葉が日常の中で頻繁に聞かれるようになるのはもう少し後のこと。なぜこの時点で「軍」の話になったのだろう。
「そこはもう思い出せないですね(笑)。書いているうちにどんどん現実に追い抜かれちゃった感はすごくありました。本当に善悪って相対的な時代だから、何が正義で何がそうじゃないかなんて分からないわけじゃないですか。だからハッピーエンドであり、アンハッピーエンドでもあるって話にしようとは決めていたんです」
恩田さんの言葉通り、「裂け目」の存在感がいよいよ増し、そこに救世主とも終末を招くとも思われる人物の登場によってこの物語は閉じられる。これはもしやシリーズとして続いていくのでは?
「いや、この話はこれでおしまいって感じですね。ここで終わることだけは決めていました。シリーズものにはあんまり興味はないですし。私、わりと書き終わるとすぐ忘れちゃうタイプなんです」
一作目を書いてから、
これからどうしようかと考えた
次に刊行される『終りなき夜に生れつく』はシリーズに興味はないという恩田さんにしては珍しい、スピンオフもの。恩田さんの代表作の一つ『夜の底は柔らかな幻』と同一の世界観の下に生まれた短編集だ。
「あの小説は終わっても世界や登場人物が珍しく自分の中に残っている感じがあって」と恩田さんは語る。
「そもそも『夜の底は柔らかな幻』は大昔に書いたベトナム戦争をテーマにした短編が基になっているんです。世界各地、たとえばジャングルの奥に人類をインスパイアするような知的生命体が隠れていて、それに触れた人が争いを起こすっていう設定の話だった。その短編を長編でやろうと思っていたんですけど、それはいまだにできずで……。世界各地のうち一つの場所が日本っていう設定で書いたのが『夜の底~』だったんです。その後スピンオフを書くとなって、改めてもう一度その設定を使ってみようと。アフリカにもそういう場所があるとして書いたのが一話目の『砂の夜』です」
内戦が泥沼化したアフリカ北部の国で、ボランティア医師として働く女・みつきが第一話の主人公。みつきたちがキャンプを設けた場所の近くには、少数民族が住む集落があり、そこで「悪魔が現れた」という騒ぎが起こる。「ひと晩に一人ずつ、一週間続けて集落で死者が出ているらしい」。
第一話はこの「悪魔」の存在を突き止める話であり、第二話は第一話にみつきの同僚として登場する軍の過去のエピソードへスライド。第三話は軍の物語に登場するまた別の人物に、という具合に、四つの短編は前作にも登場する人物たちが視点をバトンタッチしていく形で繋がっていく。
「全体の構想が最初からあったわけではないんです。一作目を書いてみて、じゃあ、これからどうしようかと。いくつかこういう短編を書いて一冊にするというイメージはあったのですが、とにかく『砂の夜』を書いてから考えました」
本という形になったものを読み、その精緻に組み立てられた世界を享受するだけの読者には信じ難い部分もあるが、恩田さんはいつも先々までのプロットは立てず、「書きながら考えていく」のだと言う。
締め切りは決まっているが、具体的に何を書くのかは決まっていない。それは一体、どんな気持なのだろう。
「怖いですよ。本当に怖いですよ、いつも」
ゾンビに税金をかけられるかという
ところから始まった
三冊目の『錆びた太陽』は前二作とは毛色が変わった、かなりユーモア色の濃い作品だ。しかしこれもまた作風の幅広い恩田さんが得意とするジャンルの一つ。
「私、基本、お笑いなんで。これはもうお笑いにしようって最初から決めていました」
原子力発電所で起こった「最後の事故」から一〇〇年程経った日本。事故の影響で人間が立ち入れなくなったエリアを管理し、汚染除去作業を行っているのは人型ロボットだ。この人類の叡智を結集して開発されたロボットたちが物語の主役。彼らには「ボス」「ゴリ」「ジーパン」など、昭和の名作刑事ドラマの登場人物たちの名が付けられている。ちなみに彼らが乗る大型トラックの名は「一番星」で、出発サイレンの代わりに流れるのは「いい日旅立ち」のメロディー。
「レトロ感満載で」と恩田さん。
ある日突然、ロボットたちの前に一人の若い女が現れる。女は名刺を差し出して言う。「国税局から来ました」。
ストーリーはここから未来における人間とロボットの交流という方向へ流れていくのかと思いきや……そうは真っ直ぐには進んでいかない。この小説、人間とロボット、そしてゾンビの話なのである。
「そう、これはロボットとゾンビの話(笑)」
この時代の日本には、「最後の事故」の影響で死んだ人間たちがゾンビになってあちこちに生息。国税局の女は「ゾンビに課税できるのか」を調査するため派遣されてきた。このシュールとも奇想天外とも言える設定は、一体どこから生まれてきたのだろう。
「今となっては何がきっかけだったのか……。ゾンビに税金をかけられるかって考えたことですかね。そういう本があったんです、ゾンビがいたら社会の仕組みはどう変わるかを研究した本が。それと打ち合わせに行った出版社の隣りに新しいビルが建てられていて、『これ何建ててるの?』と聞いたら、『国税局が来るらしいですよ』って」
「それとそうだ」。記憶を手繰るような表情で恩田さんは続ける。
「私、毎年夏に税務署に税金を納めに行くんですけど、そこに貼り出されている中学生とかが書いた税の作文っていうのを読むのがすごく好きなんです。なぜ『サザエさん』の像には税金がかかるのに、葛飾区の『両さん』の像にはかからないのかを考察した作文があったんですよ。それがすごくよくできていて、賢いなあと感心して」
生活の中で見聞きしていたいくつかのことが結びついて、たまたま小説のアイディアとして結実したということだろうか。しかし、ゾンビに課税である。こんなアイディアが生まれたのだとして、長編小説の主要なアイディアとして本当に使えるのかどうか、どうやって判断を下すのだろうか。
「それはもう、多分直感です」
恩田さんはサラリとそう答える。
ロボットと人間、そしてゾンビが織りなすドラマは、荒涼、寂寞とした未来の日本を舞台にしながらも、昭和の哀愁と生真面目なロボットの滑稽さ、ゾンビもの特有のバカバカしさが交じり合って、独特で不思議な肌触りの物語になっている。
「すごく悲惨な話なんですけど、希望を込めたところはあるんです。でも、お笑いですね。本当に今の世界はお笑いでしか書けないってすごく思います」
確かに、ベースは「お笑い」なのかもしれない。しかしいくつも張り巡らされた伏線や、ロボットたちに託されたテーマが、単に「お笑い」を目指しただけでは届かないであろう、小説としての味わいや深みを醸し出してもいる。
「連載で書いている時に、なんかこの辺に入れておかないとやばいんじゃないかみたいな勘は働くんです。嫌な予感みたいなものがあるんですよ、場数だけは踏んでいるんで。その勘に頼っているというのはありますね(笑)」
書けるだろうと思っても、
書けるという保証はどこにもない
プロットは立てず、書きながら考えるというスタイルが、小説の中にある種の意外性を呼び込むのかもしれない。締め切りを目前にして、書いている本人さえ考えもつかなかったアイディアがどこからかやってくる。勘に従ってふるいにかけられた後、小説の中にしたためられたアイディアは、恩田さんのみならず、読者にとっても思いも寄らない展開を引き連れてくる。
「まあでも怖いですし、毎回絞り出すのは苦しいです」
驚くべきは、ここまで続けて話を聞いた三冊が、直木賞受賞作『蜜蜂と遠雷』の連載と並行して書かれたということだ。しかも他にも時を重ねて書かれたものが「まだまだありますよ」とのこと。
デビュー直後の数冊以外はほとんどすべて連載という形で小説を書いてきた恩田さん。二十年以上も締め切りが連続する日々を送っている。
「まさに綱渡りですね」
もしも書けなかったら。「綱渡り」の日々でそんなふうに思うことはないのだろうか。
「怖さはいつも離れません。いつも必ず、この先どうしようか、次どうなるんだろうって考えているので。お酒を飲んだ時だけ、一瞬忘れた振りをするという(笑)。書けるだろうとは思うけど、そんな保証はどこにもないじゃないですか。たとえば何か一つのものを作る職人さんなのだとしたら、何年もやっているんだから大丈夫だっていうのもあるかもしれないけど、毎回違うものを書かないといけないわけですから。なんの保証もないんです」
締め切りを前にして追い込まれ、焦り、苦しみながら絞り出す日々。直木賞を受賞したことをきっかけに、そんな生活にも少し変化が起きてもいいようなものだが……。
「それはないですね。こういうふうにしか書けないですし。その都度、その場しのぎというか、瞬発力を出すしかない。でもそれこそ経験で、連載の時に間に合わないからと言って、端折って書いたりすると後で絶対に後悔するって分かっているんです。締め切りの都度、意地でもベストを尽くすしかない」
作家、恩田陸を支えているのはやっぱり意地なのだ。
スランプの意味が分からない私は
ずっとスランプ
ここまで何度も登場してきた意地という言葉。恩田さんを支えているその意地は、時に挫けたりはしないのだろうか。
「しょっちゅう挫けてますよ(笑)。そんな時はビジネス書を読んだりとか……」
ビジネス書? 恩田さんとビジネス書とは、不思議な取り合わせだ。
「ビジネス書を読むと一瞬賢くなった気がするじゃないですか。結構疲れて気が弱っている時、つい自己啓発的なビジネス書に手が出る。もしかしたら何かが変わるかもしれないって期待して読むんだけど、でも大抵はダメで。つまんないもの読んじゃったなとか思ったら怒りが湧いてきたりして、その怒りで頑張るみたいな(笑)。もちろん面白いドラマや映画を見て、すごい脚本だなあ、こういうの書きたいなと思うこともありますけどね」
「私、スランプって意味が分からないんですよね」と恩田さんは続ける。
「スランプがあるって人はすごい絶頂期があったんだねって思うわけですよ。私はいつも絶頂じゃない。常に絞り出さないと出ないので、そういう意味ではずっとスランプです」
作家としての意地によって絞り出された一行、一行が積み重なり、やがて本という一つの形になって読者のもとに届く。読者は恩田さんがそんな苦しい思いをしていたなんてことは露知らず、そこに在る物語に没入する。
緻密に色づけされた世界を前に溜め息をつき、予想だにしなかった展開に呆然とする。時には胸を圧し潰されるほどの切なさを抱いたり、主人公たちの決断を我が事のように受け入れたりして。
それはシンプルに言えばとても幸福な読書体験なのだ。
「そうだとしたら嬉しいです。読者の時間泥棒だけは意地でもすまいと思っているので」
※このインタビューは、小説幻冬4月号に掲載されたものです。
「小説幻冬」編集部よりの記事をもっと読む
「小説幻冬」編集部より

- バックナンバー
-
- 小説幻冬7月号発売!菅広文さん×西野亮廣...
- 小説幻冬6月号発売!『転落』発売記念鼎談...
- 小説幻冬5月号発売! 七尾与史さん『ドS...
- 小説幻冬4月号発売!太田光さん特集、鈴木...
- 小説幻冬3月号発売!東野圭吾さん新連載、...
- 小説幻冬2月号発売!伊坂幸太郎さん、恩田...
- 小説幻冬1月号発売!恩田陸さん、住野よる...
- 小説幻冬12月号発売!薬丸岳さん特集、真...
- 小説幻冬11月号発売!五木寛之さん×横山...
- 小説幻冬10月号発売!新川帆立さん、岩井...
- 小説幻冬9月号発売!秋の夜長にミステリー...
- 小説幻冬7月号発売!わたなべぽんさん、芦...
- 小説幻冬6月号発売!伊坂幸太郎さん特集ほ...
- 小説幻冬5月号発売!月村了衛さん特集、水...
- 小説幻冬4月号発売! 吉野北人さんが表紙...
- 小説幻冬3月号発売!藤岡陽子さん特集ほか
- 小説幻冬2月号発売!宮内悠介&一穂ミチ ...
- 乃木坂46・鈴木絢音さん 「小説幻冬」で...
- 小説幻冬1月号発売!2021年の小説を語...
- 小説幻冬12月号発売!上野千鶴子さん×宮...
- もっと見る