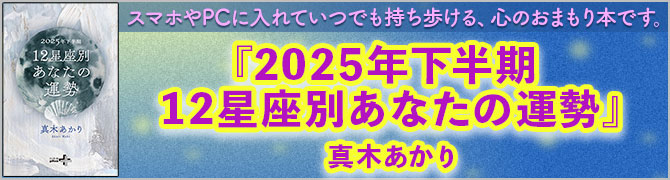「私と飲んだ方が、楽しいかもよ笑?」その16文字から始まった、沼のような5年間ーー。
カツセマサヒコさんのデビュー小説『明け方の若者たち』の文庫が11月17日に発売いたします。北村匠海さん主演で映画化も決定している大注目の作品より1章・2章を、映画の場面写真とともに、8日間連続で特別公開します。(全8回/4回目)
* * *
五月の夜にしては冷えすぎた空気が、パーカーの隙間から入り込んでくる。火照った体がキュッと引き締まる。酔いと興奮を醒ますには、最適な気候だ。近くを走る甲州街道からは、救急車のサイレンが聞こえていた。
「いま、店でた!」
駅の方角に足を進めながら、両手の親指を、スマホに滑らせる。
冷たい風に逆らうようにフウと息を吐くと、ジョッキ三杯分程度のアルコールが、体内で急速に分解されていく。全身が緊張してきているのがわかった。
「大学の横に、小さい公園があるんだけど、わかる? 駐輪場の先」
すぐに返ってきた彼女からの連絡を見て、また心拍数が上がる。ここからだと五分もかからないところだ。通っていたキャンパスのすぐ横だけれど、小さな公園だし、初めてこの駅に来た人では、辿り着けない気もする。やはり彼女は、同じ大学の学生なのかもしれない。
「なつかしい。俺、その公園で、よく元カノとキスしてたよ」
あ、これ、ミスってる。脳が判断したときには、送信ボタンを押していた。肝心なところでセンスがないよねと、該当する元カノから注意されたことを思い出して、頰が引きつる。これから二人で会う女性への連絡としては、最低な部類に入るメッセージ。早くも後悔し始めていた。スマホは、またすぐに震えた。
「私、一度ここで、セックスしたことあるなぁ笑」
それで、なんだかもう、彼女には敵わないとおもったのだった。
そもそも何を勝ち負けとするかもわからないけれど、この、どうしようもなく低俗で下品な一往復だけで、僕と彼女の関係は、常に彼女が優位に立つのだと予感してしまった。
あらゆるものには、優劣が存在しているとおもう。平等や公平なんてものは存在しなくて、どちらかが優勢で、どちらかが劣勢で、そのバランスが安定したところで落ち着いているだけだ。たとえば多くの生き物が食物連鎖の関係に抗えないように、彼女と僕もまた、いつだって彼女が優位である。その事実を、僕はこの瞬間から、うっすらと理解してしまったのだった。
明大前は渋谷と新宿、吉祥寺を繋ぐ駅として利用され、朝・晩のラッシュではかなりの人数が行き来している。その割に街自体はこぢんまりとしていて、居酒屋も数えられる程度しかない。甲州街道を越えてしまえば、街並は一気に静かな住宅街に姿を変える。
その住宅街に入ってすぐのところに、縦長の小さな公園がある。「クジラ公園」と仲間内で称していたその公園には、俗称どおりの存在感を発揮した、クジラの形をした遊具が置かれている。敷地自体はかなり小さく、十人横並びになれば手狭におもえるほどだ。
彼女がいたのは、その小さな公園だった。
「おつかれさま」
声が聞こえたのは、クジラの遊具の後ろにある、小さな滑り台の上からだった。街灯の光がギリギリ届くか届かないか、目を凝らすと、彼女のシルエットがぼんやりと浮かび上がる。
僕は足を止めて、暗闇に向けて話しかける。
「ズルいでしょ、あの誘い方」
「ん? 何?」
「スマホ、本当は、なくしてなかったでしょ」
「違う違う。本当に、なくしてたよ」笑いが混じった声は、相変わらず少し掠れていて、彼女の姿をそのまま表したような、やわらかい消極性が感じられた。
「本当に? あんなあざとい誘い方あるのかって、びっくりしたんだけど」
「たまたまだよ。着信履歴に、残ってたから」
今度は少しわざとらしそうに、えへへと笑う声がする。
こっちおいでよと、彼女のシルエットが小さく腕を振った。僕は招かれるまま、滑り台の階段を一息で上る。
「はい、おつかれ」
彼女は飲みかけのトリスハイボールを僕に渡した。横に置かれた一番小さいサイズのコンビニ袋から、おもむろに同じものを取り出して、カシュとプルタブを開ける。どうして飲みかけのやつが俺なの、とツッコむのも野暮な気がして、黙って乾杯を促す。
「変な飲み会、おつかれさまでした」
「うん、乾杯」
べん、と、アルミ缶のぶつかる音がする。
彼女の飲みかけのハイボールを口に含むと、エチケット気分で口に入れていたミンティアがアルコールの濁流にのみ込まれていった。
「ハイボール、好きだった? 勢いで買っちゃったから、飲み終わったらコンビニいこ?」
「ん。あっち、まっすぐ行ったら、ミニストップあったはず」
あれ、ローソンだったっけ? と濁したところで、なつかしいと彼女は続けた。
なつかしい、ということは、やはり初めてではないから、同じ大学だろうか。明大前のキャンパスは、大学三年になってからほとんど通わなくなったし、なつかしい、と感じる気持ちも、わからなくはなかった。
ハイボールを飲み終えるまで、僕らは「勝ち組飲み会」について、ひたすら悪口を並べて遊んだ。「きっと入社してから苦労するんだよ、ああいう場に参加しちゃう、私たちみたいな人間は」自虐も含めて話す彼女は、内定という事実だけで浮かれて踊れるほど、浅はかでも愚かでもない大人だった。行くはずだった友達が風邪で行けなくなったからと、数合わせで呼ばれた彼女が、僕にはあの場にいる誰よりも魅力的におもえていた。それまであの場に参加する自分をどこか誇らしくおもっていた僕は、彼女の苦言を聞いたその瞬間から「レセプション・パーティ」や「ローンチ・イベント」に参加するようなタイプの人間を、大嫌いになろうと決めた。誰からも賞賛されるような存在になるよりも、たった一人の人間から興味を持たれるような人になろうと決めた。

ファミマだったらファミチキだし、ローソンだったらからあげクンだけど、セブン―イレブンだけはレジ前の定番商品がない気がしない? あ、でも、意外とアメリカンドッグが美味しいかあ。でもでも、セイコーマートのレジ前クオリティには結局勝てないから、やっぱセコマが最強だよね。日本人なら、一度は北海道に行くべきだよ。すごいよセコマ、ほんとに。
クジラ公園からコンビニに向かう途中、彼女は彼女の中に確立されたコンビニ論を展開させた。飲み会のときはあんなに静かだった彼女は、二人になると饒舌で、二人のときの方がよっぽど魅力的で、積極的だった。僕らはお互いの話のほぼ全てに同意の相槌を打ちながら、夜の住宅街を踊るように歩いた。
彼女のコンビニ論で一切登場しなかったミニストップには、パートとおもわれるおばさん店員と、コピー機を延々と働かせている学生以外、誰もいない。
彼女が好きだと言って真っ先に手に取ったミミガーと、僕の独断で選んだコンソメ味のスナック菓子をカゴに放り込んだ。それから三五〇ミリリットルのストロングゼロが二本と、スミノフに、ウーロンハイ。それぞれ好きなものをカゴに入れるたび、右手の指先に重みが加わり、熱が籠(こも)る。
初対面の彼女がどんなものに興味を示すのか気になって、僕は細心の注意を払いながらミニストップ店内を回った。レジで会計しようとしたら、パートとおもわれたおばさんは、店長だったことを知った。
ビールだったらモルツが好きでね、それもプレミアムじゃないやつなんだ。海外のお酒なら、定番だけどシンハー。クラフトビールもいいんだけど、匂いがちょっとダメでね。私、鼻がきかないんだけど、なぜかビールの匂いだけわかっちゃって。なんか、アル中みたいで恥ずかしいや。
ミニストップからクジラ公園へ戻る間、彼女は彼女の中に確立されたビール論を展開させた。
あとから気付いたけれど、彼女には、彼女の中に確立されていることがいくつもあった。確立されてはいるけれど、時に嗜好の変化や習慣の遷移が起きて、大好きだったものが大嫌いになるくらい、それらは激しく変動することもあった。僕は彼女の嗜好がアップデートされるたび、彼女と同じものをおもいきり好きになったり、おもいきり嫌いになったりした。
さっきまでハイボールを飲んでいたクジラ公園まで歩く。数少ない街灯を過ぎるたび、二人の影がウニウニと伸びては薄くなって消えた。それを見て彼女が「なんか宇宙人みたい」と言った。「地球は慣れましたか?」「ややこしい星ですよね、いろいろと」少し疲れた声で返した彼女の横顔は、ヒトとは思えないほど綺麗だった。
明け方の若者たちの記事をもっと読む
明け方の若者たち

6月11日発売、人気ウェブライター・カツセマサヒコさんのデビュー小説、『明け方の若者たち』をご紹介します。
- バックナンバー
-
- なぜ『明け方の若者たち』は読まれ続けてい...
- 挫折と恋を小説にした理由とは?カツセマサ...
- 映画のエンドロールが終わっても登場人物の...
- ストーリーのある会社に“彼女”には勤めて...
- #8 下北沢は湿ったアスファルトの上で静...
- #7「何者でもないうちだけだよ、何しても...
- #6 ヴィレッジヴァンガードは待ち合わせ...
- #5 その笑顔が嘘じゃないなら
- #4 クジラ公園で、飲みかけのハイボール...
- #3 パーティをぬけだそう!
- #2 彼女の財布から溢れたレシートは下着...
- #1「勝ち組」は明大前の沖縄料理屋に集う
- 『明け方の若者たち』文庫カバーを解禁
- 『明け方の若者たち』文庫化決定!
- 【書評】終わりない「マジックアワー」の中...
- Twitterの140文字と、小説の10...
- 特製しおりをプレゼントする、インスタキャ...
- ノーコンプレックスがコンプレックス。凡人...
- 【書評】変わっていく時間の中に描かれる永...
- 【書評】極めて刺激的で鮮烈な文学世界だ!
- もっと見る