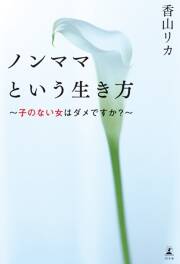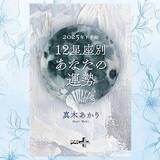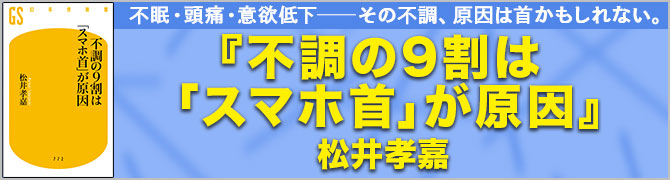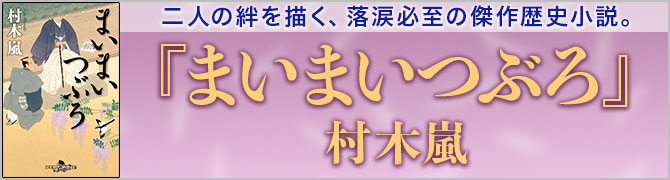自分のこだわり。自分の「ねばならない」。それがあるとしたら、なんだろう。そんなことを考えた。
きっかけは、何冊かの本を読んだことだ。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
おとなの手習い

60歳という人生の節目を前に、「これからの人生、どうする?」という問いに直面した香山リカさん。そこで選んだのは、「このまま穏やかな人生を」でなく、「まだまだ、新しいことができる!」という生き方。香山さんの新たなチャレンジ、楽しき悪戦苦闘の日々を綴ります。
- バックナンバー
-
- 「おだいじに」「この薬を飲めばよくなりま...
- オリンピック後、ひとかけらの希望は残るの...
- ワクチン接種会場で気になってしかたないこ...
- 「ウミウシの切断と再生」に思う、人生の残...
- 人生の本質は「理不尽」だと認めたくはなか...
- 目の前の病人に治療ができない医者に、存在...
- 伊是名夏子さんから学んだ「読書の真髄」
- 「私宅監置」を知っていますか
- 「あの問題」と戦後民主主義
- 日本の感染状況を案ずる中国の友人から届い...
- 「役に立つ医者」になりたくて
- 「昔はよかった」と私に口走らせた「見開き...
- 1月3日「年越し大人食堂」での出会い
- 医師が患者さんから「なぜ生きないといけな...
- 子どもを産まない自分は、生まれてきてよか...
- 1000年前から女性を苦しめる「私の人生...
- シークワーサー酒を漬ける時間
- 去年は塩むすびを頬張りながらディスカッシ...
- かつてこれほど普遍的に、人類が同じ試練を...
- コロナで失ったものがあっても、人生は続く
- もっと見る