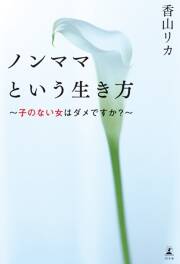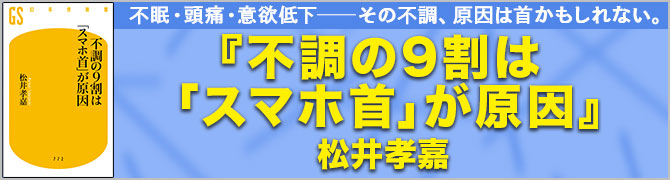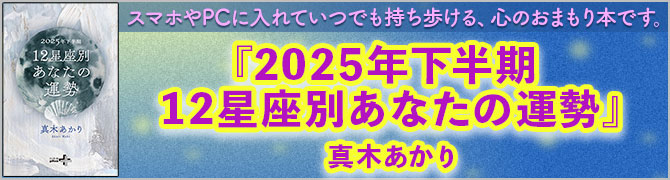今回は、「50代を超えて自分が変わることがある、しかしまた元に戻ることもある」という話をしたい。
このコラムでもときどき、精神科医の私が内科の基本を学び直している、という話を書いている。その理由は、「そのうち医療過疎の地域の診療所に勤めたいから」だとも書いた。それはもちろんウソではないのだが、精神科医としての自分に限界を感じたという側面もあったように思う。そんな日が来ようとは、若い頃にはまったく想像できなかった。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
おとなの手習い

60歳という人生の節目を前に、「これからの人生、どうする?」という問いに直面した香山リカさん。そこで選んだのは、「このまま穏やかな人生を」でなく、「まだまだ、新しいことができる!」という生き方。香山さんの新たなチャレンジ、楽しき悪戦苦闘の日々を綴ります。
- バックナンバー
-
- 「おだいじに」「この薬を飲めばよくなりま...
- オリンピック後、ひとかけらの希望は残るの...
- ワクチン接種会場で気になってしかたないこ...
- 「ウミウシの切断と再生」に思う、人生の残...
- 人生の本質は「理不尽」だと認めたくはなか...
- 目の前の病人に治療ができない医者に、存在...
- 伊是名夏子さんから学んだ「読書の真髄」
- 「私宅監置」を知っていますか
- 「あの問題」と戦後民主主義
- 日本の感染状況を案ずる中国の友人から届い...
- 「役に立つ医者」になりたくて
- 「昔はよかった」と私に口走らせた「見開き...
- 1月3日「年越し大人食堂」での出会い
- 医師が患者さんから「なぜ生きないといけな...
- 子どもを産まない自分は、生まれてきてよか...
- 1000年前から女性を苦しめる「私の人生...
- シークワーサー酒を漬ける時間
- 去年は塩むすびを頬張りながらディスカッシ...
- かつてこれほど普遍的に、人類が同じ試練を...
- コロナで失ったものがあっても、人生は続く
- もっと見る