
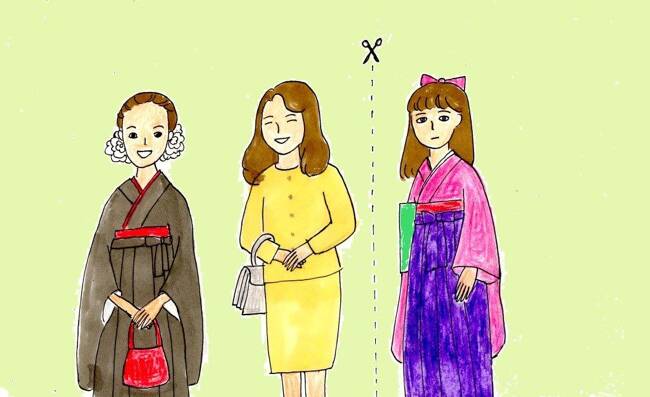
母方の祖父母が亡くなり、祖父母の住んでいた家が空き家になってから15年余り、やっと伯父が思い腰を上げて家を取り壊した。泥棒に入られたのだ。
家を取り壊す前に、伯父と母と三人で、家の中に入ってみた。玄関の木戸をカラカラカラと開ける音まで懐かしく、玄関の中に入ると、祖母が今しがた、お出かけから帰ってきたように、フードのついたシルバーのコートが棚の角に引っ掛けてあった。
マスクと軍手をつけて、靴のまま家の中に上がると、襖(ふすま)も、箪笥の引き出しも全部開き、中の物もそこら辺に散らばっていた。
もう電気も来ていない薄暗い家の中は、ほこりと蜘蛛の巣が幾重にも重なり、一歩進むごとに積み重ねてあった本が崩れてきたり、傷んだ床が、私の体重で、へこんだりした。
台所に入ってみると、シンクには、お湯のみが一つおいたままになっていた。祖母はしばらく娘の家でのんびりするつもりで、この家を後にし、そのまま、静岡の私の実家で10か月を過ごし、まだハイハイをしていたひ孫と遊んだり、一緒に昼寝したりして、自分の家に戻ることもなく、娘のうちで亡くなった。
祖父母の家を取り壊すにあたって、私が一番懐かしく、まぶたに焼き付けておきたかったのは、物書きだった祖父の書斎だった。狭い階段を上がって行き、左側の襖を開けると、懐かしい祖父の書斎があった。襖の内側には、錦絵のようなきれいな女性が描かれた千社札や、祖父の名前の書いてある千社札が、張ってあった。
襖のついた本棚の棚板は一枚一枚を違う木で作ってあり、棚板の側面は、木の皮を取り除かないで、そのまま使っていた。
原稿を書く机は、天板が桜の木で、やはり、側面に木の皮を生かしてあった。床の間の壁には、杉の木の皮を貼って覆ってあり、その間には、祖父が旅行先で買ったのであろう、きれいな簪(かんざし)やキセルが刺してあった。棚の上には、張り子の虎がおいてあった。
足元を見ると、炉畳があった。小さな頃にはちっとも分からなかったが、祖父の書斎は茶室の作りで、炉の真上には、天井から、金属の鎖がつるしてあり、その金属の部分を隠すように、竹の木で覆ってあり、その下には鉄瓶を吊るしてあった。
祖父は仕事中、その鉄瓶でお茶を沸かして飲んでいたそうだ。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
さすらいの自由が丘の記事をもっと読む
さすらいの自由が丘

激しい離婚劇を繰り広げた著者(現在、休戦中)がひとりで戻ってきた自由が丘。田舎者を魅了してやまない町・自由が丘。「衾(ふすま)駅」と内定していた駅名が直前で「自由ヶ丘」となったこの町は、おひとりさまにも優しいロハス空間なのか?自由が丘に“憑かれた”女の徒然日記――。

















