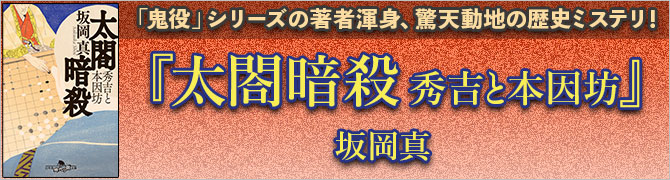長澤まさみさんが主演する映画『おーい、応為』が話題です。
モネ、ゴッホを魅了し、西洋で「東洋のダ・ヴィンチ」と称された葛飾北斎。
その名を世界に広めた画商・林忠正、そして晩年を支えた小布施の豪商・髙井鴻山。芸術と資本、江戸と西洋が交錯する中で創作に生きた画家の生涯を描いた書籍『知られざる北斎』もあわせてお楽しみください。本書から一部を抜粋してお届けします。
「この波は爪だ」ゴッホ見た北斎の衝撃
「私がさっきThe Great Waveについて最初に語った時『あの画家』と言ったのは、だれだかわかりますか?」
ロンドンでのインタビューの途中、ティム(*1)はそう言って微笑んだ。

ヨーロッパで北斎のGW(*2)を最初に認めて、言葉を残している画家――。この展覧会の会場に来るまで私は不覚にも知らなかったのだが、会場の壁にその言葉がいくつか記されていた。
「君は北斎を見て『この波は爪だ、船がその爪に捕らえられているのを感じる』と手紙に書いていたが、北斎は君にも同じ叫びをあげさせたわけだ。もちろん北斎はその線と素描によってだがね。もしただ正確な色彩とかただ正確な素描とかで書いたならば、そうした感動を引きおこさなかっただろう」
1888年9月7日、ヴィンセント・ファン・ゴッホがアトリエを構えた南仏のアルルから、弟のテオにあてて書いた手紙の中の一節だ。
ゴッホは浮世絵で見た影のない明るい色調のイメージが日本だと思い、それを南仏の強く明るい日差しに求めてアルルに移り住んだ。そして「日本人になりたい」と書いた。
「他の芸術家たちが強い太陽の下で、もっと日本的な透明さの中で色彩を見たいと望むようになるのがわかっている。だからぼくがこの南仏の入り口にかくれがのアトリエを設けるのは、それほど馬鹿げたことではない」(「ゴッホの手紙、中」第538信)
日本人からすれば戸惑いを感じる表現だが、ゴッホは大真面目だ。アルルで創作活動に励んだのは、「日本愛」の表出だったのだ。
編集部注:
*1…大英博物館で北斎展を企画した日本美術研究家・キュレーターのティム・クラーク
*2…北斎の代表作『The Great Wave、神奈川沖波裏』
不自然な色使い
その日記の中に「北斎」はしばしば登場する。ティムはこう語る。
「ヨーロッパでGWが讃えられるようになったのには、ゴッホがとても重要な役割を果たしています。北斎の『富嶽百景』は、1880年にイギリスのフレデリック・ディケンズが英訳してロンドンで出版しています。88年にはゴッホがGWについて感銘を受けたことをテオとの手紙で書いている。
アルルでゴーギャンを待っている時、彼にとってはとても重要でエキサイティングな時代に、日本のアート、ことにGWが重要だとテオに語っている。私の知っている限り、この手紙がヨーロッパの芸術家の中で最初に北斎に言及した言葉だと思います」
ゴッホが示した「日本愛」。その中心には北斎がいたのだ。ティムはこう続ける。
「ゴッホは北斎について2つのことを書いています。1つはその不自然な色使いについて。彼は北斎の色使いをシンボリック・カラーと言っている。ドラクロワが描く絵と対比して、海が青や緑といった不自然な色で描かれているというのです。
2つめはそのグラフィックパワー。GWについても『まるで動物を描くようだ』と言っている。他の芸術家たちも北斎を評しましたが、誰よりも先にゴッホが北斎を評価して称賛した人物です。その表現はテオとの手紙に書かれていますから、あるいはテオからのアイディアもあったのかもしれませんが――」
浮世絵の色彩と西洋の絵具との差異を、原材料の視点から研究している目黒区美術館学芸員・降旗千賀子はこう語る。
「浮世絵で使われた顔料は植物系の染料なので、ヨーロッパの絵具よりも蛍光性があります。だからヨーロッパの画家たちには、よりいっそう鮮やかに見えたのではないでしょうか。それに色は時の経過とともに退色しますから、当時はいまよりももっと鮮やかな作品だったはずです」
ティムもこう語る。
「大英博物館のGWも色が退色していますが、本来の北斎の多くの作品は、淡いイエロー、淡いグレー、そして空はもっとピンクがかっていただろうと想像しています。ニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵しているGWは、世界でも一番色がはっきりしています。作品全体で色は退色していますが、このブルーはいまも素晴しいと思います」
北斎ブルーは「人を怖がらせる色」?
「神奈川沖浪裏」でも北斎が使い、のちに「北斎ブルー」と言われることになる青は、「ベロ藍」と呼ばれたプルシァン・ブルー。当時の浮世絵界で盛んに使われた、比較的新しい顔料だった。18世紀初頭に「赤い染料をつくれ」と王に命じられたベルリンの顔料業者が偶然発見し、それまで使われていたアフガニスタン産のラピスラズリ石を原料とした高価なウルトラマリンに代わって使われるようになった科学染料だ。当初は製造方法は秘密とされていたが、約20年後にイギリスの科学者が銀や銅、鉛といった原料や動物の血の代わりに牛肉を使うなどして製造に成功し、世界的に広まった。
日本では1763年に発明家の平賀源内が最初に紹介。絵師としては、伊藤若冲が1765年頃に使ったのが最も早い事例だとされている。
北斎が「神奈川沖浪裏」を描いたのは1831年ころ。当時の清がイギリスから輸入したプルシァン・ブルーを大量に日本に輸出し始めたことから、安価で入手可能になっていた。「ベルリンの藍」がなまって「ベロ藍」と呼ばれるようになった。
―――ゴッホは今よりももっと色鮮やかな北斎の作品を見ているわけですね。
ティムに尋ねると、こう言った。
「そうです。そして手紙の中でドラクロワについて触れていますが、彼は嵐の中でキリストがボートに乗っている絵にはブルーとグリーンを使っている。ゴッホはこの色使いを『人を怖がらせるための色だ』と表現しています。北斎がGWにその色を使ったのも、同じように人を怖がらせるためだったとゴッホは考えたようです。GWにはグリーンは使われていませんが、パッションブルー、インディゴブルー、時には混ぜた色を使っています。私はこのブルーがゴッホの興味を引いたのではないかと思います。ゴッホは、北斎の絵をみるとドラクロワを思い出すと書いています。ただし―――」
ティムは続けた。
「ゴッホはアルルにいるときは北斎の絵を持っていかなかったのではないかと思います。記憶だけで書いたのではないか。彼が浮世絵をアルルに持って行ったのかどうか、とても興味があります」
ゴッホは、一説には約500点もの浮世絵を所有していたという。パリの馴染みのカフェで浮世絵展を開いたこともある。周知のように生前のゴッホは赤貧のどん底にいたから、それらは画商だったテオのお金で購入したものだったはずだ。ゴッホはそれを友人の画家たちに転売していたとも言われている。手紙にも、テオに浮世絵を購入するように仕向ける表記がある。
「ビング(※日本美術を扱っていたパリを代表する画商)のところには屋根裏部屋があって、そこに無数の風景や人物の版画がうんとある(※他の翻訳では「1万点以上ある」)。(中略)君がどうしてモンマルトル通りに美しい日本のものをおいておかないのか、それがぼくにはわからない。
(中略)お蔭でぼくは落ち着いてゆっくりたくさんの日本画を見ることができた。君の部屋も、いまみたいにいつまでも日本画なしではいられないよ。今のところ版画は一枚3スーで手に入る。だから90フラン払っておけば、別に100フラン分で、今あるものの外に新たに650点の版画ストックができることになる」(ゴッホの手紙、中、第510信)
明治末期で1フランは約40銭。するとゴッホが言う版画の価格は約1.2銭となる。当時は上等の職人の手間賃が25銭、新聞代が一部1銭5厘だったというから、浮世絵の値段はおよそ新聞一部程度だったようだ。意外に安いという感じもするが、浮世絵は絵師や絵の種類、摺りの状態等で価格は大きく異なる。
後述する、日本美術愛好家で文豪でもあったエドモン・ド・ゴンクールは、年間に3万フランも日本美術を買ったと言う。日本円にすると約1万2000円。米一石が2円90銭から3円60銭だった時代、現在の米一石(100升、約150キログラム)が4万5000円(10キロ3000円として概算)とすると、約1億5400万円となる。浮世絵の良品、希少な高級品は数百フランしたというのも頷ける数字だ。
ゴッホが浮世絵を求め始めたのはパリで生活した1880年代末。その後ルーブル美術館の東洋部門が新設されたり、ジャポニスムが富裕層にも広がったりしたために、浮世絵の価格は高騰した。作品により価格はピンキリだし、わずかな時代の差でも価格は大きく異なったのだ。
知られざる北斎

長澤まさみさんが主演する映画『おーい、応為』が話題です。
モネ、ゴッホを魅了し、西洋で「東洋のダ・ヴィンチ」と称された葛飾北斎。
その名を世界に広めた画商・林忠正、そして晩年を支えた小布施の豪商・髙井鴻山。芸術と資本、江戸と西洋が交錯する中で創作に生きた画家の生涯を描いた書籍『知られざる北斎』もあわせてお楽しみください。本書から一部を抜粋してお届けします。
- バックナンバー
-
- ゴッホを魅了した北斎の「不自然な色使い」
- 「8000枚売れても印税ゼロ」北斎を支え...
- 作品数は約3万4000点!画狂老人・北斎...
- 時は明治。東大のエリートはパリへ渡った
- シーボルトは北斎に会ったのか?
- 「国賊」と蔑まれ…天才画商の寂しい晩年
- オルセー美術館の奥に佇む日本人のマスク
- 80すぎたお爺ちゃんが250kmを歩いて...
- 江戸時代に「芸術」はなかった!? 欧米輸...
- 世界中があの波のことは知っている
- 新しい感性はいつの時代も叩かれる
- ロダンが熱狂した日本初の女優
- 美を通して日本を飲み込もうとした西洋資本...
- モネと北斎、その愛の裏側
- モネの家は「日本愛」の塊だった
- 2017年最大の謎、「北斎展」
- 唐辛子を売り歩きながら画力を磨いた
- 天才・葛飾北斎が歩んだ数奇な人生 その(...
- 「考える人」のロダンは春画の大ファンだっ...
- ジャポニズムが起きていなければ「世界の北...
- もっと見る