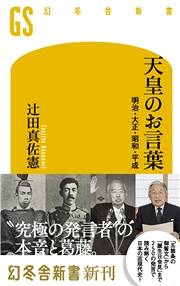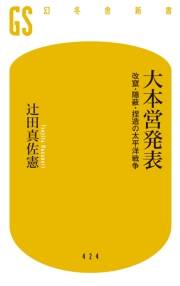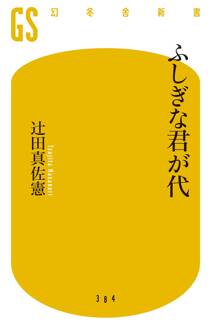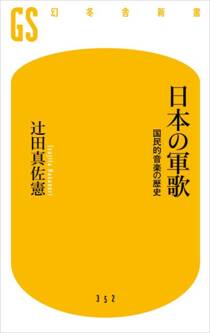近代国家となった明治以降、天皇の発言の影響力は激増した。では、1945年8月15日の終戦、敗戦への責任、神格化の否定……に天皇は実際どんな言葉を残してきたのか? 近現代史研究者の辻田真佐憲さんが250の発言を取り上げ、読み解く『天皇のお言葉 明治・大正・昭和・平成』より一部を抜粋してお届けします。

「単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず」
(昭和21・1946年)
明けて1946年の元旦。天皇は有名な詔書を発表した。今日「人間宣言」として知られるものである。ただし、天皇の意図は別のところにあったため、ここでは「新日本建設に関する詔書」と呼んでおく。
茲に新年を迎ふ。顧みれば明治天皇、明治の初、国是として五箇条の御誓文を下し給へり。曰く、
一、広く会議を興し、万機公論に決すべし。
一、上下心を一にして、盛に経綸を行ふべし。
一、官武一途庶民に至る迄各其志を遂げ、人心をして倦まざらしめん事を要す。
一、旧来の陋習を破り、天地の公道に基くべし。
一、智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし。
叡旨公明正大、又何をか加へん。朕は茲に誓を新にして、国運を開かんと欲す。須らく此の御趣旨に則り、旧来の陋習を去り、民意を暢達し、官民挙げて平和主義に徹し、教養豊かに文化を築き、以て民生の向上を図り、新日本を建設すべし。
大小都市の蒙りたる戦禍、罹災者の艱苦、産業の停頓、食糧の不足、失業者増加の趨勢等は、真に心を痛ましむるものあり。然りと雖も、我国民が現在の試煉に直面し、且徹頭徹尾文明を平和に求むるの決意固く、克く其の結束を全うせば、独り我国のみならず、全人類の為に、輝かしき前途の展開せらるることを疑はず。
夫れ家を愛する心と国を愛する心とは、我国に於て特に熱烈なるを見る。今や実に此の心を拡充し、人類愛の完成に向ひ、献身的努カを効すべきの秋なり。
惟ふに長きに亘れる戦争の敗北に終りたる結果、我国民は動もすれば焦躁に流れ、失意の淵に沈淪せんとするの傾きあり。詭激の風漸く長じて、道義の念頗る衰へ、為に思想混乱の兆あるは、洵に深憂に堪へず。
然れども朕は爾等国民と共に在り、常に利害を同じうし休戚を分たんと欲す。朕と爾等国民との間の紐帯は、終始相互の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず。天皇を以て現御神(あきつみかみ)とし、且日本国民を以て他の民族に優越せる民族にして、延て世界を支配すべき運命を有すとの架空なる観念に基くものにも非ず。
朕の政府は国民の試煉と苦難とを緩和せんが為、あらゆる施策と経営とに万全の方途を講ずべし。同時に朕は我国民が時艱に蹶起し、当面の困苦克服の為に、又産業及文運振興の為に勇往せんことを希念す。我国民が其の公民生活に於て団結し、相倚り相扶け、寬容相許すの気風を作興するに於ては、能く我至高の伝統に恥ぢざる真価を発揮するに至らん。斯の如きは、実に我国民が人類の福祉と向上との為、絶大なる貢献を為す所以なるを疑はざるなり。
一年の計は年頭に在り、朕は朕の信頼する国民が朕と其の心を一にして、自ら奮ひ自ら励まし、以て此の大業を成就せんことを庶幾ふ。
そもそもこの詔書は、GHQの発案で作られた。前年12月に神道指令で国家神道を否定したGHQは、今度は天皇の言葉で、その神格をみずから否定させようと考えた。
そのため詔書の原案は、GHQ民間情報教育局のダイク局長やヘンダーソン同局員、また学習院の山梨勝之進院長や同英語教師のブライスたちによって、英語で作成された。そしてその後、日本政府に委ねられ、幣原(しではら)喜重郎首相、前田多門文相、次田大三郎内閣書記官長などによって調整が行なわれた。
この過程で、英語草案の「日本人は神の子孫ではない」という箇所が、「天皇は現御神(現世に姿をあらわした神)ではない」に書き換えられた。
なぜそんなことになったのか。それは、「天皇が神の子孫である」ことを否定しないためだった。「日本人が神の子孫ではない」とすると、「(日本人のひとりである)天皇まで神の子孫ではない」となりかねない。それでは、天皇は一般人と変わらなくなってしまう。そこで天皇や側近は、「天皇は現人神ではない」とすることで、もとの意味を巧妙に書き換え(つまり天皇が神の子孫である可能性を残し)、神話と伝説の温存を図ったのである。
そうすると、「朕と爾等国民との間の紐帯は、終始相互の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず」という重要な箇所は、つぎのように整理することができるだろう。
戦前・戦中:神話と伝説
戦後:信頼と敬愛(+神話と伝説)
戦前・戦中、天皇と臣民の結びつきは「神話と伝説」で説明された(たとえば、文部省編『国体の本義』の、「臣民の道は、皇族瓊瓊杵(ににぎ)ノ尊の降臨し給へる当時、多くの神々が奉仕せられた精神をそのまゝに、億兆心を一にして天皇に仕へ奉るところにある」など)。これにたいして戦後、天皇と国民の結びつきは、もっぱら「相互の信頼と敬愛」で説明されることになった。ただし、このときも「神話と伝説」が完全に排除されたわけではなく、天皇の神話的な位置づけは部分的に温存された。
これに加え、もう一計が案じられた。天皇は、この詔書に「五箇条の御誓文」の主旨を挿入することを希望した。そうすることで、民主主義が占領軍によって押し付けられたものではなく、もともと明治天皇によって採用されたものだと示そうとしたのである。
天皇にとって、神格否定よりもこの「五箇条の御誓文」のほうが重要だったという。1977年8月、天皇は記者に質問されてこう答えている(高橋紘『陛下、お尋ね申し上げます』)。
そのこと[「五箇条の御誓文」の挿入]についてはですね、それが実はあの時の詔勅の一番の目的なんです。神格とかそういうことは二の問題であった。
それを述べるということは、あの当時においては、どうしても米国その他諸外国の勢力が強いので、それに日本の国民が圧倒されるという心配が強かったから。
民主主義を採用したのは、明治大帝の思おぼし召めしである。しかも神に誓われた。そうして「五箇条御誓文」を発して、それがもととなって明治憲法ができたんで、民主主義というものは決して輸入のものではないということを示す必要が大いにあったと思います。
それでとくに初めの案では、「五箇条御誓文」は日本人としては誰でも知っていると思っていることですから、あんなに詳しく書く必要はないと思っていたのですが。
幣原がこれをマッカーサー司令官に示したら、こういう立派なことをなさったのは感心すべきものであると、非常に賞讃されて、そういうことなら全文を発表してほしいというマッカーサー司令官の強い希望があったので全文を掲げて、国民及び外国に示すことにしたのであります。
第一章でみたとおり、「五箇条の御誓文」はここまで理想的な内容ではなかった。ただ、漠然としたものだったので、マッカーサーが評価するぐらい再解釈の余地があった。
天皇は同じ記者会見でこうも述べている。
そして、日本人の誇りを日本の国民が忘れると非常に具合が悪いと思いましたから。日本の国民が日本の誇りを忘れないように、ああいう立派な明治大帝のお考えがあったということを示すために、あれを発表することを私は希望したのです。
この言葉に違わず、「五箇条の御誓文」はこれ以降、日本の民主主義の証・伝統としてたびたび参照されることになった。GHQさえもある意味手玉に取ったわけで、天皇や側近たちのやり方はじつに鮮やかだった。
天皇のお言葉の記事をもっと読む
天皇のお言葉
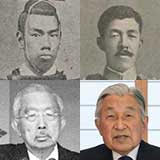
明治・大正・昭和・平成の天皇たちは何を語ってきたのか? 250の発言から読み解く知れれざる日本の近現代史。
- バックナンバー