
生き方
子供の頃から大好きだったのは山口百恵さん。
寝ても覚めても百恵ちゃんが好きで好きで、当時テレビを録画する機械などはなかったけど、彼女の出演する歌番組やドラマをテープレコーダーで録音して、歌や台詞を必死で覚え、繰り返し真似をしていました。
当時の私はいつかきっと百恵ちゃんみたいになれると信じていたのです。
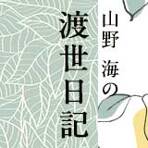
4歳(1969年)から子役としてデビュー後、バイプレーヤーとして生き延びてきた山野海。70年代からの熱き舞台カルチャーを幼心にも全身で受けてきた軌跡と、現在とを綴る。

日々更新する
多彩な連載が読める!
専用アプリなしで
電子書籍が読める!

おトクなポイントが
貯まる・使える!

会員限定イベントに
参加できる!

プレゼント抽選に
応募できる!