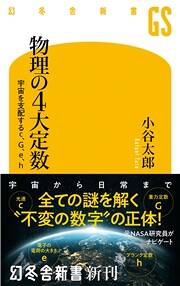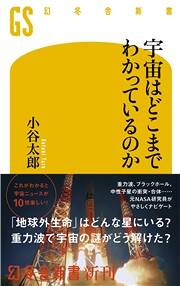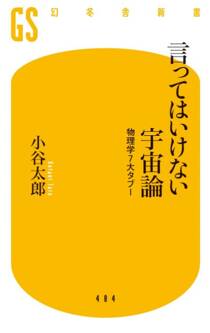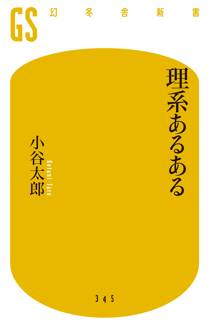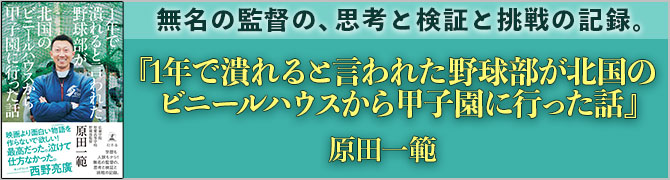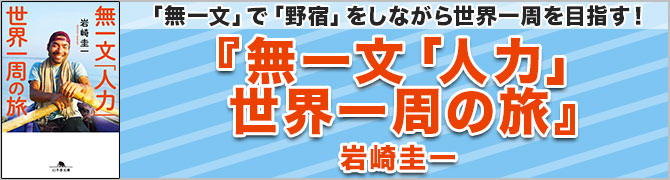光速c、電子の電荷の大きさe、重力定数G、プランク定数h。
宇宙を支配する物理の4大定数を、NASA元研究員の小谷太郎氏がやさしく解説。
ガリレオ・ガリレオの時代に人類が挑んだ光速測定実験の結果とは……!?
* * *

ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
* * *
宇宙の謎を4つの数字で解く『物理の4大定数 宇宙を支配するc,G,e,h』(小谷太郎氏著、幻冬舎新書)好評発売中!
物理の4大定数の記事をもっと読む
物理の4大定数

光速c、電子の電荷の大きさe、重力定数G、プランク定数h。この4つの物理定数は、宇宙のどこでいつ測っても変わらない。宇宙を今ある姿にしているのは物理の4大定数なのである。
宇宙を支配する数字の秘密を、NASA元研究員の小谷太郎氏がやさしく解説する。
- バックナンバー
-
- 『シン・ウルトラマン』の宇宙「プランクブ...
- 『シン・ウルトラマン』と超巨大ブラック・...
- 電子の波動関数が表わすものはなんなのか【...
- eの値が変わると宇宙は大爆発する【再掲】
- 一般相対性理論を超わかりやすく解説します...
- 光速が遅いなら宇宙はどんな姿になるのか【...
- 4大定数はどうして「偉い」のか【再掲】
- cとGとeとhの描きだす宇宙
- 太陽の数万倍もの巨星爆誕!?プランク定数...
- 自然単位系が宇宙の謎を解く日
- この世の情報の最小単位、それはプランク定...
- 波動関数の観測問題が腑に落ちる、ある解釈
- そもそも量子とはいったい何なのか?
- プランク定数は考案者にも謎の定数だった
- 真空は人類がまだ知らない素粒子まで知って...
- 華麗なる素粒子の一族には未知のメンバーが...
- 映画『テネット』の元ネタ?ふしぎな物理現...
- 奇想の人ディラックの予言どおり陽電子が見...
- 電磁気学が失われたら現代文明は即死する
- 物理ぎらいを大量発生させたフランクリンの...
- もっと見る