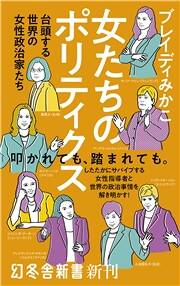2025年、ついに日本でも女性首相が誕生することになりそうです。そんな時の人である自民党新総裁・高市早苗氏は「目標は『鉄の女』」と明言し、英国のマーガレット・サッチャーを目指していると言います。果たして、サッチャー首相とはどのような人物だったのか。ブレイディみかこさん著『女たちのポリティクス』から紐解きます。
二重の意味でアウトサイダー
マーガレット・サッチャーという人ほど、日本国内で読み聞きしていた評価と、英国に来てからのそれが違った政治家はいなかった。
日本では、サッチャーは「英国病から英国を救った偉い人」みたいなイメージで語られることが多く、「鉄の女」という彼女の呼称も、グローバル・ジェンダー・ギャップ指数ランキングで153カ国中121位の国にしては、「信念を曲げないリーダー」としてポジティヴに受け取られている。
ひょっとすると、日本の人々は英国の人々よりも、頼れる強い指導者としての女性像を素直に受け入れるのではないかという気さえする。それが日本人女性でない限りにおいては。
まあもちろん、これはジェンダーだけの問題ではなく、彼女が掲げた新自由主義的政策のエッセンス(働かざる者、食うべからず。成功は自分で摑め、摑めないのは自己責任)が日本の人々の気質に合っているからかもしれないが。
そのサッチャーは、いまでこそ保守党を代表する伝説的アイコンになっているが、実は保守党政治家の中ではアウトサイダー中のアウトサイダーとして登場した。
まず、女性であること。そして出自も他の保守党政治家とはまるで違った。
保守党と言えば、イートン校だのハーロウ校だのといった名門私立校を卒業した良家のお坊ちゃんたちが集う政党だ。しかし、サッチャーは庶民の出である。リンカンシャー州グランサムで生まれ、父は食料品と日用品を扱う店を営み、グランサム市長も務めたことがある地元の名士の一人。つまり、彼女はちょっと成功した市井の人の娘という立場で育った。
地元のグラマースクール(公立進学校)に通った街の商店の娘がオックスフォード大学で化学を学ぶというのは、当時の英国社会ではそうある話ではなく、しかもその女性が保守党議員になるというのは、おそらく現在でも珍しい話だ。つまり、彼女は保守党の中の「地べた派」だったのである。けっして党の主流派ではなく、二重の意味でのアウトサイダーだった。
BBC2のドキュメンタリー『Thatcher:A Very British Revolution』の中で、第一次サッチャー内閣で環境大臣を務めたマイケル・ヘーゼルタインがこんなことを語っている。
「僕はこう思う。彼女はある社会的階層から出てきた。経済的な成功で一段梯子を上った、成功したばかりの人々に関連付けられている性質はたくさんある。寛容性のない人は不寛容なままだし、梯子のさらに上のほうに上っている人たちへの懐疑心もある。頑迷さや、我々が暮らしている社会の本質に関するやや単純過ぎる解決法も。そして彼女は大学に行って素晴らしい学位を得た。彼女は優秀な頭脳を持っている。だから、つまりこれら二人のサッチャーがいたのだ。一人は同じ特徴を持つ集団の類型に準拠するサッチャー。もう一人は知的で、その類型を超越するサッチャーだ」
貴族の家柄という、いかにも保守党らしい階層から出てきたヘーゼルタインには、サッチャーはこう見えていたということだろう。成り上がった庶民特有の頑迷さや不寛容さや単純さはあったが、それを超えるインテリジェンスもあったと言っているのだ。上から目線もいいところである。このような保守党のエスタブリッシュメントたちの中で、しかも女性であるというハンディを背負って、サッチャーは党内主流派への戦いを挑んだ。
敵と戦うことでのし上がるポピュリズム
近年、何かと話題になるポピュリズムだが、英国でこの言葉が語られるとき、「そもそも、サッチャーがポピュリストだったよね」というようなことがよく言われる。実際、スチュアート・ホールなどの左派の知識人たちは、サッチャリズムを権威主義的ポピュリズムと呼んでいたし、米国のトランプ大統領やハンガリーのオルバン首相が登場する前から権威主義的ポピュリズムという言葉はあった。
ポピュリズムには共通の特徴がいくつか存在するが、勢力を拡大するためには重要な二つの条件があると言われている。一つ目は、それが主流派ではなく、アウトサイダーから出てきたムーヴメントであること。そして二つ目は、「敵VS味方」のわかりやすい構図をつくって、敵を攻撃し続けることで勢いを増していくということだ。
トランプがわかりやすい例で、彼は政治経験や軍隊経験のない米国史上初の大統領であり、「既成政治のアウトサイダー」的な立場を売りにしてきた。さらに、リベラルや移民、中国などの敵を次々と設定し、リベラルの欺瞞を攻撃したり、壁を打ち立てると言ったり、貿易戦争をしかける発言をしたりして、それまでの政治にうんざりしていた人々に溜飲を下げさせてきた。
これはサッチャーが登場したときの姿にも似ている。エスタブリッシュメントの男社会である保守党の議員となったサッチャー(そもそも選挙区で保守党の公認候補にしてもらうだけでも涙ぐましい苦労をしており、そのあたりはアンドレア・ライズボローがサッチャーを演じたBBCドラマ『The Long Walk to Finchley』に詳しい)が、女性&庶民の出というダブル・ハンディを持ちながら党首の座を勝ち得たのも、選挙に敗けたのにいつまでも辞めない前党首(エドワード・ヒース)をなんとか引きずりおろそうとした保守党内の一派の画策のせいだった。
『Thatcher:A Very British Revolution』で、彼女が党首になったのは「アクシデントのようなもの」と話した保守党関係者もいる。要するに、前党首への反感を糧にしてサッチャーは新党首になったのだ。
さらに、彼女が首相になったのも、それまでの労働党政治への人々の反感を利用し、徹底的に「労働組合と社会福祉国家」を敵視したからだ。ときは、公共サービスのストライキが頻発し、街には回収されないゴミが溢れ、人々の不満が高まっていた頃だった。これは財政危機に陥った英国で、労働党政権がIMFの救済を受け、その代償として公共支出を大幅に削減することに同意し、いわゆる緊縮財政を始めたので労働者たちの怒りが爆発したためだった。
労働者たちを代表する政党だったはずの労働党がIMFに同意したことで、1945年発足のアトリー政権以来の労働党の福祉国家路線は間違っていたのだという攻撃材料を保守党に与えることになった。公共支出を抑え、国民は国に頼るのではなく、自己責任で生きて行かなければ国は衰退し、経済成長もしなくなるという保守党のレトリックは、サッチャーの「社会などというものは存在しない」という言葉に集約されている。
しかし、面白いことにこのサッチャーの主張は、当初、労働者階級の人々に支持された。セリーナ・トッド著『ザ・ピープル イギリス労働者階級の盛衰』で、もとは労働党支持者だったが1979年の選挙では保守党に鞍替えしたという男性が「自分を助けるためには自助をせよというメッセージが好きでした。……わたしは組合があまりにも力をもちすぎたと感じていました」と証言している。
何かがうまく行っていないとき、そのうまく行っていない理由としてみんなが納得しそうな敵を設定し、それを激しく叩きまくる。生活に不満や不安を抱えていればいるほど、誰かや何かを叩くことでスカッとできる人は多い。サッチャーは「福祉国家をぶっ叩く」ことでのし上がっていったのだ。
フェモナショナリズムへの伏線
『Thatcher:A Very British Revolution』を見ていて、非常に印象に残ったのは、中高年の女性たちがサッチャーに熱狂する姿だ。とくに、一般家庭の主婦のような保守的なファッションの女性たち。「あ、あそこにいるわ」「え、どこどこ?」と言って、ストリートで一目サッチャーを見ようと集まった女性たちの様子が撮影されている。
これを見て、ふと思った。70年代といえば、インテリ層の女性たちはロンドンを中心に精力的にフェミニズム運動を展開していたし、60年代に広まったヒッピー文化や、パンクの登場で抵抗のユース・カルチャーが盛り上がった時代である。この頃、いわゆる家庭にいるお母さんたちはどうしていたのだろう。進取のカルチャーにかぶれて奔放になり始めた子どもや、福祉国家が機能していた時代が忘れられず家で愚痴ばっかり言っている労働者の夫。子どもには古くさい母親として軽視され、夫には家政婦のように扱われていた女性たちは、
「どんな女性でも、家庭を切り盛りすることの諸問題がわかる人は、国を回すことの諸問題をほぼ理解できるでしょう」
というサッチャーの言葉を聞いて心中で快哉をあげていたのではないだろうか。
「26歳を過ぎた男性がバスに乗っていたら、彼は自分を落伍者だと思っていいでしょう」
この有名なサッチャーの言葉は、新自由主義ここに極まれりというような残酷な言葉だが、このような言葉が(残酷であればあるだけ)一部の女性たちを痺れさせていたのではないか。自分を取るに足らない者のように扱う男たち(夫や同僚や上司)を「落伍者」と女性指導者が斬り捨ててくれるのは気持ちいいはずだ。
そう考えれば、フェモナショナリストの原型はサッチャーにあるようにも思えてくる。敵を見つけて叩くことで支持を伸ばすタイプのポピュリズムは、右派の女性議員の「お家芸」と言えるのかもしれない。
サッチャーのように露骨に弱肉強食的な政策を取れた政治家は他にいなかっただろうとよく言われる。そしてそれはまたよく言われているような、彼女が「鉄の女」と呼ばれるほど意志が強く頑固な人だったからという、キャラクター上の問題ではないのではないか。そうではなく、彼女の残酷な政策に快感を覚えて支持していた女性層が一部(実はかなり)存在したからだとすれば、これは背筋が寒くなるホラー話ではある。
なぜホラーなのかと言えば、新自由主義に傍観者は存在できないからだ。サッチャーと一緒に負け犬を笑っていたら、自分の生活もどんどん苦しくなり、競争の激化と格差拡大によって女性の貧困化が益々進んだとすれば、うっぷん晴らしの代償に自分たちの首を絞めたとしか言いようがない。これはフェモナショナリズムが台頭する現代にも当てはまる教訓だ。女性たちは、快哉を叫びながら不幸のどん底に落ちていくような愚行は避けるべきなのである。
女たちのポリティクスの記事をもっと読む
女たちのポリティクス
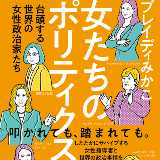
近年、世界中で多くの女性指導者が生まれている。アメリカ初の女性副大統領となったカマラ・ハリスに、コロナ禍で指導力を発揮するメルケル(ドイツ)、アーダーン(ニュージーランド)、蔡英文(台湾)ら各国首脳たち。そして東京都知事の小池百合子。政治という究極の「男社会」で、彼女たちはどのように闘い、上り詰めていったのか。その政治的手腕を、激動の世界情勢と共に解き明かした評論エッセイ。