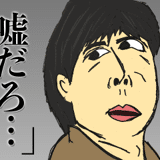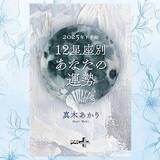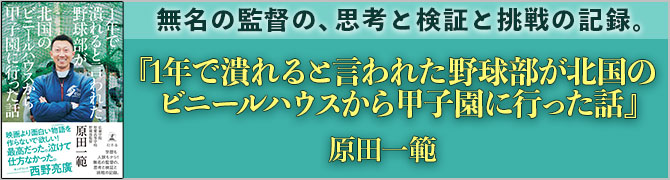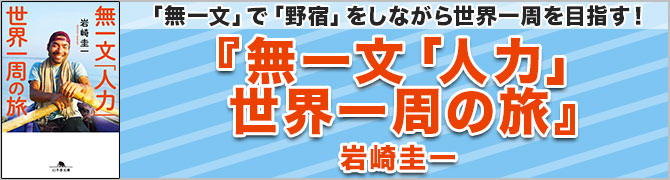毎年、書店の閉店するニュースは定期的に流れてくるが、その中でも今年は、しばし人を感慨にふけさせるような、ひとつの時代の終わりを想起させる話が多い。
具体的に言えば、一月には名古屋の七五書店の閉店があった。三月には東京駅八重洲口の八重洲ブックセンターが閉店し(この店は移転のための一時閉店)、四月は鳥取の定有堂書店、そしてこの七月末には名古屋のちくさ正文館書店本店(以下ちくさ正文館)が、その六十余年の歴史に幕を降ろした。
書店閉店のニュースが流れてくれば、それを惜しむ声、憤慨する声が、毎回決まって聞こえてくる。それを聞くのがあまり好きではないので、そうした話からはなるべく距離を置くようにしているのだが、ちくさ正文館が閉店する少し前に見かけた、店長の古田一晴さんのコメントだけは、思わず身を乗り出して読んだ。それは何というか、閉店直前の店とは思えない、あまりにも古田さんらしいコメントだったからだ。
「かつては本屋のブックフェアは特殊なことで、日本中のどこもやっていない企画をやるのがフェアだったんです。出版関係者も同業者も、どこがどんなフェアをやるのかみんな注目していた。誰それが賞をとったから著作を集めてとか、そんなのはフェアじゃないんです」
出典:Yahoo!ニュース(7月25日 文・大竹敏之)
「日本中のどこもやっていない企画」とは誇張した表現でもなんでもなくて、ちくさ正文館で古田さんが作っていた〈棚〉は、まさに日本中どこを探してもない本棚だった。
ある一つのジャンルをとってみても、本好きのあいだで話題になっている本の横に、最近発売になったが知っている人は少ない地方出版社の本が平積みされ、本棚にはある専門書版元の豪華本やニッチな特集の十年前の雑誌が、無造作に差しこまれている(それは「置くべきもの」という判断なのだろう)。一本の棚の中に、時代を画したロングセラーや少し硬めだが比較的一般向けの本、マイナーだが読むべき本、まだ評価は定まっていないがこれからのシーンを切り拓こうとする本が切れ目なく並んでおり、それはさながらそのジャンルの見取り図ともなっている。
これはご本人から何回か聞かされた話だが、古田さんはインターネットの類は一切見ないのだという。それなのに一体どこから、これだけの情報を集めてくるのだろう。
ある出版社の人によれば、新刊案内のFAXを送ると、毎回全国でも一二を争う速さで返信がくるらしい。
「あれだけ忙しい方なのに、いったいいつ見ているのでしょうね」
彼が古田さんに確認したところ、その出版社の本は注文しないと入ってこないから、毎回必ず目を通すという。そしてそうした出版社は、ほかにもゴマンとあったのだろう。FAX以外にもチラシや目録、ありとあらゆるものに目を通したのだろうし、一度価値を認めた本は、一般的な賞味期限がきたあとでも置き続けたのだと思う。
その棚ももう、いまとなっては見ることができない。
結局みなが見るものを追いかけているだけでは、同じような店がもう一つできあがるだけなのだ。人と違うことがしたければ、人が見ないもの、追いかけないものまで、細かな目配りをする必要がある。もちろん古田さんは人と違うことがやりたかったのではなく、結果的にそうなってしまったという話なのだろうが。

そんな訳で、ちくさ正文館の閉店も黙って見送る予定だったのだが、古田さんらしいコメントに呼び止められた気がして、閉店何日か前の午前中、店に電話をした――
古田さんと最初に話したのがいつか、はっきりとは覚えていないが、まだわたしが会社に勤めていたころには違いがない。そのころわたしは名古屋にいて、名古屋を離れてからもその地を訪れることがあれば、ちくさ正文館には必ず立ち寄るようにしていた。
ある時は、たまたま村上春樹がノーベル文学賞を逃した夜で、わたしが店に行くと古田さんは多くの地元マスコミに囲まれ、コメントを求められていた。わたしの姿を見つけると「よぉ」と片手をあげ、「この人にも聞いたほうがいいよ」とマスコミの方に言ったあとの話が、驚くほど本質的だった。
「彼は日本のローカリティに根差した土俗的な作品を書けば、すぐにでも受賞できるだろう。いまノーベル文学賞のトレンドがそちら側なのだから。もっとも、本人にその気があればの話だが。云々」
店の外で偶然出会うと、大抵は決まりが悪そうに素っ気なかった。Titleにも開店した年一度来てくれたことがあり、わたしが驚いて「わざわざありがとうございました」と言うと、「いや、調布で(府中だったかもしれない)歴史的な展示があったから……」と早口で言い、すぐに出ていってしまった。
――電話口の古田さんの声は相変わらずお元気そうだったが、来客が引きも切らないのだろう、さすがに疲れている様子でもあった。でもこの間には、そんな古田さんを奮い立たせたこともあったらしい。
「いや、今回はおれもさすがにやられちゃってさ。この店に人生を変えられたって人がすごく多いんですよ……。うちにあったヘンテコな本に反応してくれた人が、こんなにもいたんだねぇ」
それは古田さんにしては、珍しく神妙な声だった。
「それはもちろんそうですよ。でも古田さんがそんなことを言うの、珍しいですね」
そう話すと古田さんは、「そんな照れくさいこと言えるかよ~」と笑い、そのあと「みんな、居場所がなくなっちゃうということだからね」と続けた。
これ以上貴重な時間を割いてもらうわけにもいかないので、わたしはお礼を言って電話を切った。それからわたしは顔を洗い、手短に身支度をすませて、自分の店に出勤した。
今回のおすすめ本

『本のある空間採集』政木哲也 学芸出版社
店の実寸を測り、何色をした何段の本棚がどこにあるか、一つ一つ事実に即して描き起こしていく。それはさながら、いつまでもいることができる、もう一つの店舗空間だ。
◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS
◯2025年7月18日(金)~ 2025年8月3日(日) Title2階ギャラリー
 「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展
「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展
切り絵作家gardenの最新刊の切り絵原画展。この本は、切り絵を楽しむための作り方と切り絵図案を掲載した本で、花と動物のモチーフを用いて、5種類のアルファベットシリーズを制作しました。猫の着せ替えができる図案や額装用の繊細な図案を含めると、掲載図案は400点以上。本展では、gardenが制作したこれら400点の切り絵原画を展示・販売いたします(一部、非売品を含む)。愛らしい猫たちや動物たち、可憐な花をぜひご覧ください。
◯2025年8月15日(金)Title1階特設スペース 19時00分スタート
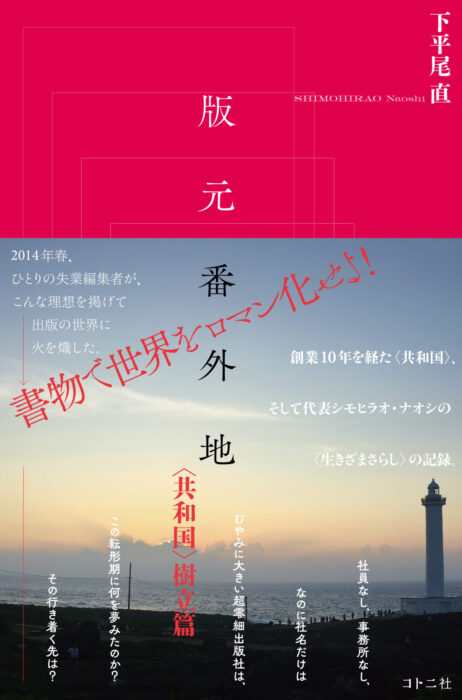 書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉
書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉
『版元番外地 〈共和国〉樹立篇』(コトニ社)刊行記念 下平尾直トークイベント
2014年の創業後、どこかで見たことのある本とは一線を画し、骨太できばのある本をつくってきた出版社・共和国。その代表である下平尾直は何をよしとし、いったい何と闘っているのか。そして創業時に掲げた「書物で世界をロマン化する」という理念は、はたして果たされつつあるのか……。このイベントでは、そんな下平尾さんの編集姿勢や、会社を経営してみた雑感、いま思うことなどを、『版元番外地』を手掛かりとしながらざっくばらんにうかがいます。聞き手は来年十周年を迎え、荒廃した世界の中でまだ何とか立っている、Title店主・辻山良雄。この世界のセンパイに、色々聞いてみたいと思います。
【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】
スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。
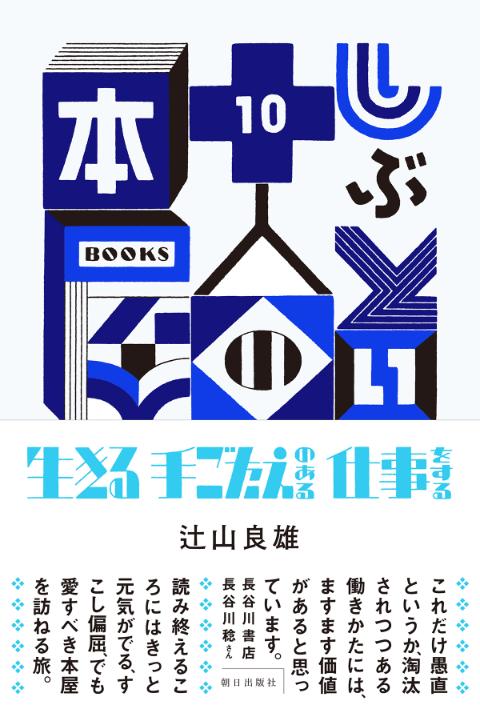 『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』
『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』
著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社
発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ
版元サイト /Titleサイト
◯【寄稿】
店は残っていた 辻山良雄
webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)
◯【お知らせ】NEW!!
〈いま〉を〈いま〉のまま生きる /〈わたし〉になるための読書(6)
「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄
今回は〈いま〉をキーワードにした2冊。〈意志〉の不確実性や〈利他〉の成り立ちに分け入る本、そして〈ケア〉についての概念を揺るがす挑戦的かつ寛容な本をご紹介します。
NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。
偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。
本屋の時間の記事をもっと読む
本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。