
社会・教養
「三十七歳で第百回芥川賞受賞。翌年の秋、パニック障害を発病し、医業、作家業ともに中断せざるを得ない事態に陥った」
このような前歴を、著者はまるで前口上のように、エッセイにおいて度々語る。ときに小説においても、登場人物に作家自身の置かれた状況を重ね合わせる。医師であるという重責を担う職業につきながら心の病が持ち出されるためか、その行間からは常にそこはかとない暗さが漂ってくる。とはいえ、気が滅入るものではない。読み終えて、ふっ、と口から漏れたため息とともに、いくぶん身体が軽くなった気がする。そして気づいた時には、後戻りができなくなっていた。その文章の「闇」の虜になってしまったかのように、わたしは南木作品に魅せられている。
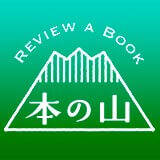

日々更新する
多彩な連載が読める!
専用アプリなしで
電子書籍が読める!

おトクなポイントが
貯まる・使える!

会員限定イベントに
参加できる!

プレゼント抽選に
応募できる!