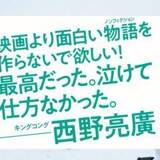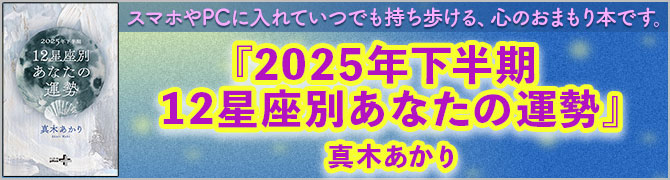映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」が9月20日から全国ロードショーになります。監督・呉美保さん、主演・吉沢亮さん、脚本・港岳彦さんのタッグとなる本作は、作家でありエッセイストである五十嵐大さんの自伝的エッセイ『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が原作。映画公開に向けて、本書から試し読みを再掲します。ろうの両親の元に生まれた「聴こえる子ども」だった幼少期から振り返ります。
* * *
──最近、友達来ないね。
母にそう訊かれるたび、言いしれない居心地の悪さを覚えるようになった。
Yくんの一件(※編集部注:前回記事をご参照ください)があってからというもの、ぼくは友人を自宅に招待できなくなってしまった。もしも、また母の喋り方を笑われてしまったらどうしよう。きっとうまくやり過ごすことはできない。
──うち、ゲーム少ないし、友達んちに遊びに行った方が楽しいから。
──そう? また連れてくるときは教えてね。
母の問いかけをなんとか誤魔化す。母はぼくがなにを考えているのか気づいていないのだろう。なんだか悪いことをしているような後ろめたさが、胸いっぱいに広がっていく。
同時に、よその母親とぼくの母とを比較するようにもなっていった。
どこの家に遊びに行っても、みんなやさしい笑顔で迎えてくれる。なかにはぼくの名前を覚えてくれて、親しみを込めながら話しかけてくれる母親もいた。
「大ちゃん、いつもうちの子と遊んでくれてありがとうね」
「大ちゃん、せっかくだから夕飯も食べていかない?」
「大ちゃん」「大ちゃん」「大ちゃん」
名前を呼んでもらえるのはうれしい。けれど、そのたびに、母はこんな風にはっきりとぼくの名前を呼ぶことができないのだ、と痛感する。いくら記憶を探ってみても、「大ちゃん」と明瞭な発音で、母から呼ばれたことがない。
「あいちゃん」
母はぼくをこう呼んだ。だいちゃん、とは呼べない。それがずっと“ふつう”だったのに、Yくんに指摘されたことで、ぼくと母の“ふつう”は、もはやふつうではなくなってしまった。
ふつうではないということは、まだ狭い世界で生きる子どもにとって恥ずかしいこととイコールだ。周囲と足並みを揃え、一ミリもはみ出すことなくいたい。悪目立ちしてしまえば、馬鹿にされ、いじめにもつながりかねないことを知っていた。
だから、徐々に母の存在を隠すようになっていった。
クラス替えから数カ月後のことだった。帰りの会で、教師がプリントを配った。
「前からまわしてね~」
前の席の子がまわしてくれたプリントの束から一枚抜き取り、それをまた後ろの席の子にまわす。わら半紙のプリントには手書きの文字で「授業参観のお知らせ」と書いてあった。
新しいクラスになり、一人ひとりがようやく馴な染じんできたタイミングで、家族に授業風景を見学してもらおうという狙いがあるらしい。
途端に教室中が騒がしくなる。
「げ~! 母ちゃん来るの?」
何人かのクラスメイトは嫌がる素振りを見せていたけれど、それが本心ではないことはすぐわかった。頬を緩め、茶化すように騒いでいる。学校に母親が来るということが照れくさい反面、うれしくもあるのだろう。
「はいはい、静かに~! プリント、ちゃんとおうちの人に渡してね」
でも、みんなのようにはしゃぐ気持ちになれなかった。学校に母を呼ぶ。それは恐怖にも近いことだった。
その日はいつもよりも遠回りをして帰った。「一緒に帰ろう」という友人からの誘いを断り、たったひとりで学校を出た。
どうすればいいんだろう。
母が授業参観に来たら、笑われるかもしれない。耳が聴こえないせいでオロオロしている母。それを見て、クスクス笑い出すクラスメイトたち。なにもできず、固まっているぼく。どんなに頭を振っても、最悪のシーンばかりが次々に浮かんでくる。
どうすれば、母が笑われずに済むんだろう。それは宿題よりも難しい問いで、いくら考えても答えなんて出なかった。
学校から自宅までの道のりを逆に進んでいくと、港が見えてくる。朝方は漁師で賑わっているそこも、放課後になると閑散としている。そこをトボトボ歩きながら、あらためてプリントを広げてみた。
授業参観のお知らせ。その文字を賑わすように、星マークや動物のイラストがちりばめられている。当日の教室にはきっと、心温まるような空気が流れるのだろう。でも、いくら想像しても、そこで笑っている自分自身が浮かんでこなかった。
プリントを手に取り、端から少しずつ破いていった。原型を留めないほどビリビリに破ると、それを海に向かって投げ捨てた。海から吹く強い風に乗ると、紙吹雪のように舞い、散っていった。手を広げてみると、指先はインクで真っ黒に汚れていた。
結局、母は授業参観に来なかった。当たり前だ。ぼくが知らせていないのだから。
ところが、後日、母がそれに気づいてしまった。
──こないだ、授業参観あったの? なんで教えてくれなかったの?
近所の人の話で授業参観があったことを知った祖母から聞いたのだろうか、母は眉み間けんに皺しわを寄せてぼくを見ている。そんな大切なことをどうして隠していたのだと、責めるような表情をしている。
どうして叱られなければいけないんだ。母が傷つかないように、馬鹿にされないようにと考えて出した結論なのに、ぼくが悪いのだろうか。
そんな想いをうまく伝えることができなかった。
──お母さんには来てほしくなかったから……。耳が聴こえないから、学校には来ないでほしいの。
そう言うだけで精一杯だった。その言葉の裏側にはさまざまな感情が潜んでいた。でも、幼いぼくには、胸の内を正確に伝えるだけの術すべがなかった。
きっとそれは間違いだったのだろう。
ぼくの言葉を理解した母は、とても傷ついた表情を浮かべていた。けれど、瞳を潤ませたまま「わかった」と頷き、それ以上なにも言わなかった。
ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと

耳の聴こえない親に育てられた子ども=CODAの著者が描く、ある母子の格闘の記録。
- バックナンバー
-
- マジョリティが「ちゃんと傷付く」ことが社...
- 聴こえない親に、いじめられていることを相...
- 息子の「声」を聴きたくて、母は補聴器を買...
- 「親が障害者だから、僕を犯人扱いするので...
- 聴こえない親ともっと話せるようになりたく...
- 親に、授業参観や運動会に来ないで欲しいと...
- 耳の聴こえない母の喋り方を笑われてしまっ...
- 聴こえない母はおかしいのかもしれない
- コーダのぼくは、耳の聴こえないお母さんを...
- コーダとして生まれ、生きてきた。「普通じ...
- 知ること、それ自体が救いになる 文庫『ぼ...
- まずは知ってもらうこと。そこに希望を込め...
- 障害のある家族と、生きる、書く
- 読み終えて影が差しました。けれど、光も差...
- 齋藤陽道さま 苦しいときは思い出してくだ...
- 五十嵐大さま 「手話で子育てする、ろう当...
- 齋藤陽道さま ぼくの本はろう親である齋藤...