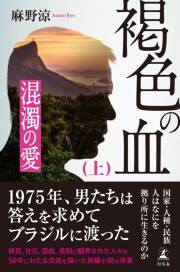差別と分断がはびこる世界で"共生”を模索して生きた人々を描いた長編小説『褐色の血』。
ついに『褐色の血(下) ヘイト列島』が発売されました。
上巻冒頭、1975年の東京国際空港の場面から始まった物語は、はたしてどんな結末を迎えるのか。
完結編である本書の発売を記念して、全5回にわたり第一章、第二章を特別公開します。(#1から読む)
* * *
「僕は母親のテレーザ一人の手で育てられた。僕はどこで生まれたのかも正直に言えばわからない。多分、母親の生まれ故郷ベレンではないかと思う」
トニーニョの出生届が提出されたのは母親がサンパウロに出てきた一九七四年のことで、この年にトニーニョはすでに二歳になっていた。何故、出生届の提出が遅れたのか。考えられるのは、そうした手続きをしなければならないことさえも、そしてその方法も、テレーザ自身、そして周囲の者が知らなかったからだろう。ブラジルの貧困家庭に生まれた者の中には、そうした子供は珍しくなかった。
「ベレンの祖父母、母の兄弟姉妹の話を一度も聞いたことがないんだ」
テレーザはベレンで暮らしていた頃の話をするのを極端に嫌がった。昔の話を聞こうとすると、急に不機嫌になるのを子供ながら感じていた。
「傷つけるようで、母親の子供の頃や、サンパウロに出てきた経緯は何も聞いていない。僕がどうして生まれたのか、父親が誰なのか、僕はそれさえも知らないんだ」
喉が渇く。いや熱い。そして痛い。
トニーニョが生まれたのはテレーザが十八歳の時だった。
「おそらく母は望まぬ妊娠で僕を出産したのだと思う」
次の言葉が出てこない。どう話せばいいのだ。大聖堂を訪れる観光客や、祈りにやってきたカトリコたちのざわめきも、高さ六十五メートル、直径二十七メートルの巨大なドームにすべてが吸い込まれ、トニーニョには水底に沈んだような静けさしか感じられない。

「母はベレンで家族の生活を支えるためだったのか、あるいは自分が生きていくためだったのか……」
言葉が途切れた。何度も深呼吸を繰り返したが息苦しい。
「男に抱かれ、それを生業にしていたんだ……」
トニーニョは正面のキリスト像を見つめたままだ。横を振り向く勇気はない。
「サンパウロに出てきてからも、母はそれ以外の職業を見つけることはできなかったと思う。二歳の僕を抱えて、すぐに現金が手に入る仕事といえばそれしかない。母は優れた女性で学ぶ機会さえあれば、違う人生を歩めたはずだ」
トニーニョは自分が学校に通い始めると、わからないところがあると母によく質問をした。テレーザから返ってくる返事はいつも決まっていた。
「自分で考えなさい。答えは教科書を読めばわかるはずよ」
母親は一日も学校に通ったことはなかった。文字を覚えたのも、簡単な計算ができるようになったのも、学校で学んだ知識をトニーニョが復習するのを横で見ながら学んだのだ。
「母が死んだのはガンだと君には伝えてきたが、それは真実ではない。君にはウソをついてた。神の前で真実を言おう。母はAIDSだった。僕はまだ高校生だった。死期を悟った母は、僕が高校を卒業し、大学に入るのを見届けてから死にたいと、よく話していた」
高校卒業も、大学の合格も知らずに亡くなった。しかし、母の死に顔は眠っているように安らかだった。体を売るしか生きる術を知らなかった母親にも、心から愛し尊敬する男性が一人いた。その男性も母親のことを忘れずにいてくれた事実を、死ぬ三週間前に知ることができた。トニーニョにとっても、テレーザにとっても、それは救いだった。
「僕が教育学部を選んだのも、母のような人生を歩む子供を一人でも減らしたいという思いからなんだ。母も僕がそうした生き方をするのを望んでいたはずだ。君と一緒にその夢に向かって未来を歩いていきたいと思っている。神に誓う。僕はセシリアを心から愛している」
トニーニョは目を閉じ、両手を組み、心の中で再び神に祈った。
──どうか僕の思いがセシリアに伝わるように、神よ。
目を開ける勇気も、隣に視線を向けるのも恐ろしくてできない。ひたすら祈った。どれほどの時間が経過したのだろうか。トニーニョにはとてつもない長い時間に感じられた。
すすり泣く声が聞こえた。
「神様、心から感謝します。私は心から愛する男性と、同じ希望、同じ夢を持って生きていこうと思います」
トニーニョはそっと目を開けて隣を見た。セシリアも両手を組み、神に祈っていた。泣いていた。頬を流れ落ちた涙が、ブラウスまで濡らしていた。トニーニョの告白を聞き、ずっと泣いていたのだろう。
うれしくてトニーニョはセシリアを抱きしめた。
抱擁し、キスしあう恋人同士の姿など、ブラジルでは珍しくもない。しかし、周囲の視線も気にせずに、泣きながら抱き合うカップルは教会には似つかわしくないのだろう。通路から好奇な視線を向けてくる者もいたが、二人にはそんなことはまったく気にならなかった。
「ありがとう、本当のことを話してくれて。私はトニーニョを愛しているし、テレーザも愛しています」
セシリアの言葉に、トニーニョは思わず力をこめてセシリアを抱きしめた。
セシリアに真実を話したことで、あれほどアプカラナに行くのを躊躇っていたトニーニョだが、そのわだかまる思いは、日向に放り出した氷の塊が灼熱の太陽に照らされて溶けていくように、いつの間にか溶解していた。
褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」
1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。
児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。
一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。
国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。
差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。
- バックナンバー
-
- #4 人生をかけた告白…差別と分断がはび...
- #3 決心するもその一言がでない…差別と...
- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...
- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...
- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...
- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...
- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...
- #3 その一方、1970年代の日本では...
- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...
- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...
- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...
- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...
- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...
- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...
- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...
- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...