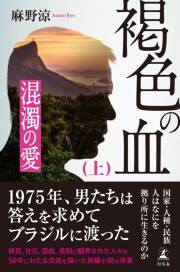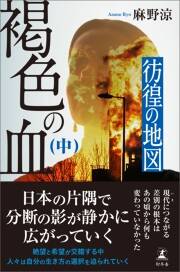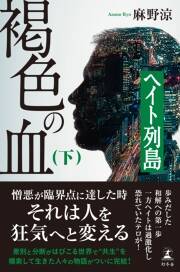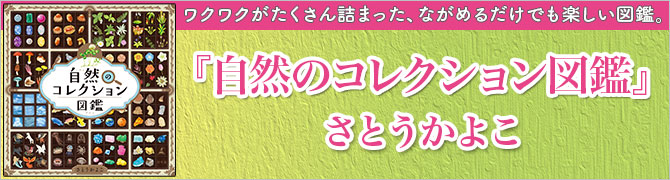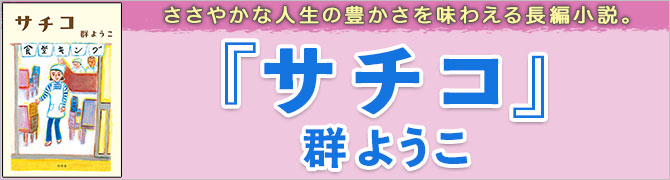ブラジルへの出発直前、意を決したように恋人との別れ告げた児玉。出発前夜2人の間に何があったのか。
『死の臓器』がドラマ化され、高橋幸春の名義でも潮ノンフィクション賞、講談社ノンフィクション賞を受賞した作家・麻野涼さんによる長編小説『褐色の血』。
その序章にあたる『褐色の血(上) 混濁の愛』の発売を記念して全5回にわたって冒頭を特別公開します。(#1から読む)
* * *
出発前夜、児玉は家族と食事をしていた。父親は国鉄の電気技術者で、長男の児玉がブラジルに行くと言ってもことさら反対はしなかった。サラリーマンの生活がどれほど味気ないものかを知り尽くしていたためか、「好きにしてみろ」とひとこと言っただけだった。母親は「苦労して大学にやったのに、地球の反対側の新聞社に就職することはないだろう」としきりに嘆いていた。
その夜、美子から電話が入った。
「明日の夜ですね、出発は」美子の声は沈んでいた。
「そうだよ」児玉は事務的な答えを返した。
「御免なさい。明日、両親の離婚裁判の判決が下る日で家庭裁判所に行かなければならないの。それで……」
「わかった。見送りはいいよ」美子の言葉を遮るように児玉は言った。
児玉は早く電話を切りたかった。それが美子にも伝わったのか、一瞬、沈黙があった。
「本当に行ってしまうんですか……」
児玉は返事をしなかった。後は美子のすすり泣く声だけが受話口から流れてきた。児玉は叩き付けるようにして受話器を置いた。そうすることによってブラジルに渡る意志の強さを美子に示そうとしたのだが、美子とそれ以上話をしていると移住の決心が揺らぐような気がしたのだ。
そんな児玉の性格を知っていて、美子が電話をかけてきたのは明らかだった。不安や孤独感に襲われると、夜中であろうと電話をかけてきた。その度に美子の自宅に駆けつけたことも一度や二度ではなかった。セックスをする関係になって二年近くになるが、それ以来深夜の電話には翻弄されてきた。ようやく美子にも、どんなに懇願しようが児玉はもう自由にならないというのがわかったようだ。泣きながら電話をかけてきたのはそれが最初だった。

すでに航空券も、サンパウロの滞在先も、すべて新聞社が手配済みだった。いまさらブラジル行きを中止するわけにはいかなかった。
「何を情けない顔をしているの。早く出国手続きをしないと乗り遅れるよ」
金子の声に児玉は我に返った。これから海外旅行をする乗客や見送りで華やいだ雰囲気の国際線送迎デッキのどこかに、美子がいるような気がして児玉はずっと彼女の姿を追い求めていたのだ。
「児玉さん、皆、もう入りましたよ。残っているのは私とあなただけです。そろそろ入りましょう」
声をかけてきたのは一緒にサンパウロに渡る移民の一人、小宮清一だった。小宮の周囲には見送りらしい人間はだれ一人としていなかった。
「見送りの方はもう帰られたんですか」
「いいえ、だれも来ていません」
気に障ったのか、小宮は一人で出国カウンターに入っていった。変わった男だと思った。
ブラジルに渡る一週間前、移民は横浜にある研修センターに集合し、移住先のブラジルやパラグアイの生活習慣や気候、風土に関する講義を受けた。夜は数人ずつ部屋に分散し、センターに宿泊した。
移民船で一ヶ月以上も船に揺られて移住した農業移民の時代は終わり、技術移民が主流で、ほとんどが独身の二十代の青年たちだった。児玉もセンターに泊まり、彼らと話す機会があった。
児玉以外の六人もサンパウロの会社に就職することになっていた。自分の持っている技術を思う存分に生かして仕事をしたいとそれぞれの夢を語り合っていた。その中の一人で、物静かな青年が移住の動機について語った。
「失恋したからブラジルにでも行ってみようと思ったんだ」
熱い口調で語り合う雰囲気の中で、唐突とも思える言葉だった。それが小宮だった。
出国カウンターに進んでいく小宮の後ろ姿を見ながら、児玉が「行ってきます」と、見送りにきてくれた仲間にもう一度、握手を求めた。
「皆、元気で。着いたら手紙を書くよ」
児玉はこう言い残して出国手続きカウンターに進み、送迎デッキに二度と視線を走らせることはなかった。出国手続きを済ませると、搭乗スポットに向かった。スポットには日航機の他にもパンアメリカン航空やキャセイパシフィック航空など世界のエアラインがライトに照らし出されていた。彼らが搭乗するのは日本航空・B747型ジャンボジェットでロサンゼルスに向かい、そこからはヴァリング・ブラジル航空でペルーのリマを経由してサンパウロに行く予定になっていた。
やがて搭乗が始まった。すべての乗客が席に着いたが、空席が目立った。若い技術移民は飛行機に乗るのが初めてなのか、窓側の空席を見つけると離陸前に移動した。
日航機は定刻通り羽田を離陸した。上昇するジャンボ機の窓から東京の夜景が見えた。その美しさに感嘆の声が上がる。しかし、児玉にはその夜景を楽しんでいる余裕はなかった。それまで抑えていた朴美子への思いが、離陸と同時に胸を小突かれたように心の中に沸き起こった。
機体が上昇を続け、日本から遠ざかるにつれて朴美子への思いはなお一層強くなっていくような気がした。深い泥沼に両足は膝までつかり、引き抜こうともがいているが、さらに身動きが取れなくなる。気持ちも沈むばかりだ。
〈これで良かった〉
児玉は自分に言い聞かせた。二、三年は日本の土を踏むことはない。時間が解決してくれる。そう思うしかはなかった。
水平飛行に移ると、食事が運ばれてきた。児玉はほとんど食事には手を付けず、ウィスキーをあおり続けた。気圧の関係か酔うのは早かった。児玉は後方の空席を三人分確保すると、肘掛けを後ろに倒して体を横たえた。
(#3へ続く)
褐色の血の記事をもっと読む
褐色の血
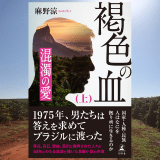
「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」
1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。
児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。
一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。
国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。
差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。
- バックナンバー
-
- #5 これからの人生をともに歩んでいきた...
- #4 人生をかけた告白…差別と分断がはび...
- #3 決心するもその一言がでない…差別と...
- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...
- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...
- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...
- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...
- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...
- #3 その一方、1970年代の日本では...
- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...
- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...
- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...
- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...
- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...
- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...
- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...
- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...