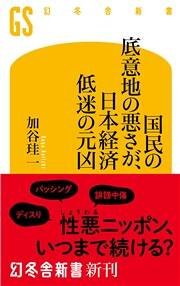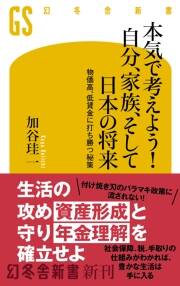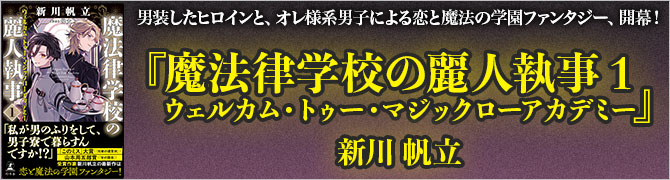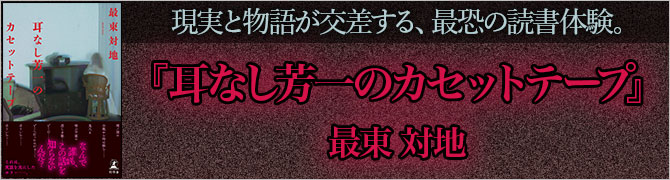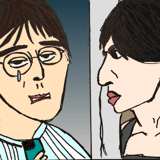
日本人の隠れた本性が景気を停滞させている! 政府系金融機関などのコンサルティングを務めた経験を持つ加谷珪一さんが、日本経済の長期的低迷を「国民性」という誰も触れたがらない視点で暴いた注目の一冊『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』。本書より一部を抜粋してお届けします。
技術大国だったはずの日本がIT後進国に
日本人の意地悪さは社会のIT化にも暗い影を投げかけています。日本は諸外国と比較してITの導入に極めて消極的なだけでなく、ITを導入しても、従来の不寛容な社会を維持しようとするメカニズムが働いてしまうのです。

コロナ対策を目的に日本政府が構築したITシステムが次々とトラブルを起こしたことや、メガバンクで大規模障害が発生したことなどから、日本はIT後進国であるという主張をよく耳にするようになりました。
実際、日本は会社の業務や学校などにおいて、もっともITを活用しない先進国のひとつとなっています。OECDの国際成人力調査によると、16歳から24歳までの若者が職場や家庭などでパソコンを利用する頻度は、OECD加盟国中最低水準です(図)。パソコン販売台数などから推定した日本のパソコン保有率は米国の半分程度ですから、職場などにもパソコンが十分に普及していない状況と考えられます。
成人が業務においてパソコンを使っていないのであれば、子どもが日常的にパソコンに触れる可能性はさらに低くなります。同じくOECDが行った生徒の学習到達度調査においても、学校や家庭でコンピュータを使える状況になっていると回答した生徒の割合は、ほとんどの質問項目において、日本は47カ国で40位以下にとどまっています。
内閣府による国際比較調査でも同じような結果が出ており、日本の13歳から19歳の子どものパソコン保有率は先進国中では突出して低く、約7割がパソコンを保有していません。
日本ではスマホが普及しているという意見も聞かれますが、ほとんど意味はありません。当然のことですが先進諸外国でもスマホが普及しており、これに加えてパソコンやタブレットも保有しているのです。個人的なコミュニケーションはスマホで、知的活動はパソコンでという使い分けが出来上がっていると見てよいですから、環境がまるで異なります。諸外国の学校教育がパソコン保有を前提としており、宿題も電子的に提出させるケースが多いという現実を考えると、この差は歴然でしょう。
菅政権はデジタル庁創設の準備を進めるなどIT政策を強化する方針を打ち出し、各府省で日常的に用いられてきたFAX利用の取りやめを検討しました。ところがあちこちから反対の声が上がり、結局、FAXを廃止することはできませんでした。
非常に残念なことですが、IT業界に詳しい人の間では、日本がIT後進国であるというのは以前からの常識でした。最近になって多くの国民が実感する形でトラブルが相次いだことから、ようやく一般社会にもその事実が知られるようになってきたわけですが、日本はなぜIT後進国になってしまったのでしょうか。
ハンコ文化に象徴される“日本的マインド”の問題
ITというのは情報技術という意味ですから、普通に考えると技術力の問題であるとイメージされると思います。では日本という国は技術という点において著しく劣っているのかというとそうではありません。最近でこそ中国などの新興国に追い抜かされる分野が増えてきましたが、技術力が高い部類に入ることは間違いないでしょう。
それにもかかわらず、なぜ日本ではITをうまく活用できないのでしょうか。その理由は、やはり日本人のマインドにありそうです。日本人の特殊なマインドがIT活用を妨げる象徴とされているのが、ハンコ文化への固執です。

菅政権は先ほどの行政IT化と同様、官民に対してハンコの利用を見直すよう要請を行いました。社内の手続きにハンコを用いている企業は多く、この手続きをIT化すれば、かなりの効率化が期待できます。ところが、一部の企業はハンコ廃止という動きに対して、驚くべき行動を取っています。
その最たるものは、「お辞儀ハンコ」を実現できるITシステムでしょう。
お辞儀ハンコとは、稟議書など複数の役職者が押印する書類において、役職が低い人ほど、ハンコに角度を付け、役職が高い人に対してお辞儀をしているように見せる押印のやり方です(図)。人間関係を常に上下関係として捉えるという日本社会の仕組みをハンコの押し方にも応用したのがこのお辞儀ハンコというわけです。
社内の手続きでハンコを用いなければいけない絶対的な理由はありませんから、菅政権の要請以前から、ハンコを廃止し、承認の手続きをシステム化しようという提案はたくさん存在していました。IT投資を行ってハンコを廃止した企業もありますが、一方ではとんでもないことが起こりました。ある企業では、ハンコを廃止すべきではないという声があまりにも大きく、画面にハンコの印影を浮かび上がらせて、あたかも押印したように見せるというITシステムをわざわざ作り上げたのです。
これでは従来と何も変わりませんし、システムを開発した分だけ逆にコストが増えてしまいます。しかも一部の企業では、これだけでは満足できず、驚くべきことに、役職によってハンコの傾きを変えるという、前述の「お辞儀ハンコ」が実現できるシステムをコストをかけて作っていたのです。
「そんなの都市伝説でしょ?」と思った方もいると思いますが、現実にシステムを開発する企業に対しては、お辞儀ハンコができるようにして欲しいという要望が寄せられており、システム会社はそうした機能を実装しています。
そもそもハンコを使用しないのであれば、ハンコの印影を画面に表示させる必要はありません。役職者の承認が必要であれば、承認ボタンを設置すれば事足ります。それにもかかわらず、わざわざコストをかけてハンコの印影を表示させ、しかも、エライ人にお辞儀をする機能まで付けさせている企業が少なからず存在しているのが現実なのです。
業務のシステム化というのはただ意味もなくITを導入するということではありません。システム化をきっかけに業務のムダを洗い出し、それを省略していくことでビジネスを効率化するという目的があります。
例えば、これまで4人の承認が必要だった稟議書も、業務の実態を丁寧に分析すれば、2人の承認で問題ないかもしれません。システム化をきっかけに業務のムダを見直すことで、企業の生産性が向上するわけですが、従来と同じことをシステムで行ってしまっては、システム費用分だけ逆にコストが増える結果になってしまいます。
これは極端なケースかもしれませんが、システム化してもムダな業務を減らせないというケースは枚挙に暇がなく、その結果として、日本企業では長時間残業が横行しているのです。特にこのお辞儀ハンコのケースは、日本人の特殊なマインドをよく表しているといってよいでしょう。
儀式的上下関係が招く非効率とその根本原因
稟議書にハンコを押すという行為には、役職者の承認欲求を満たす作用があると考えられます。これはある種の儀式ということになりますから、その行為をIT化することそのものに抵抗があるわけです。

また日本人のコミュニケーションは、相手との上下関係が基本ですから、どちらが上であるのかを確認し、上に立つ人は下の人に対して、常にマウントをとってその立場を維持しようとします。お辞儀ハンコはこうした抑圧的な日本社会の特徴を凝縮した仕組みといってよいでしょう。悲しいことに、ITを導入するという状況に至っても、上下関係を基軸にした不寛容な組織文化を死守しようとしているわけです。
確かに諸外国でも上司が部下に威張り散らす光景は時折、見られるものですが、こうした関係性を儀式化し、ITにも実装しようという国は日本以外には存在しません。
このような馬鹿げた行為を各所で繰り返した結果、日本企業ではムダがなくならず、結果的に長時間残業を抑制することもできない状態が続いています。これはテクノロジーの問題ではなく、完全にマインドの問題ですから、いくら技術力を高める努力をしても、ほとんど意味はないのです。
* * *
この続きは幻冬舎新書『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』でお楽しみください。
加谷珪一さんの新刊『本気で考えよう! 自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策』も好評発売中!
国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶
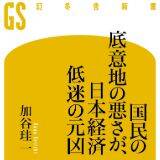
加谷珪一さんの新書『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』の最新情報をお知らせいたします。