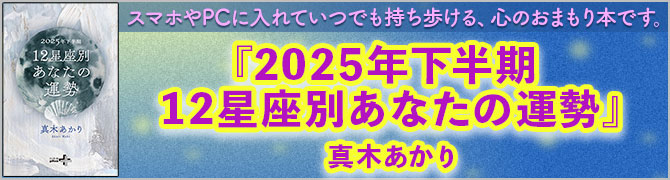現役の大学病院教授が書いた、教授選奮闘物語『白い巨塔が真っ黒だった件』。どこまでが実話なの⁉…リアルな描写に、ドキっとします。
発売を記念して、第1章「暗闇の中で」を5回に分けて公開します。
* * *
医者というのは、わりと自由に就職先を選ぶことができる職業だ。地方の国立大学を卒業したとしても、全く関係のない都内の病院で勤務することも可能だ。しかし、自由が利くのは最初の選択だけである。卒業生のほとんどは医学部を卒業後、大学病院に存在する「医局」という集団に所属する。教授をトップとした閉塞的であり封建的でもある集団、それが医局だ。消化器内科、脳神経外科、精神科、眼科、皮膚科といった具合に、大学病院ごとにそれぞれの診療科の医局が存在する。

医局に入る際に、なにも契約はいらない。教授が「よし」と言えば、医局のメンバーとして仲間に迎え入れられる。その後は、大学病院で勤務したり、関連病院と呼ばれる地域の病院で勤務することとなる。
S大学を卒業し医師となったぼくは、K大学医学部皮膚科学教室に入局した。そのK大学で一年の研修を経てから、鳥取の病院に勤務することとなった。
鳥取の病院では、毎日の外来と、週に二回の手術、それから月に四回の当直が、義務としてまわってきた。
忙殺される毎日の中でも、記憶に残る患者はいる。特に印象に残っているのは、不思議なことに、診察することができなかった患者のことだ。
その日は先輩皮膚科医の岡本正義が、当直の診察に当たっていた。この病院では、皮膚科医だろうが眼科医だろうが関係なく、救急外来を受診した全ての患者を診察する“全科当直”が行われていた。
「次の患者さん、かなりひどいですよ」
問診を取り終えた看護師の三谷尚子が、診察室に戻ってくるなり、当直医二人に声をかけた。
「赤ちゃんの爪が全部取れてます」
「どういうことですか?」
「湿疹が悪化して指がジュクジュク。お母さんがステロイドを一切使いたくないんですって」
「ステロイド忌避ですか」
岡本が、さも当たり前のように返事をした。
「ステロイドきひ?」
「ええ、ステロイド忌避です。ステロイドを極端に嫌う患者さんのこと。脱ステロイドとか脱ステなんて言い方もしますね」
「一般の方からしたら、ステロイドって怖いイメージありますもんね」
右手に問診票を持ち、左手は腰あたりに当て、三谷は仁王立ちで答えた。その表情は、うんちくもういいから早く患者を診ろ、と物語っていた。
「私が専門なので診ましょう」
岡本は重い腰を上げ、ひらっと三谷から問診票をつまみ取り診察室へと向かった。「先生、それでね」
その日に夜勤だった三谷が、一息つく間もなく、当直中のぼくに話しかける。
「岡本先生、お母さんと喧嘩しちゃってさ」
「喧嘩?」
「そう。ステロイドは危険じゃありません! お母さんは間違ってます! って」
「そんなきつい言い方したの?」
「うん、お母さんも最後泣きそうになってて大変だったのよ」
ぼくは、発熱で受診した子供のカルテを書きながら返事をする。
「そうだったんだ。で、肝心の患者さんは?」
「うん。爪が剥がれた部分にゲーベンクリームを塗ってガーゼを当てておきました。
ステロイドは処方してたけど、ちゃんと塗ってくれるかな」
「どうだろうね」
電子カルテの患者一覧には、今日もずらっと名前が並んでいる。
「あの赤ちゃん、次は大塚先生の予約だって」
そう言うと、三谷は患者がごった返す待合室へと消えていった。 母親の信念でステロイドを使った標準治療ができなかった赤ちゃんは、結局ぼくの外来に訪れることはなかった。予約日までの間に何度もシミュレーションしたその母親とのやり取りは、外来で使うことなく終わった。
「全部の爪が取れてたの」
その言葉だけで、いかにその子のアトピーがひどい状態だったのか、医者でなくとも想像がつく。あの赤ちゃんはちゃんと元気に過ごせているのだろうか?
それ以来、アトピーを患った子供を外来で診るたびに、会うことができなかったあの子のことを思い出した。

ステロイドをめぐる情報の混乱は、一九九〇年代のテレビ番組の影響が大きい。
当時、国民的な人気を誇ったニュースキャスターが、「これでステロイド外用剤は最後の最後、ギリギリになるまで使ってはいけない薬だということがよくお分かりになったと思います」と、とある番組の終わりに発言し、翌日から全国の皮膚科診療は混乱に陥った。診察室に入ってくるなり「ステロイドは使いたくありません」と訴える患者だらけとなり、現場は騒然としたのである。
子宮頸がん予防のためのHPVワクチン然り、インフルエンザでのタミフル然り、新型コロナワクチン然り、いつの時代でもマスコミの影響は大きい。放送された内容がその後、医学的に間違いであると証明されたとしても、薬に与えられた悪い印象が消えることはない。
悪徳な民間療法が誤情報に便乗し、患者は標準治療から遠ざかる。間違った情報で最終的に苦しむのは、いつも患者である。
アトピービジネスに騙され何十万も健康食品にお金を払った真っ赤な顔のOLや、十年以上自宅に引きこもっていた脱ステ患者の話などを聞くたびに、ぼくはこの状況をなんとかせねばと強く感じてきた。間違った医療情報で振り回される患者をなくすこと。そしてなによりアトピーを治すこと。
しかし、医学には限界があり、いまだに治せない病気が数多く存在する。原因が解明されていない難病も数多い。やはり自分の手で新しい薬を開発するしかない。その思いを強くしたのがこの時期だった。
こうしてぼくは鳥取での二年間の勤務を終えた後、K大学大学院博士課程へと進学し、先の「前野研」での、耐え難き日々を送ることになったのだった。 鬱からの回復というのはそう簡単なものではない。トラウマのように心に刻まれた傷は、ほんのわずかに関連する出来事に触れるだけで脳で記憶をつかさどる海馬が活性化し、耐え難き苦しみとなってぼくを襲う。
回復の段階で気がついたのだが、鬱状態にあるときは、本来であれば外に向けて発するべき怒りが、諦めや後悔といった形で自分自身に向かう。誰かが不愉快な出来事を引き起こしたとき、例えば、前野教授が人格否定を繰り返したとき、正しい心の反応として怒りは教授に対して発散されるべきだ、と今は思う。しかし鬱になると、理不尽な仕打ちでさえ、自分が悪かったからだという怒りが内に刺さり、ますます自分を苦しめることとなる。そう考えても、鬱からの回復に必要なことは、鬱になった原因を遠ざけ、あたたかな環境で過ごすことが絶対的だと分かる。
大学卒業後に入局したK大学皮膚科で高橋修教授と出会い、ぼくはその部下となる。高橋は、人心を掌握し、マネジメントに長けた医師であった。出向先の前野研で鬱になったというぼくの噂を聞きつけて、しかるべき対応を準備してぼくが戻ってくるのを待ってくれていた。
そんなこととは露知らず、医局を辞めようとぼくが高橋の部屋のドアをノックしたのは、鬱と診断されてから半年も過ぎた後。ぼくは相変わらず研究室を休んだままでいた。
その日、ぼくは医局、すなわちK大学皮膚科学教室を辞める覚悟を決めていた。インターネットで見つけた雛形を見本に、自らの退職意思を記した一枚の便箋を封筒に収め、しわくちゃにならぬようクリアファイルにしっかりと挟んでから黒色のリュックにしまい込んで家を出た。
暗く埃っぽい大学の廊下には、アカデミアの雰囲気にまるで似つかわしくないオレンジ色の防犯ランプがついた部屋がある。そこがK大学医学部皮膚科学教室九代目教授、高橋修の部屋だ。日本はおろか世界中を飛び回る高橋を掴まえるのは困難なことで、この日は事前に高橋の秘書と連絡を取り合い、一五時に教授室に来るようにとの伝言を受けての訪室であった。
携帯の時計が約束の時間となったタイミングを見計らい、ぼくは木製のドアをノックした。

「大塚です」「はい、どうぞ」という声とともに、ドアロックが自動で解除される機械音が静かに響く。
「失礼いたします」
ゆっくりとドアを開けると、白髪で細身の老紳士が椅子から立ち上がった。「さぁ」と言って、目の前の応接セットのソファを手のひらで指す。
「体調はどうだ?」
黒色の革のソファに腰を下ろすや否や、高橋は口を開いた。
「はい、まだ本調子ではないですが、だいぶ元気になりました」
「前野先生がそんな人だとは知らなかったよ」
高橋の耳には、すでにハラスメントの話が伝わっているようだった。
「ご心配をおかけしました」
「前野先生にはぼくから言っておくので、大塚くんはここの皮膚科に戻ってきなさい。まだ医学博士の学位論文ができてないだろ」
高橋はテンポよく話を進める。決意はできていたものの、いざ高橋を目の前にして、大学を辞めることを口に出せなくなってしまった。ここでもし高橋から「大塚くんはこの先どうしたい?」と聞かれていたら、ぼくの人生は変わっていたのかもしれない。
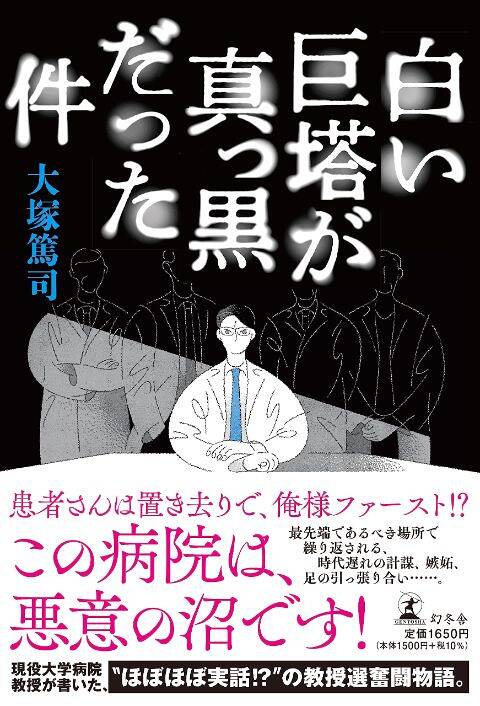
(第2章「サイエンスの落とし穴」に続く)
白い巨塔が真っ黒だった件の記事をもっと読む
白い巨塔が真っ黒だった件

実績よりも派閥が重要? SNSをやる医師は嫌われる?
教授選に参戦して初めて知った、大学病院のカオスな裏側。
悪意の炎の中で確かに感じる、顔の見えない古参の教授陣の思惑。
最先端であるべき場所で繰り返される、時代遅れの計謀、嫉妬、脚の引っ張り合い……。
「医局というチームで大きな仕事がしたい。そして患者さんに希望を」――その一心で、教授になろうと決めた皮膚科医が、“白い巨塔”の悪意に翻弄されながらも、純粋な医療への情熱を捨てず、教授選に立ち向かう!
ーー現役大学病院教授が、医局の裏側を赤裸々に書いた、“ほぼほぼ実話!? ”の教授選奮闘物語。
- バックナンバー
-
- 第3章ー6 警察官に促されて死亡宣告を行...
- 第3章ー5 12月の寒い日。いつもは朝一...
- 第3章ー4 教授の目は一切笑っていなかっ...
- 「ここまで暴露してよいのだろうか。生々し...
- 第3章ー3 「自分の後任に、自分より優秀...
- 第3章ー2 苦しくもなく熱くもない、しか...
- 第3章ー1 「変な噂が流れていますよ。大...
- 第2章-6 実は、教授選での選抜方法は、...
- 第2章-5 医局全体がソワソワ…。K大学...
- 第2章-4 「大塚くんの研究内容と似たよ...
- 第2章-3 華やかなエジンバラでの学会。...
- 第2章-2 「夢見て行い、考えて祈る」こ...
- 第2章-1 心と皮膚はつながっている!?...
- 第1章-5 「赤ちゃんの爪が全部取れてま...
- 第1章-4 小児喘息で初めて入院した3歳...
- 第1章-3 「彼女は教授の愛人だったとい...
- 第1章-2 教授から「セクハラを受けてる...
- 第1章-1 研究室には「魔の5時半」が存...
- 大塚篤司先生『白い巨塔が真っ黒だった件』...
- 現役の大学病院教授が書いた、“ほぼほぼ実...
- もっと見る