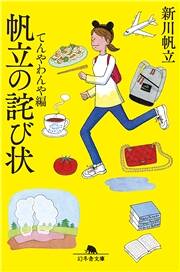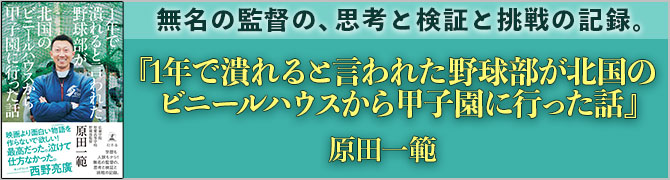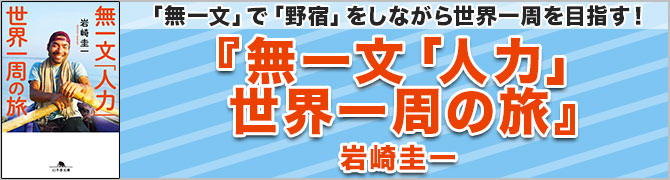米派か、小麦派か――食いしん坊にとっては永遠の問題である。
私はどちらも大好きだ。
以前、角川春樹さんから「米のうまい店に連れていってやる。あの店の米は、小食の作家でもおかわりしてしまうんだ」とお声がけいただいたことがある。さすが角川社長、本当に美味しいお米で、数えきれないくらいおかわりして(担当編集さんによると五回おかわりして、茶わん六杯ぶん食べていたらしい)、釜の米をすべて食べてしまった。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
帆立の詫び状の記事をもっと読む
帆立の詫び状

原稿をお待たせしている編集者各位に謝りながら、楽しい「原稿外」ライフをお届けしていこう!というのが本連載「帆立の詫び状」です。