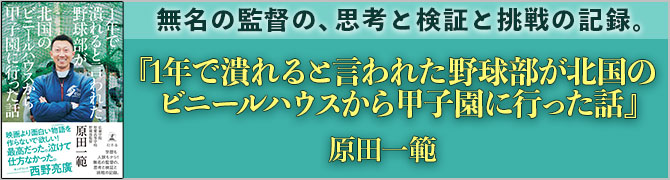世界屈指の「無宗教の国」とされる日本。しかし初詣は神社に行き、結婚式は教会で、葬式は仏式で、というのは一般的です。日本人にとって宗教とはどのようなものなのでしょうか。伝統宗教から新宗教、パワースポットや事故物件、縄文などの古代宗教。さまざまな観点から日本人と宗教の不思議な関わりを解き明かす『宗教と日本人』(中公新書)より、一部を抜粋してお届けします。
市立体育館の起工式で神式の地鎮祭 これは宗教活動か?
戦後初の政教分離訴訟である津地鎮祭訴訟は、地鎮祭という実に身近な実践をめぐって生じた。この訴訟は最高裁までもつれ込んだが、その過程では、宗教儀礼と習俗は異なるのか、クリスマスツリーを立てるのは宗教実践なのかといった興味深い議論が行われている。

訴訟の発端は、1965年1月14日、三重県津市の市立体育館の建設現場で行われた起工式である。式の運営は津市教育委員会で、式場に入る前、スタッフが参列者の手に水をかける手水の儀が行われた。式の進行は教育委員会の係長が務めた。そして地元の大市神社の神職ら4名によって、浄化儀礼である修祓に始まり、降神の儀、祝詞奏上、鍬入れの儀、玉串奉奠、昇神の儀など、神式の地鎮祭が行われた。その後、起工式の挙式費用7663円(神職への報償費4000円、供物料3663円)が、市議会で承認された体育館の建設予算から支出されたのである。
原告の津市議会議員は、起工式の1週間ほど前に、市長名の招待状を受け取っていた。事前に教育委員会にどのような形で起工式が行われるのかを確認し、神式だと分かるとすぐに宗教儀礼の部分の執行停止を求める申し立てを津地方裁判所に行った。だが、申し立ては却下され、市会議員の仕事の一つという認識で起工式に参列した。
そして起工式後、津市長と津市教育委員会を相手どり、宗教活動への公金支出に対する損害補填と、信仰していない宗教儀式に参列させられた精神的苦痛への慰謝料を求める裁判を起こしたのである。
こうして地鎮祭が宗教なのかをめぐる長い裁判は始まったが、1967年3月、一審の津地裁は原告の請求を棄却し、次のような見解を示す。日本には、体系的教義を有する近代的宗教が成立する以前、岩・樹木・山などを対象とする自然崇拝があり、そこに土地神信仰が含まれていた。こうした原始信仰は近代的宗教の成立と共に姿を消したが、「習俗化された諸行事の中にその痕跡を発見する」ことができ、地鎮祭はその1つである。
それでは地鎮祭は宗教なのか。一審判決は、地鎮祭は自然信仰に由来するが、時と共に「信仰的要素」は失われ、「形式だけが慣行として存続されて」きたとする。つまり、地鎮祭は「宗教的意識」を伴わない、広く国民に浸透した習俗であり、したがって、起工式は「神道の教義の布教宣伝」に資するものではないから合憲という判決だった。地鎮祭は信仰なき実践ゆえに宗教ではないという理屈である。
二審判決は「クリスマスツリーは非宗教だが、地鎮祭は宗教」
これに対して1971年5月、名古屋高等裁判所の二審では、違憲判決が下される。3万文字近くの判決文では、まず宗教が大きく2つに分けられる。
キリスト教や仏教のような創唱者を持つ「世界宗教」は、教義があるため世界規模で広がる可能性がある。他方、創唱者のいない「民族宗教」は、そうした普遍性を持ちえない。当然、神道は後者に含まれるが、二審は、教義のない宗教が及ぼす影響力に着目する。
それによれば、民族宗教は、原始社会の生活・生産のための「儀礼中心の宗教」であった。日本の場合であれば、稲作りを中心とする農耕社会の豊穣を祈る儀礼だ。明治以前の神道はこうした原始的性格を残しており、体系化された教義はなく、祭祀中心に営まれてきた。つきつめれば、民族宗教とは、共同体維持のための信仰なき実践だというのである。

しかし、二審判決は、信仰なき実践が所属と不可分である点を指摘する。民族宗教の集団とは社会集団そのものであり、そこから抜け出すことは「その人間の死を意味」する。神道の氏子や産土神は、こうした観念を引き継いでおり、それを共有しない者を排撃し、「個人の宗教的自由を無視する結果」をもたらす。こうして二審判決では、神道の「……国や公共団体など共同体と結びつきやすい性質」が問題視され、違憲判決が導かれたのである。
さらに二審判決は、ある実践が宗教的か否かを判断する基準として次の2点を示す。つまり、(1)主宰者が宗教専門家であるか、そして(2)作法の手順が宗教界で認定されたものかである。この基準にしたがえば、クリスマスツリーや節分の豆まきは「宗教意識を伴わない非宗教的習俗」だが、地鎮祭は宗教活動となる。したがって、参加を強制しなくとも、そうした宗教活動を公共の地方自治体が行うのは違憲としたのである。
「そもそも完全な政教分離は不可能」 最高裁で示された“目的効果基準”
しかし、1977年7月、最高裁の三審判決で、再び合憲判決が下される。まず最高裁は、そもそも完全な政教分離は不可能だと述べる。宗教は個人の内面の事象であるだけでなく、「教育、福祉、文化、民俗風習」など多方面にわたる社会事象でもあり、現実的には、国家と宗教の完全分離は不可能だというのだ。
仮に完全分離を目指せば、様々な不都合が生じる。宗教系の私立学校への助成、文化財として価値のある寺社への補助、刑務所の教誨活動など、一切が不可能になる。したがって、政教分離の原則は、国家が宗教と関わることを全く許さないわけではない。重要なのは、「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果」だとしたのである。
これが、その後の政教分離訴訟で参照点となる「目的効果基準」である。前述のように、二審判決は、主宰者と作法の手順を判断基準として示したが、最高裁によれば、そうした外形だけにとらわれず、その行為が一般に与える影響を客観的に判断する必要があるというのだ。

目的効果基準にしたがって検討を進めると、まず起工式には宗教的意義はない。地鎮祭は、工事を円滑に進めるための「慣習化した社会的儀礼」で、その目的は「極めて世俗的」である。
次に効果だが、そもそも神道は「祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられる積極的な布教・伝道のような対外活動」を行わない。したがって、地鎮祭を行っても、参列者の宗教的関心が高められたり、「神道を援助、助長、促進するような効果」は認められないと結論したのである。
本書の問題意識に引きつけて言えば、一連の政教分離訴訟では、戦後も神道が暗黙のうちに公的な位置を占めていること、そして、神道が信仰なき実践、信仰なき所属であることは吟味検討された。しかし、そうした信仰なき宗教が宗教であるか否かという最も根本的な問題は十分に議論されなかったのである。
津市で地鎮祭を執行した神職たちは専門の宗教者である。彼らは降神の儀によって土地の神を招き入れ、その神に対する儀礼を行ったと信じていたのではないか。だが最高裁によれば、神職による儀礼は参列者の心に全く響かず、工事につきものの世俗的手続きとして受け止められていたというのである。
こうした裁判所の認定に対し、当の宗教者たちはどのように反応したのか。最高裁の判決の日には、全国から約30名の神職が傍聴に訪れていたが、判決後、その1人が「あれは習俗ですよ」と発言したことが報道されている。
仮にその通りであれば、地鎮祭の現場には、それを宗教的に意味のある儀礼実践だと信じる者は原告しかいなかったことになる。この発言に対し、宗教社会学者の森岡清美は「プロの資格と作法にのっとって厳修する神式地鎮祭の宗教性を神職自身が否定し去ってよいのだろうか」と述べているが(読売新聞1977年7月18日夕刊)、宗教としての神道の根幹に関わる問いかけである。
* * *
この続きは中公新書『宗教と日本人』をご覧ください。