
生き方
数年前、『宇喜多の楽土』の前作にあたる『宇喜多の捨て嫁』を読んだとき、初めて歴史小説が面白いと思った。わたしの日本史音痴が原因で、それまでは他の歴史小説を読んでも途中で挫折してばかりだった(たいてい登場人物が多すぎて混乱してしまうのだ)。けれど、主人公・宇喜多直家の悪魔のような政略的な生き方や、それに翻弄される娘たちの姿は、当時の歴史的背景に詳しくなくても、ぐっと引き込まれる世界観を作り出していた。この出合い以来、食わず嫌いを克服したかのように、歴史小説をたびたび手に取るようになった。
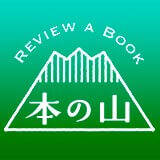

日々更新する
多彩な連載が読める!
専用アプリなしで
電子書籍が読める!

おトクなポイントが
貯まる・使える!

会員限定イベントに
参加できる!

プレゼント抽選に
応募できる!