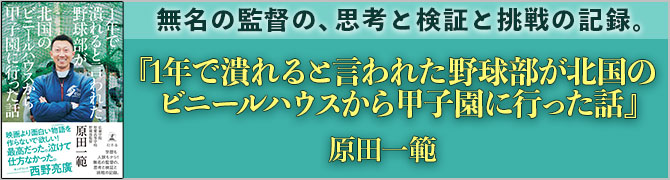中国の威信を賭けた、北京五輪の開幕直前。開会式に中継される“運転開始”を控えた世界最大規模の原子力発電所では、日本人技術顧問の田嶋が、若き中国共産党幹部・鄧に拘束されていた。このままでは未曾有の大惨事につながりかねない。最大の危機に田嶋はどう立ち向かうのか……。2011年に発生した、福島第一原子力発電所の事故を予言していたとも言われる、真山仁の社会派小説『ベイジン』。今回は特別に、本書の冒頭をみなさんにお届けします。
* * *

運開すれば世界最大となる紅陽原子力発電所──。この核電の運転と安全を司る中央制御室には、数百に及ぶ最新鋭の計器が並ぶ。まるで軍事基地の作戦本部を思わせる、ハイテクの要塞だった。そこに今、通常の五倍以上の人間が集まり、二人の男のやりとりを固唾を呑んで見守っていた。
男の一人、鄧学耕は努めて感情を殺し、自分より頭一つ高い日本人を冷たく見上げていた。
「田嶋さん、今すぐそこをどいてください」
「鄧さん、あなたこそ、私の邪魔をしないでくださいよ。安全に著しい疑問が出たので、原子炉を停める。それが、私の責務です」
田嶋伸悟は怯む気配もなく、終始笑顔を浮かべている。この期に及んで原子炉を停めろとは、この男は正気を失ったのか。
「今日がどういう日か分かってるんですか。しかも核電は既に三日前から、出力一〇〇%の状態で何の問題もなく動いている。北京への送電だって始まっているんです。運開なんて、書類上の手続きじゃないですか。なのになぜ、この期に及んで停止するんです」
相手の目に狂気の気配を探りながら、鄧は諭すように話しかけた。
「問題があるから停めるんです。私は紅陽核電の技術顧問として、ここにいる。絶対的な安全が確認できない以上、停めるのは当然の職務だ」
普段は権威や肩書きを嫌う田嶋が、珍しく権限を振りかざしてきた。彼は日本人だが、中国政府から乞われて技術顧問に就任していた。そのため、紅陽核電建設の最高責任者としての権限を持っていたのだ。
本来はこんな強い権限を、外国人、しかも日本人に与えるべきではない。しかし、自国の技術だけでは核電建設がままならぬ中国は、核電先進国の日本やフランスからベテランの技術者を技術顧問として招いていた。田嶋もその一人だった。
中国人民なら一発で黙り込む党幹部の意向というのも、外国人であるこの男には通用しなかった。
「一体、どこに問題があるんです」
鄧は詰問口調にならないように心掛けたが、田嶋のように緊迫した空気の中で笑みを浮かべる余裕はなかった。
信じられないというように、田嶋が大げさに首を振った。
「停電時に起動するはずのDG(非常用ディーゼル発電機)の起動失敗率が、規定の一〇〇〇分の一はおろか、三〇%にも達している」
すかさず鄧の隣にいた発電所長がファイルを突き出し、該当箇所を指で叩いた。
「ここには、一〇二四分の一にまで改善されているとありますが」
「私が昨晩チェックしたら、起動失敗率は三〇%を超えていました」
チェックだと……。
鄧は昨夜、核電を留守にしていた。もう一つの任務を全うするためだったが、その間も、田嶋は核電の安全チェックを続けていたのだ。
「粗探しをしたわけじゃないですよ。ただ、ちょっと気になることがあったので、再調査をした結果、問題が見つかっただけです」
鄧の目つきが険しくなったのに気づいたらしく、田嶋はすかさず言葉を足した。
「しかし、DGが今すぐ必要になる可能性は、万分の一以下じゃないんですか」
それは、以前に田嶋自身が言っていたことだ。にもかかわらず彼は揺るがなかった。
「でも、ゼロではない。さらにね、鄧さん。自家発電用の軽油が何者かに抜き取られていたことも判明したんです。現在は規定の一〇分の一以下の量しか残っていない」
真偽を質すように発電所長を見たが、彼は肩をすくめるだけだった。
いつ使うか分からないものは、いま必要な者が使う。それが、中国なんだよ、田嶋さん。
「何より気になるのが、核電内の清掃がこの期に及んでも徹底されないことです」
田嶋は本当に狂ったのだと鄧は確信した。掃除が不十分だからと言って原子炉を停める奴が、どこの世界にいるんだ。
「そんな理由で、核電を停めろというのは合点がいきません」
二人のやりとりを見守る所員たちも、呆れたような声を上げた。
「核電内が不潔では、重大事故のシグナルを見落としてしまう。たとえば廊下の隅に染みや水溜まりがあれば、事故の可能性を考えなければならない。だが未だに、原因不明の水溜まりや汚れが、少なくとも一〇〇カ所以上ある」
田嶋の目は真剣だった。いや怒っていると言った方が正しい。何がそんなに彼を怒らせるのか。鄧は珍しく戸惑った。
「分かりました。全てきれいにさせましょう。だが、とにかくセレモニーだけはやらせてください。安全性に問題があるのであれば、その後で、あなたの好きにすればいい」
最大限の妥協だった。無論、約束を守るつもりはなかった。だが、時間が迫っている。
北京五輪の開会式のこの日、国家環境保護総局の検査官から総合負荷性能検査の合格証授与があり、紅陽核電は晴れて営業運転を開始する。
その模様が、五輪の開会式会場の大スクリーンに映し出されるため、副首相までもが北京からやって来るのだ。今は何としてでも田嶋に引き下がって欲しかった。
「世界中に、やらせの証拠を握らせるのかね。そんなことをしたら、あんたの国の威信は、地に墜ちる」
田嶋はわざとらしく、上方にある見学ルームを見上げた。世界最大の核電運開の一瞬を捉えるため、世界中のメディアがカメラを構えていた。
連中が見ているぞ、田嶋は暗にそう言っているのだ。鄧はその挑発を無視した。
「だからこそ、我々は予定通りのセレモニーをおこなわなければならないのです」
「でもね、鄧さん。こんな状態で運開したら、世界中の物笑いになる。心急吃不了熱豆腐(熱い豆腐は急いては食べられない)、急いては事を仕損ずるです」
田嶋が中国語で格言めいた言葉を口にした瞬間、鄧の我慢は限界を超えた。不安そうに控える紅陽市の警察署長に、命令口調で促した。
「この男を拘束し、排除しろ」
背後で署長が躊躇している気配を感じ取った。署長と田嶋は、酒飲み友達だった。鄧はゆっくりと振り向くと署長を睨み付けた。
「呉署長、大連市党副書記である私の命令が、聞こえましたね」
署長は不承不承なのを隠そうともせず、部下にあごで指示した。二人の若い警官が、田嶋の両脇を掴んだ。
田嶋は鄧を睨みつけたが、抵抗せず素直に従った。異変を感じ取ったらしい見学室からストロボの光が降り注いだ。
「事故が起きた時、誰もあんたを庇ってはくれないんだ。私の判断を信じなさい」
通り過ぎざまに、田嶋が言葉をぶつけてきた。鄧は思わず彼の顔を見つめた。日本人エンジニアの哀しげな目が、鄧の心に小さな穴を開けた。
誰もあなたを庇ってはくれないんだ、という一言で、得体の知れない不安が暴れ出した。だが、鄧はすぐに動揺を鎮めた。
今に始まったことじゃない。そんな状況の中を、俺はずっと生き抜いてきたんですよ、田嶋さん。
鄧は発電所長の方に向き直ると、検査官を招き入れるように告げた。

「なあ呉さん、友達をこんな目に遭わせて、心が痛まないのか」
署長は足下を見つめたきり無言を通した。田嶋の目は、その足下の先に吸い寄せられた。何かが染み出たような跡があった。
田嶋が思わずしゃがみ込もうとするのを、二人の警官が慌てて制した。脇を吊り上げられた痛みを堪えて、田嶋は訴えた。
「ほら、そこの染みを見てごらん、呉さん。核電にこんなものがあってはいけない。見つけたらすぐに染みの原因を調べなきゃならないんだ。こういう染みが大事故を生むんだ」
彼が指摘する染みを、誰も見ようとしなかった。見ざる聞かざる言わざるの文化は、この国の方が遥かに徹底されている。
──日本の原発建設の技術力を世界に誇示してくるんだ。世界で一番安全な原発を造れるのは、我々だということを中国で証明してこい。
そう言われて紅陽に送り込まれたが、技術を誇示する気などなかった。そんな奢りを持てば、必ずトラブルや事故の原因となる。安全な原発を造り上げたい。その一心でやってきた。
紅陽に赴任して三年余り。若いスタッフに原発のいろはを叩き込む過程で、田嶋はこの仕事に大いなる誇りを抱くようになっていた。巨大プロジェクトに挑む思いが、国や民族の壁を超えて一つになった実感があった。
それだけに、念には念を入れたかった。調べた箇所全てで、問題が見つかった。いずれも些細ではあった。しかし、“小さな違和感を見過ごすな、臆病になれ”という原発マンの鉄則からすれば、放っておけないものばかりだった。
誰にだってミスはある。仕事を適当に流す時もある。だが、原発という怪物は、人間がわずかでも隙を見せた瞬間、取り返しのつかない暴走を始める。
「なあ呉さん、俺はいい加減な男かい」
「お願いだ、田嶋さん。私を厄介事に巻き込まないでくれ。私たちにとって党幹部の意向は、絶対なんだ。私には、あんたを救えない」
タンクのような肥満体型の署長が、喉から振り絞るような声で言った。
「あんたが救うのは、私じゃない。この国の人民なんだよ」
署長が意外そうな顔をした。
「人民を救う?」
「そうとも。いいかね、呉さん。紅陽核電は危ない。俺の長年の勘が、そう言ってるんだよ。このままでは死人が出る」
呉の目が怯えていた。何事も聞かざるを決めこんでいた彼の耳に、ようやく田嶋の言葉が届いたらしい。田嶋は勢い込んで続けた。
「あんたの奥さんも可愛い孫たちも、死ぬかも知れない」
思わず口をついた一言が意味するものに気づいて、田嶋の背筋に悪寒が走った。そんな軽はずみなことを言ってもいいのか。まだ、決定的な危険を確認したわけじゃない。ただ、小さな違和感があるだけだ。
もしかすると、この巨大プロジェクトの最終的なゴーサインを出すのが単に怖いだけかも知れない。
いや、違う。この現状は杜撰すぎる。誰も経験したことのない巨大プラントをなめてはいけない。原発の絶対的な安全性を守るために、俺はここにいるんだ。ならば、躊躇してはならない。
「なあ、呉さん。勇気を持ってくれよ。あんたの家族の命を守るために、俺に力を貸してくれ」
呉が自問自答するように頭を振った後、田嶋をまっすぐに見返した。呉の目に同意の意思が浮かんだように思えて、田嶋はさらに一歩踏み込んだ。
「お願いだ、俺にこの発電所を停めさせてくれ」