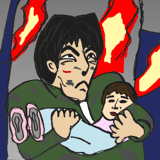2019年に発売された傑作ノンフィクション『森瑤子の帽子』が文庫になりました。80年代、都会的でスタイリッシュな小説と、家族をテーマにした赤裸々なエッセイで女性たちの憧れと圧倒的な共感を集めた森瑤子。母娘関係の難しさ、働く女が直面する家事育児の問題、夫との確執、そしてセックスの悩みといった今に通じる「女のテーマ」を日本で誰よりも早く、そして生涯書き続けた作家です。
書き手は島﨑今日子さん。「AERA」の「現代の肖像」や著書『安井かずみがいた時代』などで名インタビュアーとして知られる著者が、80年代と森瑤子に迫った渾身の1冊です(文庫版には酒井順子さんによる解説も収録)。一部抜粋してお届けです。

* * *
尊厳を持って死にたい
九二年の春、森の突然の提案で、田村のアトリエで気功の勉強会を開くことになった。森が知り合ったばかりの気功師を招き、毎週一回、大宅や安井ら親しい仲間が十人ほど集まって、「気」の入った餃子を作ったり、足ツボの講義を聴いたりということを三カ月ばかり続けた。
もうこの頃には身体の異変を感じていたのだろう、森は気功だけではなく、身体にいいというものには敏感に反応した。ストレスを解消してガンの予防になるという笑いもそのひとつ。田村のもとに「笑いの工房」なるもののオープニングパーティーの案内がファクスで届いたのは、九三年二月十九日の夜であった。それから半月もしない三月の初旬、検査で森の胃ガンが発見された。
月末の手術までの間、作家はぎっしり埋まった仕事と社交のスケジュールをすべてこなし、夫と一緒に田村夫妻と福島へゴルフにも出かけていた。
「伊豆に行く予定が珍しく伊豆が雪で、取りやめようと提案したら、『北のほうに雪の降っていないゴルフ場があるから』と言われて、一泊で福島に行きました。入院のことは聞いていたけれどガンという言葉はなくて、『胃潰瘍かしら。いつも胃が痛いのはアイヴァンの運転が乱暴だから』と、言っていました。あの時代は、今と違って、告知といった考えはなく、ガンという言葉は医者でも口にしませんでした」
森はやつれた風もなく、夜はみなとトランプを楽しみながら、小さな魔法瓶に入った野菜スープを「身体にいいの」と飲んでいた。
手術の一週間前、与論の別荘にいる森から田村に、壁画を描いた病院の医師を紹介してほしいと電話がかかってきた。「医師としてのアドバイスを聞きたいの」。後に、田村が医師に聞いたところによると、森はできるなら手術をしたくないと考えており、抗ガン剤を使えば意識がどうなるかなど、自分の病状を確認しようとしていた。
森が助言を受けた医師に送ったお礼のファクスの文章を、医師から電話で教えられた田村が古いノートに書き留めていた。
〈私が恐れるのは痛むあまり人間の尊厳を失うような最後です。自分の苦しみもさることながら、肉親や親しい友人たちにそのような姿を見せるのは、彼らの苦しみにもなります。私が少しでも安楽に過ごせる場所を確保してくだされば、どんな救いになるかしれません。おおげさに言えば、死の設計図が描けます。この二週間私がしがみついたのは、いかに死ぬかということばかりでした。しかし、まるで自分の頁をめくるようにそれがひらりといかに生きるかということへの準備に切り替わったのでした〉
「死を迎える気持ちがこんなに幸せとは思わなかったわ」
死を覚悟した作家は誰にも会いたがらなかったが、田村は度々、電話でホスピスに呼ばれた。病室に出向くと、「葬式みたいで嫌だ」と言う森の気にいるように花の並べ方を工夫し、「本を読んでちょうだい」と言われて本を読み、森が約束していたゴルフに代わって行った。そんな日々の中で田村の記憶に焼きついているのは、娘の病状をはじめて知らされた森の両親が病室にやってきた日のことである。
自分の弱った姿を両親に見せたくないと病状を知らせることも拒んでいた森は、六月の初旬、「両親を呼んでほしい」と周囲に頼んだ。驚いた両親がやってくるその日、森は「どんな精神状態になるかわからないから、傍にいてちょうだい」と田村を放さなかった。両親と入れ代わりに病室を出た田村の耳には、森が「お母さん、ごめんなさいね」と嗚咽するのが聞こえた。
「いつも華やかで、強気の森瑤子が泣くなんて。胸がつぶれそうになりました」
既にその美意識で死をデザインしていた森は、木村を病室に招いた。
「何回目かに行った時は、『お別れのキスをして帰れ』と僕に言ったんですよ。傍についていたお嬢さん二人が『ママ、そんなこと言っちゃダメ』と止めたんですが、唇にキスして、『またね』と言って帰りました。多分、最後のキスをしておきたいなと思った男には、みな、同じことを言ったんじゃないかな」
これまでトラブルが起こると法律相談をもちかけてきた森が最後に木村に頼んだのは、遺言を作る役目であった。その内容について固く口を閉ざす弁護士は、「家族を思いやりで包んだ森さんらしい終わり方だった」とだけ話す。
「病気になる前から『安楽死の法律を作れ』と言っていたし、『いつ死んでもいいように身の回りの整理をしている』『これが最後と思って桜を見てる』とも言っていました。病床では、『生きていくのも死んでいくのも、どっちも幸せだ』と言っていた」
大宅も同じ言葉を聞いている。聖ヶ丘病院に会いにいくと、ベッドの上の森はいつもとそれほど変わりなく、「申し訳ない、美しくあらねばならない森瑤子がこんな姿で」と微笑みながら親友を迎え入れた。大宅は、病気になってまで傍にいる夫に気を遣う森が気になったが、森は「死ぬのは怖くないけれど、もう少しゴルフしたかった」と言った後、「胃なんて一日で穴があくのだから、あなたも死に対する準備はしないといけないのよ。死を迎える気持ちがこんなに幸せとは思わなかったわ」と呟いた。
「赤い華やかな口紅と帽子のイメージのまま逝ってしまいました。森瑤子のばばあになった姿なんて見たくなかったけれど」
友人たちに「私を忘れないで」と告げた森瑤子は、七月六日に永眠した。二日後に行われた四谷聖イグナチオ教会での告別式の帰りに、大宅は安井から「私、キャンサーなの」と打ち明けられた。翌九四年の三月十七日、「キャンサーなんかに負けない」と言っていた安井かずみも、その生涯を五十五歳で閉じた。
洗練を求めて手にした作家と洗練の極みを生きた作詞家、二人の女たちの憧れは日本経済が暗転してまもなくいなくなってしまった。日本の「失われた二十年」は始まっていた。
森瑤子の帽子の記事をもっと読む
森瑤子の帽子

よき妻、よき母、よき主婦像に縛られながらもスノッブな女として生きた作家・森瑤子。彼女は果たして何のために書き続けたのか。
『安井かずみがいた時代』の著者が、五木寛之、大宅映子、北方謙三、近藤正臣、山田詠美ほか数多の証言から、成功を手にした女の煌めきと孤独、そして彼女が駆け抜けた日本のバブル時代を照射する渾身のノンフィクション。