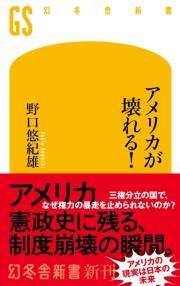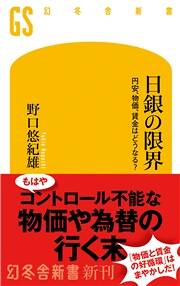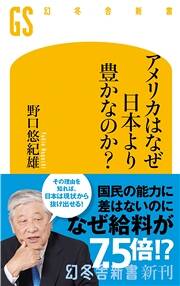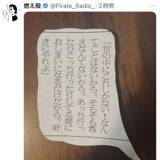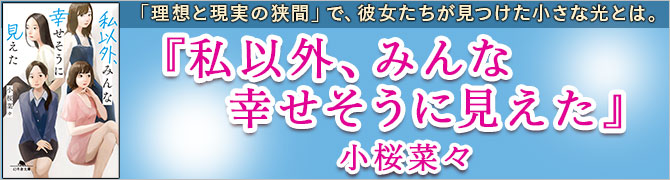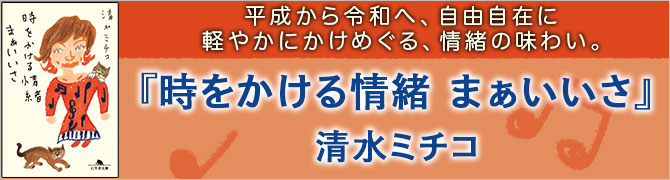なぜ世界最強の民主主義国家、アメリカは、権力の暴走を止められないのか?
その制度崩壊は、同盟国・日本の経済と安全保障にどのような打撃をもたらすのか?
経済学者・野口悠紀雄さんが、アメリカの現実と日本の危機を鋭く読み解いた、幻冬舎新書『アメリカが壊れる!』。本書より、一部を抜粋してお届けします。
* * *
フランス革命とアメリカ革命は、全く異なるものだった
ドイツ出身のアメリカの政治思想家ハンナ・アレントは、『革命について』(ちくま学芸文庫、1995年)の中で、フランス革命とアメリカ革命は、全く異なるものだったと述べている。
フランス革命は、身分の違いによって希望を断たれた平民階級が、既存の社会構造を覆そうとして起こした革命だった。そして、「社会的苦悩(misery)」の解消を優先した結果、政治が暴力へと堕していった。
それに対して、アメリカ革命は、植民地が不当に扱われているという不満から始まったのだが、植民地の人々は生死の境をさまよっていたわけではなかった。革命の目的は、イギリスの支配から脱して、自分たちの自由な国を建設することであった。そして、建国の父たちは、「公共的自由(public freedom)」という概念を中心に据え、持続可能な政治的秩序を作り上げた。

トランプ革命はプアホワイトの怨嗟に基づき、制度を破壊する
トランプ政権下のアメリカにおいて進行している現象は、「プアホワイト」と呼ばれる貧しい白人労働者が、社会の構造を覆そうとしているものだと捉えることができる。
その根源にあるのは、フランス革命当時の平民階級が持っていたのと同じく、現存の社会に対する不満だ。だから、これは、「制度を建設する革命」ではなく、「制度を破壊する革命」である。
プアホワイト層は、1990年代以降のアメリカ経済の新しい発展の中で、仕事と尊厳を失った。彼らが働いていた工場は海外に移転し、ラストベルトの工場は閉鎖された。
目覚ましい発展を始めたのは、シリコンバレーのIT産業や、ラストベルトの製薬産業であり、彼らが働いていた鉄鋼産業や自動車産業ではなかった。こうして、彼らは、エリート層に裏切られたと感じてきた。
この怨嗟の感情は、トランプ氏の「アメリカ・ファースト」とか、MAGAというスローガンに収斂する。ただし、その本質は、ナショナリズムではなく、エリート体制への「報復」に他ならない。そうであれば、エリート階級が攻撃の対象となるのは、当然のことだ。
「関税をかければ、ファブレス製造業には不利に働く」と指摘しても、「そうした先端産業で働くエリートたちを破滅させることこそ、我々の目的だ」との反応が返ってくるだろう。
だから、トランプ革命の本質は、フランス革命と同じものであり、「反アメリカ革命」なのである。

なぜ大統領に過大な権限?
アレントが指摘するように、「立法・行政・司法が相互に抑制することによって、権力の集中を防ぐ」という「三権分立」は、アメリカ革命を制度面で支える核心的な装置だった。
しかし、強固に見えたこの仕組みが、1970年代頃から徐々に変貌してきた。とくに重要な変化は、第1章の8で述べた1970年代からの通商政策の変化だ。1974年通商法や1988年包括通商競争力法などの導入によって、それまでは議会の権限であった関税率の決定が、大統領に委任されるようになった。
これらの措置は、1980年代~90年代の日米経済摩擦の中で導入された。当時のアメリカは、激増する日本やドイツからの輸入に攪乱され、経済が疲弊状態に陥っていた。それに対処するために、これらの措置が必要と考えられたのだ。
いまから見れば、こうした措置は、一時的なものとして廃棄されるべきだった。しかし、それらは放置された。そして、これらの特例措置が、今回の関税戦争を可能とする基本的な手段になっている。
これは、立法権限の行政への過剰な移譲という制度的劣化であり、アレント的視点からすれば、「革命を支えた制度」の破壊である。
これが三権分立のバランスを著しく壊すことになろうとは、その当時は、誰も考えなかっただろう。しかし、結果的に見れば、そうなっている。つまり、制度面からいうと、「反アメリカ革命」は、いまに始まったものではない。
三権分立が崩壊しつつあるアメリカ
トランプ大統領は、就任初日の2025年1月20日に、2021年の連邦議会襲撃事件で有罪とされた約1600人に恩赦を与えた。重大な犯罪で長期刑を受けた受刑者14人については、減刑の上、釈放を命じた。
これは、アメリカにおける「制度の死」を象徴する重大な出来事だった。司法によって有罪とされた者に対し、大統領が政治的思惑から恩赦を与えることは、法の支配の否定であり、三権分立の理念に反する行為としか思えない。
暴力的手段で選挙結果を覆そうとした者たちを「愛国者」と呼び、その行動を免責する措置は、民主主義の根幹にかかわるものだ。
これによって、選挙という制度の源泉が危機にさらされ、議会の権威は著しく低下した。形式上は立法・行政・司法の三権分立が維持されているかのように見えても、実質的には大統領の権力が突出しており、制度のバランスは破綻している。
アメリカ革命が確立した憲政的秩序は、いまや大統領の権限強大化で空洞化しつつある。これは単なる制度の劣化ではなく、アメリカ民主主義に対する内側からの破壊行為に他ならない。

エリート攻撃は必然?
こうした視点から見れば、トランプ政権が科学研究を敵視し、大学を弾圧する意味がよく分かる。それらは「エリート攻撃」という意味で、必然性を持っていると考えることができる。
バンス副大統領のブレーンであり、ノートルダム大学教授であるパトリック・デニーンは、「エリート層は大衆を恐れ、その不満を表現させないようにしている。これは、本質的に非民主主義的なことです」と述べている(注1)。
こうした認識は、保守主義内部に広く浸透している。これに呼応する形で、トランプ政権は、大学や研究機関を「敵」として扱い、科学的知見を否定する政策をとっている。こうした政策は、今後もますます先鋭化するだろう。
(注1)朝日新聞「(帝国の幻影 壊れゆく世界秩序)第1章 失敗した米のエリート層 副大統領ブレーン、米教授に聞く」2025年5月20日。
ソフトパワーの破壊
一方、ハーバード大学名誉教授であった故ジョセフ・ナイは、トランプ政権の行動様式を「ソフトパワーの破壊」と評した(注2)。
ナイが定義したソフトパワーとは、軍事力や経済力とは異なるものであり、文化・価値観・制度・政策といったものだ。
これらは、「他者を魅了し、自発的に従わせる力」であり、アメリカの国際的影響力の核心をなしてきた。とりわけ、民主的制度、法の支配、学問の自由、移民を受け入れる包摂性は、世界中の人々を惹きつけるアメリカの魅力の源泉であった。
しかし、トランプ氏は、こうした制度的基盤を軽視し、それらを破壊する方向に動いている。研究費の削減、大学の締めつけ、移民排斥、そして国際協調の否定は、いずれもナイの言う「アメリカの魅力」を破壊する行為だ。
これこそが、「トランプ革命」の本質である。それは、アメリカ内政にとどまらず、自由主義的国際秩序そのものを揺るがす事態につながっている。
世界各国は、これまでアメリカの制度的安定を信頼し、協調関係を築いてきた。だが、そのアメリカが魅力と信頼を失えば、国際社会におけるリーダーシップは瓦解し、力による対立の時代へと復帰する危険がある。そうだとすれば、この問題が世界に及ぼす影響は甚大だ。
(注2)日本経済新聞「ソフトパワー失うアメリカ ジョセフ・ナイ・ハーバード大学名誉教授」2025年5月3日。
* * *
この続きは、幻冬舎新書『アメリカが壊れる!』でお楽しみください。
アメリカが壊れる!
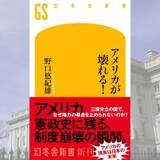
第2期トランプ政権の誕生以来、大統領の一挙手一投足がニュースにならない日はない。政策運営のあり方はアメリカの大学・研究機関や経済を弱体化させ、国内の秩序は崩壊寸前になっている。その影響は世界にも波及し、同盟国である日本の経済や安全保障への深刻な打撃は避けられない。こうした状況の中で、日本はいかに対抗すべきか? アメリカの政策の弱点はどこにあるのか? AI分野でアメリカに迫る中国は、新たな覇権国となりうるのか? かつてない不透明な局面で、日本の進路を示す渾身の一冊。