

この世にひとつしかないものと出会いたいという気持ちが、わたしの場合は強い。そういうものばかりで自分のささやかな王国を形成したいと、どうも願っているようなのである。
「記憶」『ふらんすの椅子』鈴木るみこ
いまわたしが座っている店の椅子からは、たくさんの置物やポストカード、ブリキの缶や木っ端などの並んでいる姿が見える。そのほとんどは日本各地で買い求めたものだが、中には展示のとき「店にどうぞ」と画家がつくってくれた手びねりの人形や、実家じまいの際に家から救出してきた張り子の面なども交じっている(母も彼女の言葉で言えば「こちゃこちゃと」民芸品を集めるのが好きな人だった)。
この雑然とした空間を見て、「ここは辻山さんの国ですね」といみじくも言ってくれた人がいたが、考えてみればその一つ一つに手に入れた時代と場所とが刻印されているのだ。中でもお客さんから尋ねられるのが、大福帳の台座の上に、卵から孵ったばかりの白ヘビが頭をぴょこんと突き出している置物である。
これは昨年の夏、福島県の大内宿に行った際に買い求めた。どこの大きな街からも離れた山村なのに(だからこそと言うべきか)、駐車場には車がぎっしりと停まっていて、かつて宿場町だったメインストリートには、古民家を利用した蕎麦屋や土産物屋があいだを開けずに並んでいる。予想以上の観光地ぶりに気がくじけそうになり、もう行こうかなと思った矢先、道ばたの木に小さく控え目な字で、「土人形」と書かれた紙が貼られているのを同行のAが見つけた。
少し奥まったところにあるその店は、遠目には周りと変わることのない、古民家の軒先を利用した店だった。しかしひな壇のように設えられた飾り棚には、昔ながらの素朴な土人形が大小様々に並べられ、その手前には小柄なおばあさんが、小さな椅子に腰かけている。最初彼女は冷やかしの観光客と思ったのか、何も話しかけてはこなかったが、我々があまりにも熱心に人形を見ているものだから、そのうちいわれについて説明しはじめた。
・これらの人形はここからずっと山のほうに入っていった工房で、職人が一人だけでつくっている
・人形は一つ一つ姿かたちが異なる。店に何が届くかは、その職人が持ってくるまでわからない
・白ヘビは神さまの使いで縁起がいい。特に商売をやっている人にはよろこばれている
などなど。おばあさんの隣には貫禄のある黒猫が、我々の存在など気にすることなく寝そべっていた。撫でても起きようとはせず、名前は「キュウ」というらしい。店には気の向いたときにしか出てこないという。
今日は久しぶりにここにいます。お客さんたちは運がいいですよ。
そういうとおばあさんは「どれでも好きなものを持っていってください」と、軒先で販売していた朝採れ野菜を指さした。

「鈴木るみこ」という名前を意識したのは、雑誌『クウネル』が創刊されたあとだったように思う。わたしはこの雑誌を10号くらいまでは熱心に追いかけていたが、それ以降は気になる特集があれば手にする程度の読者にすぎなかった。それでも鈴木さんの名前を記した文章を見かけると、それがその号の柱となる記事であることはすぐにわかったから、わたしは彼女のことを、『クウネル』を象徴する存在として受け取っていたのだ。
その後かなり時が経った2018年のある日。わたしは鈴木さんの訃報を知り、自分でもその存在を忘れていた大切な何かが失われたような気がした。あらためてよく考えてみれば、わたしは彼女の書く文章が好きだったのだ。しかしあたらしいものを目にする機会は、これで永遠に失われてしまった。
そしてそれから更に時が過ぎた今年の夏、彼女の遺稿集『ふらんすの椅子』が、出版社・港の人より突然発売になった。いつか本というかたちでその文章をまとめて読みたいと願っていたので、出版情報を見たときには、うれしさと同時に本当かな? という疑いが拭えなかった。そのことは多くの人も同じだったのか、本を買いに来られたかたはみな慌てて(本は逃げませんから!)、そして神妙な顔をして、大事そうに買って帰られた。
『ふらんすの椅子』は、雑誌などに寄稿された文章と、書き下ろしの単行本になるはずだった未発表の原稿を基に編まれた本だ。子どものころの思い出から、勤めていた出版社を退社し、憧れだったフランスに留学、そしてライターとして自分を発揮できる場所を得たあとのことまでが記されており、全体を通して読むと、一人の女性の魂の道行きが、自然なかたちで浮かび上がってくる。
冒頭に引用した文章は、この本の最初に置かれた「記憶」からの一節だ。わたしは同じエッセイを、もう少しプライヴェートにつくられた本でも読んだことがあるが、『ふらんすの椅子』で読むとよりその「願い」が切実に際立つようで、身に沁みた。
「(わたしは)そういうものばかりで自分のささやかな王国を形成したいと、どうも願っているようなのである」
思えば『クウネル』で鈴木さんが取材した人たちは、有名・無名を問わず、みな自分なりの「王国」を形成しようとしていた人ではなかったか。『クウネル』の記念すべき第1号は、「高橋さんは直線の部屋を探していた」からはじまる、高橋みどりさんの取材記事で幕を開けたが、それ以降の誌面には、自分の魂の居場所をつくった人たちが、鈴木さんの文章で大切な物語のように紹介されていた。
「記憶」は、フランスで暮らすようになった彼女が、その地で椅子を一脚購入するまでの話。そして「気に入った椅子を一脚」というのは、探しはじめるとこれが中々難しい。それは絶えず願っていないと現れず、「これが自分の人生なのだ」と言える時間を過ごしているあいだ、どこからか不意に差し出される贈りもののようなものだと思う。
たとえ人には短く感じられても、鈴木るみこさんは自分の人生を駆け抜けたのだ。
今回のおすすめ本
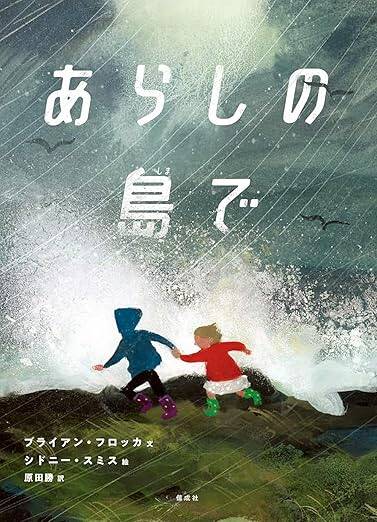
『あらしの島で』ブライアン・フロッカ=文 シドニー・スミス=絵 原田勝=訳 偕成社
嵐がくるその少し前の、生あたたかくて重たい空気。自然のスペクタクルを描き切った、迫力のある絵が魅力の絵本。
◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS
◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー
本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。
【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】
本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。
各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。
Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。
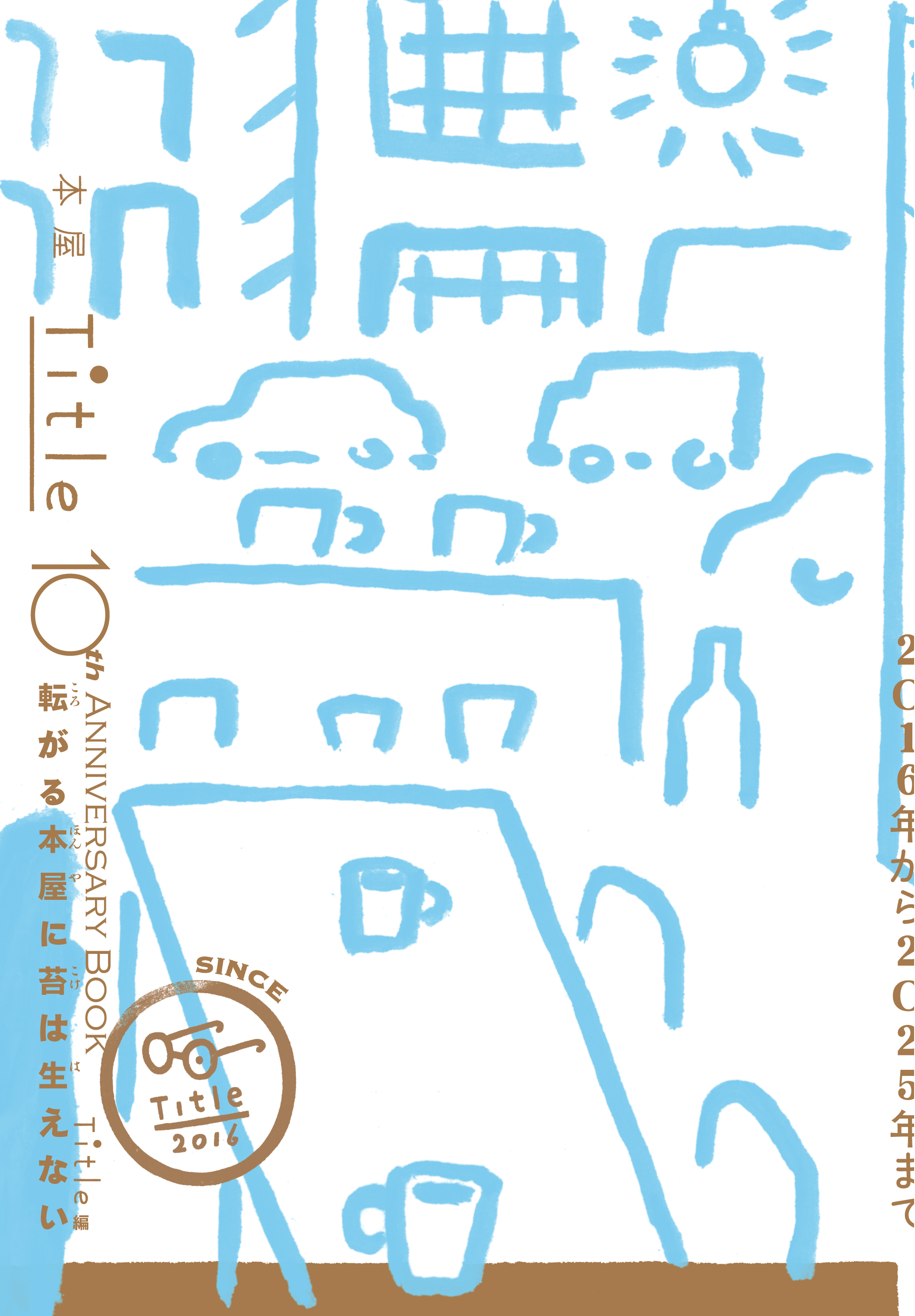 ■書誌情報
■書誌情報
『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』
Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画
256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)
◯【寄稿】
店は残っていた 辻山良雄
webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)
◯【お知らせ】NEW!!
養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)
「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄
今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。
NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。
偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。
本屋の時間の記事をもっと読む
本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

 本屋Title10周年記念展「本のある風景」
本屋Title10周年記念展「本のある風景」

















