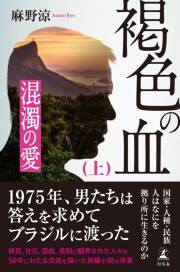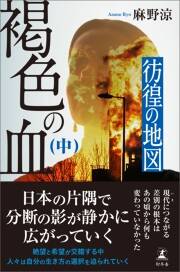過去と決別するためにブラジル移住に希望を抱く小宮の話を聞きながら、児玉はこれまでの人生を回想していた。
高橋幸春の名義で『カリブ海の「楽園」』で潮ノンフィクション賞、『蒼氓の大地』で講談社ノンフィクション賞を受賞した作家・麻野涼さんによる長編小説『褐色の血』。
その序章にあたる『褐色の血(上) 混濁の愛』の発売を記念して全5回にわたって冒頭を特別公開します。
冒頭公開の最後には著者による、本作に込めた思いも掲載します。(#1から読む)
* * *
中学一年生の時、児玉は横浜市長津田で暮らしていた。二学期の終業式を目前に控えた頃、神奈川県の作文大会で、ある女子生徒が優秀賞を受賞し、朝礼でその作文が本人によって朗読された。金という姓の在日朝鮮人だった。彼女は中学を卒業すると高校には進学せず、就職することになっていた。就職試験を受けるには履歴書を提出しなければならないが、日雇いで定職に就いていない父親の職業欄は空白だった。
民族差別によって父親は働く機会を奪われていた。そのことは彼女自身もよくわかっていた。しかし、彼女は父親を責め、職業を問い詰めた。作文はそれを後悔し、父に詫びる内容だった。そして、差別をやめてほしいと訴えていた。
朝礼台で作文を読む彼女は毅然としていた。在日朝鮮・韓国人の歴史などまったくわかっていなかったが、彼女の作文に感動したことを児玉は今も鮮明に覚えている。このことを忘れずにいるもう一つの理由は、児玉の横に周囲の視線も気にせずに涙を流している女子生徒がいた。作文を読んだ生徒の妹だった。
児玉が通った中学校はいくつかの学区から生徒が集まってきていた。のちに友人が、彼女たちが住んでいる地区に連れていってくれた。児玉の家の暮し向きも決して豊かとはいえなかったが、そこから通ってくる同級生の家はみすぼらしく見えた。
「あそこに汚ねえ家が並んでいるだろう。あそこがチョン公の連中の家だ」
戦前に建てられた、いわゆる長屋で家はひしげて見えた。屋根は雨漏りがするのか、ビニールシートのようなものでおおわれ、その上に石が置かれていた。
「チョン公って何のことだ」
児玉が聞いた。クラスには数人、その長屋から通ってくる生徒がいた。直接本人に向かって「チョン公」と呼ぶ者はいなかったが、裏では日常的にその言葉が飛び交っていた。
「お前、チョン公も知らねえのか。朝鮮人は皆、チョン公なんだよ。金の家もあそこにあるんだぜ」
「金て、金幸代さんのことか」
「ああ、そうさ」
児玉はそれ以上、長屋の住人を詮索することに罪悪感を覚えた。「チョン公」という侮蔑の言葉を悪びれずに繰り返すその友人と、遠くから長屋を眺めている自分も同罪のように思えた。クラスメートの金幸代に向かって「チョン公」と児玉も罵っているような気がして、その場を一刻も早く離れたかった。
「もっとそばへ行ってみようぜ」
「もういいよ」
児玉は長屋に背を向けて、一人で歩き出した。友人が後から追うように付いてきた。
「汚ねえだろう、なあ」
同意を求めるように友人が言った。それには答えず児玉が聞いた。
「どうして朝鮮人が日本にいるんだ」
「そんなこと俺も知らねえよ」
「なんでチョン公なんて言われるんだ」
「チョン公だからチョン公なんだよ。結局、外人だから差別されるんだろう」
何故、外国人だと差別されるのか説明になっていなかった。外国人とはいっても、彼らは日本語を話し、日本人と何一つ変わるところはなかった。児玉にはそう思えた。この世の中に貧富の差があることくらいはわかっていたが、朝鮮人、韓国人が差別されているという現実をその時初めて知った。
児玉は中学一年を修了すると父親の転勤で横浜を離れ、この姉妹のことも次第に記憶から薄れていった。
在日朝鮮・韓国人の差別が身近なものになって児玉の前に現れたのは、早稲田大学に通っていた時だった。
在日朝鮮・韓国人の二世らによって出版された「まだん(広場)」という季刊誌の編集部で朴美子と出会ったのだ。
その頃、児玉は大学の授業を放り出し、韓国を一ヶ月おきに訪ねていた。闘争目標を失って学生運動はセクト間の対立を激化させていた。早稲田も内ゲバ騒ぎで休講が続いた。テストはレポート提出に振り替えられ、図書館で日韓の歴史を調べていた時に、在韓日本人の存在を知った。
韓国全土に多くの日本人妻と呼ばれる人々がいた。一九一〇年から一九四五年まで朝鮮半島は日本の支配下に置かれ、その支配政策の一つに内鮮結婚があった。朝鮮人と日本人の結婚奨励である。
朝鮮人も天皇の下に「平等」であり、日本人、朝鮮人、「差別」することなく結婚すべきだ──これが朝鮮人の差別に対する怒りをそらすための手段であり、朝鮮統治を揺るぎないものにするための政策であることは明白だった。
一九四五年八月十五日の敗戦。この日を境にして、中国や朝鮮半島から続々と引揚者が日本の土を踏んだ。しかし、内鮮結婚によって結ばれた日本人妻は朝鮮の地に留まった。彼女らには朝鮮人の夫があり、愛すべき子供たちもいた。彼女たちが日本に引き揚げるためには夫や子供を置き去りにしなければならなかった。多くの日本人妻はそれを拒否したのだ。
敗戦と同時に彼女たちの運命は一変した。三十六年間の罪過が彼女たちやその子供に負わされた。彼らは貧困と差別に苦しんだ。政策とはいえ最も人間的なところで朝鮮の人々と関わった日本人女性やその子供たちが、日本人の罪過を一身に背負わなければならなかった。
日韓基本条約締結以後、日本人妻とその子供たちは日本の土を踏むようになったが、貧困に喘ぐ在韓日本人家族は帰国もできずに息をひそめて生活していた。児玉はトラック運転手のアルバイトをして旅費を稼ぐと、一人で韓国を訪れた。在韓日本人の問題を専攻した社会学のレポートテーマに選んだのだ。それ以来、韓国からの引揚者問題に深く関わるようになっていった。釜山と下関の間を日韓定期連絡船が就航している。児玉自身も数回この連絡船に乗り込み、引揚者と共に帰国した。
しかし、日本は決して安住の地ではなかった。彼女らに向けられた視線は惨めな敗残者を見る目に等しく、その子供たちは韓国人として差別された。日韓混血児たちの中には日本人であると主張した者もいた。同様に韓国人であると主張した者もいた。すべての者が日本に帰国後、差別の中で苦悩した。韓国人として生きるべきなのか、自分たちは日本人なのか。彼らの多くは生きる座標軸を見失っていた。

児玉は在日の交流の場として、一九七三年に創刊された「まだん」編集部に、彼らの意見を聞くために頻繁に顔を出していた。創刊直後にそこで朴美子と出会った。
「私、ウリマル(母国語)の勉強を始めたんです」
「今度、ソウルに行ったら韓日辞典を買ってきてあげるよ」
編著者の、金素雲のサインを書き入れてもらったものを児玉は持ち帰った。児玉は韓国を度々訪れているうちに、在韓日本人や広島、長崎で被爆し、戦後帰国した在韓被爆者の記事をいくつかの雑誌に寄稿し、原稿料を稼ぐようになっていた。詩人でもある金素雲を取材して以来、ソウルに行った時は時間が許す限り彼の家を訪ねた。
その頃の美子の韓国語は、簡単な日常会話を話せるようになっていた児玉に比べても劣っていた。彼女の家庭では韓国語を話すことはなかった。彼女は早稲田大学に進学したいと受験勉強に熱を入れていたが、大学に進学することが目的ではなく、在日韓国人サークルの韓国文化研究会に入るためだった。
児玉と美子は急速に親しくなり、アルバイトで書いた記事の原稿料が入ると、美子を連れて飲み歩くようになっていた。そして数ヶ月後には、ラブホテルに泊まる仲になった。
「美子、俺と一緒に暮らさないか」
「暮らしてどうするの」
「どうするって、気が合えばそのまま結婚したってかまわないじゃないか」
「冗談じゃないわ。結婚なんて考えたくもない」
「どうして」
「私は二十歳で死ぬから」
「俺は真剣に話をしているんだ」
「私も真剣なの」
「二十歳まであと一年もないだろう。その君が、何故、死ななければならないんだ」
「二十歳で死ぬと決めたからそれまでは生きているだけよ」
実際、美子はそれまで何度も自殺を試みていた。
その方法をいやというほど児玉は聞かされた。美子はセックスが終わった後、時にはその最中でも、その話を繰り返した。毎回同じことが続くと、話を聞いてやることが美子とのセックスをする対価のように思えてくる。美子にとっては前戯のようなものだったのかもしれない。聞かされる方は、サラダオイルをそのまま飲まされている気分で、吐くにも吐けずに、わだかまる思いだけが心に沈澱していく。
「愛している」児玉がその話を打ち切ろうとして言った。
「そんなかったるいもの、私は要らない」
「愛も家庭も何も要らないというわけか」
「そう」
「それで寂しくないのか」
「私の気持ちは日本人のあなたにはわからないわ」
児玉は美子の言い草にも辟(へき)易(えき)していた。
「在日も日本人も、所詮は男と女の関係でしかない。くだらんことを持ち出すな」
美子も苛立った表情を浮かべながら、バッグの中から小さな箱を取り出した。箱はすでに封が切ってあった。瓶の蓋を開け、小さな白い錠剤をシーツの上に撒き散らした。
「今、私のことを愛しているって言ってくれたよね。だったら私と死んで」
錠剤は睡眠薬だった。挑発的な目で児玉をにらみ付けた。
「断る。死にたければおまえが勝手に一人で死ねばいい。俺は止めない」児玉は怒鳴るように言い返した。
「私は韓国で生まれたかった。日本で生まれたばっかりにこんな重荷を背負った生き方をしなければならない。私は家庭なんて要らない。あなたにはわからない。私がどんな家庭で育ったか。まして私と同じ重荷を子供に背負わせることも、それを見るのも私には耐えられない」
児玉と朴美子の仲は急速に熱くなっていったが、それと同時に亀裂も広がっていった。二人は矛盾する感情を絡ませながら、体を求め合い、心をいたぶるような関係を続けていた。
朴美子は富士山の麓のある町で生まれた。家の前にK湖があった。美子がもの心つく頃には両親の不仲は決定的なものになっていた。「アイゴー」と泣き叫びながら父を引き止めようとする母の姿、その手を振り払い愛人のもとに走る父。二人は結婚したことを後悔し、口汚なく罵り合っていた。その罵声を聞きながら、美子は育った。
愛情豊かな家庭のイメージを育む代わりに、荒涼とした家庭像だけを紙を漉(す )くように脳裏に刻み込み、家族から無条件に愛されているという実感を抱くことなく、自分が存在することのやましさだけをK湖のほとりで醸成してきた。
両親に対する反発は彼女が中学生になった時、自殺という形となって現れた。
「私がどんな方法で自殺しようとしたかわかる」
「そんなこと、知りたくもないし、考えたくもない」
「ちょっと、クイズだと思って答えてみてよ」
こんな時の美子は不気味なほどあどけない表情を見せた。児玉の上に馬乗りになり、腰をくねらせ、時には上下させながら、笑みを浮かべ、美子の胸に手をあてている児玉の顔を覗き込んできた。
「私、考えたの」
「何を」
「アボジ(父)とオモニ(母)が一番、苦しむ自殺の方法を。わからないでしょう。私が考えたのはタバコを一本飲み込んでしまう方法」
朴美子はK湖にボートを浮かべ、その方法で実際に自殺を試みた。タバコを飲み込んだ直後、襲ってくる激しい嘔吐と体の震えを、意識がなくなるまで彼女は正確に記憶していた。彼女の自殺の試みは両親に対する彼女の未熟な抵抗だった。胃洗浄後も体内に吸収されてしまったニコチンによって、苦悶する自分の姿を両親に見せつけることが、彼女にとっては復讐だった。
「そんな話は聞きたくない」
付き合うようになって二年の歳月が流れていた。児玉は朴美子を真剣に愛していた。大学に入学したばかりの美子を連れてブラジルに渡ろうかとも考えた。しかし、美子の心の中には家庭というものが存在していなかった。まして子供を産み育てるなどということは到底考えられなかった。
美子は家庭を拒否していた。しかし、それは二人が別れた決定的な理由ではなかった。別れた本当の理由は児玉が日本人であり、朴美子が在日韓国人だったということだ。
在日朝鮮・韓国人一世の多くは結婚における血の純潔を守ろうとしていた。外国人の血が混じれば、その家系の血は薄れ、生活の秩序も風俗習慣も、朝鮮人、韓国人としての家の固い絆が破壊されてしまう。生まれた子供は混血児として、将来、悩み苦しむことになり、悲劇を生む。
日本人は朝鮮半島を支配し、侵略と差別の歴史を清算するどころか、差別をそのまま維持している。愛は国境を越えると言ったところで、日本人と朝鮮人、韓国人の間には宿命的な差別が存在する。
ゲルマン民族はその純血を唱え、優秀性を誇示してユダヤ人を虐殺し、ナチズムの道を突き進んだ。しかし、朝鮮人、韓国人が血の純潔を唱え、日本人との結婚を拒絶するのは、民族を維持し、存続するための自衛手段だった。これが在日社会では当然のこととして考えられていた。
しかし、これはあくまでも理屈の上での話だった。男と女の感情に民族などまったくの無力だ。二人は感情のおもむくままに抱き合い、愛し合った。セックスが終わった後、美子はアイデンティティ、民族、差別という言葉をしきりに口にした。
最初のうちは美子の話に真剣に耳を傾けていた児玉だが、またかと次第にうとましく思うようになっていった。適当に聞き流す児玉を、刺々(とげとげ)しい声で美子はなじった。
二人の別れは出会った時から始まっていたのかもしれない。児玉のブラジル移住はその契機でしかなかった。
まだ二人が知り合って間もない頃だった。早稲田大学の大(おお)隈(くま)講堂で在日作家の高史明が講演を行った。何のテーマで講演したのか、児玉は覚えていないが、最後に締めくくった言葉だけは鮮明に覚えている。
「在日を生み出したような世界のありように一筋の光を投げ掛けた時、在日は解放されるのではないだろうか」
児玉はその一筋の光を求めてブラジルに移住しようとしていた。その光を見出すことができない限り、朴美子と共に暮らせる日は永久に来ないと思った。
褐色の血
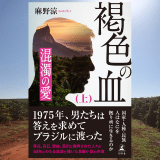
「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」
1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。
児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。
一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。
国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。
差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。