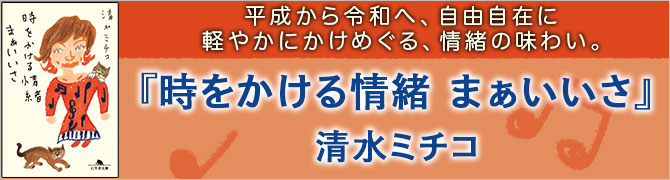取材でお世話になった知人の見舞いを兼ねて、当時カメラマンを務めた女友達とふたりで二泊の旅をした。山崎というウイスキーが世界一の賞をとり、入手困難になるかならないかという頃のことだ。
仕事を通じて知り合った彼女とはひどく波長が合い、二五年来の付き合いに。国内外さまざまな旅を重ねてきた。
どんなに長くいても疲れないのは、ともに酒好き路地歩きが好きというのもあるが、前もって調べたり予約するのが苦手という共通点も大きい。
そう、旅仲間との相性は、「好き」より、「嫌い」「苦手」の共通点が多い方がうまくいく。こういう考え方や価値観、習慣が苦手、というところで一致していると、ストレスがない。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
ある日、逗子へアジフライを食べに ~おとなのこたび~

早朝の喫茶店や、思い立って日帰りで出かけた海のまち、器を求めて少し遠くまで足を延ばした日曜日。「いつも」のちょっと外に出かけることは、人生を豊かにしてくれる。そんな記憶を綴った珠玉の旅エッセイ。
- バックナンバー