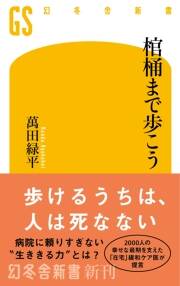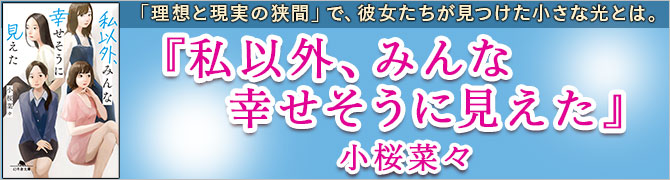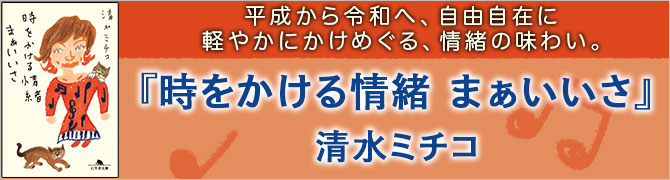不健康寿命が延び、ムダな延命治療によってつらく苦しい最期を迎えることへの恐怖が広がる今、「長生きしたくない」と口にする人が増えています。先行き不透明な超高齢化社会において、大きな支えとなるのが、元外科医で2000人以上を看取ってきた緩和ケア医・萬田緑平先生の最新刊『棺桶まで歩こう』です。
家で、自分らしく最期を迎えるために、何を選び、何を手放すべきか。本書の「はじめに」から、一部をご紹介します。
* * *
歩けるかどうかで「余命はほぼ決まる」
僕は、歩くスピードや歩幅で、その人の余命がほぼわかると考えています。
スタスタと歩ける人は、おおむね10年以上生きられるでしょう。イスから腕の力を使わずに立ち上がれる方なら、余命1年以上。立ち上がれない方は余命半年以内。ちょこちょことしか歩けない人は、余命数カ月、歩けない人は余命1カ月以内、というところです。
人間というものは、歩いている限りは死にません。
ですから本書のタイトルは逆に言えば、「棺桶なんかに入りたくなかったら歩こう」という提案なのです。
というわけで僕は、患者さんが自分で歩けることに徹底的にこだわっています。
僕の患者さんは、体重30キロでもスタスタ歩いています。その方はほとんど食べられず、栄養ドリンクを1日500㏄飲むくらい。その半年後、さらに25キロくらいまで痩せましたが、歩けます。25キロというと、ほとんど骨と皮です。それでも人間は歩けるのです。
歩くために必要な力は、実は「根性」と「気力」です。決して筋力だけの問題ではなく、自分のがんばりで歩くことができるのです。そして「がんばれる」ということは気力があること、つまり脳の若さです。
繰り返しますが、歩けるうちは、人は死にません。ですから、人間は気力によって、弱っていくのを遅らせることができる、余命を延ばせるのです。

だから僕は、患者さんに「余命は自分で測ってください」と言います。背筋を伸ばして座っていられる時間が長くなったら、余命が延びたと思っていい。短くなってきたら、「そろそろだなと思ってください」と言います。
頭がしっかりしている、気力のある人は、寝たきりがいやだから歩こうとします。亡くなる2時間前まで歩いていた、50歳の患者さんがいました。
自分の足でトイレに行って、戻ってから昏睡状態になり、その2時間後に息を引き取りました。すごくがんばって歩いていたから、歩けなくなったらすぐ亡くなるだろう……と思っていました。その方は、筋力がなくなったから歩けなくなったのではなく、脳が止まったのです。人間が死ぬときは、まず脳や腎臓や肝臓が止まります。次に肺が、そして最後に心臓が止まります。
心臓が止まる前に脳が止まりますが、高齢者だと亡くなる数日前に脳が止まる場合もあります。患者さんが若ければ若いほど脳は元気なので、亡くなる直前までしゃべっていられることが多い。この患者さんも50歳と若く、亡くなる直前まで脳が元気で気力があったので、歩けたのです。
脳が弱ってくるとぼーっとして、がんばれなくなるから歩けなくなります。逆に言えば、脳が元気でがんばれる、気力があるなら歩けるのです。
というような話をすると、ほとんどの方はこう言います。
「どうせ死ぬんだったら、死ぬ直前まで普通の生活がしたいよ」
そうなのです。今病気がある人も、健康だという人も、人間はみんないつかは死にます。であれば、せめて直前まで、自分の家で自分らしく生活をしたいのではないでしょうか。
寝たきりの「余命」と超延命治療の現実
では、寝たきりの人はどうでしょう。寝たきりになると、もうほとんど話せない方が多いのですが、先日診た患者さんはめずらしく、寝たきりなのに話をすることができました。そこで電動ベッドの角度を上げてみると、「疲れた」と言うのです。ベッドの角度を少し上げただけで、寝たままであっても「疲れる」と言う。もう、身体が重力に対抗できないのです。こういう状態になったら、余命はわずかと思ったほうがよいでしょう。
ただし、「超延命治療」を受けている患者さんは、寝たきりでもある程度生きます。ただし、それはただ「生かされている」状態と言ってもよいでしょう。
僕はもともと外科医でした。外科医として、病院でむりやり「生かされている」患者さんをたくさん見てきました。それは本人はもちろん、家族、また医師や看護師にとってもつらいものです。そうではなく、自宅で死ぬ直前まで自分らしく生きたい、歩きたいという思いは、人間の当然の願いだと思います。

自宅で最期まで暮らすために──緩和ケアの役割
17年前、僕は外科医をやめて、がん患者専門の訪問診療を始めました。患者さんが最期まで自宅で暮らせるようなケアをし、その一つの手段として緩和ケアを施しています。
「緩和ケア」という言葉を耳にすることは多いと思いますが、重い病を抱えている患者さんやその家族の、心身のさまざまな苦痛を和らげるための医療です。
僕はこれまで2000人以上の患者さんを、自宅で看取ってきました。亡くなる直前までご自宅で、家族や友人と笑い、好きなものを食べ、「ありがとう」と笑顔で去っていった方たちがたくさんいます。大好きなお酒を楽しんだり、タバコを嗜んだり、何よりも好きな競艇に出かけた人もいました。亡くなる直前までトイレに歩いて行くどころか、大好きなゴルフを楽しんだという方もいました。
本来死とは、苦しいものではありません。考え方を変えれば、こうした幸せな亡くなり方ができるのです。では、何をどう考えればいいのか。前向きなお話を、これからさせていただこうと思います。
僕は、病院での治療を否定するわけではありません。
ただ、治療をやめて、家で人生を終えるという選択肢も知ってほしい。
だから僕は、「棺桶まで歩こう!」と何度でも呼びかけたいと思います。
* * *
最期まで自分らしく生きたい方、また“親のこれから”を考えたい方は、幻冬舎新書『棺桶まで歩こう』をお読みください。
棺桶まで歩こう
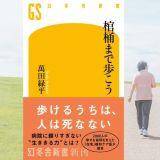
体力も気力も衰えを感じる高齢期。「長生きしたくない」と口にする人が増えています。
不健康寿命が延び、ムダな延命治療によって、つらく苦しい最期を迎えることへの恐怖が広がっているからです。そんな“老いの不安”に真正面から応えるのが、元外科医で2000人以上を看取ってきた緩和ケア医・萬田緑平先生の最新刊『棺桶まで歩こう』です。
家で、自分らしく最期を迎えるために――いま何を選び、何を手放すべきか。
本書から、一部をご紹介します。