
社会・教養
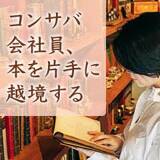
2025.05.24 公開 ![]() ポスト
ポスト
「コールレポート妖怪」
後輩たちは恐らく、私をそんなあだ名で呼んでいるはずだ。
コールレポートとは、面談や打合せで何を話したか記録する議事録のこと。作成したら、関係各所への送付・社内フォルダへの保存がマスト。お客さんとのアポの帰り、他部との打合せの後、同席していた後輩に向かって「コールレポート、早めにお願いね」が私の口癖。
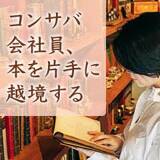
筋金入りのコンサバ会社員が、本を片手に予測不可能な時代をサバイブ。

日々更新する
多彩な連載が読める!
専用アプリなしで
電子書籍が読める!

おトクなポイントが
貯まる・使える!

会員限定イベントに
参加できる!

プレゼント抽選に
応募できる!