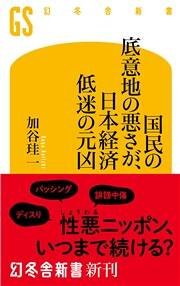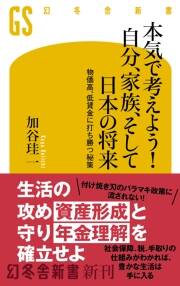日本人の隠れた本性が景気を停滞させている! 政府系金融機関などのコンサルティングを務めた経験を持つ加谷珪一さんが、日本経済の長期的低迷を「国民性」という誰も触れたがらない視点で暴いた注目の一冊『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』。本書より一部を抜粋してお届けします。
数字より空気が大事?データと科学を忌避する日本
日本は明治維新によって見かけ上は近代化を実現したことになっていますが、夏目漱石も指摘しているように、表面的に制度を真似ただけの部分も多く、内実が伴っているとは言い難い面があります。そして、こうした表面と内実のギャップが顕著に表れるのが国家や企業の意思決定です。
国家であれ企業であれ、近代的な組織において意思決定の基礎となるのは、データや自然科学(サイエンス)を土台とした客観的な状況分析です。

マクロ的なデータというのは恐ろしいもので、細部にわたって100%正確とは限りませんが、正しく扱いさえすれば、大まかな方向性についてほとんど間違うことはありません。筆者は数年前から日本の賃金や購買力が下がっており、貧困が拡大しているという主張を行ってきました。当初、筆者は凄まじいまでの誹謗中傷を受けましたが、筆者をバッシングしたところで現実が変わるわけではありません。筆者は感覚で主張しているのではなく、すべてデータに基づいた分析を行っています。結局のところ社会の変化は数字になって表れますから、データは決してウソをつかないのです。
ところがコロナ危機では、データと自然科学を重視するという基本原則がことごとく無視される結果となりました。
近代組織においては、科学的なデータ収集や分析は「専門家」が行い、「リーダー」はそこから得られた知見を元に最終的に決断を下すという明確な役割分担が確立しています。そしてデータの収集と分析はすべての基本であり、この行為が制限されることはあってはなりません(仮にリソースが足りない場合でも、可能な限り最優先すべき事項と考えるべきでしょう)。
近代組織ではラインとスタッフが明確に区分されていますが、データを分析し判断材料を提供するのはスタッフの仕事です。一方、その情報を元に決断を下し、指揮命令系統を動かすのはラインの役目であり、ラインのトップに立つ人をリーダーと呼びます。
ところが、日本の組織ではスタッフとラインの関係が曖昧であることが多く、近代合理主義に基づいた組織運営が無視されるケースが後を絶ちません。どの役職がスタッフなのか、あるいはラインなのか認識できていない人も多いのではないでしょうか。
状況分析を行うスタッフは、純粋に科学的知見に基づいて分析を行えばよく、その結果について周囲を忖度する必要はありませんし、ラインの人間がスタッフに圧力をかけて結果を変えさせるなどということも絶対にあってはなりません。そしてどんな決断であれ、その結果責任はすべてリーダーが負うことになります(そうだからこそリーダーの社会的地位は高いのです)。
「言霊信仰」の弊害? 数字や数式ではなく「言葉」で解釈したがる日本人
加えて言うと、近代科学というのは予言や魔術ではありませんから、将来の出来事を言い当てる必要もありません。前提条件を設定し、モデルを使って予想を行うのが専門家の仕事であり、結果が予想と違っていた場合には、どのパラメーター(変数)の設定を変えればよいのか、モデルのどの部分を修正すればよいのか突き止めるところまでが責任範囲です。日本では、悲観的なシナリオを提示したり、間違った結果を示した専門家をバッシングする人が後を絶ちませんが、これは近代合理主義や自然科学を理解していない野蛮な行為といってよいでしょう。
ちなみに近代以前の社会では、科学と魔術は区別されておらず、物理的にできないことができるとされたり、逆に実現可能なことであっても、不吉だ(あるいは不安を煽る)といった理由で拒絶されることが普通にありました。つまり自然現象と人間の感情が区別できず、自然現象の分析にも意思や情緒が入り込んでしまうのが前近代社会の特徴です。
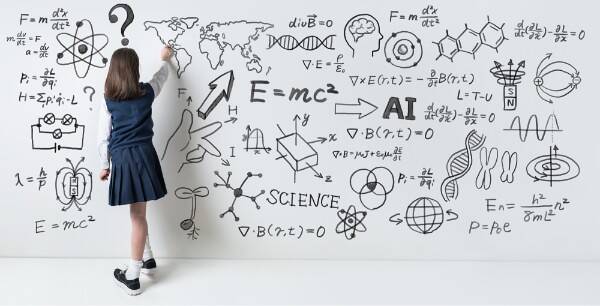
近代科学の基礎を作ったニュートン力学では、なぜ重力があるのかという根本的な問いには答えていません。物理学の教科書を見れば一目瞭然ですが、質量を持つ物質には重力という力が存在することを前提に、質量を持つ物質同士の力学的な関係を数式で示しただけです。ところが、この方法論が極めて重要な思考の転換点となりました。
数式を使った客観的な関係性の提示に専念することによって、情緒が入り込む余地を排除することに成功したのです。この画期的な業績によって魔術や予言と科学が完璧に峻別できるようになり、社会の近代化を推し進める原動力となりました。
筆者の大学の専攻は原子力工学だったので、自然科学に関しては一通りの基礎教育を受けてきました。まずは対象を観察し、普遍的な関係性や法則性を見出すという科学的思考プロセスは、自然科学の教育を受けた人間にとっては至極当然のことなのですが、日本ではこうした常識が通用しないことが多々あります。
福島第一原発の事故やコロナ危機では、対象の観察を抑制すべきであるという奇妙な意見が出てきたり、数字や数式ではなく「言葉」で解釈するという手法が横行しました。
断定は避けますが、日本の社会風潮には「悪いことを口にするとそれが実現するので口にしてはいけない」あるいは「不都合な真実に遭遇した場合には、正反対の言葉を声高に叫び、なかったことにする」という、ある種の「言霊信仰」が関係している可能性があります。もし、そうだとすると、この概念は近代国家あるいは近代社会とは到底、相容れないものです。
ムラ社会と情緒が支配する日本の意思決定
本書で何度も指摘してきたように、前近代的なムラ社会では、たいていの場合、合理主義とは正反対のプロセスで意思決定が行われます。集団を構成するメンバー同士の上下関係や情緒、あるいはその場の雰囲気が最優先されるので、科学的な知見が無視されたり、相互矛盾の状態が維持されたりするわけです。

欧米各国もローマ帝国崩壊以降、中世の時代までは、似たような意思決定が行われており、ルネサンスをきっかけに一気に開花した近代化の動きは、こうした知性なき社会に対する反発と考えてよいでしょう(欧米人が中世のことを自虐的に暗黒時代と呼ぶのはこれが理由です)。
日本も明治維新以後、日清戦争や日露戦争のように徹底した合理主義で決断が行われ、成功したケースもあるのですが、これは近代合理主義というよりも、維新という壮絶な権力闘争を勝ち抜いたリーダーの才能に依存する面が大きかったと考えられます。
近代的システムというのは、特定の個人の才能だけに依存するものであってはならず、仕組みとして合理的な意思決定ができなければ意味がありません。
* * *
この続きは幻冬舎新書『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』でお楽しみください。
加谷珪一さんの新刊『本気で考えよう! 自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策』も好評発売中!
国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶
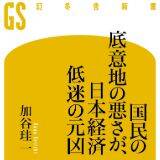
加谷珪一さんの新書『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』の最新情報をお知らせいたします。