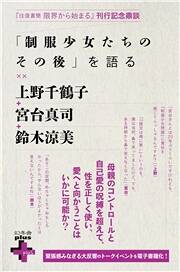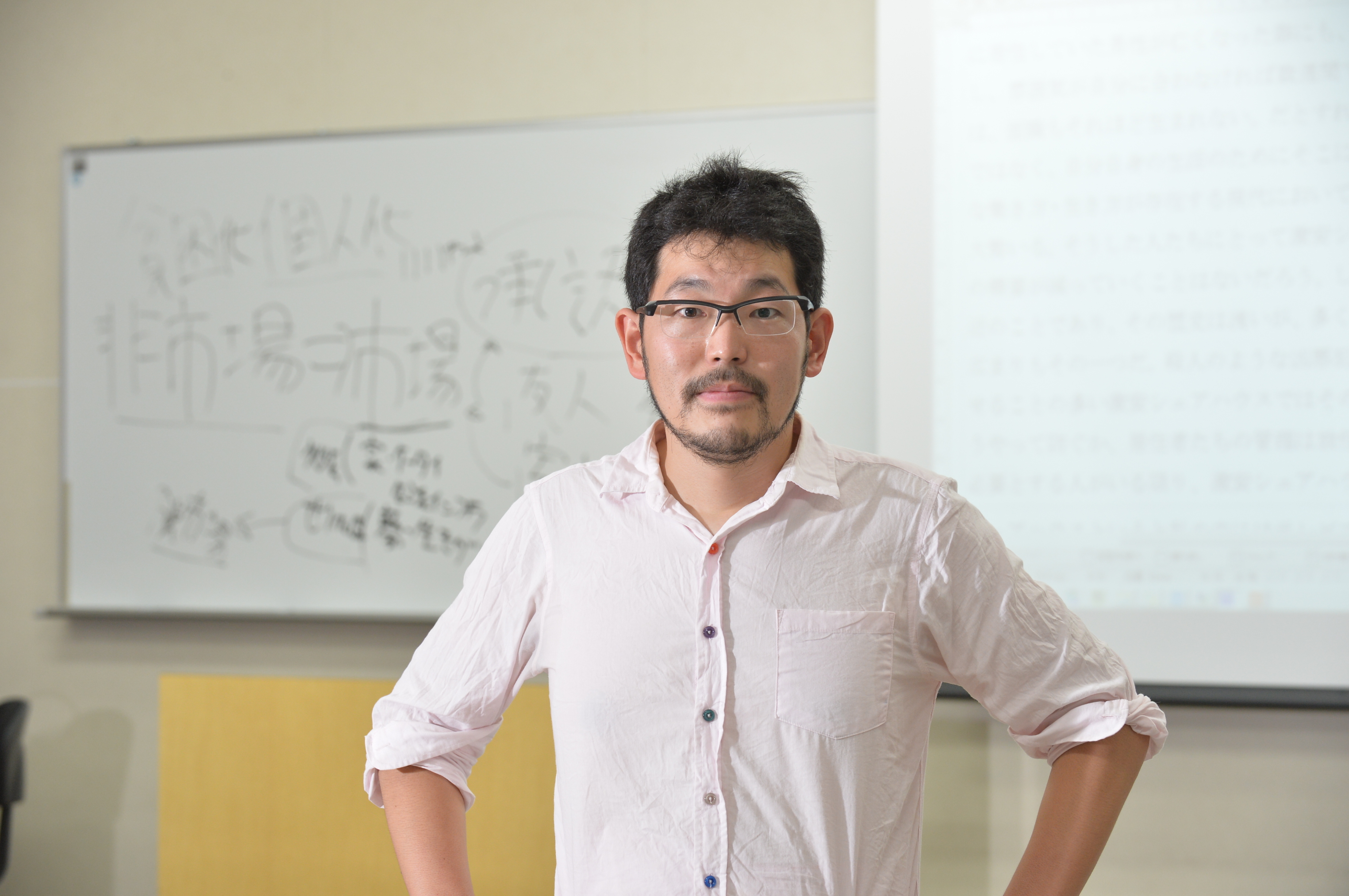ヒリヒリとした言葉が突き刺さる、上野千鶴子さんと鈴木涼美さんによる『往復書簡 限界から始まる』が話題です。男女の非対称性がはびこる日本社会で女性が生きることに真正面から向き合う本書は、共感か、反発か、自分のなかで蓋をしていた感情が刺激されることは間違いありません。と同時に、ここで描かれているのは、女性の生き方だけではなく、本質的には、社会の構造についてです。社会学者の開沼博さんにご寄稿いただきました。

3つの魅力と本書が残す大きな課題
鮮やかな試合だ。力量差がありすぎればそうはならないし、互角であっても傍から見れば膠着状態にしか見えないつまらないものになることもある。そもそも、何ら共有する土台が無く噛み合わない試合は見せ場も、深い意味も生まれようがない。だが、いまの世の中、そんな試合も多い。持てるものを曝け出して試し合い、それを見世物にするには相応の取り合わせが必要だ。
"小説の登場人物の設定としてもできすぎている"感すらある経歴と新聞記者を自主退職してからの物書きとしての(気づけば『身体を売ったらサヨウナラ』(幻冬舎)刊行からも7年経とうとしている)実績を積んできた鈴木涼美と、東大教授定年退職から10年を経てもなお鬱勃(うつぼつ)たる活動を多領域において続ける上野千鶴子。
両者の往復書簡は「エロス資本」「母と娘」「恋愛とセックス」「結婚」「承認欲求」「能力」「仕事」「自立」「連帯」「フェミニズム」「自由」「男」という12ものテーマを切り口にしつつ、一つの流れをなしている。読者はそれに身を任せながら他には存在し得ない風景を観る経験をすることになる。各テーマ自体に興味がなくても、あるいは「女」ではなくても、様々な理論や文学作品や現場のエピソードが散りばめられ読みあきることのない、また、我がこととして問いを突きつけられるような内容だろう。
鈴木が上野とどう対峙するか。隙を突き合うようなやり取りがあるわけではない。冒険心と行動力とそれを支え得るだけの力とをもった鈴木が、それをもってしても自分の中で突き詰められていない答えを探していく作業が(そういった意味で古代ギリシャ哲学的な意味での緊張感ある)「対話」の中で展開される。思わず他では言わないことを書いてしまったと繰り返すとおり、それは上野にもまた新たな思考を展開させていく。
両者の得たものとはまた別に、オーディエンスが引き込まれるであろう本書が持つ魅力。それは大きく3点あるように見える。
一つは、多くの人の悩み、それに向きあうヒントがここに様々に提示されているということだ。
ジェンダーやキャリア、老い。それぞれに全く悩みを経験してこなかったという人はおそらくいない。両著者には女、社会学、経済的・文化的に豊かな家庭の出自と通じるところこそあれ、生まれ育った土地も生きてきた時代背景も仕事の積み重ね方も人間関係・遊び方も当然違うし、何より年齢差が存在する。その個人的な立ち位置の差異を明かしながら、社会・政治を立体的に捉える普遍的な視座が提供される。
例えば、かつては同じ空間にいた同世代が、子どもの有無で全く異空間に分かれて生きるようになっていることを実感し、結婚して子どもを持つことを当然とするイデオロギーの強固さに戸惑う鈴木と、それに対する上野の応答は(その回答の内容自体は熱心な上野千鶴子読者からしたらベタな回答であるかもしれないが)温かみとリアリティを感じさせるものであり、少なからぬ読者の心の奥底に深く届くものとなるだろう。
2つ目は、両者の他の著作等には再現され得ない内容がここには描かれ、それは両者の為してきた仕事の核心を知る機会になるということだ。
鈴木の才覚は『「AV女優」の社会学』(青土社)に見られた論理的思考と、いまの主たる仕事に見られるそこにとどまらない言語化能力との「バイリンガル」性の中で発揮されてきたわけだが、その両言語が架橋される。本書は鈴木の今後への希望・上野の期待とともに閉じられていくが、将来振り返った時、「限界」にあるという鈴木にとってのターニングポイントとなるのかもしれない。
一方、それに対する上野の言葉のさばき方・振る舞いというのは、一通目での「お前の先生じゃないんだから先生と呼ぶな」という、逆にそう言われた側を恐れ多くさせるところからはじまり、(そういう些末な部分のみならず)議論の核心についてもある種の上野節のパターンの連続だ。卓越した職人・武道の達人・高名な宗教者が見せるような芸の円熟の極みを見せてもらったという感がある。大した読者ではない私ですらそう思うわけであるから、コアな上野読者からしたらよりニヤリとするところがあるだろう。
であるが、現在、そんな「上野千鶴子のライトユーザー・ヘビーユーザー」ではない読者に、この感覚を届けることが容易くないのではないか、と感じることもある。それはひとえに、これまでのこされてきた上野の仕事が膨大かつ多分野に及びすぎているからだ。その芸を知るにはまずこれを見れば良い、という何かがなかなか思い浮かばない。
例えば東大入学式でのスピーチを通して上野言説にはじめて接し感化された層がいる。それは若い世代の女性がという話にとどまらない。
先日、私の住居の管理人があのスピーチを知って「上野先生って良いですねー。徹子の部屋出るみたいだから見てみようと思って」と話かけてきたわけだが、それまで上野千鶴子を知らなかった、知り得なかった人に届くような花火をまだ打ちあげ続けているんだなと、そのアクチュアルな影響力に改めて驚いたところだった。
上野千鶴子のニーズが潰えない社会が継続してしまっている、常に新たな仕事をし続けている、肩を並べ乗り越えるオルタナティブが出てこない。色々背景はあるにせよ、需要は持続・拡大している。じゃあその時に「フェミニズムの」という形容だけでは表しきれない一つの生態系を作っている体系、いわば「上野千鶴子学」とはなんぞやということを掴む上で、本書は学術的専門家以外に対しても推奨できる一つの選択肢となるだろう。
3つ目は、鈴木の「悟り」と言い表しても大げさではないだろうこの重厚な対話の結論のもつ現代的意義だ。すなわち、鈴木の「実践的なレベルで自分の幸福感を毀損せずに、しかし傷は傷として知覚し、またその傷を作る構造自体を疑っていく、というバランスを取るのは本当に難しいことだと思います」という一文に集約されていく思考。その前提となったタテマエが変わることこそ変革だという上野の言明。
このゴールに向かう出発点には、鈴木の男への絶望、被害者としての立ち位置をとることへの拒絶感、といった具体的かつ固有の問題意識があった。しかしながら、この結論には広範な現代の病理に見えるものに対峙する知恵が詰まっているように、本書を通読した読者には感じられるはずだ。改めて提示されたホンネ・タテマエ論も、ホンネがネットに溢れ、ホンネ風の言説を器用に量産する政治家・論者が求心力を集め、しかしそれが人に届き、社会を変容させているわけでも必ずしもないように見える現代において、多くの人の想像力を喚起するだろう。
そして、鈴木が「本当に難しいことだと思います」と言うとおり、ここに本書が残した大きな課題も見えるだろう。
理論的にそれしかない、として、じゃあそれをだれが、いかに実践できるのか。担い手は担い手であり続けられるのか。
例えば、フェミニズムの理屈を理解した上野の教え子も少なからず(その理屈にはそぐわない)制度的な結婚をし、それを上野に言い辛そうにする。いや、自分自身はその選択はしないけど祝福はする、と上野は常に言っているわけだが。世の中、理屈でわかっていても、それを実践できるかは別だ。
ホストクラブにもある「市民社会の分断」をどう突き詰めるか
上野が以前から鈴木に興味を持っていたというところから本書ははじまるが、それがなぜなのかというところは結局最後まで明確には言及されていない。人への興味なんて直感的なものだからそこに論理的理由は無い、のかもしれないが、少なくとも、学者・メディア人・実践者という3つの側面を持つ上野にとって、鈴木もまたその3つの側面を持つ、持ちうるという点で稀有な存在に見えたのではないか。
専門知をもって知識生産者としての鍛錬をしてきた学者として、メディア上で変幻自在に振る舞いオーディエンスを魅了する者として、社会変革の実践者として。上野自身はこの三つ巴の人格をもっているが、これまでの対話者の多くは、そのうちのどれか1つしか持たない。通常はどれか1つの人格で十分だが、鈴木は3つをあわせ持つようにも見える。両者の邂逅は理屈を実践につなげていくのだろうか。
基本的には大きな溝も無く話は前に進んでいくように見えるが、もう一点突き詰められていないように見える問題がある。
対話の終わりにかけて「自由」というテーマで触れられた「炎上→謝罪・削除」がループする文化の危うさ、そこに象徴されるような現代社会のあり様への鈴木の懸念は、仮に両著者と読者の中で解消されたとしても、むしろ加速・深刻化し続けている現実だろう。
上野による、「公権力/市民活動」と切り分け後者ならOK、というような単純な図式には回収しきれない問題は巷に溢れている。例えば、鈴木がホストクラブで目にする「プライドの置き所の違う女の子たち」同士の(政治・社会が表立って為すものではない)「熾烈な分断と差別」のように、市民レベルの生権力的な、相互不信の中で生まれる葛藤・足の引っ張り合い・潰し合い。これこそが、例えばトランプ現象を、大阪・東京、あるいは日本全体の政治権力の強固さを、3.11後の福島や新型コロナ禍に関するデマ・差別の蔓延を、他のここ10年ぐらいの諸々を生み出し、新たな抑圧を生み出している。
「市民活動」が常にどの「市民」にとっても都合が良いわけはなく、"幸福感"も"疑われるべき構造"も、一枚岩であるはずもない。そこかしこの市民の中に抑圧をする側に立ちやすい強者と弱者の溝が生まれている(例えばある種のトランプ支持者は、自らこそが虐げられ、最もラディカルに構造を疑っていると認識してきただろう)。
鈴木はフェミニズムについて、「私たちの語りをうまく利用して、主体的だとか逆に犠牲者だとか言っている学問だと感じることも多かったのですが、そんな日常は女の人生のごく一部だった」と自らのかつてのシニカルな視点を振り返る。いまも、フェミニズムに限らない様々な対象への、新たなシニシズムが、必ずしも公権力に根源をもつものではなく、市民の内部でこそ生まれ続けているであろう現実は、ホストクラブの風景にとどまらず、またマクロな政治のみならずミクロな部分でも鈴木の目にうつってきていて、それ故にここで問題提起したのではないかとも思わされたが、ここは鈴木が"物分りが良い対応"で終わっているようにも見える。
より高解像度の目をもって現代社会の隅々を見ている部分もあるだろう鈴木の視座からより深い議論が提示されれば、皮相的ではない形で、既存の構造を揺るがす具体的道筋が見えたかもしれないと思わされた。とは言え、この論点は対話の終わりにかけて出てきた話であり、紙幅の関係もあるだろうから、また次の対話を楽しみに待ちたい。
"構造に抗って生きる"ことはもちろんのこと、"構造のもとで強かに生き伸び、構造自体を変化させていく"=バランスを取ることも大方の人にとっては容易ではない。「それにもかかわらず」実践することは可能なのか。挑戦しがいのある問いが託されている。
【お知らせ】
12月3日(水)19時半~21時半、上野千鶴子さん、鈴木涼美さん、伊藤比呂美さんによるオンライントーク「結婚すること、産むこと、育てること。そして老いること、ケアすること」を開催します。
詳細・お申込みは、幻冬舎カルチャーのページをご覧ください。
往復書簡 限界から始まる

7月7日発売『往復書簡 限界から始まる』について
- バックナンバー
-
- 「どうやって男に絶望せずにいられるのか」...
- 妊娠すると自分の心の変化を語りたくなるの...
- 「娘の母になることへの恐怖は、上野さんの...
- 「このまま子どもは作らない人生を生きるの...
- 「文庫解説は伊藤比呂美さんにお願いしたい...
- 「結婚」「妊娠」「看取り」…上野千鶴子、...
- 鈴木涼美さま「『被害者』と呼ばれたくない...
- 上野千鶴子先生「女性は『被害者』だと受け...
- 「何回も泣いた」上野千鶴子・鈴木涼美の往...
- 上野千鶴子×宮台真司×鈴木涼美 「時代の...
- 上野千鶴子さん、鈴木涼美さんも参加の読書...
- 女であることに窒息しながらも、女であるこ...
- 上野千鶴子さん、鈴木涼美さんの直筆サイン...
- 上野千鶴子へのニーズが消えない社会で鈴木...
- 私だって放蕩娘になりたかった。女性ばかり...
- 鈴木涼美を母と男の手から離し、人間として...
- 往復書簡を依頼したのは2020年3月12...
- 上野千鶴子さん鈴木涼美さんが往復書簡を終...
- 上野千鶴子と鈴木涼美による手加減なしの言...