
もし大好きな姉の夫が殺人犯で捕まったらーー。衝撃タイトルと、そして驚愕の事件から始まるミステリ『まだ人を殺していません』。気になりすぎる本編を一部お楽しみくださいませ。
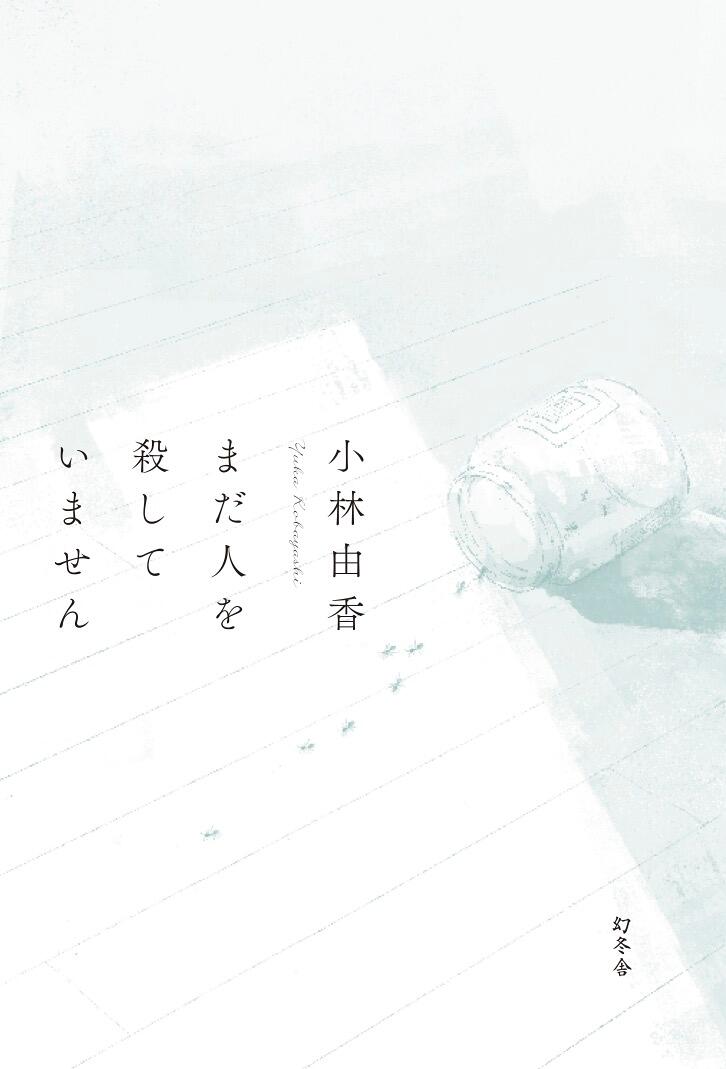
遅い時間だったせいか、道が空いていたのでちょうど二十分で兄の家に到着した。
南国のリゾート地を連想させるようなオフホワイトの外観。広い庭にはヤシの木が植えられ、モダンなタイルテラスが設置されている。まるで住宅雑誌から出てきたような豪奢な造りだった。
門の表札には『桐ケ谷』と書かれている。
兄の葉月雅史は、結婚相手の麻友子がひとり娘だったため、婿養子になったのだ。
家の中で防犯カメラの映像を見ていたのか、玄関のチャイムを鳴らす前に勢いよくドアが開いた。セキュリティ対策が万全なのは羨ましいけれど、監視されているようでいつも落ち着かない気持ちになる。
ドアから顔をだしたのは麻友子ではなく、兄だった。いつもは健康的な印象を与える小麦色の肌がくすんでいる。顔には隠しきれない疲労が滲み出ていた。
なにかを確認するように庭に視線を走らせてから、兄は家の中へ招いた。
「迎えに行けなくて悪かったな」
選挙に出馬する予定の兄は、義父に「車の運転を控えるように」と言われていたのだ。
私は気になっていたことを尋ねた。
「麻友子さんは?」
「体調が悪くて……今は自室で子どもたちと休んでる」
兄は掠れた声で「あがってくれ」と言い残し、リビングに続く廊下を歩きだした。
急いで靴を脱ぎ、背の高い兄のあとを追いかけた。普段は姿勢のいい背中が、少しだけ丸まっている。そのせいで身長まで縮んでいるように見えた。
子どもの頃、姉や兄は歩くのが遅い私を気遣い、いつも歩幅を合わせてくれた。だから寂しい思いをした経験はなかった。
今日はなぜか、幼い頃の思い出ばかりが呼び覚まされる。
リビングに入ると、息を呑むほど豪華な家具や調度品が並んでいた。イタリア製の巨大な猫脚テーブル。それを囲むように深緑の革張りのソファが置いてある。スタイリッシュな棚が並び、その上にはトロフィや賞状がたくさん置いてあった。兄の息子たちのものだ。彼らはスポーツや作文が得意で、表彰されることが多いようだった。
ソファを勧められ、私が腰を下ろすと、兄は緑茶のペットボトルをテーブルに置いた。贅沢な部屋に似つかわしくないペットボトルは、緊張している気持ちを少し和ませてくれる。
兄は乱暴な手つきでキャップを外し、緑茶を一口飲んでから苦い顔つきで言った。
「さっき警察と児相から連絡があったんだ」
「児相って……児童相談所のこと?」
兄は顔をしかめてからうなずいた。
「一時保護所で良世を預かっているそうだ。もうすぐ夏休みだが、通っている小学校には就学義務免除の手続きを行ったらしい」
なにもかもが初めての出来事だったので、話についていけない。
良世には何年も会っていないけれど、歳はすぐに答えられる。
娘と同い年だったからだ。私は姉よりも二週間早く娘を出産した。
当時、私は二十八歳、姉は三十二歳。ふたりとも初産だったので不安なことも多く、よく電話で相談し合っていたのを鮮明に覚えている。私は埼玉、姉は新潟にいたので、身重の身体では簡単に会えなかった。けれど今となっては、同じ日本にいるのだから、もっと頻繁に会っておけばよかったと後悔している。
良世を出産後、姉は羊水塞栓症で帰らぬ人となった。
姉が亡くなった日、不思議な夢を見た。光に包まれた姉は「ショウちゃんの出産が先でよかった。不安にさせちゃうから」と優しく微笑んでいた。
目覚めたときは、その言葉の意味が理解できなかった。けれど、姉が亡くなったという連絡を受けて、正夢だったのではないかと実感した途端、胸がわなないて涙がこぼれてきた。いつも優しい姉は、最期まで妹を気遣ってくれた気がしたのだ。
私は良世の顔を知らない。
姉の葬儀の日、面会を求めると、勝矢に「良世はまだ病院にいるので、会えません」と断られた。それでも兄が食い下がると、彼は冷たい口調で「面会は無理です」とつぶやいた。小さな声なのに拒絶するような威圧感があったのを覚えている。その後、良世のことが気になって連絡しても「元気で過ごしています」と迷惑そうな声で言われ、一方的に電話を切られた。子どもがまだ小さく、住んでいた場所も離れていたため、容易には会えず、たまに電話をかけて簡単な現状報告をするくらいの浅い関係になっていた。
こんな未来が待っているなら、もっと気にかけてあげるべきだった。けれど、それは今だから思えることで、当時は自分の子育てもうまくいかず、心に余裕がなかったのだ。
「最初から怪しいと思っていた。だから俺は、あれほど姉貴の結婚に反対したんだ」
兄はこちらに鋭い目を向けながら悔しそうに吐きだした。
きつい視線に射すくめられ、私は反射的に目をそらし、唇を嚙みしめて顔を伏せた。
両親が他界してから、兄は妙な責任感を持ち始め、姉や私に対して過剰なお節介を焼くようになった。亡くなる間際、母から「家族をお願いね」と頼まれたのが原因なのかもしれない。
姉から勝矢を紹介されたとき、少し地味な印象があるものの、真面目そうな雰囲気に好感が持てた。ふたりは目が合うたび、優しい笑みを浮かべ、互いを労っているように見えた。けれど、慎重な性格の兄は納得していないようだった。結婚が決まったとき、調査会社に依頼し、勝矢の身辺を調べさせたのだ。
送られてきた調査報告書には、哀しい経歴が記載されていた。
幼い頃に両親を事故で亡くした勝矢は、独り身の叔父に引き取られ、そこで問題行動を起こして児童養護施設に移されたという。その後、中学生になった勝矢は更生し、もう一度叔父の家に戻り、大学の薬学部を卒業したそうだ。育ててくれた叔父は数年前に死去し、現在は身寄りのいない状態だと書かれていた。
姉の結婚に否定的だった兄を説得したのは、紛れもなく私だった。大切なのは生い立ちではない。姉には本当に好きな人と幸せになってほしかったのだ。
私は静かに息を吐いてから、頼りない声で訊いた。
「警察は……お義兄さんのことをなんて言っていたの?」
「姉貴は死んで、あいつとはなんの繫がりもないんだから二度と『お義兄さん』なんて呼ぶな」
兄は厳しい声で忠告したあと、顔を歪ませて言葉を続けた。「警察は根掘り葉掘り事情聴取するくせに、こっちが質問すると『捜査中なので詳しいことは話せない』の一点張りだ。だが、あいつの自宅から遺体が発見されたなら、殺害したのは事実だろ。子どもを殺めるなんて鬼畜の所業だよ」
鬼畜の所業。さっき見たふたりの写真が頭に浮かんだ。
初めて会ったときは真面目そうな人物に思えたけれど、私は真実を見誤っていたのかもしれない。勝矢の取り繕った仮面が砕け、歪んだ顔があらわれる。良世に会わせてもらえなかったのは、なにか理由があったからなのだろうか。今思えば、写真の作られたような笑みも、どこか軽薄そうな雰囲気を漂わせているように感じてしまう。心に怯えがあるから、否定的な見方をしてしまうのだろうか。
胸の中の不安が濃くなり、私は重い口を開いた。
「良世はこれからどうなるの」
「専門的なケアが必要ないと判断されたときは、俺のところに連絡が来るようになっている」
「連絡が来たら?」
「一時保護所に迎えに行く」
「お兄ちゃんが引き取るの」
一瞬、兄の顔が曇った。
しばらくの沈黙のあと、兄は暗い表情で言葉を吐きだした。
「俺には子どもがいるから無理だ。麻友子はひどく動揺していて、とにかく殺人犯の息子と一緒に住むことはできない」
「殺人犯の息子」という残酷な言葉に胸がずきりと痛んだ。
私は微かに芽生えた怒りを呑み込んで訊いた。
「良世を児童養護施設に預けるつもり?」
「それはできない。県議会議員の義父は、子育て支援の充実や子どもの貧困対策に力を入れている。里親や養子縁組制度の普及についてもそうだ。施設に預けているのをマスコミに嗅ぎつけられたら大問題になる。南雲勝矢とは血縁関係にないから加害者の家族という面においてはどうにか逃げ切れるが、良世の今後については慎重に考えろと釘を刺された」
兄は悔しそうにテーブルを睨みながら吐き捨てた。「地元の企業や支援者との関係も良好だった。俺もこれから選挙へ出馬しようとしていた矢先だったんだ。バカなことをしてくれたよ。もう名刺や広報誌作りだって進んでいたのに、すべて見送りになりそうだ」
なぜ私を呼んだのか、その身勝手な理由を理解した。心にある不安が一気に増大していく。
兄は顔を上げると核心に迫った。
「独り身のお前なら、良世を引き取っても問題ないだろ。金ならできるだけ援助する。もう九歳だから普通養子縁組も視野に入れて──」
私は遮るようにして声を上げた。
「ちょっと待って、無理だよ」
「再婚したい相手でもいるのか?」
兄妹間で恋愛の話をしたことがないので気まずくなる。
しばらく逡巡してから、胸に秘めていた決意を口にした。
「もう二度と結婚するつもりはない」
「それなら良世を息子にすればいい。結婚する気がないなら、ちょうどいいじゃないか」
「どうしてそんなに軽く言うの」
「軽く? あれだけ反対したのに軽い気持ちで姉貴の結婚に賛成したのはお前だろ」
その子どもじみた責任追及に、かっと頭に血がのぼった。
「私たちはいつもお姉ちゃんに助けてもらったよね。学生時代のこと覚えている? お兄ちゃんが大学を中退して劇作家の道に進みたいって言ったとき、お父さんはすごく怒ったよね。私は、お父さんが怖かったから口出しできなかった。でも、お姉ちゃんだけは助けてくれたじゃない。『みんないつかは死ぬ。限られた時間を生きるなら、やりたいことをやればいい』って味方してくれた」
兄は鼻で笑うと、大切な思い出を切り捨てた。
「いつの話だよ。あの頃は幼稚な夢を見ていたんだ。親父の判断は最善だった。姉貴はいつもどこか甘いんだ。結婚だって、俺の意見に耳を傾けていれば、あんな男と一緒にならずに済んだはずだ。そうすれば命も奪われなかった」
「麻友子さんが引き取ることに反対しているの?」
「子どもがいる母親なら、殺人犯の息子なんて引き取れないだろ」
「そんな言い方……」
「息子に罪はないのはわかってる。俺が独り身なら、迷うことなく引き取れるが、俺たちには大事な息子がいるんだ」
こちらをまっすぐ見据える兄の目に噓は見当たらなかった。
責められた気分になり、小声で返した。
「私は……」
「自信が持てないか。子育てに失敗したからか?」
冷淡な口調とは違い、兄の顔には憐れみの表情が浮かんでいる。「失敗」という言葉に失意を感じ、私は痛みを紛らわすように残酷な言葉を投げた。
「お兄ちゃんは立派だよ。人生で負けた経験も失敗したこともほとんどないよね。でも、それって人の痛みに鈍感だったからじゃない。誰かの痛みに気づかない振りをして、いつも安全な道を選んで生きてきた結果だよ」
「なにが言いたいんだ」
「あのとき……命がけで助けてくれたのはお姉ちゃんだった」
兄の顔からすっと表情が消えた。
なぜだろう──他人には言えない暴言も、家族が相手だと吐きだせてしまう。とことん傷つけてやりたくなるときがある。
小学三年の冬に起きた事件。あの忌まわしい記憶が頭から離れない。心の奥底に隠した怒りが、まだ燻っていた。姉が助けてくれなければ、私の人生は大きく変わっていたはずだ。
言葉にならない哀しみを視線に込めながら、口を動かした。
「あのとき、お姉ちゃんはとても怖かったと思う」
兄は苛立った表情を浮かべて言い返した。
「俺は逃げたわけじゃない。助けを呼びに行ったんだ。あれが最善の判断だったと今も思っている」
「そうだよ。最善だった。だからお兄ちゃんを責めているわけじゃない。ただ、最善じゃない判断だからこそ、救われたんだと思う」
「そんなに姉貴を神みたいに崇めたいなら、お前が良世の面倒を見ればいいだろ」
「私が……引き取る」
唇が震えて視界が滲んだ。自分の言葉に驚くほど、無意識だった。押し寄せる不安を打ち消すように「良世は、お姉ちゃんが命がけで産んだ子だから」と続けた。
ソファから立ち上がり、リビングを出ていこうとしたとき、うしろから「タクシーを呼ぶよ」という声が聞こえたけれど断った。
私は振り返ると、自分自身に言い聞かすように言った。
「この選択は最善ではないかもしれない。でも、良世が一緒にいたいと思ってくれるなら……引き取ろうと思う。命がけで助けてくれたお姉ちゃんのことを絶対に忘れられないから」
姉とのあたたかい思い出ばかりがよみがえってくる。
ピアノの発表会の前日、会場に行きたくないと言いだした私に、姉は小さな女の子の人形を作ってくれた。まるで人形が喋っているかのように腹話術で「ピアノを聴かせて。翔子ちゃんの奏でるピアノが大好き」と言ってくれた。発表会当日、私は譜面台に人形を置き、彼女のためだけにピアノを弾いた。まるで魔法のようだった。一気に緊張はほぐれ、氷のように固まっていた指がスムーズに動き始めた。演奏を終えてから気づいた。心が強くなる魔法を与えてくれたのは、姉だったのだ。
親から期待されなかった私が、自分らしく生きてこられたのは姉の優しさのおかげだ。
勝矢の有罪が立証されれば、良世は間違いなく殺人犯の息子になる。まだ小学生の幼い子どもなのに、その残酷な事実を背負って生きていかなければならない。
なにもかもが怖く感じる。問題なく育てていける自信なんてない。この先のことを考えると心に濃い霧が立ち込めてくる。
それでも歯を食いしばり、薄暗い道を震える足で進んでいく。
闇夜の中、姉の言葉が耳の奥で繰り返し響いていた。
──ショウちゃんの出産が先でよかった。不安にさせちゃうから。
次回に続く
まだ人を殺していません

書き下ろし感動ミステリ『まだ人を殺していません』(小林由香著)の刊行記念特集です。
















