
なにげない日々のなかにある静かな熱狂を描く宮崎智之さん。単行本『平熱のまま、この世界に熱狂したい』にも収録された本エッセイに登場する、ケンイチさんは、会社員をしながら約20年、宅録を続け、このほどdifferent calfとして1stデジタルEP『velvet』をリリースしたとのこと。お祝いの気持ちとともに、あらためてご紹介します。
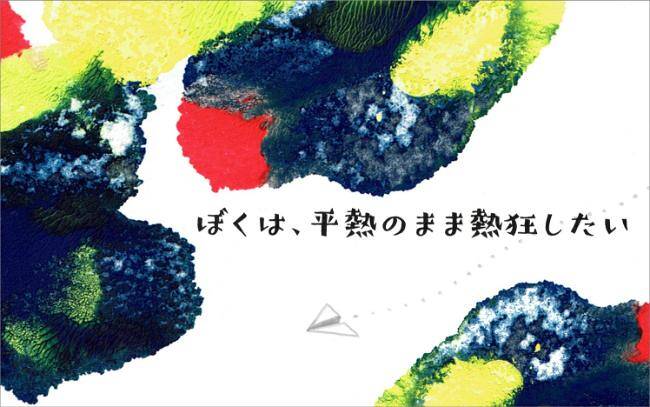
ケンイチに会うたびに、「こいつ恐竜の赤ちゃんみたいな顔してるな」と思う。思い出すのは、『REX』という映画。ぼくとケンイチと同い年である安達祐実の好演が、可愛らしい恐竜のレックスとともに記憶に残っている。亡くなった父が、初めて連れて行ってくれた映画だ。
さすがに最近では少しおじさんになってきたが、20代後半くらいには見える。そのことを女の子に指摘されても、興味なさそうに受け流しているけど、まんざらでもない様子がぼくには手に取るようにわかるため、心の中で「恐竜の赤ちゃんだけどな」とツッコミを入れている。
38歳、独身。趣味は音楽とファッション。そんなケンイチと出会ったのは17歳で、同じ大学受験の予備校に通っていたことがきっかけだった。かれこれ20年以上の付き合いになる。
出会った時、ケンイチは金髪だった。当時、組んでいたバンドのライブに誘われ、受験生なのに国立のライブハウスまで観に行ったことがある。小柄で細身な体で、ここまで大きな叫び声が出るものなのかと驚いたものだ。悔しいけれど、カッコいい奴だなと思ってしまった。
その後、別々の大学に進んでも、予備校時代の仲間とともに、友達の関係が続いていた。最近では、音楽フェスやキャンプに一緒に行く仲でもある。そんな過程で、当たり前だが、当初のイメージは変わっていった。こいつ、なんてうだうだした奴なんだ、と。
20歳の時、当時ぼくが付き合っていた彼女と、お互いの友達を呼びあって合コンを開催することになった。まだ若くて元気だったこともあり、所沢という辺鄙な場所で挙行されたその合コンをなんとか盛り上げようと、ぼくは必死にその場を取り仕切った。しかし、ケンイチは端っこでちまちまお酒を飲んでいるだけ。家から遠いところで開催していたこともあり、結局、その合コンは二次会もないままお開きとなったのであった。
ところが翌日、彼女の元に参加したある女の子から連絡があった。ケンイチくんのことが気になるから、メールアドレスを教えてほしい、と。恋愛に奥手だった(のように見えた)ケンイチにチャンスが転がり込んできたとよろこび、ぼくは彼女にケンイチのメールアドレスを教えた。そのことを伝えると、なんとケンイチも「俺も、あのことの子が気になっていたんだよね」と言うではないか。現場では、あんなにだんまりを決め込んでいたくせに。
しかし、その子からケンイチにメールがくることはなかった。たいして盛り上がらなかった合コンにめげず、ちゃっかりその子のメールアドレスを聞いていた別の男と付き合うことになったのである。その男は、ケンイチのバンドメンバーだった。ケンイチは愚痴を言っていたが、別に取られたわけでも、抜け駆けされたわけでもなんでもない。だって、ケンイチとその子の間にはなにも起きていないんだから。ただ単に、その男が積極的に頑張っただけである。ケンイチも悠長に待っている暇があったら、自分から連絡をするべきだったのだ。
25歳くらいの時、ケンイチは珍しく自分から恋をしていた。相手は、ぼくの小学生の頃からの幼馴染。周囲の友達も、なんとなく二人がいい感じだということはわかっていたけど、いつものごとくのらりくらりとしているケンイチにヤキモキしている様子だった。
たまりかねたお節介なぼくは、ある時、その子に「ケンイチのこと、どう思ってるの?」と聞いてみた。すると、「わたしはいいなと思ってるんだけど、いまいちケンイチくんがわたしのことどう思っているのかわからなくて」と言った。ぼくは、お酒を飲んだオール明けの元旦の早朝、駅のホームでそのことを伝えた。「今すぐ気持ちを伝えるべきだよ」と。
3日後、その頃ぼくたちの恒例行事になっていた高尾山登山でケンイチと会った。ケンイチはなぜだか高いところが大好きで、高尾山の山頂からの景色を眺めながら、「やっぱり高いところにくると気持ちいいよな」と呑気に恐竜の赤ちゃんの目をしていた。結局、何か月も気持ちを伝えるのを躊躇しているうちに、その子も別の男と付き合って、そのまま結婚した。
まあ、だいたいそんな感じである。もちろん、尊敬できるところもたくさんあって、とくに音楽は、自分でやるだけではなく、アーチストにもとても詳しい。ぼくも音楽は好きだけど、常に最先端を追えているわけではない。幸いなことに音楽好きの友達が周囲に多いため、彼、彼女たちから教えてもらっては、たまにチェックして聴いている。でも、ケンイチが勧めるアーチストはハイコンテクストで、さらに言うことも難しすぎて(というか、要領を得ないので)、どのようにいいのか、どんな魅力があるのか、すんなりとは伝わってこない。ぼくのリテラシーが低いだけかもしれないけど。
そんな腐れ縁のケンイチとも、実は二人きりで会って話したのは人生で二度しかない。
一度目は、20代の後半に差し掛かったころ。突然、「今から飲まない?」と連絡があったのだ。当時、アルコールに溺れていたぼくは、お酒が飲めるならいつでも、どこでもといった感じだったので、とくに深く考えずに高円寺の安居酒屋に向かった。
3、4時間くらい飲んでいただろうか。ほどんどお酒を飲めないケンイチは、いつもの「あ〜」「う〜」という歯切れの悪い間投詞を交えながら、たわいもない世間話をしていた。こいつは、なんのためにぼくを呼んだんだろう。たしかに仲はいいが、お酒が弱いケンイチが、わざわざぼくを呼び出したからには、なにか理由があるのだろう。
次第に訝しく思い始めたぼくは、酩酊する頭をなんとか現実とつなげて、ケンイチの言わんとしていることを読み取ろうとした。それでわかったのが、要は仕事に悩んでいるらしいことだった。
ケンイチは大学を卒業したあと、音楽の仕事に就かず、営業職として働いていた。とくに不満はないのだが、残業が多く、宅録(自宅録音)の時間が取れないというのだ。バンドをやめても音楽を続けていることは知っていた。しかし、その時に聞いたところによると、宅録した音源をネットで公開し、海外からのコメントももらっているという。ケンイチは今の職場を辞めて、残業がなく宅録の時間が取れる職場に転職するべきかどうか悩んでいたのである(たぶん)
そのころ、ぼくは昔からの夢だった文章を書く仕事に就き、アルコールに溺れながらも早く成長したいと必死にもがいていた時期だった。ケンイチの選択に半分は同意をしつつ、「もっと思い切って環境を変えるべきなんじゃないか」「音楽一本で挑戦してみてはどうか」とせっついたことを覚えている。しかし、ケンイチは転職し、仕事をしながら宅録を続けることを選んだ。
その後、ケンイチが音楽とどのように向き合っているのか気になってはいたものの、なにしろ自分のことだけで精一杯だったから、深く語り合うことはなかった。たまに会ってみんなで遊んだり、お酒を飲んだり(ぼくは依存症になったり、離婚したり)、友達関係は続いた。
そういうぼくも、自分の企画として初めて単著を出したのが36歳の時だったのだから、20代で華々しくデビューした同業者からすると、のんびりした奴だと思われているのかもしれない。でも、別にのんびりしていたわけではなく、ただただ愚鈍さゆえに自分の目で世の中を見て、少しはなにかが語れるようになるまで時間がかかっただけである。自分なりに生き急ぎ、身も心も削りながら走ってきたと思っているが、ぼくもまだ何者でもなく、たいしたこともない。
ただ、単著を出してからは、ありがたいことにメディアに出演したり、取材されたりする機会が増えた。そこで思い出したのは、ケンイチが音楽のセンスがいいだけではなくお洒落でもある、ということだ。ケンイチはシンプルながらもどこか惹かれるところがある服を着ていて、サイズ感も色合いも雰囲気にぴったりあった着こなしをしている。
メディアに出るならもっとお洒落をしなければと思った頑張り屋のぼくは、ケンイチに「いつもどこで服を買ってるの?」と聞いてみた。ケンイチは、渋谷にあるセレクトショップを教えてくれた。そこは自店のブランドも扱っていて、雑誌などの取材もほとんど受けない小さな店だという。しかも、なんとケンイチは、15年間も長きにわたり、その店でしか服を買ったことがないという。長い付き合いなのだから、普通なら世間話でそのことをぽろっと言いそうなものだが、そのときはじめて知った。いかにもケンイチらしい。
ファッションにはうるさいケンイチのことだから、どうせお高い服しか置いていないんでしょと思ったけど、ネットで調べてみた限りでは、意外とお手軽な値段の服が揃っているようだった。ぼくはすぐに渋谷にあるその店に向かった。通りには面しているものの、すぐには見つけにくい構えをしていて、何度か通り過ぎてからやっと辿り着いてその店に入った。狭い店内に、秩序立ってシンプルな服が並んでいる様子をぼくは見渡した。その途端、ぼくは軽い眩暈を起こしてしまった。まるで、ケンイチの家のクローゼットにいるかような感覚を覚えたのである。
つい先日、ケンイチから二人で飲もうと連絡があった。二度目のお誘いである。その日はあいにく仕事が詰まっていたため実現はしなかったが、後日ケンイチから同じ連絡があった。
10年ぶり二度目となる二人での会合。昔と違ってケンイチは少しはお酒が飲めるようになり、3年半断酒している素面のぼくを連れて、気になる店やいきつけの店を何店舗か案内してくれた。
ぼくは、ケンイチがなにを相談したいのかだいたいわかっていた。どうせケンイチのことだから、すぐには切り出さないということも。ケンイチはまだ宅録を続けているらしかった。一時はスランプに陥ってやめていたものの、今はネットで知り合ったその道のプロの人に直接教えてもらって、さらに腕を磨いているらしい。人が誰かに相談するときは大抵そうだが(とくにケンイチは)、相談するときには、すでに本人の気持ちはだいたい固まっているものである。背中を押してほしいのだ。だから、ぼくは以前のように「環境を変えて、音楽をやってみたらどうか」と言った。
実際に、今では大きなビジネスにしなくても、個人のユーザーに直接、表現物を届けることができる環境が整いつつある。音楽は文章と違って、言語の壁に縛られることもないのだから、それこそ海外でファンを開拓してみてはどうか。教えてもらっているプロの人に頼んで、ツテをたどってみることくらいの図太さがあってもいい。同い年の安達祐実だって、新しいことに挑戦してさらに輝きを放っているではないか、と。
20代のころより少しは世の中がわかってきたぼくの言葉には、以前のような確信はなかった。自分自身への確信も、せっかちさも、歳を重ねるたびに少しずつ薄れていった。でも、15年以上も同じ服を着て、ひとりで宅録していた目の前にいる男への見方は変わっていた。

あの、渋谷にある店に入った瞬間、ぼくは時間が歪んでいるような錯覚におちいった。しっかりした生地に、しっかりとした縫合がほどこされたシンプルな服の数々。そこには、ぼくが感じていた(と思っていた)時間とは、別の時間が流れているような気がした。急速な激しい時間の流れとは縁がないが、滞留している、では決してない。積み重なっている、とも違う。
家に帰って、ケンイチがネットに公開している音源を聴いてみた。ぼくは音楽に特別詳しいわけではないし、楽器も弾いたことがないから、正直、ケンイチの音楽がどんなものなのか、正確な言葉でとらえることはできないけど、ケンイチが自宅で録音した音楽を聴きながら、ぼくはまた「時間」について考えた。そこには、ケンイチの時間が流れているような気がした。
吉田健一の批評に『時間』という作品がある。エッセイや小説と評されることもあるが、ぼくは吉田が晩年に掴んだ人生や文学に対する「批評」だと思っている。『時間』はこんなふうに始まる。
冬の朝が晴れていれば起きて木の枝の枯れ葉が朝日という水のように流れるものに洗われているのを見ているうちに時間がたって行く。どの位の時間がたつかというのではなくてただ確実にたって行くので長いのでも短いのでもなくてそれが時間というものなのである。
そして、そのすぐ後にこうつづく。
(…)我々が時間とともにあると正当に呼べる状態にあり、我々のうちにも時間があってそれが殆ど我々をなしているものの凡てと思える際にその状態を検するならば時間がたって行くのではなくて我々が或る場所、現にいるその場所にいるのを感じる。又それが時間がたって行くことなので我々が急いで何かしていて時計を見て急いでも間に合わない気がするというようなのはその早さで時間がたつということでなくて我々の方で時間の観念を失ってそのことに脅かされているのである。
時間は、時計の秒針が正確に時を刻むように経っていくのではない。ぼくが感じている時間を、誰もが感じているわけでもない。我々が或る場所、現にいるその場所にいる−−。ぼくがケンイチの音楽や、あの渋谷の店から覚えたのは、そういった彼らの感覚だったのかもしれない。やっぱりぼくは愚鈍で、なにかを掴むのに時間がかかる男なのだ。まあ別にそれでもいいや、と最近では思う。
今でもケンイチに会うたびに、「こいつ恐竜の赤ちゃんみたいな顔してるな」と思うし、なんてうだうだした奴なんだとも感じる。これからケンイチが、どのような道を歩むのかもわからない。ケンイチには、ケンイチの時間があるのである。ただ、次に両想い女の子が現れたら、今度こそちゃんと気持ちを伝えろよ、とは友達として思っている。
(宮崎智之 @miyazakid)
【告知】
宮崎智之さんが司会を務める、詩の朗読と本の野外フェス『POETRY BOOK JAM』が6月3日(金)に上野公園野外ステージで開催されます(17時開場、17時30分開演)。出演は、高橋久美子さん、GOMESSさん、鳥居さん、Kacoさん、宮尾節子さん、向坂くじらさん(Anti-Trench)、平川綾真智さん、村田活彦さん(poetry reading tokyo)。バンドは、ミコ・トコマレさん(Gt.)、小林洋さん (Ba.)、堀口たかしさん(Dr.)。
書店&出版社ブースには、ネコノス、代わりに読む人、本の種出版、書肆海と夕焼け、カラポネヤミ書房、百年の二度寝、双子のライオン堂、Après-midi 、田畑書店、左右社、ナナロク社、駒草出版、素粒社が出店します。
入場無料のチャリティーイベントになります(カンパ制)。オンライン配信あり。
詳細は、『POETRY BOOK JAM』ホームページ にて。
公式Twitter:@poetry_book_jam


















