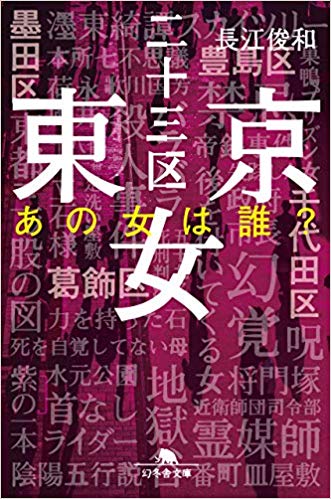大都市の問題といえば、渋滞、人口過密、保育園の不足など多々ありますが、一番の問題は、「ゴミ処理」問題なのではないでしょうか。東京は人口増加の激しかった江戸時代から、早くもゴミ処理の問題が発生。川にゴミを投げ入れていたが、それでは収まりきらないということで、海への投棄が始まり、気づいたら陸地までできてしまったといいます。そして、そのゴミ投棄、埋め立ての歴史が現在に至るまで続いているといいます。そんな江東区のゴミ処理場で、なぜか「心霊写真」がとれた、ということから江東区の謎を追うミステリ『東京二十三区女』より「江東区の女」の試し読みで、お楽しみください。
* * *
江東区
東京湾に面した東京東部の区。昭和二十二年、深川区と城東区が合併し、隅田川の東側に位置することから、『江東区』と名付けられた。
深川や門前仲町などは、江戸情緒溢れる、東京下町の雰囲気を色濃く残している。東京湾に面した臨海エリアは、九〇年代後半から開発が急速に進められ、発展を遂げた。
江戸時代から埋め立てが行われている地域であり、区の面積の三分の二以上は、明治以降に埋め立てられた土地である。
*
熱い。
燃え尽きてしまいそうだ。彼女の周りを囲む、ぶくぶくと泡を噴いている熱い土。女は暗闇の中で身悶える。ひと思いに、焼き尽くして欲しい。この熱を帯びた、ひどい臭いがする土の中で消滅してしまえば、どんなに楽だろうか……。
しかし、それは叶わぬ望みだ。彼女は自分が成仏できぬことを知っている。決して許す訳にはいかない。自らの不埒な行いが招いたことだとしても。死んでも死にきれない。
湧き上がってくる。泡噴く土のように、女の内側から激しい怨念が、とめどなく膨張している。
光届かぬ地の底で、激しい憎悪に苦悶する女。彼女の耳にかすかに届く、鳥の鳴き声と波の音──
深川
雲一つない。というほどではないが、清々しい青空が広がっている。川からそよいでくる風が冷たく、肌に心地よい。
原田璃々子は橋の中央部分で立ち止まり、川面の景色を眺めた。
ダークグレーのダウンジャケットにジーンズ、肩に黒い大きなトートバッグをかけた璃々子。高めにまとめた長い髪が、早春の風に揺れている。
川幅が優に百メートル以上はある、隅田川下流の風景。さざ波の上をエンジン音とともに、水上バスが遠ざかって行く。その先の上流方向には、高速道路が横断しており、奥にスカイツリーの塔身が見える。
反対の東京湾側の下流方向に視線を動かした。河口はさらに広がっている。佃島の高層マンション群が陽光に照らされ、川面にその影を落としていた。
永代橋。中央区と江東区の間を流れる隅田川に架けられた橋である。全長約百八十メートル。青色の塗装にリベットが打たれた、迫力あるがっちりとしたアーチが印象的だ。
「永代橋は、ドイツのライン川に架かっているルーデンドルフ鉄道橋をモデルとし、日本で初めて全長が百メートルを超えた、帝都東京の門と言われた橋である」
背後に立っていた先輩が、唐突に語り始めた。先輩の名前は、島野仁。ヒョロリとした長身の体軀。パリッとした襟なしの縦縞シャツに、プレスの効いたスラックスの出で立ち。欄干の方に歩み寄り、薀蓄を披露し続ける。
「この橋が架けられたのは、江戸時代のことだ。当時、この先の江東区側の佐賀町一帯は、永代島と呼ばれる島だった。その島に架ける橋だから、永代橋と呼ばれるようになったという説がある」
「へえ、島だったということは、ここから先の江東区のエリアは、昔は海だったんですね」
「そういうことだ。江東区の土地のほとんどは、江戸時代以降になって埋め立てられた場所だからね」
「そうなんですか」
「永代橋は、赤穂浪士が討ち入りした後、吉良上野介の首を掲げて渡った橋としても知られている。また江戸中期には、祭りで押し寄せた群衆の重みに耐えられず、千四百人の水死者を出した、史上最悪の落橋事故を起こした。関東大震災の時は、多数の避難民とともに炎上、多くの焼死者や溺死者が出た。現在の橋は、震災復興事業の第一号として、その時架けられたものだ……」
「あの、先輩」
「何だ」
「永代橋についてはもうそのくらいで大丈夫です。今日の目的はここじゃないんで」
「あ、そう」
まだ喋りたそうな先輩を尻目に、璃々子は欄干沿いを江東区側に向かって歩き出した。
永代橋を渡り終え、橋のたもとに着いた。隅田川沿いの堤防に歩を進める。川沿いに並ぶベンチでは、スポーツ新聞を読んでいる中年男や、居眠りしているサラリーマンの姿などが見えた。璃々子はスマホの地図サイトで、場所を確認する。
「この堤防の裏側ですよ、永代公園」
堤防沿いに続いている、コンクリートの隔壁の裏側に回る。隔壁のすぐ裏は、細長い公園になっていた。隅田川の堤防と、住宅街の路地の間にある児童公園。その中に、璃々子は足を踏み入れた。公園内は木々が鬱蒼と生い茂り、決して明るい雰囲気ではない。まだ昼前だからなのか、散歩している老人を見かけるだけで、通行人の姿もあまりなかった。
しばらく進むと、ブランコや滑り台、砂場など遊具のあるエリアにさしかかった。璃々子は立ち止まると、トートバッグから一枚の写真を取り出した。
若い母親と幼い五、六歳の女児が写った写真──。その背後には、公園の遊具が写り込んでいる。璃々子は写真をかざして、目の前の公園の風景と見比べる。
「う~ん……なんか、ちょっと違うような」
「ちょっとというか、全然違うだろ」
背後から、写真を覗き込んだ先輩が、突っ込みを入れた。
「というか、無理だと思うけど。何の手掛かりもなく、この写真が撮られた場所を探すなんて」
「いや、探さなくちゃいけないんです。彼女のためにも。この心霊写真がどこで撮られたのか」
璃々子が持っている写真。
満面の笑みを浮かべている娘を抱いた母親。三十代半ば頃、髪を短く切りそろえた、整った顔立ちの女性である。彼女の肩の向こう側には……。うっすらとした、小さな影。髪の長い女性のように見える。首から下はなく、宙に浮いているような……。
女の生首──
彼女は、憂いを帯びた眼で母親を凝視していた。
前日のことである。
あと一時間ほどで、日が暮れようとしていた頃、璃々子は都営地下鉄大江戸線の門前仲町駅の改札を出た。地上に上り、人混みで賑わう永代通りを歩く。深川という東京下町の一帯である。ファストフードのチェーン店や、漬物店や甘味処など、昔ながらの商店が混在している街並みの中を進んで行く。永代橋も、ここから歩いて十分ほどの場所だ。
しばらく歩くと、一軒の古い喫茶店に入った。昭和の純喫茶という趣の店だ。内装や調度品が、レトロな意匠で統一されている。夕方ということもあって、店内は割と混み合っていた。待ち合わせの相手は、まだ来ていないようだ。約束した時間まで、まだ二十分ほどある。窓際の席は全部埋まっていたが、カウンター脇の二人掛けの席は空いていた。
席について、ブレンドコーヒーを注文する。しばらくすると、制服姿の女子高生が璃々子に声をかけてきた。
「あの……原田さんですか。原田璃々子さん?」
髪を二つに結んだ、純朴そうな女子高校生だった。璃々子は立ち上がり、笑顔で出迎えた。
「原田です。初めまして。あなたが」
「……はい。メールを出した者です。益子由菜と言います。初めまして」
そう言うと彼女は、深々と頭を下げた。こういった取材を受けるのは初めてなのか、いささか緊張しているようだ。化粧気はほとんどない、真面目な雰囲気の女子高生である。くりくりとした瞳が可愛らしい。
「どうぞ、座って下さい。何飲みますか」
璃々子は、優しく彼女を促した。
「はい。ありがとうございます」
ハキハキした声で、璃々子の対面に座った。ウエイトレスを呼んで、彼女の飲み物を注文する。由菜はオレンジジュースを頼み、少し雑談する。
「それでは、話を聞かせてもらえますか」
「分かりました」
由菜の表情がわずかに曇る。彼女は視線を落とすと、静かに話し始めた。
璃々子が企画を売り込んでいる雑誌社の編集部に、不気味なメールが投稿されたのは一ヶ月ほど前だった。
『私たち家族は呪われています。この写真を鑑定して下さい』
メールに添付された一枚の写真。公園らしき場所で笑う母と娘。その背後に潜む不気味な影。女の生首……。
「これ、記事になるかな」
編集部で写真を見せられた時、身体中が総毛立った。璃々子は人一倍霊感が強い。かなりヤバイ。この写真は本物だ。記事になるかどうかはさておき、放っておく訳にはいかない。すぐに返信メールを送った。そして、送信者の益子由菜と落ち合うことになったのだ。
由菜は都内の公立高校に通う高校一年生。彼女の家はこの近くにあり、深川でクリーニング店を営んでいるという。
「古いアルバムを整理していたら、この写真があったんです」
そう言うと由菜は、鞄から無地の茶封筒を取り出した。中に入っていた写真を、璃々子に差し出す。メールで送られてきたものの現物である。璃々子は手に取って眺めた。思わず生唾を飲み込んだ。やはり、パソコンで見たものとは雰囲気が違う。尋常ならざる気配が漂っている。
「この写真は、いつ頃撮られたものですか」
神妙な面持ちで、由菜が答える。
「さあ、多分私が五、六歳ぐらいの時だと思うんですけど」
「ここに写っている女の子は、あなた?」
「そうです。一緒に写っているのは母です」
「撮影した場所は? この写真、どこで撮ったか分かる?」
「それが、覚えてないんです。幼い頃のことなんで。母にも聞いてみたんですけど、分からないって。母は心霊写真とか、そういった話があまり好きじゃないので」
由菜の話によると、写真自体はデジタルカメラで撮られたもので、オリジナルのデータは残っていないという。
「そうか……撮影した人は? この写真を撮った人なら、覚えているかも」
「撮影したのは父です。でも父は、私が小学生になった時に亡くなりました」
そう言うと由菜は、少し目を伏せた。
「そうか。ごめんなさい」
「いえ、いいんです……。メールにも書いたんですけど、私の家族、呪われているんです」
「呪われているって、どういうこと」
「私の家族、みんな変な死に方しているんです。祖母は、私が生まれる前、浴室で首を吊って自殺したらしいんです。そのあとすぐに、祖父も自分で手首を切って、命を落としたと言います。父も、電車の線路に飛び込んで……」
そう言うと由菜は、一旦言葉を止めた。ストローに口をつけ、ジュースを含む。しばらく彼女の様子を窺い、璃々子が声をかけた。
「由菜さん、兄弟はいるの」
「いいえ。いません」
「じゃあ、ご家族は」
「今は母と二人暮らしです。父が亡くなってからは、母が一人でクリーニング店を切り盛りしています。ずっと働き詰めで……。祖父が生きていた頃は、料亭を何軒も経営していて、うちの家は裕福だったと聞きます。でも祖父が死んだ後は、経営が苦しくなり……。父は養子だったんですが、料理店から鞍替えして、クリーニングのチェーン店をやろうとして借金を重ねた挙げ句、失敗して……。父の死後、母は一人で借金を返しながら、私を育ててくれて……だから、怖いんです。私の家は、呪われているんじゃないかって」
テーブルの上の忌まわしい写真に目をやり、由菜は言葉を続けた。
「この写真……後ろに写っている女。母をじっと見ているような気がするんです。母にもしものことがあったらと思うと、恐ろしくて、不安で」
由菜の目に、涙がにじんでくる。彼女の感情が伝染し、思わず璃々子の涙腺も緩んだ。
「だから気になって、雑誌に投稿したんです。この写真、持ってても大丈夫なんでしょうか」
「そうね……この写真の女の影。その正体が分かればいいんだけど。何か、手掛かりはないかしら。どこで撮影されたものなのか。例えば、家族で旅行に行った時に撮った写真とか」
「父も母も休みなく働いていたので、旅行に行った記憶は、ほとんどありません。多分、家の近くの公園だと思うんですけど」
「近くというと、深川あたりの公園かな」
「そうですね……。はっきりとは分かりません。ごめんなさい。家族で遠出したことは、あまりなかったと思うので……。せいぜい江東区か、その周辺のどこかの公園じゃないでしょうか」
「やっぱり、この公園じゃないみたいですね」
由菜から預かった写真を掲げ、目の前の砂場や遊具のある広場と見比べる。
「遊具の感じも違うし、空の見え方も違います。この写真は、空が広く写っていますけど、この永代公園はずっと、木々や建物に遮られ、あまり空は広くありませんね」
そう言うと璃々子は、バッグに写真を手早くしまい、歩き出した。
堤防とは反対側の出口から、公園を出る。古い工場や住居が建ち並ぶ一帯を進んで行く。運河が縦横に流れており、趣のある海苔工場や屋形船の乗り場が見えた。眼前には、古き良き東京の風情が広がっている。
「だから、そうやって闇雲に歩き回っても、見つからないと思うが。ネットで調べるとか、色々方法はあるだろ」
「ネットで見ても、よく分からなかったんで。江東区の公園は全部で三百ほどです。しらみつぶしに探せば、いずれ見つかると思いますが」
「江東区で撮られたかどうかも分からないんだろう。それに、公園じゃないかもしれない」
璃々子は答えず、そのまま歩き続けた。先輩が後ろから、ゴチャゴチャと言ってくる。
「とにかく、そんな心霊写真なんかデタラメに決まっている。光の加減による錯覚か、投稿した女子高生のイタズラに違いない。そんな写真、パソコンで簡単に捏造できるからな」
「由菜さんは、そんなことするような人間じゃありません。私は彼女を信じています。何とか、この写真の公園を探したいんです」
「確かにそうだな。女子高生のやらせを真に受けて、記事にした方が君にとっても得だからな」
「そんなんじゃありません」
別にどうしても記事にしたい訳ではなかった。由菜さんの訴えに、絆されたからだ。何か彼女の力になれればと思った。それに……。もしかしたら、璃々子の探し続けているものが、この江東区のどこかで見つかるかもしれない。そんな期待もあった。彼女が直面している、ある恐ろしい事態……。璃々子はその原因を突き止め、解決に導くため、この東京二十三区を巡っているのだ。
小さな橋をいくつか渡って行くと、川沿いの開けた場所にさしかかった。視界のずっと先まで、整地された公園が広がっている。越中島公園である。隅田川の支川になる豊洲運河沿いに造成された、堤防沿いの公園だ。隅田川の支川と言っても川幅は広く、対岸まで優に百メートル以上はある。公園に整地された堤防には、緑とベンチが並び、人々が憩いの一時を過ごしている。
「もしかしたら、ここじゃないでしょうか。さっきの永代公園と違って、空が開けています。由菜さんの家からも、歩いて来られますし」
「だが、肝心の遊具の類が見当たらないようだが」
「どこかにあるはずです」
そう言うと、璃々子は歩き出した。しかし結局、この越中島公園の中で、由菜の写真が撮影された場所を見つけ出すことはできなかった。公園の中に、子供が夏場に遊ぶ、じゃぶじゃぶ池はあったのだが、ブランコや滑り台などのいわゆる遊具の類はなかったのだ。
越中島公園を出て、由菜さんの自宅のクリーニング店がある深川に向かう。途中、いくつか児童公園に立ち寄ったが、写真が撮影されたと思しき場所はなかなか見当たらない。
深川に到着する。門前仲町の駅前、永代通り沿いの商店街を歩く。足繁く行き交う人々。自転車の配達人や、台車を転がすランニング姿の若者。街並みは独特の活気に溢れている。
駅を越えてしばらく歩くと、大勢の参拝客で賑わっている参道の入り口にさしかかった。江戸相撲発祥の地として知られる富岡八幡宮や、深川不動尊に続いている参道である。
「なぜ、この一帯を深川と言うか、知っているか」
唐突に、後ろを歩いていた先輩が口を開いた。
「いえ、知りませんけど」
璃々子がそう言うと、先輩は水を得た魚のように語り出した。
「深川という地名の由来は、徳川家康が江戸に入国してからのことだ。さっきも言ったように、当時このあたりは永代島という島だった。島といっても、川が運んできた堆積土が形成した海辺の干潟で、とても人が住めるような場所ではない。その土地を埋め立て、開拓したのが深川八郎右衛門という人物だった。慶長元年、家康が巡視に訪れた際のことだ。『ここは何という名前の土地か』と、八郎右衛門に聞いた。彼はこう答えた。『ここはまだ、埋め立てたばかりで名前はありません』。すると家康は、『しからば汝が名字を以て村名となし、起立せよ』と命じ、八郎右衛門の名字をとって、深川という地名が生まれた」
先輩の薀蓄は止まらない。彼の言葉をありがたく拝聴しながら、歩き続けた。参道には茶店や屋台、老舗のうなぎ屋などが並び、江戸の風情が残されている。
「それから百年ほどの間、深川に来るためには、〝渡し〟という船に乗るしかなかった。富岡八幡宮が創祀され、元禄の頃に永代橋ができると、深川には大勢の人が訪れるようになった。橋一つで隔てられた島という場所柄もあって、お上の目も気にせず、武士も町人も自由気まま、本土では味わえない遊蕩の気分に浸ることができた。独特の風土と人情が相まって、深川情緒という言葉も生まれた。いわゆる江戸っ子の気風は、この深川で形成されたと言っても過言ではない」
「なるほど。深川にある独特の雰囲気は、もともと島だったからなんですね」
先輩の薀蓄に耳を傾けながら、深川の参道を進んで行く。しばらく歩くと、深川不動尊までやってきた。本殿に入り参拝をすませ、左手にある深川公園に向かった。町中の公園にしては、かなり広い敷地がある。先輩の話によると、もともとこの場所は永代寺という寺院だったという。門前仲町という名称も、永代寺の門前町であったことを意味するらしい。
公園に入ると、何人かの主婦が、子供を遊ばせている。ブランコや滑り台といった遊具はあるが、ここもやはり、由菜の写真が撮影された場所とは違っている。
深川公園を出て住宅街の中を歩いた。十分ほど進むと、小さなクリーニング店が見えてきた。二階建ての住宅の一階部分が店舗になっている、年季の入った店構えだ。入り口のサッシの上に掲げられた紺色のシート看板。店名と電話番号が記された文字が色あせている。
由菜の自宅である。店内を覗き込むと、ガラス戸の向こうに、アイロンプレス機を前に熱心に作業している、一人の中年女性がちらりと見えた。白いタオルを頭に巻いた、エプロン姿の女性。写真に写っていた女性だ。由菜の母親である。直接話を聞いてみようかとも考えたが、思いとどまった。
璃々子は声をかけず、クリーニング店を後にする。由菜は、写真を雑誌に投稿したことを、母には内緒にしていると言っていた。見ず知らずの人間が、自分の古い写真を持って現れたら、母親も驚くだろう。
その日は夕暮れまで、深川周辺の公園を隈なく歩き回った。だが、写真が撮影された場所が特定されることはなかった。
亀戸
翌朝、璃々子と先輩は亀戸駅にいた。亀戸は江東区の北部に位置する街である。駅の西側はすぐに墨田区であり、東側を流れる旧中川を越えると、江戸川区になる。亀戸駅は、JR総武線と東武鉄道が乗り入れ、駅周辺は繁華街が広がり、大きく発展している。
亀戸駅の改札を出て、駅の周辺を少し歩く。パチンコに消費者金融の看板、ホルモン屋にキャバクラや風俗店がひしめき合っている。道行く人も、人生に疲れたみたいな中年以上の男性が多い。駅前のカメリアプラザという区の施設の前には、亀戸名物の羽の生えた亀の銅像がある。「カメリアプラザ」「亀の銅像」と亀尽くしなのは、やはり亀戸という地名にあやかっているらしい。
駅の南側に出る。明治通りと京葉道路の交差点で立ち止まった。通勤ラッシュを過ぎた時間だが、多くの通行人が歩いている。後ろから先輩が声をかけてきた。
「亀戸は江東区内では、最も歴史がある古い町だ。江東区のほとんどの土地は、縄文時代以前は海の中にあったと言われている。その後、河川が押し流す土砂によって、陸地が広がっていった。江戸に幕府が置かれる遥か以前、このあたりは、砂浜や入り江が入り組んだ地域だった。亀戸の地名の由来は、亀の形に似た島で『亀島』と言われたという説がある。後に島の周辺に土砂が堆積して、周りの島々と陸続きになった。亀島は亀村に変わり、近くに井戸があったので、『亀井戸』と呼ばれるようになった」
先輩の話を聞きながら、交差点を渡る。
「それで今度は一体、どこへ行くつもりだ。由菜さんの自宅がある深川からここは、随分離れているように思うが」
ここから深川までは五キロぐらいある。今日は、亀戸から江東区を南下しながら、写真の公園を探すことにした。
京葉道路から、南へ延びている遊歩道の道を進んだ。大島緑道公園という、都電の線路跡を公園化した遊歩道である。しばらく歩き続けるが、特に遊具があるような場所は見当たらない。首都高速七号線の高架道路の下を過ぎる。ここから先は、大島という町名に変わる。そのまま緑道を歩き続ける。
「もっと効率的なやり方はないのか。付き合わされる、こっちの身にもなってみろ」
後ろから先輩が、ぶつぶつ言ってきた。
「だから、いつも言っているように、無理してご足労頂かなくても結構ですから」
「でも、僕がいないと困るだろ」
「いえ、別に」
「大丈夫なのか? 僕がいなくても」
「全然、大丈夫です」
「本当か」
「本当です。だって先輩は……」
璃々子は立ち止まると、先輩をじっと見た。
「何だ」
「……ただ喋りたいだけですよね。こうやってずっと、ついてくるの」
先輩が口を閉ざした。図星である。先輩は本当のことを言われると、黙り込んでしまう。再び、璃々子は歩き出した。
遊歩道を二十分ほど進むと、明治通りにぶつかった。遊歩道を出て、明治通りを南下する。しばらく歩くと橋が見えてきた。欄干の前で立ち止まり、橋の下を流れる川を眺めた。さほど、川幅は広くない川である。蛇行することなく、一直線に流れている。
「小名木川だ。徳川家康の命によって開削された運河である」
久しぶりに先輩が口を開いた。やっぱり黙っていられなかったようである。
先輩によると小名木川は、徳川家康が、江戸に塩などの物資を運び入れるために掘らせた運河だという。江戸時代は、水上交通が流通の要であり、東京の至る場所に運河が張り巡らされているのは、その名残らしい。
「江東区や墨田区などの東京下町と言えば、関東大震災と東京大空襲で、多くの犠牲者が出た場所だ。関東大震災では、墨田区本所の空き地に集まった避難民の家財道具に引火し火災旋風が起こり、およそ四万八千人が灼熱地獄の中で命を奪われた。その際、この小名木川には、畳を敷き詰めたようにびっしりと、焼死体が浮いていたという。小名木川だけじゃない。江東区のほとんどの河川は、無数の遺体で溢れかえっていたんだ。その後の東京大空襲では、震災の死者の二倍を遥かに超える死亡者が出た。その時も同じように、江東区の川は、空襲の犠牲となった死体で埋め尽くされている」
璃々子は灰色の運河を眺めた。ポンポンとエンジン音を立てて、遠くに屋形船が走っている。何の変哲もない、東京下町の風景である。しかしそう遠くない過去、この川は地獄だった。無念のまま命を落とした、夥しい数の無惨な死体で川面は埋め尽くされていたのだ。しかも二度にわたって……。
由菜の写真を初めて見た時から、感じていた。写真に写り込んだ、恐ろしい異形の存在。その正体は、歴史の奥に封じ込められた負の存在……。そんな気がしてならなかった。
小名木川を越えて、そのまま明治通りを南下し続ける。途中、公園に立ち寄りながら彷徨い続けるが、由菜の写真の場所を見つけ出すことはできない。一時間ほど歩き続け、地下鉄東西線の駅がある東陽町までやって来た。
東陽町は、ちょうど江東区の真ん中に位置している。江東区役所も東陽町にあり、江東区の中心地とも言える町だ。駅周辺は開けていて、庶民的なスーパーや古い商店が建ち並び、東京下町の雰囲気がある。由菜のクリーニング店がある深川は、ここから西へ二キロほど先に位置している。
「さっきも言ったように、江東区の土地は、河川の土砂が堆積して広がっていった。明治の初め頃の地図を見ると、陸地はこの東陽町のあたりまでで、ここから先は海だったようだ」
璃々子の前を歩いていた先輩が、また話し始めた。
「明治時代? そんな昔という訳ではないですね」
「そうだ。ここから南側の江東区の陸地は全部、明治以降に人間の手によって埋め立てられた土地なんだ」
「ここから南って、かなりの範囲ですね」
「ああ、江東区の三分の二以上の土地は、明治時代以降に造成された。もっとも土地の埋め立ては、江戸時代から行われている。深川や永代島の周辺も、その頃に埋め立てられたものだ。江東区の土地のほとんどは、江戸時代から近代、そして現代……そう、今この瞬間も埋め立ては続き、広がり続けている」
突然、先輩が立ち止まった。璃々子の方に振り返り言う。
「一体なぜ、江東区の土地が拡大していくのか、その理由は分かるか」
「それは……人口増加とか色々あって、土地の面積を増やして、住居を増やしたりとか」
「もちろん、そうだ。だがそれだけではない。江東区一帯には、土地を拡大し続けなければならない、拠んどころない理由があった」
「拠んどころない理由?」
「知らないのか」
呆れたような眼差しを璃々子に向けると、先輩は黙り込んでしまった。思わず璃々子は返事する。
「分かりません」
彼女の答えを聞くと、先輩は無言のまま歩き出した。何か怒っているようにも見える。〝江東区の土地が拡大し続ける理由〟。それが何なのか? その時、璃々子には本当に分からなかった。
その後、東陽町にある公園を隈なくあたるが、めぼしい成果を得ることはできない。ここから西へ行くと深川になるが、深川あたりの公園は昨日探したので、そのまま南下し続けることにした。
明治通りを、東京湾に向かって歩き続ける。大型トラックが轟音を上げて走っている。片側三車線の幅広い直線道路。周囲には運河が縦横に張り巡らされ、橋が多く高低差が激しい。
しばらく進むと、新砂という地名の場所にさしかかった。道路の両側には、大きな工場や物流センターが建ち並んでいる。先輩は、さっきからずっと黙ったままだ。前を歩く先輩に、恐る恐る璃々子が声をかけた。
「あの……このあたりも、埋め立てられた場所ということですよね」
「そうだ」
振り返りもせず、ぶっきらぼうに先輩が答えた。
璃々子は先輩の背中に向かって、先ほどの質問を切り出した。
「すいません。さっき先輩が言っていた、江東区の土地が拡大し続ける理由。教えてもらえませんか」
先輩が立ち止まった。じろっと璃々子に乾いた目を向ける。再び歩き出すと、話し始めた。
「江戸の町が発展するにつれて、人口が急激に増加した。そして、ある大きな問題が発生し、江戸の庶民は悩まされることになる」
「土地が足りなくなった……ということですよね。だから埋め立てて……」
「土地不足だけが、埋め立ての理由ではない。人口が増えると、都市には様々な問題が発生する。その中で最も深刻な問題がある。何だと思う」
「深刻な問題ですか」
「分からないのか」
「はい」
先輩は深くため息をついた。そして言う。
「ごみの処理だ」
「ごみ?」
「江戸の初め頃、庶民はごみを近くの空き地や堀や川などに捨てていた。当時は空き地も多く、ごみを捨てる場所が至るところにあった。堀や川もごみを捨てるには最適の場所だった。水の流れが、ごみをどこかに運び去ってくれるからだ。しかし、人口が増加するにつれて、ごみはどんどん増えていった。空き地はごみの山となり、川のごみは船の通行の邪魔になる。江戸に幕府が開かれてから五十年後、幕府は川筋にごみを捨てることを禁じ、ごみは船に積んで海に出て、永代島の周囲に捨てるように命じた。だが、海までごみを捨てに行くのは、なかなか厄介なことだった。そこで家々が共同して、芥取請負人という専門の業者に委託するようになった。ごみ収集の始まりである。永代島周辺の隅田川河口部の海域には、江戸中のごみが投棄された。ごみは増え続け、海中に堆積して新しい陸地となった」
「ごみによって生まれた、陸地ですか」
「そうだ。ごみと言っても、今の感覚とは少し違う。当時のごみは、紙や土、瓦など土砂に近いものだった。海に捨てると、自然と陸地を形成したんだろう。こうして、江戸市中のごみ問題は解決し、土地の面積も増えた。幕府にとっては一石二鳥の名案だった。以降、海にごみの投棄場所を定め、計画的に陸地を作っていこうということになった。その始まりが、深川を含む永代島の一帯なんだ。だが、江戸の人口増加に伴い、ごみの量も増えていった。永代島周辺は埋め尽くされ、ごみ投棄によってできた陸地は、どんどん広がって行った。今日歩いてきた、小名木川から南の土地は全部、江戸時代に埋め立てられた場所だ」
「江東区の一帯はほとんどが、そうやってできた土地だったんですね」
「そうだ。明治以降もごみ投棄による埋め立ては続いた。さっき歩いてきた東陽町や木場は、明治時代に埋め立てられた土地だ。この先の豊洲や有明は大正から昭和にかけて……。江東区の土地は、どんどんと広がり続けている」
江東区の土地が拡大し続ける理由。それは江戸の時代から、私たちが排出し続けたごみだった。東京に暮らしていながら、その事実を知らなかった。璃々子は、そんな自分を恥じた。
先輩の話に耳を傾けながら、明治通りを南下し続ける。工場街をしばらく歩き、新砂二丁目の信号を越えると、運河に架かる大きな橋にさしかかった。砂町運河という広い運河である。運河の西側には、高層のタワーマンションが建ち並んでいるエリアが見える。豊洲という人気の新興住宅地だ。これほどの広大な土地が、増殖し続けているのだ。それも、人間の生活の中で生み出された、ごみの廃棄が大きく関係している。そのことを思うと、複雑な心境になった。
橋を渡ると、周囲の景色は一変する。今まで工場や倉庫が並んでいた道路の両側には、緑溢れる公園がずっと先まで、延々と続いている。
「高度経済成長期。東京の人口は爆発的に増加した。それに比例して、東京の人間が吐き出すごみの量も著しく増大する。そして当時、東京二十三区中のごみのほとんどは、僕らが今歩いている、江東区のこの場所に集められ投棄されたんだ」
先輩は立ち止まり、周囲を眺めながら言う。
「この一帯は十四号埋立地という。別名〝夢の島〟……」
つづきは文庫本で。
ドラマ「東京二十三区女」も毎週金曜日深夜0時からWOWOWにて好評放送中です。
放送第二回は、まさに「江東区の女」。お楽しみください。