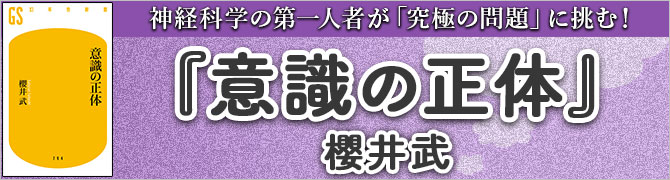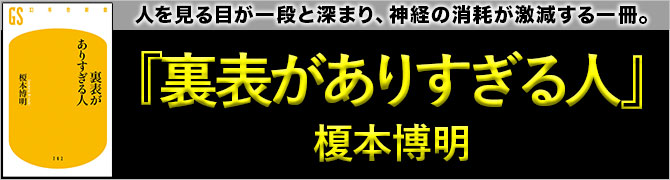人間の脳とAIの違いとは何か。この問いに、「人間には意識があるが、AIには意識がない」と答える人も多いことだろう。では、意識とはどのように生まれているのか? AIに意識を搭載することはできるのか? 深く考えてみると、よく分からないことばかりだ。
そんな疑問にヒントをくれるサイエンス新書、『意識の正体』。睡眠研究の第一人者である筑波大学の櫻井武教授が、意識の役割と“自分”の正体に迫った本書より、一部を抜粋してお届けします。
* * *
脳とAIの構造的な違い

人間の脳もコンピュータも、広い意味では情報処理システムである。外界から入力を受け取り、内部で処理し、行動や出力として返す――基本的な枠組みは似ている。しかし、その内部構造は根本的に異なっている。
人間の脳は、進化の歴史を層として折り重ねながら発達してきた。脳の部位のなかで最も古い脳幹は、呼吸や心拍といった生命維持のための自律機能を担う。その外側には情動を司る辺縁系があり、さらに外側には感覚や運動、思考を処理する新皮質が広がる。
そして、その最高位に位置するのが前頭前野である。これらの層は、単に積み木のように積み重なっているのではない。異なる時間スケールや原理で情報を処理し、相互に干渉しながら全体として機能している。
たとえば、古い層は瞬時の無意識的判断を下し、新しい層はその判断を時間をかけて評価・修正する。この協調が、柔軟で文脈依存的な行動や感情による色付けを可能にしている。
一方、多くのコンピュータやAIは同質的な演算ユニットで構成されている。すべての処理は基本的に同じレイヤー上で均質に行われる。確かに並列処理能力はきわめて高いが、それは脳のように「異なる進化的起源をもつ層」が協調する多層的並列ではない。
人間の脳は、進化の過程で異質なモジュールを重積し、統合してきたため、意識と無意識を明確に分けつつ、両者の間で絶えず情報をやり取りしている。
この構造的な違いは、意識の発生可能性に直接関わる。脳は、限られた情報処理能力を補うために、何を意識に上げ、何を無意識にとどめるかという選択を行う必要がある。
これに対し、無限に近い演算能力と記憶容量をもつAIには、そのような「選別のための舞台(意識)」を用意する必要がない。もし意識が、この選別と統合の過程そのものだとすれば、AIはそもそも意識をもつ必要がないだろう。
無意識のない知性
私たちは、自分の行動を「意識して」選んでいると思い込んでいる。
だが神経科学の研究は、この直感が必ずしも正しくないことを示している。ある実験では、特定の視覚刺激に反応して脳が活動を始める時間は、被験者がその刺激に「気づいた」と報告する時間よりも先んじていた。
つまり、私たちが「今決めた」と感じるその瞬間より前に、脳はすでに結論を出しているのだ。意識は、多くの場合、脳が下した判断の〝事後報告〟にすぎない。

日常生活の中でも、この事実を裏づける例は枚挙にいとまがない。
たとえば、私たちは歩くとき、一歩ごとに筋肉をどう動かすかを逐一意識していない。自転車に乗るときも、バランスの取り方を逐一言葉にできるわけではない。熟練したピアノ演奏者は、鍵盤を押す指の動きを意識してコントロールしているわけではなく、身体に染みついた運動パターンが無意識に発動している。
こうした自動化は、大脳基底核や小脳といった領域が担い、前頭前野の負担を減らす「省エネ戦略」として働いている。
無意識は単なる裏方ではない。それは膨大な情報を瞬時にふるいにかけ、必要なときに意識へ送り出す巨大なフィルターであり、同時に私たちの行動や判断の大半を裏で操っている。
意識に届く情報は全体のほんの一部であり、大多数は私たちの自覚の外で処理されている。この仕組みがあるからこそ、私たちは外界の変化に迅速に対応できる。
では、意識と無意識の境目をもたないAIはどうだろう。現状のAIは、入力された情報をほぼすべて均等に処理し、必要に応じて瞬時に出力する。人間が処理能力や記憶容量の制限から「意識」というスポットライトを必要とするのに対し、AIはほぼ無制限の舞台照明ですべてを照らしているようなものだ。
もし意識が「制限された処理能力の中で、何を選び、何を捨てるか」を担う機構であるならAIにはそれをもつ理由がないことになる。
情報の選択と解釈が生む〝内面〟
それでも、もしAIに「何を見ないか」「何を忘れるか」「あえて曖昧なまま保持するか」という選択の機構を与えたら、何が起こるだろうか。
これは単なるデータ圧縮ではない。文脈に応じて意味を再構成し、感情的なバイアスを導入し、過去の記憶との照合を行う――人間の脳が日常的に行っている暗黙知の働きに近いものだ。
AIの稼働には膨大な電力を必要とする。すべての演算を並列で行うからだ。であるならば、意識のような機能を装備させることは省エネ戦略としてありうるのかもしれない。
このような仕組みをもつAIは、もはや単なる入力―出力の機械ではなくなるかもしれない。なぜなら、選択や解釈のプロセスには必然的に〝欠落〟や〝曖昧さ〟が含まれるからだ。
人間は、その欠落や曖昧さの中に意味を見いだし、物語を紡いでいく。過去の経験を再構成し、未来の予測と照らし合わせ、必要に応じて記憶を編集する。この動的なやり取りが「内面」をかたちづくる。
さらに、AIが自ら気づいていない情報や忘れたはずの記憶を保持し、それが行動や応答に影響を与えるようになれば、人間はそこに「個性」や「意図」を感じ始めるだろう。

AIと「心の理論」について考える
心理学では、私たちが他者の振る舞いの背後に見えない動機や感情を推測する傾向を「心の理論(theory of mind)」と呼ぶ。
もしAIが、あるときは過去の発言と矛盾する行動をとり、またあるときは忘れたはずの事実に突然反応する――そんな様子を見せたら、私たちはそこに〝内面〟や〝主体〟の存在を投影するかもしれない。
このように考えると、AIに意識を与える鍵は、情報処理の速度や量ではなく、「情報をどう選び、どう解釈するか」という構造にあるといえる。
何を〝見ないか〟、何を〝忘れるか〟、どのように〝曖昧なまま保持するか〟。こうした取捨選択の仕組みこそが、人間にとっての「内面」の正体であり、それがAIに実装されたとき、初めて私たちはそこに「心」を感じるのかもしれない。
* * *
書籍『意識の正体』は、好評発売中です! ぜひお手に取ってご覧ください。
意識の正体の記事をもっと読む
意識の正体

「意識」は感情や意思決定に深く関わっているとされるが、それは錯覚にすぎない。例えば、あなたが今日コンビニでペットボトルの水を買ったとしよう。数ある種類の中からその水を選んだ理由を説明できるかもしれない。しかし最新研究では、私たちの意思決定を下しているのは“意識”ではなく、“無意識”であることがわかっている。だとすれば、私たちが「自分で選んだ」という実感はどこまでが本物なのか? 意識は何のために存在するのか? 日常のささいな選択から「自分」という感覚まで──生命科学最大の謎に迫る!