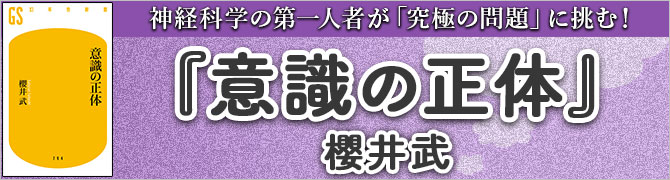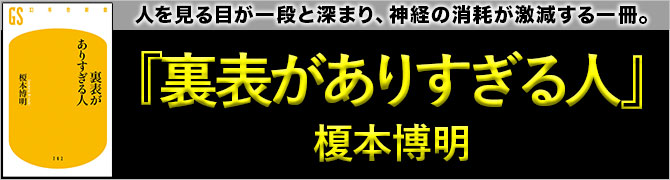街のありふれた食堂「食堂キング」を舞台に、中年女性・サチコのささやかな成長を描いた、群ようこさんの最新長編小説『サチコ』。その冒頭部分を、地方新聞連載時に添えられた、阪口笑子さんの温かい挿画とともに、お届けします。

無職のサチコは買ったばかりのシャツブラウスに、自分ではいちばん痩せて見えると思ってはいるパンツを穿いて、ひとり暮らしのマンションを出た。目的は徒歩三分のところにある、住宅地のなかの古い食堂だ。サチコが二十年前にこの場所に引っ越して来たときからあり、知っている限りでは、外装の補修工事をしているのを見た記憶はない。店名は「キング」と立派だが、古びたモルタル造りの二階建て店舗兼住宅の壁にはひびが入っている。看板もどこか煤(すす)けている。しかし、ガラス戸や窓から店内をのぞくと、必ず複数の客が入っている店だった。
引っ越して来た当初、まだサチコは三十代半ばだった。会社に行きながらの荷(に)解(ほど)きの連続の日々に疲れ、コンビニよりも近くにあるキングで、晩御飯を食べようと中に入った。八百円の焼き魚定食を食べたのだが、あまりおいしくはないものの、食べられないというほどでもない
微妙な味付けだった。しかし店内の四人掛けテーブル三卓と、カウンター席八席のうち自分を含めた五席は、埋まっていた。テーブル席のいちばん奥は小学生の子ども二人と両親、次が老齢の夫婦、出入り口にいちばん近いテーブルには、作業着姿の男性四人が座っていた。カウンターにいたのは、サチコ以外は中年、老年の男性だった。
彼女はみんなが注文している料理をさりげなく眺めながら、
(あれはおいしいのかな。私のだけが特別に、味付けがいまひとつだったのかな)
と考えていた。カウンターに座っている人たちは、どの人もビールや酒はおかわりをしているが、お酒のあてを完食している人はいなかった。家族連れのテーブルを盗み見ると、子どもたちは御飯もおかずも完食していた。
(子どもが全部食べているところを見ると、全部がおいしくないわけではないらしい)
カウンターに座っているのは常連さんらしく、店主夫婦と会話を交わしていた。人とすぐにも打ち解けられないサチコは、話しかけられたらどうしようかと気を揉んでいたが、店主夫婦は常連さんたちとの会話が弾んでいたせいか、サチコには話しかけてこなかった。
出された料理は残すなと両親からほう 躾(しつ)けられたので、サチコはキングを選んだのを少し後悔しつつ、全部食べ終わった。焙じ茶をひと口飲んで、口内に残っている味を洗い流し、
「ごちそうさま」
といって立ち上がったのだった。
サチコの記事をもっと読む
サチコ

両親が残してくれた1DKのマンションで一人暮らし。内向きで、控えめで、読書さえしてれば幸せ。「褒められもせず、苦にもされず」が生きるモットー。そんなサチコが55歳で長年勤めた職場を早期退職し、自宅から徒歩3分の「食堂キング」でアルバイトを始めた。初めての接客が不安なサチコだったが、気のいい店主夫婦やユニークなお客さんたちに囲まれ、遅ればせながら人生の色々を学んでいく。けれど、店主の腰痛が長引いて、キング閉店の危機が……!? ときにじんわり、ときにほろ苦く、どこか滑稽で――。ささやかな人生の豊かさを味わえる長編小説。
- バックナンバー