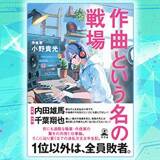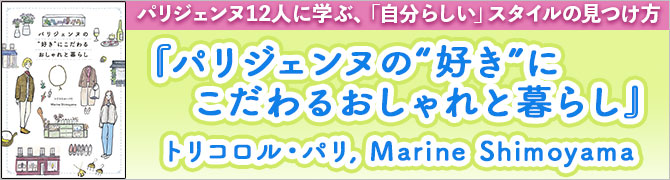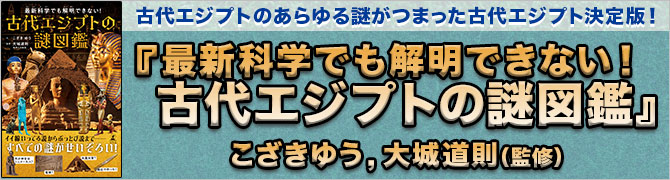AKB48、なにわ男子、日向坂46をはじめ、声優の内田彩、内田雄馬、小倉唯、千葉翔也、アニメ「テニスの王子様」「アイカツ!」、ゲーム「THE IDOLM@STER」「刀剣乱舞ONLINE」など、多彩なジャンルで唯一無二のメロディを提供する作曲家・小野貴光さん。音楽を仕事にすることのリアルを綴ったエッセイ『作曲という名の戦場』から一部抜粋・再編集してお届けします。
* * *
時代の話をすれば、最近はやはり無視できないのがAIだ。
人工知能は恐ろしいスピードで進化している。これと戦おうなんていうのはすでにナンセンスだ。共存の道を探るべきだと僕は考える。
僕が小さい頃から時間をかけて築いてきた音楽への造詣を、AIは世界中の利用者から膨大なデータをディープラーニングして築いている。もちろん驚異的なスピードで、だ。AIはあっという間に人間の想像を超えてくるはずだ。
現時点でも、AIは数秒で一曲を書き上げる。何十曲、何百曲、何千曲だって問題ない。その良し悪しを見極める力を人間のほうで持っていれば、もはや作曲家なんていらないのではないかとすら思う。
現に僕もAIに曲を作らせてみることがあって、もちろんお遊び程度ではあるのだが、たまに「こうきたか!」と驚かされることがあるのだ。参考にできそうなこともなかにはあるし、こういった使い方は今後増えていくかもしれない。

なんなら、BGM程度ならAIに作らせるほうが簡単だろう。たとえばホテルのラウンジで流すBGMならピッタリのものをすぐに作ってくれるし、コミカルなシーンに合わせたちょっと抜けた感じの曲や、戦闘シーンに合わせるような緊張感のある曲なんてお手のものだ。頼もしいじゃないか。
かくいう僕は、実はBGM制作が得意ではない。アニメなどでは「劇伴」と呼ばれ、各シーンのSE(サウンドエフェクト)として使用される音源だ。依頼されれば作家としては光栄なことなので、ありがたく引き受けるが、音域の制限がまったくないなかで作るのは途方もない作業だと感じる。どこまで作り込めばいいのかゴールが見えなくなり、ついメロディを組み込んでしまうのだ。すると「ドラマティックすぎて画の邪魔になる」なんて意見もいただく始末。
以前、ある声優のプロジェクトから、ライブのoverture(オーバーチュア)の制作を依頼された。演者がステージに登場する際のBGMで、これから始まるライブの盛り上がりを予感させるような音楽を作る必要があった。
僕は悩みに悩んだ。声優のキャラクターを念頭に置けば、どうしてもメロディが先行してしまうが、されどメロディは必要ないわけだ。さあどうしよう⁉
結局、これはどうかな、あれはどうかなと思い悩んだ末、二曲を書き上げて「好きなほうを使ってください」と言って両方とも提出した。事務所サイドはビックリしていたが、僕にはどうにも決められなかった。作曲家としての小野貴光らしさはやはりメロディにあると自分でも考えているので、らしさを出さずに曲を作るというのは思うよりずっと難しいことなのだ。
その点、AIは、悩むことも傷つくこともなく、人間が求めるままにひたすら曲を書き続けてくれる。批判やダメ出しなどまるで意に介さない。それだけでも強い。
最近はコンペに曲を出す際に仮の歌詞をつけることも多いが、どのみち仮なので、幾度もダメ出しをしながら歌詞の世界観をつくり上げるのにもAIは向いている。
ベーシックなところを組み立てさえすれば、何十回でも突き返して、納得のいくレベルまで持っていけるだろう。なにしろAIは、何回やり直しさせても、深夜でも明け方でも、文句の一つも言わずにこちらの要望に応えて新しいものを書き出してくれる。生身の作詞家にそれをすれば、間違いなくクレームに発展するやつだ。

とはいえ、AIにすべてを任せるには、まだ人間側の工夫が必要だろうと思う。要求を明確に言語化して指示を出す必要があるからだ。音楽という抽象的なものを言葉ですべて表現するのは不可能に近く、それゆえに的確な指示が出せず、望む結果をAIから得られない場合が多々ある。
たとえば、こちらが曲のイメージを的確に言語化できたとしても、AIのアルゴリズムがその意図をうまく汲み取れなければリクエスト自体が弾かれてしまう。その壁を越えるには、ひとえに世界中の多くの作曲家がAIを使用し、アルゴリズムを組み立てていくしか方法はないが、それは遠い道のりだろう。
同じメロディと向き合っても、人それぞれに感じ方が違えば言語化の仕方も違い、人の数だけ答えがあるのが音楽だからだ。
すでに自らの手で曲を作ることに慣れた僕のような作家にとっては、AIは未来永劫、補助的な役割に過ぎないのかもしれない。そのぐらいライトに考えれば、かなり出来のいい助手だと思う。
ただし、未来の作曲家に関してはその限りではない。鍵盤やギターで、あるいは五線譜に向き合いながら、自らの知識と経験に基づいた曲作りを経験しないままAIの利便性に頼れば、そこで出てきたものがいい曲の基準になってしまうからだ。
なにしろAIは、それなりにいい曲を書く。
事実、ダンスミュージックのようにメロディに重きを置かないジャンルであれば、AIはかなり上手に作る。そう考えると、これからはジャンルや用途によって、人間の作曲家とAIとの棲み分けが進んでいくのかもしれない。
音楽業界にしろクライアントにしろ、今のところはAIに作らせた曲だというだけで抵抗を感じる世代がビジネスの中心にいるので、まだ人間の作曲家が生き残る余地があるが、コンペの大半をAI曲が席巻する日が来てもまったく不思議ではない。しかもそれは案外、そう遠くない未来に訪れる気がするのだ。