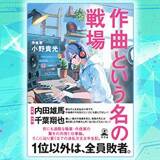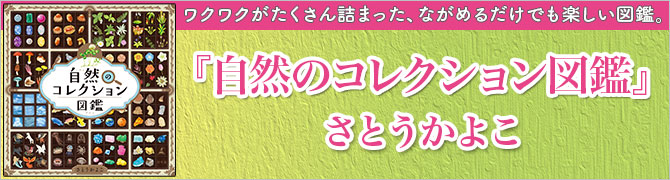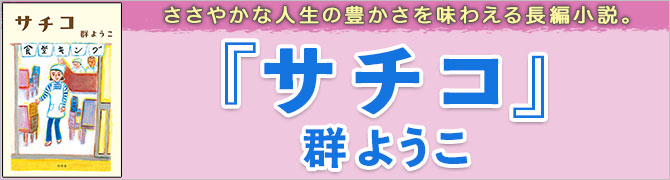AKB48、なにわ男子、日向坂46をはじめ、声優の内田彩、内田雄馬、小倉唯、千葉翔也、アニメ「テニスの王子様」「アイカツ!」、ゲーム「THE IDOLM@STER」「刀剣乱舞ONLINE」など、多彩なジャンルで唯一無二のメロディを提供する作曲家・小野貴光さん。音楽を仕事にすることのリアルを綴ったエッセイ『作曲という名の戦場』から一部抜粋でお届けします。
* * *
作曲家の仕事の、おそらく90~95パーセントぐらいはコンペに向けて曲を書くこと。コンペとは、楽曲コンペティションのことだ。
たとえばアイドルグループの次のシングル曲、あるいは制作予定のアニメの主題歌などを求めて、レコードメーカーなどが主催者となり、音楽制作事務所に所属する作曲家に募集要項を提示し、広く楽曲を集めて最良の一曲を選ぶという、いわばオーディションだ。
提出した曲が採用されればどこかのアーティストが歌い、作品化され、そこで生じる著作権料(印税)が作曲家の収入となる。
世の中の多くの人は、プロの作曲家の仕事について、きっとこう思っているだろう。
どこからか楽曲制作の依頼が来て、テーマや歌い手に合わせて曲を書き、締切日までに納品すれば、しばらく後に少なくない印税なりギャランティなりが銀行口座に振り込まれる。それを一年のうちに何曲もこなして、悪くない自由な生活を謳歌している、と。
しかし実際は、そんなに簡単なプロセスで稼げる仕事など、ほぼないと言っていい。最初からリリースが決まっている作曲の依頼など滅多にないのだ。レコードメーカー所属の作家や、アニメ監督と直接つながりがあるなど太いコネクションがある場合を除き、ほとんどは曲を書いてはコンペに参加し、採用されてはじめてそれが仕事になり、収入につながる。
採用されなければ、どんなにたくさん書いても対価は支払われない。

つまり二番手じゃダメなのだ。常に一番を勝ち取らなければいけない。しかも一度だけではまぐれの一発屋で終わってしまう。何度も一位を取り続けることで職業として成立し、それでようやく飯を食っていくことができるようになる。僕の皮膚感覚で言えば、よっぽどのヒット曲を生み出さない限りは、一年間に最低でも十五~二十曲はリリースしないと東京では生活できないだろう。
現状、日本で作曲家として専業でやれているのは、百~百五十人ほどと言われている。実のところ、とんでもなくニッチな職業だ。
コンペ開催の情報は、主に各メーカーの担当者からメールで送られてくる。作曲家になるための第一関門として、このメールを受け取れるようになるまでがこれまた果てしなく長い道のりなのだが、詳しくは後述する。
コンペは、エントリーが必要な案件もあるが、多くは信頼関係をもとに情報を送ってくれているので、返信すらせず、そのまま作品を送ることも少なくない。
募集の内容はさまざまだ。
〈○月○日締切某アーティストのミニアルバム収録曲。華やかに盛り上がる楽曲で、ラップも入れてください〉
〈某アニメの主題歌用楽曲依頼、積極的にご参加ください。甘酸っぱい恋愛がテーマ。ポジティブなイメージで、速めのテンポです。ストーリーは……〉
シンプルなものから、コンセプトや楽曲のイメージ、タイアップの情報、参考曲のリンクまで貼り付けられた、正式オファーと見紛うほど立派な企画書まで、その内容は実に多岐にわたる。ごく稀にではあるが、丸投げで「お任せします」という案件もなくはない。
資料が多ければ多いほど、作曲するまでの事前準備に時間を要するが、大変な思いをしたからといって採用確率が上がるわけではないのがつらいところだ。
締切は、最長でも三週間ぐらい。仮に一週間だとしても、それで新しい曲を仕上げられなければプロとはいえないので、納期までの時間はさほど問題ではない。

僕は以前、「明日までに二曲仕上げてください」というオファーを受けたことがある。夜の八時だった。
すでに僕の曲がコンペに通ったはずなのに、「シナリオが変わったので新しい曲が必要なんです」とのこと。なかなかのブラック案件だ。でも、それを引き受けないと、次がないかもしれないと思わされるのがこの仕事の怖いところ。
もちろん、その夜は寝ずに曲を書いた。翌朝までに二曲きっちり、仕上げて送った。
企画によってまちまちだが、一つのコンペに集められる曲数は百ないし千のときもあるらしい。千曲集めても選ばれるのはたったの一曲だ。あるいはアルバム収録曲を全部そこで選んだとしても、せいぜい十曲。つまり残りの九百九十曲はボツ。
採用されなかった作品は基本的には作家に返却されるが、最初から「応募楽曲は返却しません」と明記されているコンペもある。「返却されない」とは、不採用の場合でも、その楽曲を他のコンペに出したり、自分でリリースしたりできなくなるということ。どれだけの自信作でも、採用されなければ永久に日の目を見ることなく、葬り去られることになる。
採用する側とされる側、その力関係は言うまでもない。納得できないなら最初から応募しなくて結構ですよ、というわけだ。
何が正しくて何が間違っているのか。どんなに疑問を抱いても、往々にして弱い立場の作家は異を唱えることができない。これからの時代はさすがに変わっていくのかもしれないが、もしかしたら何も変わらないかもしれない。音楽業界の体質は案外、旧態依然としているからだ。
だけど、文句ばかり言っていたって仕方がない。そのなかで生き抜いてこそ、作家として独り立ちできるのだ。