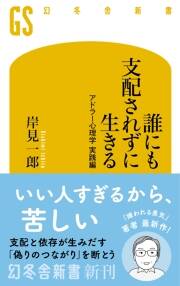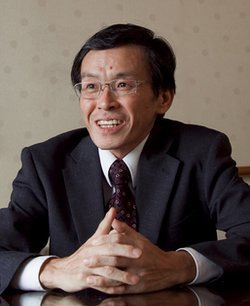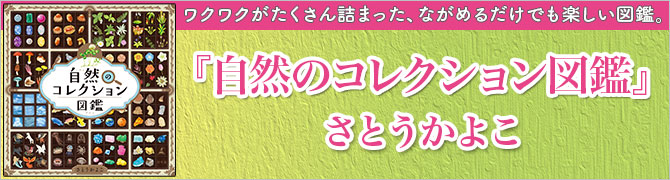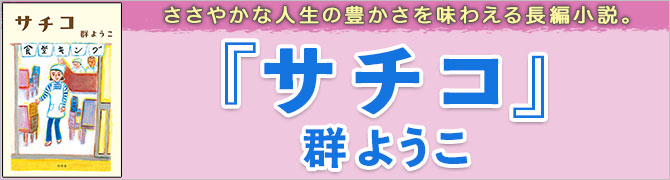「親の期待に応えなきゃ」「職場では空気を読まなきゃ」――そんなふうに“他人軸”で生き、人生を縛られてしまってはいないでしょうか?
「人の期待に反して行動する勇気を持つ」「自分を過小評価しなければ、もっと自由になれる」といったアドラー心理学の実践的な考え方を、哲学とあわせてやさしく解説した、幻冬舎新書『誰にも支配されずに生きる アドラー心理学 実践編』。本書の一部を再編集してご紹介します。
* * *
他者は“敵”ではなく、“仲間”
普段私たちは、電車に乗っている時にまわりの人にそ知らぬ顔をします。窓の外を眺めているわけです。隣にいる人との距離があまりに近いと、その人に関心を持っていると思われないように、私はあなたには関心がないというふりをしていないといけません。
でも、もしも電車の中で倒れる人がいたら、皆が可能な限り助けるだろうと考えていないわけではありません。そういうことが起こった時に、知らない人同士の集まりなのに、一体感が作られます。知らない人なのに皆がつながっているというその感じこそ、私の理解ではアドラーがいっている共同体感覚です。
共同体感覚という言葉を定義することにはあまり意味がありません。実際、その場の知らない人たちが何か緊急事態が起こった時に皆で助け合っている状況で他者との一体感を持てるとしたら、その感覚をアドラーは共同体感覚という名前で表していると私は理解しています。
アドラーの言葉を使うと、本来的に他の人は仲間です。私たちは他者を仲間と見ることもあれば、敵と見ることもあります。アドラーは、他者は隙があれば自分を陥れようとするような怖い人ではなく、「仲間」だといいます。仲間というのはアドラーの言葉を使うとMitmenschenです。これは訳しにくい言葉です。
mitは「共に」という意味です。英語ではwithです。Menschenは人々という意味なので、Mitmenschenはつながっている人々、即ち共同体感覚を表すMitmenschlichkeitは、人と人とがつながっているという意味になります。誰も一人では生きられないという意味で他者とつながっているのですが、アドラーは他者を仲間と見て、その仲間とつながっていると感じられなければならないといっているのです。

「頼まれもしないことをする」のが“甘やかし”
子どもの話に戻すと、子どもにしてみれば何か助けてほしいことがあって親に援助を依頼した時に、「それはあなたの課題でしょう」という言い方をされると、親を仲間とは見なさないかもしれません。
子どもが何らかの形で、本来自分の課題であるにもかかわらず援助を求めてくることがあれば、できる限り援助をしようと決めておいた方が安全かもしれません。中にはできないことがあるかもしれませんが、言葉で援助を求めてきて、それが無理なことでなければ援助しようと決めておくのが安全だと私は考えています。
親が、本来子ども自身が解決するべき課題で困っているに違いないと考え、子どもが頼んでいないのに援助しようとすることがあれば、それは甘やかしだと考えていいと思います。
これは私の息子が子どもの頃に教えてくれたことの一つです。ある日小学生だった息子に、甘やかしとはどういうことかわかるかとたずねたら即答されました。頼まれもしないことをすることだ、と。確かに私たちは頼まれもしないことをしていることが多々あります。ですから、まず、子どもを信頼する以上は子どもの課題に口出しをしないで、未知に飛び込む勇気を持って見守ることが必要です。でも、もしも子どもから依頼があれば、できることであれば援助しましょう。
何とか力になりたいのであれば、何かできることがありますかという言い方をよく使います。それに対して、放っておいてくれといわれたらそれで終わりなので、大人は一切何もする必要はありません。
大人同士でもこの言い方は使っていいと思います。もちろん、対人関係によって言い方は違ってくると思います。英語でいうとMay I help you?とかWhat can I do for you?ですが、何かできることがあればいってくださいねという言い方をすることはよくあります。これぐらいのことは、いってもいいのではないかと考えています。
信じる根拠がなくても信じるのが、“信頼”
信頼するという言葉のもう一つの意味は、よい意図があると信じることです。言葉として理解するのは難しいことではありません。しかし子どもの言葉を信じられないことがあるので、そう思うにはかなり勇気が必要です。
こんなことを思い出しました。私の家はかなり特殊な作りで、一階にはトイレと風呂しかなく、二階に主な生活スペースがあるという構造になっていました。
夜中に、当時四歳の息子がトイレに行きたいといいました。母親と息子が一緒に階下に降りて行ったので、そのことを知ったまだ生まれて間もなかった娘が、泣き始めました。しばらくすると、息子が大きな音を立てて階段を上がってきました。夜遅い時間だったのと、父がその日たまたま帰ってきていて部屋で寝ていたため、わざと大きな音を立てて上がってきた息子に注意をしようとしました。
すると、息子は指を口の前に持っていきました。これは話があるというサインです。何か意図があると思って私は黙ったのですが、息子の説明はこうだったのです。もし僕が大きな音を立てれば、**ちゃんはお母さんが上がってきたと思って泣きやむと思った、と。これが彼の行動のよい意図でした。
でも、そういうことを私たちは聞かないで、いきなりそんな大きな音を立てて上がってきてはダメじゃないかというような言い方をしてしまいます。親がこんなことをいうと、親と子どもとの間の信頼関係は大きく損なわれます。ひょっとしたら何かよい意図があってこういう言動をしたのではないかと立ち止まって考える余裕があればいいと思います。

条件付きの“信用”ではなく、未知へ飛び込む“信頼”を
作家の沢木耕太郎が香港に滞在していた時に、ある若者に中華ソバ屋で会いました。彼は日本に行けたらいいのにと夢見るような表情で語っていました。二人がソバを食べ終わると、若者はソバ屋のおばさんに中国語で何かを話しかけて、グッド・バイと言い残しお金を払わずにその場を立ち去ってしまったというエピソードを書いています。
沢木はこちらも自分で金を払うつもりだったから全然かまわないけれど、お礼の一つぐらいいってもいいじゃないかと思った、見事な手際でたかられたことにがっかりしたと書いています。しかし、お代を払おうとすると、おばさんはいらないといいました。明日仕事にありつけるから、この二人分は付けにしておいてくれとその若者がいったというのです。
沢木は、自分が情けないほどみじめに思えた。それはもちろん失業中の若者におごられたからではなく、一瞬でも彼を疑ってしまったからだったと『深夜特急』の中で書いています。
皆さんもこれに近い経験をされているかもしれません。信じることが難しい状況で信じること、あるいは、信じる根拠がない時にあえて信じることを信頼といいます。
普通私たちは信用という言葉を使いますが、信用は条件付きなのです。明らかに信じる根拠がある時に信じるのであって、未知に飛び込むことではないのです。確実にわかっている場合に信じるというのは信用でしかない。
例えば、銀行がお金を貸すような時ですね。担保があればお金を貸してくれますが、私は若い頃は銀行の預金残高が十数万円とかでした。そういう時代が長かったので、銀行は全く相手にもしてくれませんでした。銀行は顧客を信用するけれど、信頼していないのです。でも、親子関係を始めとする対人関係の中では、相手を信じる条件がなくても、未知の中に飛び込む勇気を持っていないといけないと考えています。

「監督された人生」を生きないために、必要な勇気
残念ながら、信頼される側の問題もあります。ここまでは信頼する側の話をしてきましたが、信頼される側の問題も考えておかなければなりません。
本章の初めに、よい対人関係の条件の一つとして尊敬ということをあげましたが、私の言葉を使うと相手を対等の人格として扱う、見なすということです。
加藤周一が中学生の時のエピソードを話しています。加藤は、ネギ先生というあだ名で呼ばれていた「一人の尊敬すべき人格」に出会いました。ネギ先生は生徒を独立の人格として扱おうとしました。
ネギ先生は生徒を信頼し、中学校の最初の試験を監督なしで行おうといい、次のような話をして教室から出ていきます。
諸君の試験が監督されるということは諸君が信用されていない、つまり諸君の人格が侮辱されているということです。諸君はそれを侮辱と感じなければいけません。私は諸君を信用せずに諸君を教育できると思わない。しかし、私の見ていない時に万一不正が行われれば、それを放っておくわけにもいかない。私は諸君を信用します。どうか信用を裏切らないでください。私のためにではなく、諸君自身の名誉のために。
加藤がこの話を引用しておきながら、生徒は先生の信用に応えましたという話であれば、わざわざここでこのエピソードを引いてこなかったかなと少し斜に構えながら読んだところ、果たしてこの監督なしの試験は失敗に終わりました。要するに、不正行為をする生徒が続出したのです。
こういう状況で、自分がどうするか想像してください。先生は教室から出ていくわけです。だから、カンニングし放題。不正行為をしてもかまわない状況に自分が置かれた時、その先生の信頼を裏切るような行為を自分はするのだろうかということは、考えておかないといけません。
この監督なしの試験が失敗したのは、中学生には人格に対する侮辱を侮辱として受け取るだけの人格の観念がなかったからです。試験が監督されることが人格に対する侮辱であるということの意味がわからなかった。
「学校の教育方針は、監督された試験で、『またおそらくは監督された人生で』よい成績をあげる生徒をつくることにあり、その試験に監督を必要としない生徒をつくることにはなかったのです」(『『羊の歌』余聞』)
これはかなり厳しいことだと思います。「おそらくは監督された人生で」とわざわざ鍵カッコをつけて加藤はいっていますが、試験だけではありません。
私たちは人生を生きる時も、誰かに常に監督されないといけない。つまり、誰かに指示されないといけない。自分の責任で行動するということをしないのです。他方、不正を犯そうと思えばできる状況で、自分の判断で不正をしない選択ができる人がいます。でも、多くはないでしょう。加藤は戦前の話をしていますが、今日も少しも変わっていないのではないでしょうか。
「監督なしの試験が正しく行われるためには、権威に従うのではなく、みずから定めた掟に従う自由な精神の道徳が必要なはずで、ネギ先生こそは、そういう道徳をもとめていたのです」(前掲書)
* * *
アドラーの教えを詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『誰にも支配されずに生きる アドラー心理学 実践編』をお読みください。
誰にも支配されずに生きる アドラー心理学実践編
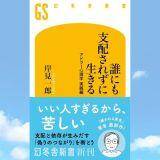
「親の過度な期待」「職場の同調圧力」「SNSでの承認欲求」――他人の期待に応え、空気を読み続けるうちに、知らぬ間に“支配と依存関係”に囚われてはいないだろうか。そのような“偽りのつながり”こそが、あなたの生きづらさの原因である。本書では、「人の期待に反して行動する勇気を持つ」「自分を過小評価しなければ、もっと自由になれる」など、よい対人関係を築き幸福に生きる方法を、哲学とアドラー心理学を長年研究してきた著者が解説する。自分の人生を自分のために生きる勇気を与えてくれる一冊。