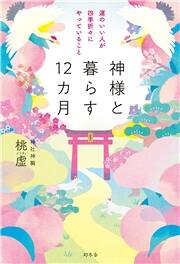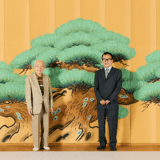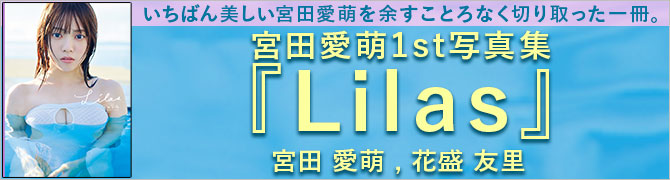11月と言えば、七五三の季節ですが、昔は、男女ともに三歳、五歳、七歳の儀礼をおこなっていたそうですよ。それも、理由は「神様」。
神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。
* * *
いにしえでは、「7歳までは神のうち」 11月は「七五三まいり」の季節。
個々に行われていた子どもの人生儀礼が、11月に定着したのは、江戸時代に徳川5代将軍・綱吉が、息子・徳松の「袴着(はかまぎ)の儀」という人生儀礼を11月15日に行ったから、という説が有力です。さすが徳川、民衆への影響力が大きいですね。
古式では人の年齢を、生まれた時点で「1歳」と数え、おおむね生後1カ月で初宮詣を行って、赤ちゃんの誕生を神様にお知らせします(ただし生後百日の地域もありますし、寒冷地では生後3カ月以降に行うこともあります)。
その後、お正月がくるごとに、「年神様」から次の一年をいただきます。
1月1日に、みんないっせいに1歳年をとる――これが今で言う「数えの年齢」。
神社で行われる、厄年の厄祓(やくばら)いなどの人生儀礼は、この「数えの年齢」に沿って行われます。
七五三まいりも本来は数えの年齢で行いますが、近年では、数えの年齢でする子と、満年齢でする子が、半分ずつぐらいの割合になっています。

昔の日本は、栄養も、医療も、今のように充実していませんでした。ですから、たくさんの子どもが、大きくなる前に命を落としました。このことを昔の人は「幼いあいだは、魂(たましい)が肉体に定まっていない。だから、魂がいつ肉体から離れてもおかしくないのだ」、と考えていたようです。
この、魂が自由に時空を行き来している感じをイメージすると、「それって神様じゃない?」ということになります。そのためか、昔は「七つ前は神のうち」と言われていて、数え7歳ごろになってようやく、神的な存在から人になったとみなされ、神社の「氏子(うじこ)」として認識される、という地域も多かったのです。
そんなこともあり、生まれた「1歳」から、人として魂が肉体に安定する「7歳」までは、ことあるごとに、子どもの成長を祝い、感謝する儀式が行われてきました。
これが、貴族や武士の人生儀礼の様式とまざって、1歳の誕生から2年刻みで3歳、5歳、7歳……と、陰陽道における吉数である奇数の年に年祝いをし、神様にさらなる無事成長を祈願する、という、いまのような七五三の儀式を行うようになったと言われています。
では、3歳、5歳、7歳の儀式について、かんたんに見ていきましょう。
まず、数え3歳は、「髪置きの儀」。髪を結うために伸ばし始める儀式です。

昔は、赤ちゃんが生まれると、生後7日めに髪を剃り、それ以降は、数え3歳になるまで、女の子も男の子も髪を剃って丸坊主にしていました。免疫力が弱いうちは、毛髪を剃ったほうが頭を清潔に保てますし、のちのち健康な毛髪が生えてくると考えられていたからです。
数え3歳になると、髪を剃らずに置いておく、「髪置きの儀」という儀式を行い、髪を伸ばして、結うヘアスタイルにする、というのが定番でした。この「髪置きの儀」の時の衣へ装が「七五三まいり」での3歳の衣装となります。ひも付きの着物に兵児帯(へこおび)を簡単に結び、「被布(ひふ)」という、ベストのような、袖なしの羽織を着ます。
それから数え5歳は「袴着の儀」。初めて袴を着ける儀式です。

「袴着(はかまぎ)の儀」は、「着袴(ちゃっこ)の儀」とも呼ばれ、女の子も袴をはいていた平安時代から室町時代にかけては男女ともに行われていました。江戸時代に入ってから、武家の男の子のお祝いへと変化したと言われます。碁盤にのって着付けをしたり、碁盤から飛び降りたりするならわしがありますが、これは、四方を制することができるように、という意味があります。
現代の七五三では、5歳の男の子が紋付の羽織袴を着ます。剣を懐に差し、白足袋に草履(雪駄)をはいた姿は、まるで小さな殿様のようです。
7歳は「帯解きの儀」。本式の帯をつけ始める儀式です。

昔は本式の帯を締めて一人前とみなされました。室町時代以前は男女ともに行われていましたが、江戸時代になり、男児は5歳で「帯解の儀」を、女児は7歳で「袴着の儀」を行う形になったと言われています。
現代の七五三では、数え7歳の女の子が華やかな振袖に袋帯や丸帯を締め、しごき帯という飾り帯を結びます。帯締めには「丸ぐけ」か「丸うち」を使い、胸元に「箱せこ」という小物入れをはさみ、扇子をもちます。
こうして3歳・5歳・7歳の儀式を見てみますと、どれも、もともとは、男女とも行っていた儀式だということがわかります。
そして、七五三まいりには、「年は神様からいただくもの」「数え7歳までは神のうち」という、人と八百万の神々との、自然で親密な関係性を見ることができます。
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること
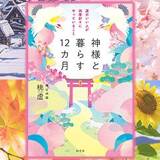
古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!
* * *
神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。
- バックナンバー
-
- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...
- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...
- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...
- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...
- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...
- 神々がしていることを真似すると、運が開く...
- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...
- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...
- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...
- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...
- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...
- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...
- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...
- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...
- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...
- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...
- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...
- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...
- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...
- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...
- もっと見る