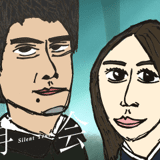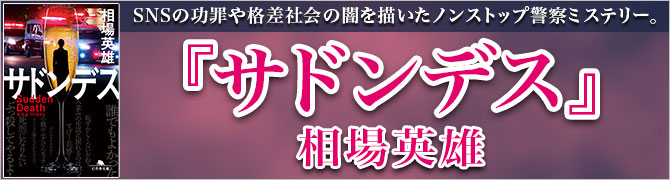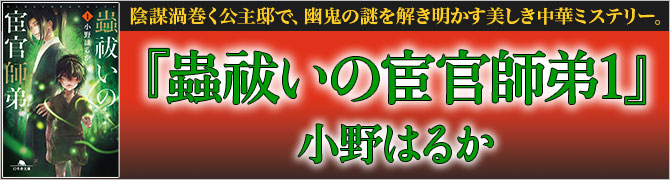「海ノ向こうコーヒー」で働く田才さんが今回訪れたのは、ラオス南部・ボラベン高原。
かつてフランス植民地時代に持ち込まれたアラビカ種が、今も豊かな香りを放つコーヒーの名産地です。
そこには、産業としてだけでなく、暮らしの中に息づく“コーヒーの文化”がありました。
* * *
前回の記事では、ラオス北部ルアンパバーン県で僕たちが国連世界食糧計画(WFP)と共に実施している「COFFEE-JAPANプロジェクト」について紹介した。現地パートナーのサフロンコーヒーと、森のなかで農作物を育てるアグロフォレストリーによるコーヒー栽培や精製の技術を村々に伝え、農家がコーヒーによって生計を立てられるようにしていこうという取り組みだ。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
幻のコーヒー豆を探して海ノ向こうへ
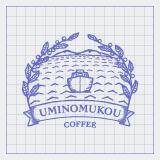
──元・国連職員、コーヒーハンターになる。
国連でキャリアを築いてきた田才諒哉さんが選んだ、まさかの“転職先”は……コーヒーの世界!?
人生のドリップをぐいっと切り替え、発展途上国の生産者たちとともに、“幻のコーヒー豆”を求めて世界を巡ります。
知ってるようで知らない、コーヒーの裏側。
そして、その奥にある人と土地の物語。国際協力の現実。
新連載『幻のコーヒー豆を探して海ノ向こうへ』、いざ出発です。