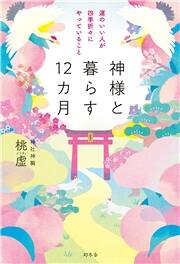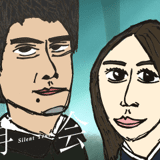「秋」を楽しめるようになると、大人になったなあ、という気がしますが、実際に根拠があるようです…!?
神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。
* * *
秋というのは「陽と陰」を分け合って同居している季節です
日本人は、春は花見、秋にはもみじ狩りに出かけては、その美しさを言祝(ことほ)ぎ、愛(め)で、鑑賞と言っては盃をくみかわしてきました。それは神様を言祝ぐ、神様と遊ぶということでもあったのです。
とはいえ、赤や黄色に染まった葉に秋をしみじみと感じる文化は、中国にもありました。
林間に酒をあたためて紅葉(こうよう)を焼(た)く 石上に詩を題して緑苔(りょくたい)を掃(はら)ふ
これは「和漢朗詠集」の巻上に収められた、中唐の詩人、白居易(はくきょい)の詩です。林の中で、紅葉を集めて燃やし、酒をあたためる。石の上の苔(こけ)を掃いおとして、詩を書きつける。
「いいよね」という世界をそのまま描写した、ただそれだけなのですが、秋の味わいがぎゅっとつまっていますよね。
お酒から立ち上る湯気と、もみじの色と、火のあたたかさ。それに対比するような苔の緑と石のひんやり感。
これこそ「陽」と「陰」が分け合って同居する秋ならではの味わいではないでしょうか。

そして秋が深まるにつれ、「陰」が強くなっていきます。
空気が澄んで、夜の月もよく見える。控えめな秋の虫たちの声。澄み切っていく心。研ぎ澄まされていく五感。そこにふとおとずれる、さみしさ。
秋の味わいは、大人になるほどしみじみとわかるものなのかもしれません。
見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮れ
これは藤原定家のあまりにも有名な歌で、たしか高校生のころに習ったと思うのですが、当時はちっともぴんときませんでした。
「見渡してみると、美しく咲く花も見事な紅葉も見たらないことだよ。浜辺の粗末な漁師の小屋だけが目に映る、なんともわびしい秋の夕暮れであることよ」という歌です。
「花」は桜で、「紅葉」はもみじ。それらを見渡しているかと思ったら、「なかりけり」。
大阪の人なら「ないんかい!」とつっこむポイントです。でも、「なかりけり」ですべてがなくなるわけではないのです。花ともみじが残像として、ふわっとある。そこに、漁師の粗末な小屋が見えているよ、という、絶妙なあんばいです。
花やもみじの「陽」がうっすらと残像のように遠くにあり、寒くて粗末な小屋にフォーカスされて「陰」が近くにあることを知る。そんな秋の夕暮れの、うらさびしさ。それも全然、悪くないですよね。むしろ良い。味わい深い。

神様たちによって「もみぢる」植物を愛でる秋。世界は神々からの贈り物にあふれていることを知る収穫の秋。私の生まれた国、インドでは、この時期にヒンドゥー教の新年を迎え、収穫と新年をまとめて祝う「ディワリ」というお祭りをして盛り上がるので、なんとなく血がさわぐ季節でもあります。
「ディワリ」では、家をそうじし、清めて飾りつけするところが、日本の年神様迎えに似ています。「ディヤ」と呼ばれるオイルランプを灯し、家族や友人と集まってお菓子を食べる。豊かさの女神、ラクシュミーを祭り、ディワリセールが各地で開催され、消費が活発になる。そんな福々しいところも、日本のお正月に通じるものがあります。
それにしても、日本人は、夏に怨霊の神様をもてなしてお祭りをし、10月の実りを神様に感謝してお祭りをし、その2カ月後には新年の年神様を迎えてお祭りをするのですから、相当、お祭り好きな民族と言えるのではないでしょうか?
それもこれも、日本の季節が豊かで、たくさんの神様がいるからですよね。
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること
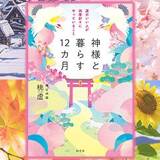
古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!
* * *
神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。
- バックナンバー
-
- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...
- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...
- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...
- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...
- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...
- 神々がしていることを真似すると、運が開く...
- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...
- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...
- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...
- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...
- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...
- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...
- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...
- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...
- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...
- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...
- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...
- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...
- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...
- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...
- もっと見る