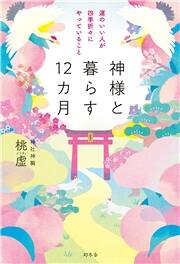9月の花、菊は「不老長寿の薬」として栽培されてきた植物なのだそうです。
ということで、9月9日の重陽の節句では「菊の花をひたした清酒」を飲んで、健康と長寿を願いましょう!
さらに、平安時代から、菊には、貴族の間でこんなことが流行っていたそうで‥‥
神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。
* * *
菊の花は不老長寿の薬だった!美肌と若返りを願う「菊の着せ綿」とは?
9月9日は重陽(ちょうよう)の節句です。
陰陽思想で、奇数は「陽」。奇数の中でも一番大きい数字「9」が重なる9月9日は、陽が重なると書いて「重陽」の節句なのです。
とはいえ、3月3日の桃の節句や、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕など、ほかの節句よりも、馴染みが薄い気がしますよね。でも、重陽の節句は、飛鳥時代にはすでに中国から日本に伝わっており、平安時代には「重陽節」として正式な宮中行事がありました。
いったいどんなことをしていたのでしょう?
平安時代に編纂された歴史書「日本紀略」の大同2年(807)の記事には、
「九月九日者菊花豊楽聞食日」
とあり、これが最初の重陽節の祝宴とされています。真ん中あたりに「菊花」という文字が見えますよね。
9月9日は「菊」なのです。菊の花をひたした清酒を飲み、和歌を詠み音楽をたのしんで健康と長寿を願うのが、この日のならわしでした。
中国では、「魏の初代皇帝、曹丕(そうひ)は幼いころ、体が弱く、長くは生きられないと言われたが、菊酒を飲んで健康になり、のちに皇帝になった」という伝説もあるほどで、菊は「不老長寿の薬」として栽培されてきた植物。そのアンチエイジング効果は、重陽の節句の行事とともに、日本にも知らされたようです。
菊を使ったアンチエイジングのおまじないが、「枕草子」にも書かれています。
九月九日は暁がたより雨すこし降りて、菊の露もこちたうそぼち、おほひたる綿(わた)などもいたく濡れ、移しの香ももてはやされたる
(=9月9日は明け方から雨がすこし降り、菊の露もたくさんできたので、菊をおおっていた真綿がじゅうぶんに濡れて、移り香がもてはやされている)
ここでいう「綿」は、真綿(まわた)のことで、絹(シルク)のわたです。このころの宮中では、前の晩からシルクのわたで菊を覆っておいて、9月9日の朝に、朝露と菊の香が移ったわたを取り入れ、それで顔や体をぬぐうという、アンチエイジングのおまじないが行われていたのです。
これは「菊の着せ綿(わた)」と呼ばれていた風習です。
「紫式部日記」には、紫式部が、ある人から「菊の着せ綿」を届けてもらったときのことが書かれています。
9月9日の朝、藤原道長の妻、倫子(ともこ)から紫式部に「特別に」と菊の着せ綿が送られ、「これで老いを充分にぬぐい去りなさいませ」とことづてがありました。倫子は紫式部よりも身分が上です。そんなお方が、手間のかかる菊の着せ綿を(お付きの者にさせたにせよ)、わざわざ届けてくれた。
そこで紫式部が取ったリアクションはこうです。
菊の露若ゆばかりに袖触れて花のあるじに千代は譲らむ
(=この菊の露に、私はほんのちょっと若返る程度に袖を触れるだけにして、この露がもたらす千年もの齢(よわい)は、花のあるじ(倫子さま)にお譲りします)
この歌とともに菊の着せ綿をお返ししようとしたけれど、倫子はすでに帰ってしまっていたので、お返しできずに手元に残った、と、「紫式部日記」には記されているのです。
こののち、倫子は90歳まで生きるご長寿となり、紫式部は生まれ歳がわからないので不明ですがおそらく40~45歳まで生きたとされています。当時貴族の女性の平均寿命が27歳くらいであったとされていますから、二人とも長生きしたのです。きっと、菊の着せ綿のおかげですね。
(つづく)
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること
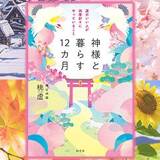
古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!
* * *
神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。
- バックナンバー
-
- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...
- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...
- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...
- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...
- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...
- 神々がしていることを真似すると、運が開く...
- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...
- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...
- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...
- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...
- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...
- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...
- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...
- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...
- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...
- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...
- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...
- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...
- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...
- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...
- もっと見る