
各論編、これまでは同じ属とか同じ科の野菜をまとめて紹介してきましたが、ネタもつきました。終わりに近づいた今回は、あまり仲間のいなさそうなインディーズ系の野菜からであります。
本当は兄弟じゃなかったネバネバ三兄弟
夏の畑をにぎわしてくれる、というか、やたらと採れる野菜のひとつにオクラがある。オクラはアオイ科オクラ属の植物で、ハイビスカスの仲間ではあるが、近縁種で食卓にのぼる野菜はほとんどない。オクラって、なんとなく日本っぽい名前やと思っていたが、英語のokraに由来する。というか、まんまである。元々は西アフリカ原産でnkrumaとよばれていたのが、奴隷貿易の時代にアメリカ大陸にわたりokraになったらしい。
オクラの実の成長スピードはものすごく速い。花が咲いたと思ったら2~3日後には5センチ程度になる。もうちょっと大きくしてと思っていると、あっという間に10センチ以上に育って硬くなってきてしまう。これは以前に書いたことのあるリグニンという物質が増えるせいだ。オクラ殿、油断なりませぬな。

お蔵入りという言葉や大倉という苗字があるから、オクラは日本語っぽい印象があるような気がする。もうひとつ、ネバネバ三兄弟の影響も無視できないのではないか。ご存じ、山芋、納豆とオクラである。山芋は日本原産のものもあるし、ほぼ和食でしか出てくることはない。しかし、納豆はイメージ的には和食であるが、ノンフィクション作家・高野秀行さんの詳細なる研究成果(?)である『謎のアジア納豆』(新潮文庫)や『幻のアフリカ納豆を追え!』(新潮社)によると、世界各地に存在する。ただ、乾燥系のものが多く、ネバネバしたものは日本だけらしい。
ネバネバ三兄弟、山芋は日本オリジンでいいけれど、オクラなんぞはアフリカ生まれだし、日本でよく食べられるようになったのは1970年代になってからでしかない。ネバネバ納豆は日本固有とはいえ、大豆は中国からやってきた外来種である。山芋は在来の民だが、オクラは移民、納豆はその中間といったところと由来が違うんやから、三兄弟という名前は嘘偽りのたぐいやん。ネバネバ三兄弟ではなくて、ネバネバトリオという名称を使うことを推奨したい。
買ってきたものと味が違う野菜選手権
つぎはアスパラガスを。子どものころ、アスパラといえば、ふにゃふにゃっとしたホワイトアスパラの缶詰しかなかった。いまでも、時々サラダの具材として出てくることがあって、おぉなつかしいと思いはするが、あいかわらず味も歯ごたえも見かけどおり頼りない。日本でアスパラガス、そのほとんどがグリーンアスパラ、がよく食べられるようになったのは、80年代に入ってからのことだ。
アスパラといえば想い出がある。1989年から2年近く留学していたドイツ――当時は「西ドイツ」――のハイデルベルク周辺は、アスパラガス――ドイツ語ではシュパーゲル――の名産地である。住んでいた丘の麓にはシュパーゲル畑があって、春になると、広々とした畑の一隅で朝掘りのホワイトアスパラが量り売りされる。これが抜群に美味しかった。現地ではバターソースやクリーム煮が主流だが、我が家では茹でて味噌田楽にして食べていた。
土から出る前に若い茎を掘り出して、新鮮なうちに食べる。植物としてはまったく違うけれど、朝掘りのタケノコに似た印象だ。そう言うたら、タケノコも味噌田楽にして楽しめるし、どちらも春だし、成長速度がすごいというのも似てますわな。それに、食べ頃に採取しないと、硬くて食べられなくなる点も同じである。アスパラガスは一日数センチ伸びるので、毎日チェックしないと食べ頃を逃がしてしまう。
ホワイトアスパラもグリーンアスパラも、採りたては柔らかくて、信じられないくらいみずみずしくて美味しい。甘さもすごくて、買ってきたものと味が違う野菜選手権の王者と認定したい。ちなみに、ホワイトアスパラとグリーンアスパラはまったく同じ植物で、光があたらないで育つとホワイト、あたるとグリーンになる。
シュパーゲル畑では盛り土の中でホワイトアスパラを育てるが、家庭菜園では専用の遮光用袋をかぶせて育てる。ネット販売で見つけたんですけど、なんでも便利なもんが売られてますなぁ。
シュパーゲルとアスパラ、ずいぶんと違う名前のように思うが、語源は同じく古代ギリシャ語で「芽」や「若い芽」をあらわすasparagosである。英語はほぼそのままだが、ドイツ語はラテン語asparagus から最初の「a」が脱落してSpargelになったという。
アスパラといえば、生化学で習ったアスパラギンというアミノ酸を思い出す。これは、アスパラガスに由来する名称だ。19世紀の初め、アスパラガスの汁から得られた結晶性の物質がアスパラギンである。当時はまだタンパク質が何からできているかわかっていなくて、アスパラギンは世界で初めて発見されたアミノ酸なのである。なんかえらいぞ、アスパラギン。
そのグイグイ伸びる性質のせいか、フレッシュ感のせいか、アスパラはなんとなく元気ハツラツのイメージがある。ただ、アスパラギンはオロナミンCの成分には入っていない。その代わりでもでもないけど、田辺三菱製薬にはアスパラドリンクαっちゅうものがある。
いきなりですが、なぞなぞです。「胸に槍が刺さりました。さてどうしたらいいでしょう?」答えは「アスパラ」。どうしてかというと、大昔に「♪アスパラでやりぬこう!」っていうTVコマーシャルがあったから。って、年寄りにしかわからんわな。
アスパラガスは多年草で、いちど植えると10~15年は採取することができる。我が家はまだ3年目なので、あと10年も採れそうだ。飽きっぽい性格なので、そのころには、「昔、えらそうに『知的菜産の技術』とか書いたことあったけど、家庭菜園なんか完全にやめてしもたわ」状態になっている可能性もありそうだ。あるいはもう死んでるかも……。
しかし、たとえそんな状態になってもまだ採れ続けるかもしらんと思うと、嬉しいというか不憫というか、不思議な気持ちになってくる。いや、アスパラガスが生え続ける限り、生きて知的菜産を続けるぞと、ここに強く決意しておきたい。ということにしておきたい。
アーディチョーク、コーラビも作ってみた
おそらく我が家で収穫できた野菜でいちばん珍しいのはアーティチョークかと思う。ご存じだろうか、アーティチョーク。日本で食べられることはほとんどなかろう。以前、どこか外国へ行った時に食べたことがあって気に入り、もう一度食べてみたいと思い続けていた。なので、種が売られているのを発見して、栽培を開始した。
1年目はまったく育たなかったのだが、2年目の再挑戦では立派なのができた。特になにかを改善したという訳ではないのだが、時々こういうことがある。当然、その逆で、何故かうまくいかなくなることもある。まぁ、このあたりは素人菜園の限界ですわな。
アーティチョーク、日本で珍しいだけでなく、野菜界でもちょっとした変わり種である。キク科の植物で、食べるのは花が開ききる前の段階のつぼみ(花蕾)の部分のみ。葉は数十センチの長さになるし、背丈は2メートル近くにもなる。かように立派な植物なのではあるが、とても悲しいことに食べるところはほんの少ししかない。その上、なんやかやと下ごしらえが大変だし、加熱時間もやたらと長い。ついでに書いておくと、信じられないくらいたくさんアブラムシがつくので、指でプチプチと潰さにゃならん。なにかと面倒なのである。

妻からは、じゃまくさいのでもう育てていらんと見捨てられている。多年草なのに、せっかく立派に育ったものを抜くのもしのびないんやけどなぁ。花がアザミに似ていて美しいとあるので観賞用でええか思ったけど、我が家のはそれほどきれいじゃなかった。花がアザミに似ているので和名はチョウセンアザミだが、江戸末期から明治に外国から渡来したものに「朝鮮○○」と名付けられることがあったためで、朝鮮とはゆかりがないらしい。
原産地が朝鮮半島ではないのに、チョウセンなんとかという名前がついているものには、熱帯アジアあるいはインド原産のチョウセンアサガオがある。あの華岡青洲が麻酔薬「通仙散」の材料にしたやつ、和名・曼陀羅華である。それと同じようなもんですわな。関係ないけど、チョウセンアサガオには、その神経毒性から「キチガイナスビ」という放送禁止用語みたいな名称もある。ちなみに、アーティチョークは地中海沿岸が原産で、古代ギリシャ・ローマ時代から食べられていたそうな。しかし、なんでこないに面倒なものをと思ってしまう。
コーラビ、あるいはコールラビも日本では珍しい。知名度としてはアーティチョークよりも低くて、見たことも聞いたこともない人が多いかもしらん。これもドイツ時代想い出の野菜で、ご当地ではごく普通に食べられる野菜である。英語名は kohlrabi だが、これはドイツ語の Kohlrabi に由来する。Kohl はキャベツ、Rabi はカブの意味なので、どっちやねん! と言いたくなる。が、アブラナ科アブラナ属で、キャベツの仲間だ。いや、仲間どころではなくて、共に同じ種Brassica oleraceaである。
元々は地中海沿岸の野生キャベツに由来するのだが、なんと、キャベツだけではなくて、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツも同じ種とは驚くしかない。よく、セントバーナードからチワワまで、あれだけ大きさと見かけが違うのに同じ種で、とかいうけど、キャベツ一族の多様性はそれどころではない。元来、自然変異が豊富だった野生キャベツが品種改良されていった結果だという。
葉が大きくなって丸くなったのがキャベツ、花蕾の巨大になったやつがブロッコリーとカリフラワー、わき芽が肥大化したものが芽キャベツ、そして、茎がボール状に肥大化したものがコーラビである。

同じ種ということは、ゲノムは当然ほとんど同じで、交配も可能である。キャベツ一族の違いは、ごくわずかな形態形成関連遺伝子やホルモン応答遺伝子の違いにすぎないと考えられている。コーラビの茎を肥大化させる候補遺伝子はいくつかあって、おそらく単一の遺伝子ではなくて複数の遺伝子によるらしい。でも、ホンマにすごいなぁ。どう見てもキャベツちゃうし。
春と秋の2回種蒔きが可能だし、例によってあまり大きくはならないが、仲野家菜園でもそこそこのものは採れる。生でサラダにしてよし、煮ても焼いてもよし、味もよろしい。しかし、何故か日本では普及していない。ちょっとキャベツがかった風味のカブみたいな感じなので、カブで十分といったところなのだろう。わざわざ導入するほどのメリットがなかったし、これからもないやろうなぁ。
キャベツ、レタス、白菜。結球までの100年の歩み
キャベツ、ブロッコリー、カリフラワーも栽培したことがあるけれど、どうもうまく育たない。キャベツはほとんど結球してくれなくて、戦績は1勝18敗1引き分けくらい。植えつけにけっこう場所をとるので、効率の面から栽培はギブアップした。できたところで、味は市販のものとたいしてかわらんかったし。
ブロッコリー、カリフラワーも同じく、うまい具合に玉になってくれない。土がキャベツ類に適していないような気がせんでもないのだが、コーラビは善戦している。
結球といえば、白菜もほとんど結球してくれない。家庭菜園をしている人とキャベツや白菜の話になると、うまく結球しないという嘆きになることが多い。なんか、コツがあるんかしらん。調べてみても、日当たり、肥料、害虫といった当たり前のことしか書かれてない。そういえば、レタスも結球してくれんなぁ。ということで、結球系の野菜はほぼ完全にあきらめている。
普通に目にするから当たり前に思うけれど、結球って不思議ですわな。キャベツ、白菜、レタスは結球という共通項があるけれど、種が違う。レタスなんぞは属のレベルで違う。なので、それぞれが別々に進化した、というか人為選択で「平行進化」させたものなのである。いずれも、葉の曲がり具合を制御する遺伝子などが関与していることがわかっている。
そんなことをまったく知らずに結球を目指して育種したって、けっこうすごくないですかね。軽く内巻きになったキャベツとかの原種を見て、おもろいやないか、もっと巻け巻けとか思ったんでしょうな。内巻きが進むにつれて、面積あたりの葉の量が増える、内側の葉が柔らかくて甘くなる、外側の葉が内側の葉を守ってくれる、とかいうことに気がついて、結球意欲を高めていったに違いない。
結球の育種にかかった期間は正確にはわからない。ただ、文献的な記録からいくと、半結球から結球までで100年くらいはかかったのではないかとされている。親子とかご近所さんで、もっと巻かんかなぁと何代かにわたって頑張って作られたと考えると、結球せんで腹立つわ、ケッ! とか思ったらバチあたるかも。
知的菜産の技術
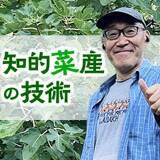
大阪大学医学部を定年退官して隠居の道に入った仲野教授が、毎日、ワクワク興奮しています。秘密は家庭菜園。いったい家庭菜園の何がそんなに? 家庭菜園をやっている人、始めたい人、家庭菜園どうでもいい人、定年後の生き方を考えている人に贈る、おもろくて役に立つエッセイです。
- バックナンバー
-
- 家庭菜園で育てに育てた55種類。人生まで...
- アスパラは絶品、キャベツは1勝18敗。家...
- えっ、僕たちもう食べられちゃうの? キュ...
- 驚きの事実が次々と。トマト、ナス、ピーマ...
- ソラマメ、エンドウ、枝豆。自家菜園のお豆...
- 大葉、ミョウガ、ショウガ、ネギ。和風ハー...
- スカボロフェア4人娘からカメムシソウまで...
- トマト、タマネギ、バジル。イタリアすき焼...
- ジャガイモvs.トウモロコシ、味・収穫で...
- 「連作障害」どないする? ChatGPT...
- 家庭菜園で野菜を作るのは果たしてお得なん...
- いざ収穫! 生来の野菜嫌いも野菜好きに。...
- アブラムシ・カメムシと格闘するも、仲野家...
- 水やり、草取り、マルチ張り。菜園はちっこ...
- 苗を間引いたり移植したりしながら、劣化し...
- ミレーと権兵衛に教えてあげたい、本当の種...
- 開墾終わって次は「畝(うね)立て」。労力...
- 荒れ放題、ミニジャングルと化していた畑を...
- まずは土作り?? どないしたらええねん
- 楽しい! 健康的! 知的刺激! 定年退職...
- もっと見る















