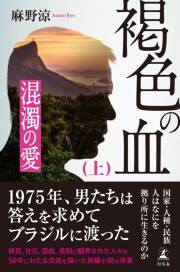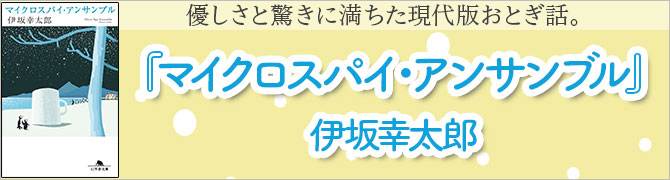ブラジル移住に光を見出した児玉だったが、同じく移住する小宮にブラジルのある一面を聞く。児玉にとって移住は希望の光なのか。
『死の臓器』がドラマ化され、高橋幸春の名義でも潮ノンフィクション賞、講談社ノンフィクション賞を受賞した作家・麻野涼さんによる長編小説『褐色の血』。
その序章にあたる『褐色の血(上) 混濁の愛』の発売を記念して全5回にわたって冒頭を特別公開します。(#1から読む)
* * *
「児玉さん、起きて下さい」
小宮の声で児玉は目を覚ました。
「もうすぐロサンゼルスに着きますよ」
児玉は座席から体を起こすと、機体は降下を開始していた。
「それにしても熟睡されていましたね。海外旅行は初めてだし、日本ともしばらくはお別れだと思うと、僕らは興奮してほとんど眠ることはできなかった」
「仕事がたまっていて、その処理に最後の十日間は追われっぱなしだったから、疲れていたんだよ」
児玉が眠そうな目をこすりながら言った。疲労が蓄積していたのも事実だが、美子のことを考えると酒を飲まずにはいられなかった。いつ寝たのかもわからないほど児玉は泥酔していた。
やがて日航機はロサンゼルス空港に着陸した。七人の移民は国際協力事業団の引率員に案内されて空港近くのホテルにチェックインした。現地時間ではまだ明け方で、ヴァリング・ブラジル航空の出発時間までは十時間以上あった。それまではホテルで休むことができた。他の移民は観光を兼ねてダウンタウンへ繰り出していったが、児玉はひたすら眠るだけだった。
夕方、目を覚まし移民たちは再び空港に戻り、ブラジル航空の搭乗手続きを済ませた。機内には日本人の乗客は彼らだけでブラジル人乗客が多かった。彼らはアメリカ観光を楽しんで帰国するのか、食事が出された後も大声で話したり笑ったり、隣に寝ている客がいても遠慮する様子などなかった。
「ブラジル人は何事にもおおらかとは聞いていましたが、エチケットも何もあったものではありませんね」
小宮は他の移民と打ち溶けることができないのか、しきりに児玉に話しかけてきた。
「そうだね、本当にうるさい連中だ。でも、ブラジルで暮らすにはこれに慣れるしかないんだろうね」
児玉もブラジル人の賑やかさに閉口した。しかし、二人ともホテルで十分に睡眠を取ったせいか、それほど気にはならなかった。ブラジル人は、だれもがよく食べ、よく飲んで、話し、笑い声が響き渡っていた。児玉も小宮も、楽しそうにしているブラジル人の輪の中に加わりたい衝動にかられた。
そんな二人に気づいたのか、ブラジル人の男性が話しかけてきた。
「オンジ・ヴォッセ……ヴァイ?(どこに行くんだい)」
「パラ・サンパウロ」
答えたのは小宮だった。
「ヴォッセ・インテンジ・ポルトゲース?(ポルトガル語を話せるのか)」
「ウン・ポッキーニョ(少しだけさ)」
「ヴォッセ・エ・ツーリスタ?(旅行者か)」
「ノン、ソウ・イミグランテ・ジャポネース(いや、日本人移民さ)」
「イミグランテ!」
男は大袈裟に驚いて見せた。
「ヴォッセ・ゴスタ・ド・ブラジル?(ブラジルが好きか)」
「クラーロ(もちろん)」
ブラジル人は「ちょっと待ってろ」と小宮に言い残して、自分の仲間のところに戻っていった。男は大袈裟なジェスチャーを交えながら、日本からブラジルに移住する小宮のことを報告しているようだった。
児玉は小宮の語学力に呆気にとられていた。児玉はまったくポルトガル語が話せない。会話の本さえ一度も開いたことがなかった。サンパウロで生活している間に、自然に話せるようになるだろうと、たかをくくっていた。新聞社も邦字紙であり、日本語の記事を書くだけだ。語学力が必要だとは思ってもいなかった。しかし、ブラジル人と楽しそうに話す小宮に、自分だけが置いてきぼりにされたような不安を感じた。
「すごいね。あんなに上手に話せるなんて」
「でも初めてなんです。ブラジル人と会話をするのは」
「なおさらすごいじゃないか」
「自信が湧いてきました」
小宮は嬉しそうに笑った。小宮はほとんど独学でポルトガル語をマスターしたという。
「私はまだ何も勉強していない。ブラジルに行ってから勉強すればいいと思っていたんだ。すべてはサンパウロに着いてからだ」
「そうですよ。すべてがサンパウロから始まるんです」小宮が興奮ぎみに言った。

「児玉さん、ロナルド・ビッグズのこと知っていますか」
「あの有名なイギリスの列車強盗のことかい」
「さすがジャーナリストですね。よくご存じだ」
「ロナルド・ビッグズがどうかしたんですか」
「僕はロナルド・ビッグズにブラジルの良さが象徴されていると思っているんです」
「どういう意味ですか……」
「彼は列車強盗で大金を強奪しましたが、人は殺していない。ヨーロッパ中を逃げ回り、そしてオーストラリアまで逃亡しましたが、整形手術はパリで受けたようです。イギリス警察の追跡は執拗で、その追及をかわすためにブラジルに逃げ込んだんです」
「でもイギリス警察はブラジルに潜んでいるロナルド・ビッグズを見つけ出し、引き渡すよう要求したはずだが」
「その通りです。しかし、その後の対応がいかにもブラジル人らしいんです」
イギリス政府の国際的な圧力に、ブラジル政府も犯人引き渡しを約束し、国外追放の決定を下さざるを得なかった。ただ国外追放は一年以内にという条件が付いていた。
「この一年というのが曲者だったんです」
児玉は小宮の熱い口調にいつの間にか引き込まれていた。
「彼には当時、愛人がいて、その愛人との間に子供をもうけたんです。そうしたら、ブラジル政府はいったい何をしたと思いますか」
「いや、わからんね」
「ブラジルは出生地主義を取っているんです。観光客であろうと、移民の子であろうと、あるいは密入国者の子供であっても、ブラジルで生まれた子供はすべてブラジルの国籍を取得することができます。ましてブラジル人女性の子供です。ロナルド・ビッグズの子供もブラジル人になります」
「それで」
「ブラジル政府は子供の誕生と同時に国外追放処分の決定を覆してしまったんです。ブラジル政府は父親と子供の仲を引き裂く非人道的な決定を行使することはできないという理由で」
「ロナルド・ビッグズはリオで優雅な生活をしていると聞いているが、そんなことがあったんですか。いつか機会があれば取材してみたいものだ。でも、小宮さんは何故、それがブラジルの良さだと思うんですか」
「移住するということは、ゼロからの出発が可能になるということだと思うんです。画家が真っ白なキャンバスに絵を描くのと同じだと思います。過去を問われない。一切の過去と決別できる。それが移住の最大の魅力だと思っています」
「新たなスタートということは言えるだろうが、過去と決別するなんてだれにもできないと思うけど」
「いいえ、決別して見せます。僕はそのために移住するんです」
「だって日本には君を育ててくれた両親もいれば、兄弟だっているでしょう。その絆を断ち切るわけにはいかないだろう」
「いえ、日本にあるすべてのしがらみを断ち切って移住するんです。僕が移住することを友人はもちろん、家族も知りません。一切の過去を断ち切るためにはそれくらいの覚悟が必要なんです」
小宮は怒っているようでもあり、今にも泣き出しそうな表情だった。児玉は日本を離れる時のことを思い出していた。小宮は見送り客もなくたった一人で空港の夜景を見つめていた。小宮の過去にいったい何があったのだろうか。児玉はそれ以上立ち入るのを躊躇った。躊躇わせる雰囲気を小宮は滲ませていた。聞けば小宮は答えたかもしれないが、聞いてはいけないような気がしたのだ。
小宮も急に寡黙になった。児玉はスチュワーデスを呼んだ。
「通訳してよ。ワインが飲みたいんだ」児玉が言った。
小宮の表情が以前の柔和なものに戻った。児玉はポルトガル語会話の勉強方法やブラジルの社会事情などを小宮から聞いた。
「ブラジルは人種の坩堝と言われています。ポルトガルの植民地となり、先住民のインディオやアフリカから連れてこられた六百万人の奴隷、一説には百ヶ国以上の移民がブラジルには入国しているとさえ言われていますが、その移民が混血し、現在のブラジル国民を形成しているんです」
小宮はブラジル関係の本をかなり読んでいた。
「ブラジルで一番美しい女性の肌の色は何色だと思いますか」
「いや、わからんよ。私が知っているハーフは、ゴールデン・ハーフくらいなものだからな」児玉が冗談交じりに言った。
ゴールデン・ハーフはハーフの女性アイドルグループで、テレビでは売れっ子のだった。
「ゴールデン・ハーフももちろんいいですが、ブラジルではモレーナと呼ばれる女性がカーニバルでももてはやされるんです」
「そのモレーナというのは何ですか」
「茶褐色の肌をした女性のことです。白人、黒人、黄色人種が何代にも亘って混血した結果、生み出された肌の色なんです。それがブラジルでは最も美しいとされているんです」
「早く、そのモレーナにお目にかかりたいものだね」
「児玉さんもそう思いますか。ブラジル人は人種なんてくだらないもので人間を差別しないんです。モレーナの肌の色はその証明とも言えるんです」
小宮は熱い口調でサンパウロに着くまでブラジルについて語り通しだった。話を聞きながら、本当にそうなのだろうかと児玉は思った。
(#5へ続く)
褐色の血の記事をもっと読む
褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」
1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。
児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。
一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。
国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。
差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。