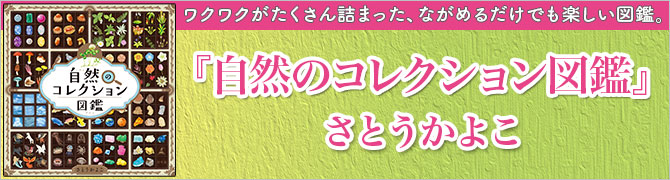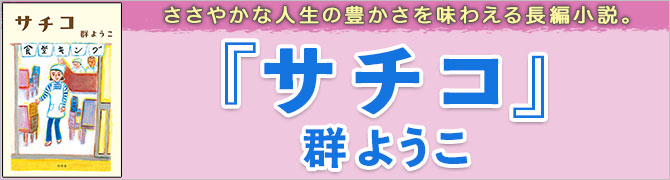世界経済には日本人が見落としがちな「死角」が存在する。それを押さえずして、為替、物価、賃金その他、私たちの生活に直結する経済問題の見通しを立てることはできない――超人気エコノミストの2人が、世界経済と金融の盲点についてあらゆる角度から徹底的に議論し、たちまち重版となった『世界経済の死角』から序章をお届けします。

未来に展望を持ちづらいからこそ、知っておくべきこと
河野 海外から日本を訪れる人たちにとって、今、日本は実に「ワンダフルな国」です。質のよいモノやサービスを非常に安く買うことができますから。
唐鎌 2024年にはカナダ企業がセブン&アイ・ホールディングスに買収提案を仕掛けたことが話題になりました。海外の企業や投資家が日本企業に買収を仕掛けるといったニュースも、心なしか増えてきたようにも感じますね。海外の人たちにとってお買い得なのは、観光時のモノやサービスだけでなく、投資先としての企業も同じということですね。
河野 その通りです。しかし、日本で暮らしている私たちからすると、「この国の経済は素晴らしい」とはなかなか思えません。賃金はなかなか上がらないのに、食料品やガソリンだけでなく、様々なモノやサービスの値段はどんどん上がっていく。ここ数年、賃上げが進んでいるといっても、物価上昇に追いつかず、実質賃金(受け取った賃金から物価変動の影響を取り除いたもの)は足踏みしています。
働いても暮らしがよくなる実感がない一方で、株価や住宅価格だけが上昇している……。こうした状況に、違和感を覚える人も多いはずです。
唐鎌 そもそも、人々は「株価が上がる=経済全体がよくなっている」と思いがちですが、そうとも言い切れない部分が大きいのは否めませんよね。
2024年以降はっきり目にしたように、株価が上昇しても、それが直接私たちの暮らしの豊かさにつながるとは限らないばかりか、体感する貧しさは酷(ひど)くなったとすら言われています。
2022年以降に株価が上昇した要因は、大企業、特に輸出製造業を中心として、円安に駆動されて海外収益が伸びているという事実でした。しかし、それと日本人の暮らし向きは、決して相関関係にはありません。
河野 その通りです。大事なことは、海外で儲(もう)かっている影響が大きいとはいえ、日本企業がそれなりに高い利益を上げているのに、なぜ私たちの暮らしが一向によくならないのかという点です。つまり、日本で働く人々の実質賃金がなぜ上がらないのかという問題です。
唐鎌 経済的な暮らしやすさは、単に賃金が高いか低いかだけで決まるものではないということですね。景気実感はあくまで「賃金の水準」と「モノやサービスの値段」との相対的な関係で決まるものであり、それを端的に判断するための材料が実質賃金ということですよね。
2022年以降、食料品やガソリンをはじめ、身の回りの物価がどんどん上がっています。海外から日本へやってくる人たちから見れば、円安を背景として日本のモノやサービスにはずいぶん割安感が生じている状況です。しかし、日本人にとっては、海外から仕入れるモノやサービスの割高感がすさまじいスピードで増している状況です。
河野 日本人が見た日本と、外国人が見た日本との間にあるギャップが話題になると、とりあえず「円安のせい」というシンプルな解説で片づけようとする風潮がありますね。
唐鎌 2022年以降、日本国内で起きている物価上昇や日本人が海外で覚える割高感の原因を円安に求める解説は、完全に間違いとは言えません。ですが、完全に正しいとも言い切れないと思います。
現在の日本の経済状況には、円安以外にも様々な要因が絡んでおり、円安はその一部にすぎないと私は考えています。この点については、河野さんとの対談の中でも詳しく取り上げたいと思っています。
日本人が海外で覚える「割高感」について「円安のせい」とは言い切れないと述べるとき、私は次のような説明をよくしています。
たとえば出張時、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港で600mlの水が3・6ドルくらいで売られているのを見かけました。1ドル150円換算で540円です。多くのメディアはこの事実を「円安の副作用」としてクローズアップするでしょう。
しかし、これは仮に1ドル80円換算でも290円弱ということになります。ブランドにもよるのでしょうが、日本ならほとんどの場合、600mlの水は150円未満で購入できるのではないでしょうか。つまり、円安の影響だけで内外価格差を説明するのは無理があるということだと思います。
たしかに円安によって輸入品の価格が上がり、割高に感じる部分はあります。しかし、それは本質的な理由ではなく、そもそも商品の「値札」が海外のほうが高いという事実に気づくべきだと思います。
「値札」の違いはどこから来るのか。おそらく「賃金の違い」に起因するはずです。
河野 むしろ、為替の変動で説明できない残りの部分について、いったい何が起きているのかに、もっとスポットライトが当てられるべきですよね。
唐鎌 同感です。
河野 私たちの暮らしが豊かにならないのは、特定の誰かが悪いという話ではありません。
私は、2010年代に入る頃から、「バッド・ラック(不運)」、「バッド・ポリシー(まずい政策)」、「バッド・マネジメント(よくない企業経営)」という3つの要因が複合的に重なった結果だと考えてきました。
まず1つ目ですが、不運なことに、過去30年、日本経済に繰り返し危機が訪れました。1997年の金融危機は不良債権問題を先送りしてきた結果で自業自得とも言えますが、その後、2000年のドットコム・バブルの崩壊や、2007年以降のサブプライム・バブルの崩壊といった国際的な危機の巻き添えを食らいました。
2011年には東日本大震災が起こり、2020年にはコロナ禍の到来といった具合に、100年に一度、あるいは、1000年に一度といわれるような危機が数年おきに訪れました。そして今回は、まさに「トランプ関税ショック」でしょうか。
実は、それだけではなく、世界経済が回復している間も、日本が輸入する原油などの資源価格の上昇が続き、そのことも日本の実質所得の改善を遅らせる要因になっていました。
2つ目は、そうした繰り返し訪れた危機に対して、政府の政策の舵(かじ)取りが、あまりうまくなかったことです。グローバル経済の構造変化に対しては、そもそも認識が甘かったため、政府は完全に無策だったと思われます。これが「バッド・ポリシー(まずい政策)」です。
さらに3つ目について、対談の中でも詳しくお話ししていきたいと思いますが、多くの大企業の経営判断も的確とは決して言えませんでした。それが「バッド・マネジメント(よくない企業経営)」です。
これらが互いに影響し合った結果、私たちの賃金がまったく上がらない状況が続いてきました。最近になってようやく賃金が上がり始めているとはいえ、いまだに物価上昇には追いついていません。そのため、実質賃金はむしろ下がっており、これまでと同じような生活を維持することさえ厳しくなっているのが現状です。
唐鎌 「生活が苦しくなった」という声は、本当によく耳にするようになりました。しかし、日本人は何も怠(なま)けていたわけではないと思います。それなのに、なぜ一生懸命働いても暮らしが豊かになっていかないのか。
具体的には、日本企業は生産性の向上に力を入れてきたはずなのに、なぜ働く人々の賃金はずっと伸び悩んでいるのか。そして、激しく揺れ動く世界情勢や、生成AIの急速な進展といったグローバルな変化が、日本経済にどのような影響を及ぼしているのか。今、世界経済の構造の中で見落とされがちな“死角”を直視することが求められている気がします。
これらのテーマについて、エコノミストの世界の大先輩であり、読書家としても知られ、膨大なインプットとアウトプットを続けてこられた河野さんの意見を伺いながら、時が経っても腐らない、実のある議論ができればと思っています。
河野 私も為替や海外情勢、特にヨーロッパの政治・経済の専門家である唐鎌さんにお聞きしたいことがたくさんあり、今回の対談を楽しみにしていました。どうぞよろしくお願いします。
世界経済の死角の記事をもっと読む
世界経済の死角
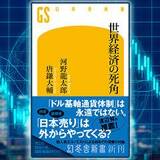
新NISAの導入をきっかけに海外の金融資産を保有する日本人が増加するなど、日本経済はかつてないほど世界経済への依存度を高めつつある。そうした中、トランプ大統領による相互関税措置を受け、国際金融市場は大きく揺れ動いている。しかし、そもそも世界経済には、日本人が見落としがちな「死角」がいくつも存在する。それらを押さえずして先の見通しを立てることはできない。そこで本書では超人気エコノミストの2人が世界経済と金融の“盲点”について、あらゆる角度から徹底的に対論する。先の見えない時代を生き抜くための最強の経済・金融論。
- バックナンバー