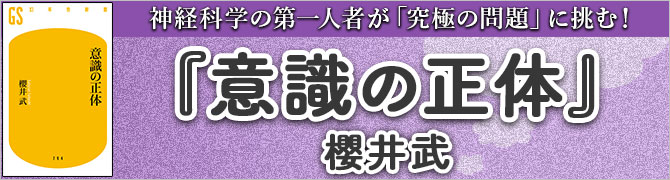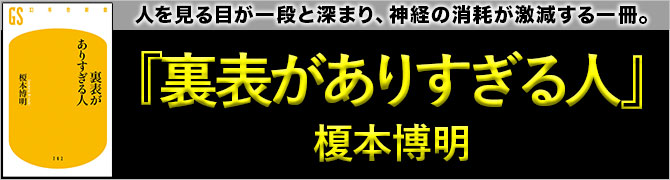「私が男のふりをして、男子寮で暮らすんですか!?」
『このミス』大賞(『元彼の遺言状』)、山本周五郎賞(『女の国会』)受賞作家・新川帆立の最新作は、恋と魔法の学園ファンタジー『魔法律学校の麗人執事』!
12月24日『魔法律学校の麗人執事3 シーサイド・アドベンチャー』の発売を記念して、プロローグ全文公開を再掲いたします。
* * *
魔法律学校――その名の通り、魔法と法律の学び舎である。
悪魔と契約すると、魔法の力を得られる。
狡猾な悪魔と安全に契約を交わす法技術、それが「魔法律」である。
日本全国に五百余を数える魔法律学校では、若き魔法律家の卵たち――己の才能の限界を未だ知らず、人生の春を謳歌する者たち――が切磋琢磨しながら勉学に励んでいる。
西洋諸国への憧憬を胸に、我が国の先人らが連綿と積みあげた魔法律研究の成果は、いまや世界最高の水準に達していた。
その頂点、最高峰の学び舎として名高いのが「帝桜学園 高等部 魔法律学科」である。
誰しもが一度は憧れ、いつしかそっとあきらめて、その後の人生をよりよく生きるために、幼き日の憧れ自体を忘れようとする――それが「学園」だ。
学園はどの時代においても、希望と絶望、栄光と挫折、勝者と敗者を生み出してきた。
強い光のもとに濃い闇が生まれ、光と闇は対一体となって、世界が終わりを迎える日まで、摩訶不思議な舞踏を続けるだろう。
二十一世紀も四分の一が過ぎた頃、二人の若者が学園の門をくぐった。
“皇帝の眼”を持つ魔法の天才、条ヶ崎マリス。
そして執事、野々宮椿。
一方は、世界を支配する帝王となるべく育てられた御曹司である。
他方は、名もなき女子修道院で育った孤児だった。
何もかも正反対な二人が出会い、主従関係を結ぶことで、この物語は始まる。
野々宮椿は自らを男と偽り、男装したうえで、条ヶ崎マリスに仕えたという。
彼らが経験した風変わりな物語は、高度な記憶抽出魔法により、永年魔法博物館に保管されている。
本書でひもとくのは、彼らの輝かしい青春の日々の、ほんの一部だ。
後に続く若人の一助となり、愛と平和で満ちた世界の礎とならんことを。
魔法律家に光あれ!
プロローグ 修道院にて語る者
みんな今日まで、どうもありがとう。
そこ、喧嘩しない。女子修道院のみんなはファミリーなんだから。
働かざるもの食うべからず、ってことで。お姉ちゃんは明日修道院を出て、働き始めるけど、これからもみんな仲良く暮らすんだよ。
えっ、また怖い話をしてほしいの? まあいいけどさ。せっかくだから最後に、とっておきの怖い話をしてあげよう。
準備はいい?
あれはそうね、今から三カ月くらい前、クリスマスの夜だった。
お姉ちゃんは男の子といたの。
いや、そんなんじゃない。実に健全なものよ。だって私まだ、中学三年生、十五歳なんだし。いかがわしいことをするわけないでしょ?
クラスメイトが開いたホームパーティに呼ばれただけだよ。
主催者の男の子は、かなり広いマンションに一人で住んでいたの。両親が海外赴任してるんだって。一人でクリスマスを過ごすのもなんだし、みんなで集まって騒ごうってわけ。
で、あの日、私が何時に出かけていったか、覚えてる?
そう、朝の七時。
おかしいよね? おかしいと気づくべきだった。クリスマスパーティは夜から始まるのにね。
主催者の男の子――面倒だからもう本名で言っちゃう。本田君っていうんだけど。
本田君に「できれば朝からきてほしい」って言われていたんだ。真に受けて家に行ったら、呼びつけた当の本田君は寝間着姿で出てきて、こう言ったの。
「おう、野々宮。本当にきてくれたんだ。今夜はパーティだしさ、まずは家の掃除を頼むわ」
玄関から部屋の中を見ると、そりゃあもう、ひどい状態だった。
服は脱いだまま放ってあるし、マンガや雑誌が散乱しているし。足の踏み場もない状態ってやつ。テーブルの上には、カップ焼きそばの殻とか、ペットボトルとか、ぎっしり。においもひどいわけ。
よく友達を呼ぼうと思ったなあって感じ。
そうなるとお姉ちゃん、もううずうずして仕方ない性分だからさ。
しかも本田君って結構イケメンなわけ。何度か一緒に帰ったことがあって、なんかいい感じだなーって思ってたの。だから悪くないかなあっていうか。好きなほうっていうか。
いや、正直に言うわ。
結構好きだったわけ。いや、かなり好きだった。
ハハハ、今となってはどうでもいいんだけど。
気になる彼に頼られたと思って頑張ったの。もともと掃除は得意だし。いいところを見せようと思って。ものすごい勢いで掃除した。リビングルームをピカピカにしたあと、キッチン、ダイニングルーム、トイレとお風呂、そしてなぜか本田君の部屋と、本田君のお父さんの書斎、お母さんの趣味のドールハウスが置いてある部屋まで掃除した。もちろんドールハウスの中も綺麗にした。
家が丸ごと生まれ変わったようなものだよ。プロに頼んでもこれほどの仕上がりにはならないだろうってくらい。
でもまだ昼の十二時なんだ。お姉ちゃん、超優秀でしょ?
まあほら、修道院の大掃除もお姉ちゃんがしたよね。財政難でシスターさんも減っちゃって。
業者になんて頼めないし。だから私、掃除は慣れているわけ。めっちゃいいお嫁さんになれそうじゃん? そう思うよね?
本田君もさすがに感心するだろうなーなんてニヤニヤしながら「終わったよ」って声をかけたら、彼はなんと、リビングルームでテレビゲームをしていた。
私が話しかけても「ああ、サンキュ」って返すだけ。
「てか、俺、腹減ったんだけど」って言うから、冷蔵庫の中を見て、余っている素材でパパッと作ってあげた。和風パスタ。
「パスタかよー。手抜き?」って本田君、最初は言っていたけど、食べてみると「うわ、うまいわ。すげえな、お前」って目を丸くした。
ま、これも当然よね。修道院でみんなのご飯、毎日作ってるし。
そしたら本田君、急にこう言い出したの。
「てかさ、今夜はパーティだしさ、みんなの分のメシ、テキトーに作っといてくんない?」
いやいやいや、さすがにないよね。だってクラスメイトは十五人くらいくるんだよ。しかもクリスマスなんだもん。ご馳走じゃなくちゃ。無理無理って、普通思うじゃん? そこで無理と思わないのがお姉ちゃんなんだなあ。残念ながら。
近くのスーパーに全速力で走ったよ。
知ってると思うけど、私、スポーツテストで全国一位なんだよね。特に短距離走はやばいくらい速いから。そこらの男子はゴボウ抜きだからね。
一瞬でスーパーについたわ。
かごを手に取ると、七面鳥とかシャンメリーとか、クリスマスっぽいものを片っ端から入れていった。
そのときハッと気づいた。本田君からお金もらってないなって。
本田君にお金ちょうだいって言うか、迷ったよ。でもそれってなんだかダサい気もしたんだ。
財布を見たら、家庭教師のアルバイトで稼いだお金が少しだけ残っていた。
ほら、お姉ちゃん、全国模試で一位だからさ。
近所の奥様方に頼まれて、子供たちに勉強を教えているから。普通の中学生よりはお金があるんだよ。だからかな。仕方ないなあ、お金を出してやるかって思ったの。そしたら本田君、喜ぶかなあって。
家事もできてお金も稼げる女って、お嫁さんとして最高じゃない? アピールになるかなって下心もあった。
やりすぎだってのは分かってる。
でもさ、私、筋肉質だし、身長が高いし、ちょっと男っぽいっていうか。可愛い格好が似合わないから。何もせずにいたら、女として扱われるか不安なわけよ。
せめてもの女らしさをと思って、あの頃は髪を伸ばしていたから、男の子とは間違われないけど……いや、そういえば男の子と間違われたこともあったわ。
私、毎朝ランニングしてるんだ。知らない? いや筋トレの前だよ。毎朝五時から走ってるの。
そのあと筋トレ、巻藁突き、棒術、木刀素振り、キックの練習、縄跳びを二千回してから朝ご飯を作ってるんだよ。
何のために鍛えてるのかって? みんなを守るために決まってるじゃん。
このあたりは治安が悪いから。修道院も泥棒によく狙われてるんだよ。隙あらば忍び込んでくる泥棒たちを日々撃退してるの。毎日戦っているうちに、だいぶ強くなったわ。今では大抵の男には負けない、ちょっとしたストリートファイターだよ、ハハハ。
って、何の話だっけ。そうそう、朝のランニングをしていたときのこと。
あの日も着古したジャージを着て、髪をしばって帽子の中に入れて、走ってたの。そしたらちょうど、引ったくりと遭遇して。
お姉ちゃんの近くをよたよた歩いていた白髪のおばあちゃんが「あの人を捕まえて!」って、前を走る原チャリを指さした。そもそも、なんでおばあちゃんが朝早くから出歩いているのって不思議に思ったんだけど。お年寄りってのは朝に強いんだろうね。
おばあちゃんはものすごい力で私の腕をつかんで、「お兄さん、助けて。鞄を盗られた。あの人を捕まえて」って言った。おばあちゃんが左手の小指に着けていたゴールドの指輪が私の腕に食い込んで痛かった。
「あの引ったくりを捕まえてよ。大事なものが入っている鞄なんだよ。お兄さん」
「えっ、お兄さん?」って声がひっくり返っちゃった。でもほら、私は声も低いから。しかもおばあちゃん、耳が遠いんだろうね。ずっと「お兄さん、お兄さん」って言い続けていた。
とりあえず私は走った。原チャリくらいなら余裕で追いつけるから。並走しながら「おい、止まれ!」って叫んだんだけど、原チャリは逃げようとするばかり。仕方ないから、わざと大げさな動きでひじ打ちを繰り出して、運転手がよけようとしてバランスを崩したところを引きずりおろしたよ。それで、ベロアの可愛い巾着鞄を取り戻したの。
気づいたときには、近くにおばあちゃんがいてびっくりした。結構走ったのに、どうやって追いついたんだろうと思ってね。
鞄をおばあちゃんに返して、引ったくり犯を振り返ったら、やつはもう逃げ出していた。犯人をとり逃したのは惜しかったね。原チャリから引きずりおろした瞬間、耳下に手刀を入れて気絶させておくべきだった。
アハハ、お姉ちゃん、おっちょこちょいだよねえ。
おばあちゃんには泣いて感謝されたよ。「お兄さん、ありがとう。イケメンだねェ」って拝まれながら。イケメンだってさ。ぶっちゃけよく言われるけど。本当は私だって、可愛いとか、綺麗とか言われたいよ。
で、クリスマスパーティの話に戻るけど。
お姉ちゃんにはバイト代があるとはいえ、みんなにお菓子を買ってあげたり、おもちゃを買ってあげたりしていた。それにここ最近、修道院は資金不足で、本当に潰れそうだったのよ。焼け石に水だと分かってるけど、バイト代から修道院にも少しお金を入れてるんだ。財布にあんまり余裕はなかった。
七面鳥とシャンメリーはいいとしても、それ以外の出来合いのものを十五人分も買うなんてまず無理。だから小麦粉とか砂糖とか材料だけたくさん買って、ピザとかケーキとか、せっせと焼いたの。
午後七時、クリスマスパーティは盛大に始まった。当然よ、お姉ちゃんが準備したんだから完璧に決まってるじゃん。本田君もすごく嬉しそうだった。彼の顔を潰すといけないから、私が全部やったってのは内緒にしておいてあげた。
無事クリスマスパーティが終わって、帰ろうとしたら本田君が耳打ちしたの。「ちょっと残ってよ」って。
うわきた! って思うでしょ。告白タイムだよ。
だってどう考えてもそうでしょ?
クリスマスの夜だよ。みんなと一緒に遊んで、そのあと二人きり。十五歳の男の子と女の子を密室に入れておくわけだよ。告白じゃなきゃ何って感じだよ。
心臓がものすごくバクバクした。
だってこれまで男の子といい感じになったこと、なかったんだもん。本当だって。女友達は多いけど、なんか男ウケしないの。
ちなみに、本田君のマンションからは東京タワーとスカイツリーが一度に見えるから。めっちゃいい感じのシチュエーションだった。二人で向かい合ってシーンとしていて。
そしたら外で雪が降り出したんだ。
「ホワイトクリスマスだね」って言うと、本田君は「ああ、うん」って気のない返事だった。緊張してるのかなって思った。
その瞬間、「あっそうだ、私から言おう」って思ったんだよね。
人間ってさ、告白するより、告白されるほうが嬉しくない? だから私から告白しようって思ったの。変かな。でもさ、私は人が喜ぶことをしてあげたいんだよね。
「私、本田君のことが好き。付き合わない?」って言ったよ。
ド直球だよね。ハハハ。でもいいじゃん、直球。「君が作る味噌汁を毎日飲みたい」とかさ「朝起きたときに君に隣にいてほしい」とかさ、そういう男の自己満足みたいな告白、あれ女子的に微妙じゃん。
やっぱり気持ちってのは、まっすぐ伝えてナンボだと思うわけ。
そしたら本田君、すっごい嫌そうな顔して言った。
「無理。俺、お前のこと、女として見られない」
せきええー、マジ? って思った。本当、ガビーンって感じだった。あ、古い? でも本当に、隕石が落ちてきて頭にぶつかったような衝撃だったの。
「え、じゃあ、さっき『ちょっと残ってよ』って言ったのは、何だったの?」
思わず訊いたね。本田君は気まずそうに答えた。
「いや。部屋の片付けしてもらおうかと思って」
部屋を見回すと、確かに散らかっていた。クラスのみんなが空けた皿とかコップがそのままになっていた。
なるほどー、これを片付けてほしかったのかーって、妙に納得してしまった。
もちろん片付けたよ。本田君が一人で片付けるには大変な量だと思ったし。まあ、私が片付けているあいだ、本田君はリビングルームでゴロゴロしながら、クラスメイトの美咲ちゃんと電話してたけどね。
美咲ちゃんと初詣に行くんだって。
なるほどねーって思ったよ。美咲ちゃん、すっごく可愛い女の子だから。サラサラのロングヘアでさ、色白で、華奢で。小動物系? 守ってあげたくなる感じっていうの?
そんなことを考えながらも手はテキパキ動いた。一時間もしないうちに部屋は綺麗になりました。めでたし、めでたし。
「じゃ、帰るから」と声をかけてから玄関に向かうと、本田君が慌てたように追ってきた。
両手を顔の前で合わせて「野々宮、サンキュ」って言った。
「別にいいけど」って低い声で返すと、本田君は目をぎゅっとつぶって、こう言った。
「野々宮には感謝してる。ってか、すごいやつだなって尊敬もしてる。でも、告白はごめんな。どうしても女に見えないんだよ。いや悪い意味じゃなくって。なんていうか、一緒にいると、自分がしょうもない男に思えてくるんだ。なんでかなあ。野々宮が男前すぎるんだよ。お前、男に生まれたらよかったのにな。すっげえモテただろうな」
変な励ましだよね。
私は返事をせずに家を出た。
訳も分からず走ったわ。もちろん、すっごいスピードで。
街中にいるとつらくなるから、ガーッと走って、隅田川の河川敷のところまできた。走りながら、ふと思い出したんだ。
本田君の意中の女の子、美咲ちゃんにも言われたことがあった。
「椿ちゃんが男の子だったら、私、絶対彼氏にするのにな」って。
「ざまあみろ、本田!」思わず叫んだ。「お前が私に勝ってるのは、股についてるイチモツだけだからな! それ以外は、何をとっても私のほうがいい男! 私が男だったら美咲ちゃんは私に惚れて、私は美咲ちゃんを好きにして、あんなことやこんなことを……くそっ、私が男だったら……」
河川敷にうずくまった。
なんか泣けてきてさ。涙がどんどん出てきた。
「私、女やめる! やめてやる! 男になる!」鼻水ダラダラ流しながら声の限り叫んだ。「絶対にやめてやる! 女なんてやめるんだから! 男になってやる」
――男になるって、本当かい?
「なるよ。そう言ってるじゃない」
――じゃあ、契約成立だ。
「あれ? ん?」
今、私、誰かとしゃべってた?
一瞬、正気に戻って、周りを見回した。誰もいない。
「ここだよ、ここ」頭上から声が聞こえた。
天を見あげると、雪がはらはらと降っていた。月の光に照らされてものすごく綺麗だった。でも綺麗なものを見ると、みじめな気持ちになるよね。雪のほうが私より綺麗だなって思ったもん。雪って結局はH2Oじゃん。あー私、H2Oに負けるんだって思ったね。また泣けてきて、ぼんやりと空を見あげながら涙をぬぐっていると、視界の中央に大きな影があることに気がついた。
「え、えええーー!?」思わず絶叫した。
隅田川の上空に、ドでかいソリに乗ったサンタさんがいたの。
ソリを引くトナカイまでいる。
それが、浮かんでるの! 空中に!
ふわりふわりと舞い落ちる雪の中で、月の光を浴びたソリが輝いていた。
呆気にとられていると、ソリはすうーっと移動して、私の前に着地した。思った以上に大きかった。ストンと尻もちをついて、顔だけソリに向けた。
「君は今さっき、女をやめて男になると言ったね?」
「……あ。はい」
「この世界では、口約束も立派な契約。契約は絶対だよ」
急に何なんだろう。
混乱しながらじっと見つめたのだけど、サンタさんは全然動かない。で、よくよく目をこらして見ると、それはよくできた人形だったの。
「メリークリスマス! 君は世界一のラッキーガールだ。世界一のクリスマスプレゼントを――」
「って、トナカイがしゃべってるんかい!」
つい突っ込んだね。お姉ちゃん、東京育ちなのに関西弁になっちゃった。
だって目の前で悠然と立っているトナカイが、むっしゃむっしゃと口を動かして人間の言葉をしゃべってるんだもの。
「そんなに驚かなくたっていいじゃないか。サンタのコスプレを考えたときに、何が重要だ?
そう、トナカイだよ。だってサンタはぼんやりしていてもいいけど、トナカイが働かないとソリが動かない。ということは、化けるならトナカイになるべきだ。今の話から導き出される寓意は何だ?」
と言っているあいだに、トナカイはぐにゃぐにゃと変形していって、一瞬ものすごくグロテスクな感じになったかと思ったら、いつのまにか、小太りのおじさんになっていた。
おじさんは、派手な縦じまのスーツを着ていた。うすぼんやりとした月明りの下で見ても、よく日焼けしているのが分かる。お金持ちで、チャラそうな感じ。ギラギラ系のイケてるおじさん。
おじさんは笑いながら朗らかに言った。
「つまり、主人より召使が重要ということだ。召使が無能だと何一つ立ちゆかなくなる。ということで、君にはトナカイになってほしい。君は日本で一番優秀な十五歳だから。最高のトナカイになれるよ。ちなみに、サンタはうちの息子だ」
何が何だか分からなかった。けど、おじさんは胸ポケットから名刺を取り出して、「僕はこういう者なんだが」って名乗った。びっくりしたよ。
日本で一番有名な魔法律一族、条ヶ崎家の当主だったから。
私たちみたいな庶民には、魔法なんて関係ないけど。それでも五摂家くらいは知ってるじゃん。
魔法の素質は遺伝で決まるからさ。強力な魔法律家を代々輩出している五つの家。その筆頭格が「条ヶ崎家」なんだよ。
「えっと……これは、どういうことですか?」
おじさんは私の肩をぽんぽんと優しく叩きながら言った。
「うちの執事にならないか。息子と一緒に魔法律学校に行って、あいつを助けてやってほしい。難しいことは何もない。親の欲目を差し引いても、あいつは魔法の天才だ。世界中どこを探しても、あんな逸材はいない。性格に少々難があることも否めないが……ま、君なら大丈夫だろう。どうだい、執事になって、魔法律学校、行くかい?」
何が何だか分からないよね。
でも魔法律学校に行ったら人生薔薇色じゃん。いまどき、政治家も医者もエリートサラリーマンもみんな、魔法律学校出身だもん。
百年くらい前かな。スペイン風邪っていうやばい病気が世界中で流行ったの。世界の人口の三分の一くらいの人がかかって、数千万人が亡くなった。日本でも大変だった。四十万人近くの死者が出たんだ。生き残った人に話を聞くと、「枕元に悪魔が現れて契約しないかと誘われた」って言うの。どうもそこで、悪魔と契約した人ばかりが生き残ったみたい。進化論的にはこういう現象を「選別」っていうらしいけど。スペイン風邪の流行を機に、悪魔と契約する素質のある人間の割合がグッと増えたわけ。
魔法としか呼べないような不思議な力を使う人は、ずっと昔から世界中にいたんだけど。百年くらい前の出来事をきっかけに、「悪魔と契約すると魔法を使えるようになる」って現象が、改めて「発見」されたわけ。そこから研究がどんどん進んで。今となっては、人口の二割くらいの人が魔法を使えるんじゃないかな。見たことないけど。
だって東京でいえば、私たちみたいに魔法が使えない可哀想な人たちは二十三区内に押し込められてさ。地下鉄だとかスマートフォンだとか、「科学」なんていう時代遅れの代物に頼って暮らしてるわけじゃん。魔法が使える人たちは二十三区外の魔法特区で、魔法と自然に囲まれて優雅に暮らしているらしいよ。
じゃあ私たちも悪魔と契約して、魔法を使えばいいじゃんって思う? それがそうもいかないんだよ。
悪魔ってのは意地悪でずる賢いんだ。契約の穴をついて、人間を陥れようとする。素人に契約させるととても危険だってことで、法律を学んで司法試験に受かった人だけが悪魔と契約して、魔法を使えることになった。国際的にそう決まっているわけ。「持続可能な魔法の取扱いに関する条約」ってのがあるんだよ。
いい? だからみんなも、枕元に悪魔が現れたって契約しちゃダメだからね。違法だよ。刑務所行きだよ。
でも毎年、違法に悪魔と契約して捕まる人はいるんだよね。魔法って便利らしいから。でも危ないんだ。悪魔と変な契約を結んで、暴走しちゃう人がたまにいる。二十三区内、一般地区でもたまに事件が起きてるんだって。情報統制があるから、詳しいことは私たち庶民には分からないけどさ。
……って、何の話だっけ。
そうだ、隅田川上空から降りてきたおじさんの話。おじさんは続けて言った。
「君に行ってもらいたいのは、魔法律学校の中でも最高峰の学校、帝桜学園高等部魔法律学科だ。誰もが憧れる場所だよ。帝桜学園を卒業したとなれば、その学歴だけでどんな企業にも入れる。もっと勉強したければ、どの大学にだって奨学金付きで進学できる。学歴はすべてを解決するのさ。帝桜学園に入りさえすれば、明るい未来を選び放題!」
と、あおってくるのだけど、そんなうまい話あるのかな。さすがに疑問に思った。だって、見ず知らずのおじさんが、いきなりエリートコースに乗せてくれるって言うんだもん。新手の詐欺なのかな。警戒心を捨てられなかった。
「そもそも、どうして私なんですか?」
至極当然の質問をすると、おじさんは大げさに両手をひろげて「当たり前じゃないか」と言った。
「さっきも話したけど、日本の十五歳の中で、君が一番優秀だからだ。運動も勉強も一番じゃないか」
驚いた。なんで知っているんだろう。
でもトナカイに化けられるんだから、事前に私を調べるくらい簡単にできるのかな。よく分からない。ほめられたのは素直に嬉しかったけど。
だけどねえ……断るしかないって分かっていたから。正直に申告したよ。
「私、修道院で育った孤児なんです。両親が誰だか分からないから、魔法律学校には入れないと思います」
親のどっちかが魔法律家じゃないと、魔法律学校に入れないって話を聞いたことがあったから。
どうも、悪魔と契約するには対価として魔力を差し出さなくちゃいけないらしい。その魔力の量ってのが、遺伝的に決まってるんだって。だから、魔力量の多い家系の人だけが魔法律学校に入れることになってるの。
お姉ちゃん、正直何でもできるけど、魔法はさすがに無理かなーって思ってさ。そしたらおじさん、「心配ご無用」って言うわけ。
「二名以上の魔法律家が推薦すれば学校に入れるよ。帝桜学園はトップスクールだから著名な魔法律家の推薦状が必要になる。しかし、条ヶ崎家からの推薦があれば、君一人をねじ込むことくらい訳はない。報酬なら弾むよ。聞くところによると、君が身をよせている修道院は資金不足で潰れそうなんだってね。子供たちはどうなっちゃうんだろうねえ。せっかく姉妹同様に暮らしてきたのに、修道院が閉鎖されたら、みんなバラバラになっちゃうねえ」
嫌な言い方だよね。こっちの足元を見ているみたいで。
でも実際、修道院は潰れそうだったじゃん? あと数カ月で運営費が尽きるっていう話、シスターさんがしてたよね。ほら、そこ、泣かない。いいの。大丈夫だから。
おじさんは、両手をもみながら、にっこりと笑って言った。
「僕もその話を聞いて、胸を痛めたんだよ。君みたいな優秀な人材をはぐくんだ修道院が潰れるなんてね。だから決めたのさ。この仕事を引き受けてくれたら、修道院を救えるくらいの報酬を出そう。君相手じゃなきゃ、こんなにいい話を持ってこないよ。修道院は君を立派に育てた。今度は君が修道院に恩返しをする番だ」
おじさんは胸元から一枚の紙を取り出して、私の前に差し出した。
それが不思議なものでね。文字が光っていて、夜なのにはっきり読めた。
一番上には、『雇用契約書』って書いてあった。
「難しいことは何も書いていない。雇い主の指示に従って、学園生活全般の面倒を見ること。期間は高等部卒業までの三年間。報酬額はこれだ」
おじさんが指さしたところには、とんでもない金額が書いてあった。
「実は、この話を聞きつけた人が他に何人かいてね。やりたいって手をあげる人も、一人や二人じゃないんだよ。その人たちに今、待ってもらってる状態なの。だから君がもしやらないって言うんだったら、この話は他の人のところにいくけど――」
「やります」大声が出た。
だってこんな莫大なお金、一生かけても稼げないもん。
いいんだよ、みんなが負い目を感じることはない。お姉ちゃんが修道院を守りたくて、自分で決めたことだから。
「じゃあここに印章指輪を押しつけて……いや、君はまだ印章指輪を持っていないのか。仕方ないから、拇印でいいよ」
と言うと、おじさんは素早く朱インクの瓶を差し出した。
「左手の親指にインクをつけて、契約書の末尾に押し当てるんだ」
私はひと思いに、朱インク瓶に親指を突っ込んだ。考える間もなく、親指を契約書の下のほうに押し当てた。
その瞬間、契約書の文字がピカッと強く光って、小刻みに震え始めた。慌てて手を離すと、契約書は宙に浮き、次第に二重に見えてきて、いつのまにか、目の前に二通の契約書が浮かんでいたのよ。
「これが君のぶん」おじさんが二通のうち一通を私にくれた。
「えっ、私の?」
「契約書は大事だからね。大事に保管しておくんだよ。勤務開始日にこの契約書に向かって『出勤』って言えば、雇い主の家までワープさせてくれる。そういう魔法があらかじめかけてある。ほら、うちって結構な名家だから、セキュリティ上かなり辺鄙なところにあるの。部外者が入ってこないように、魔法でしかたどり着けないようにしている。敷地内に大きな魔法陣があって、ワープ装置みたいなものが備え付けられていてね。難しくて珍しい魔法だから、かなりコストもかかる。この契約書だと一回しか使えないよ。ということで、契約書は大事に保管すること」
「分かりました」契約書を丁寧に折りたたんで、ポケットに入れた。
ふう、と大きく息を吐く。なんだか大きい仕事をやり遂げた気分だった。実際の仕事はこれからなんだけど。
おじさんも、「いやあ、契約成立。よかった、よかった」ってニコニコしていた。
勢いで契約したものの、さてどうしたものか。戸惑いながらおじさんを見返すと、
「じゃあまず、男になってもらおうか」
って、一点の曇りもない笑顔で言われたの。真っ白な歯がピカーンって輝いていたわ。
聞き間違いかと思って、「今なんて?」と尋ねると、「だから、君には男になってもらう必要があるね」と繰り返す。
「ここを見てごらん」
おじさんは契約書を裏返して、その端のほうにある「(別表3)委託業務一覧」ってところを指さした。
「しっかり書いてあるだろう。『執事は、別途の指示がない限り、主人と同じ寮、同じ部屋で寝食をともにすること。なお、執事は同業務に必要なあらゆる措置を講じる』って」
暗闇の中でも薄く光って文字が読めた。米粒みたいな小さい文字で、確かにそう書いてある。
「えっ、ちょっと、待ってください」
頭がこんがらがって、心臓がばくばく鳴っていた。だけど何か言わなくちゃと思って、必死に反論した。
「私が男のふりをして、男子寮で暮らすってことですか?」
「いかにも」おじさんは意地悪く笑ってうなずいた。「学園は共学だけど、寮は男女別だからね」
「そんな。さっきはそんなこと、言ってませんでしたよね? 聞いてないです」
「聞いてなくたって、ここに書いてある。『執事は同業務に必要なあらゆる措置を講じる』とな。そして君は契約書に署名した」
頭が真っ白になった。
男になる? 男子寮で暮らすために必要な措置を講じる? 何が何だか分からない。
「一応ね、僕も年頃の女の子にこんなことを頼むのもどうかなと思っていた。だけど君はさっき、男になると言ったよね。僕と約束したじゃないか」
確かにそう言った。でもそんなの――「本気じゃなかった?」おじさんがこちらの思考を読むように続けた。「君が本気かどうかなんて、僕には分からない。ここにある契約がすべて」
ぐっと顔を近づけて、地に響くような低い声で、
「契約は絶対だ」
とうなった。
これはさすがに、かなり焦った。やばい、私、魔法で男の子に変えられちゃうんだ、と思って、身構えた。だけどおじさんは軽い調子で、「じゃ、入学までに髪を切っておいてね。それで君は男に見えるから」って言ったの。
ひどくない? ひどいよね。
どうやら、魔法で一時的に姿を変えることはできるらしい。だけど、その魔法はものすごく珍しいし、難しい。使える人はほとんどいないんだって。しかも魔法を使ったところで、何時間かすると、もとの姿に戻ってしまう。そんな不安定な方法で魔法律学校の三年間を乗り切るのは無理だから、いっそのこと、女の身体のまま男のふりをしたほうがいいというの。
で、今の髪型になった。
見てよ、ショートカット。なかなか似合うでしょ? 男として見れば。
なんで説得されたかって? 説得とか、そういうの、ないない。
おじさんは一方的に勤務開始日と学園入学に必要な手続きを説明すると、「じゃ」と片手をあげて、一瞬のうちに消えてしまった。サンタの人形もソリも消えていた。
私に選択肢なんてなかった。
一見、フレンドリーで優しげな人だったけど、腹の底は真っ黒の狸オヤジだったんだよ。
河川敷に一人とり残されて、とぼとぼ歩いて帰ったよ。すっかり雪もやんでいて、そこはただの冬、何の情緒もない寒い夜だった。正直なところ、だまされた感じがした。だけど改めてよく考えると、男になって魔法律学校に行くってプランは悪くないと思った。
正直もう、女でいるのに疲れたっていうか。
恋愛とかもういいし。
男として勉強だけして、猛烈に仕事して生きてくってのもいいかな。ていうか、そのほうが自分に向いているかもっていう気持ちがあった。私が働けば修道院が救われるんだから、やりがいはあるしね。もうどうにもならないから、前向きに考えて自分を慰めているだけかもしれないけど。
そんなわけで、お姉ちゃんは明日には女子修道院を出て、ご主人様の家に行くよ。そのまま帝桜学園に入学する予定なの。
ご主人様と顔を合わせたかって? まだだよ。でもどんなやつがきても大丈夫。私ならどうにか……いや、俺ならどうにかなると思うんだ。
ふふふ、男みたい? かっこいい?
大丈夫、お姉ちゃんのことだから、たくましく、なんとかやってくよ。心配はいらない。
え、怖い話はどうなったのかって?
充分怖かったじゃん。
いや、契約書を読まずに契約すると怖いよって話じゃないって。そこが怖いんじゃなくて。
しゃべるトナカイのところが怖かった? そこじゃないよー、話聞いてた?
男に尽くしまくったのに、無惨にフラれた女の話。
そう、そこを話したかったの。
だってホラーでしょ?
いいかい、お嬢さんがた。君たちは妹同然だから言うけどね。
男に尽くしてもらう女になるか、バリバリ働いて一人で生きていくか。
君たちの進む道は二つに一つだ。
くれぐれも、男に尽くして愛されようなんて思わないことだね。
ハハハ、私はもういいんだ。恋愛を捨てて仕事に生きるって決めたからね。
かっこいい人が現れてアプローチしてきても? なびくわけないじゃん。てか別に、かっこいい人は現れないし、現れたとしてもアプローチしてこないでしょ。アハハ。
それじゃ、みんな、元気でね。
強くて優しい、いい子に育つんだよ。
◆
私はじっと体育座りをしながら、椿ちゃんを見つめていた。
驚いて、声が出なかった。確かに修道院は資金不足で困っていた。だけど椿ちゃんが一人で背負って、解決しようとしていたなんて、私はちっとも知らなかった。ただ普通に、修道院を出て高校に進学するだけだと思っていた。
椿ちゃんは一気に話し終えると、「さて、もう寝ようか」と立ちあがった。
着古したスウェットから、凜々しい顔がのぞいている。瞳には、野生のシカやウサギが見せるような清廉な美が宿っていた。恋愛は捨てるとか、男ウケしないとか、自分を卑下することばかり言う椿ちゃんが、私には不可解だった。
「椿ちゃん」背中に声をかけた。「二人で話したいことがあるの」
彼女は振り返り、少しだけ表情を曇らせた。だけどすぐに「どうしたの? 早緒莉ちゃん」と笑った。戸惑いをごまかすような笑みに、胸がきりきりと痛んだ。
私たちは連れ立って、修道院の裏に出た。椿ちゃんが毎朝筋トレしている空き地だ。高台にあるから、東京の街が一望できる。住宅地には灯りがともり、海岸の向こうの工場地帯からは煙があがっている。二十一世紀、どこにでもある都会の外れだ。
春風が吹き、梢が揺らぎ、ささやくような葉音が私たちを包み込んだ。夜を切り裂くように、修道院の鐘が鳴り響いた。ちょうど九時を回ったらしい。
「椿ちゃん、本当に修道院を出ていっちゃうの?」
「うん、さっきも話したでしょ」
椿ちゃんは、妙に大人びた笑みを私に向けた。年も一個しか違わないのに、椿ちゃんはいつも凜としている。涼しい顔で私の前に現れてすべてを解決してくれる。
貧乏すぎてクラスの男子にからかわれたときも、友達の彼氏を誘惑した疑いでいじめられたときも、いつも一番に椿ちゃんが駆けつけてくれた。アハハッと大きく笑う顔も、ほめられると本気で照れるところも、実はけっこう乙女趣味なところも、私だけが知っている。
毎日一緒にいて、これからもずっと一緒だと思っていたのに。明日から会えなくなるのかと思うと胸が詰まった。涙がこぼれそうになるのを必死にこらえて声を絞り出した。
「椿ちゃん、これ、もらって」
後ろ手に持っていた小さい紙袋を差し出した。椿ちゃんの高校進学祝いとして用意していたものだ。
「えっ、何? 開けていいの? うっわあ、可愛い! 新作のリップだ」
椿ちゃんの白い指先に、銀色に光るリップスティックが握られた。花模様の彫刻が入っていて、ピンク色のラインストーンもついている。
「お姫様の持ち物みたい。可愛いーっ! 私、実はこういうの、好きなんだよね。あんまり似合わないから、恥ずかしくって持ってなかったけど」
「似合うよ」つい強い口調で言った。「椿ちゃんは何でも似合う」
「ええ、そうかなあ?」
「新しい学校にも持っていって。それで、早緒莉のこと、忘れないで」
「早緒莉ちゃんのこと、忘れるわけがないじゃん」
満面に笑みを浮かべて、私の肩を叩く。
ほら、そういうところだよ。何も分かっていやしない。心のうちでつぶやいた。
「学校では男の子のふりをしなくちゃいけないから、可愛いこのリップを使うわけにはいかないけど。お守りみたいに持ち歩くね。早緒莉ちゃんが近くにいるみたいで心強いよ」
「男の子のふりをするってことはさ、同級生の女の子から告白されたり、するのかな?」
え、と椿ちゃんは言った。「確かに。そういうこともあるのかな。私、意外と女の子にはモテちゃったりして?」
軽い冗談みたいに言うから、腹が立った。人の気も知らないで。
「椿ちゃんはさ、早緒莉のこと、どう思ってる?」
心臓をバクバクさせながら訊いた。
「どうって? 大切な人だよ。家族というか、妹みたいっていうか。早緒莉ちゃんは可愛いから、変な男が寄ってこないか心配だよ」
それならさ、と言ったが、あとが続かなかった。
「もう遅いから寝よう。今生の別れってわけじゃないんだし。手紙も書くし、長期休暇には帰ってくるよ」
穏やかに笑うと、椿ちゃんは歩き出した。その背中を見送りながら、私はため息をついた。
一番大事なことは、いつも言えない。
椿ちゃんは私を守ってくれた。今だって、修道院ごと守ろうとしている。だけど椿ちゃんのことは誰が守るの?
「大丈夫かなあ、椿ちゃん」
独り言は静寂に吸い込まれていった。
* * *
この続きは書籍『魔法律学校の麗人執事1 ウェルカム・トゥー・マジックローアカデミー』でお楽しみください。
魔法律学校の麗人執事

「私が男のふりをして、男子寮で暮らすんですか!?」
男装したヒロインと、オレ様系男子による恋と魔法の学園ファンタジー、開幕!
新川帆立の新境地!
ライトノベルシリーズ始動。